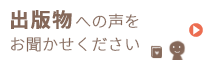学名・用語など
□豊国秀夫(編):植物学ラテン語辞典
386pp.1987.至文堂.東京.¥9,000.
植物の学名を扱うためのラテン語の参考書としては、朝比奈・清水の植物薬物学名典範と牧野・清水の植物学名辞典くらいしかなかったが、本書は両者をとりまとめたような本で、期待していた人も多いことだろう。辞典部ではラ-和(約7,800語)とともに、これまで無かった植物学和-ラ辞典(約5,400語)が作られたことで、有用性はずっと大きくなった。物質名や花粉学用語などがふんだんにみられるのも有難い。文法部は50頁で、長野県植物研究会誌に連載された記事を骨子とし、ラテン語に堪能な編者の知識を駆使して、いずれも具体例をあげてわかり易く解説している。植物の新名発表に義務付けられている、ラテン語の記載文や特徴記述(diagnosis-編者訳)の作文は容易なものではないが、本書の出現により、学名のつけ放しをする者は言い訳がしにくくなることだろう。新学名の発表は、混乱をおそれて専門家にまかすべきであるとの意見の人もあるが、私たちはこういう本を参考に誰でも発表できる方がよいと考える。どういう発表のしかたをするかは、本人の教養の問題であろう。
[植物研究雑誌63(2):38(1988)]
□大橋広好(訳):国際植物命名規約 1988
214pp.1992.津村研究所.¥2,500.
1988年に承認された、いわゆるベルリン規約の全訳である。これまで我が国には国際植物命名規約の独立した日本語版はなかった。中井、北村、広江、上村などによる全訳や抄訳が、雑誌や単行本の中に発表されており、研究者の中には勉強をかねて自分の訳本をもっておられる方も少なくない。一方、「学名のことは分類学の専門家にまかせておけばよい」という空気がなかったわけではない。しかしながら今日のように環境保全、絶滅危惧種、ワシントン条約、外来種、開発事前調査など、植物種を扱う多くの社会問題が広範囲に発生し、たくさんの地域同好会誌があって、それらにおいても学名の検討がなされたり新名が現れている状況では、学名というものはもはや分類学者の専売ではなくなってきた。特に、学名の理解なしに和名を扱うことは、いたずらに混乱を招くだけである。国際植物学会議でも、命名規約を各国語に翻訳することが勧告されている。韓国ではすでに、国際植物命名規約(鄭 英男583pp.1986)という大部の本が出版されている。本書の出版はまことに時宜にかなったもので、これによって問題点を誰でも自らチェックすることができるようになった。とは言っても元来が法律用語に近いものなので、文章はそうやさしいものではない。熟読のうえ原文にも当たる必要があるだろう。これらを更に噛みくだいた解説が本誌あたりに載れば、一層の理解に役立つだろう。147頁までが規約本文、以降が各種の索引である。これまでなんとなく原語で済まされていた用語についても、翻訳にあたって新しく工夫され、判別文、公認代置名などの新語がつくられた。当初予定していた出版社が販路の予測がつかずに辞退し、訳者は苦労したようだが、幸いに本誌の発行元の津村研究所のご理解により出版された。書店には出ないものなので、直接申し込まれたい。中身にくらべてきわめて安価なものなので、本書が多くの人の参考に供されることを希望する。
[植物研究雑誌67(4):245(1992)]
□全国自然科学名詞宙定委員会:植物学名詞
192pp.1991.科学出版社.北京.¥3,350.
わが国の学術用語植物学編にあたるもので、3,304件の基本用語を14の分野別に華文英文を対置してある。用語の順序は華文でも英文でもなく、関連性の高い用語をまとめてあるようだ。一語ずつ分野番号と分野内の通し番号がついている。用語説明はなく、注釈欄には別称などが必要に応じて記されている。分野と用語数は次の通りである。総論(216)、植物形態学(595)、植物解剖学(449)、植物胚胎学(261)、藻類学(134)、真菌学(395)、地衣学(77)、蘚苔植物学(40)、植物生理学(374)、植物化学(170)、植物生態学(333)、植物地理学(94)、古植物学(73)、胞粉学(93)。植物学の現況からみて、生理や化学の用語が、他にくらべてずいぶん少ないように思うし、実際、新しい用語はのっていない。遺伝学という分野は見当たらない。これが中国の現状だとすれば、ちょっと首をひねりたくなる。わが国と同様、新展開している分野の用語は消化する暇がなく、言語にそのまま漢字を当てて苦労しているようだ。この点わが国の片カナというのは便利な文字だと思う。一方、現在は使われていない用語もかなり含まれている。巻末に華英索引と英華索引がある。とくにおすすめする文献ではないが、日本での用語を選ぶ時に、文字の使い方の参考にはなる。例えば、abortion 胚育、telome 頂枝、lenticel 皮孔、zygote 合子、abundance 多度、vicarious species 替代種、tetrad 四合花粉。shoot と言う用語は議論が多くて決めかねたと序文にある。
[植物研究雑誌68(1):62-63(1993)]
□日本菌学会(編):菌学用語集
86pp.1996.メディカルパブリッシャー.¥3,000.
文部省学術用語集とはちがって、学会が独自の活動として作ったものである。語数が英和では約4,600件、和英では約5,200件とかなり差がある。この理由は、英和では1つの単語に対応する和文をいくつも並べているのに対して、和英ではすべての和文を見出しとしているためである。和文は用語のよみの50音順であるが、読み方は記されていない。これはよみをつけるべきだった。細胞がサイボウかサイホウかでつっ張り合った記憶がある筈だ。よみはデータベース検索にも必要である。もっとも、学術用語集のような訓令式ローマ字は願い下げである。名詞の他に形容詞が非常に多く取り入れられ、ときには動詞も入っている。これはこれで、論文を書いたり読んだりするときの参考になるだろう。菌学用語だから、他の生物分野の用語とは違う場合がある。たとえばautoclave:オートクレーブ/オートクレーブする〔植物学用語集では高圧滅菌器(オートクレーブ)〕、epiphyte:植物着生生物〔植物学用語集では着生植物〕、incubator:ふ卵器〔植物学用語集では定温器(ふ卵器)〕、sign:標徴〔動物学用語集では記号〕など。植物学用語集ではascusは「子嚢」であるが、本書で「子のう」である。用語集を作るとき感じたことだが、同じ英文でも分野が違えば用語も使うしニュアンスも異なり、「統一」することに無理がある場合が多い。現在、生物関係だけでも動物、植物、遺伝、農学の文部省学術用語集があり、生物教育用語集も学術用語集と離れて検討されている。今回の菌学用語集で、おそらくかなりの異なる表現が出てきたのではあるまいか。もし文部省学術用語集菌学編を作るとなると、これらの多くは半強制的に先行の用法に「統一」させられるおそれがある。私には教科書だの試験のために、1つの外国語に1つの日本語しか対応させないように「統一」するのは無理があるように思う。学術用語集で、分野が違うからと別々な用法を容認していれば、「統一」の理念と離反してしまう。実際には「統一」せねば不都合がある用語はそんなに多くはないはずだから、自然の成り行きにまかせても大したことはなさそうに思う。
[植物研究雑誌71(5):304(1996)]
□万谷幸男(編):植物学名大辞典
B5版.420pp.1995.植物学名大辞典刊行会.¥12,000.
編者は趣味の多肉植物愛好家で、学名の意味に興味をもち、植物全般の小名の意味を多くの文献から書きとめた資料を遺して、1984年亡くなられた。本書は知人有志がその努力が無になるのを惜しんで、遺品を整理し、出資刊行したものである。小名をabc順に並べ、その意味を解説してある。解説は原典からの引用で、とくに新しい解釈などは含まれていないようだが、採録件数はざっと数えて23,000語である。この数は牧野・清水の植物学名辞典が約11,000語であることを思えば、故人の努力のほどが察せられる。学名を調べたり発表したりするときの参考となるだろう。
[植物研究雑誌71(3):178(1996)]
□Bailey L.H.(八坂書房編集部訳):植物の名前のつけかた 植物学入門
238pp.1996.八坂書房.¥2,884.
名前はよく知られているが、訳書の少ない原著者の、How Plants Get Their Names(1933)の全訳である。リンネの二名法の確立に始まり、同定・標本・それを保存する標本館の意義、命名規約とはなしが進み、学名にまつわるエピソードに及ぶ。学名の解説書というと堅苦しい印象があるが、本書は物語り風の柔らかい読み物であり、植物分類学をやらない人でも入ってゆけるだろう。命名規約の部分は最近のものに置き換えて読むべきことは勿論である。訳者の工夫のほども察せられ、このことはあとがきの懇切さにも表れている。約3,000語におよぶ種の形容語一覧には、訳者によると他書にない語彙が含まれているそうで、これまた有用な資料となるだろう。
[植物研究雑誌72(4):253(1997)]
□丹羽基二:日本苗字大辞典
1979+1977+2098pp.1996.芳文館.¥330,000.
高校国語教師の著者のライフワーク、世界で1番多いといわれる日本人の苗字291,531件を、①よみ順、②頭字画順、③末字画順に配列し、よみとローマ字をつけてある。既製のパタンがなくて、新たに作った漢字は13,000件に達するという。これだけでも国字研究への貢献は大きい。こういう辞典は世界でも最初のものらしい。ユニコードという世界共通文字コードの開発が進んで、文字情報の国際化が達成されれば、こういう辞典は日本のみならず、世界の共通財産となるだろう。苗字は民族のルーツと交流の歴史を反映しているが、その85%は環境としての地名に由来しているという。植物関係の苗字はどれほどあるか、民俗植物学研究の絶好の資料である。3冊で13.5kg、おまけにこの値段では、個人としては無理だろが、各地の図書館に、重要参考図書として購入を要求すればよかろう。
[植物研究雑誌72(4):254(1997)]
□清水建美:図説植物用語事典
323pp.2001.八坂書房.¥3,000.
植物の形や性状といった、分類や同定に用いられる用語約1,400件が収められている。文字だけではわからない形状の説明のため、700点を超える写真や図が付けられ、図や写真だけの頁は87頁におよぶ。図のほとんどは梅林正芳氏の手になり、写真のほとんどは亘理俊次氏の作品である。おかげで、あちこち探さないと見られない植物の細部の良い映像を、この1冊で目にすることができるのはありがたい。昨今は著作権問題もあって、他社の作品に良い図や写真があっても、それを引用しにくい、またさせにくい風潮があるようだが、本書では一々了解を得て利用している。優れた作品をこのように有効利用することは望ましい。学術用語集植物学編増訂版(1990)には解説がなく、生物教育用語集(1998)は学習指導要領に制約された解説なので物足りない。その点本書は著者の永年の経験を踏まえて、自由に記述されている。その代わり、たとえば私がよく観察会で話しの種にする、コゴメウツギやキンモクセイの縦生副芽は、ジャケツイバラとエゴノキで代表されているし、MagnoliaやFicusを特徴づける托葉鞘の記述はない。多くの事典では用語の配列は文字順だが、本書では植物群、習性、花、果実と種子、葉、茎、芽、根、生殖と分けて、それぞれに関連する解説に伴って、用語の和文、英文(単、複数形を示す)が、植物名を挙げて示されている。
著者がまえがきやあとがきで述べているように、名前を聞き、小話しを聞いておわりになるような自然観察会から抜け出して、特徴の観察から入って植物名に行き着くようなスタイルを目指したのが本書である。私も観察会については同じ意見を持っている。けれども盛り沢山で、著者の意図したものよりはむずかしい感じになったようで、形態学の教科書といったところである。分類の研究者が形態を扱うのは当然だが、これ迄は形態学者による形態学の本に頼ってきた。本書はその逆のはじめての例だろう。本書を足場にして、次にはそれこそ観察会に持ち出せるような一般向きのものも工夫してもらいたい。すでに原ら(1986)による植物観察入門などがあるから、それと一線を画するものにしてほしい。付録として、形やつき方を表す用語、突起や毛・腺に関する用語、クロンキスト系による日本産種子植物分類表がある。和分索引、欧文索引がついているが、例示された植物のリストがあるとよかった。野外で見つけた植物、どんなところに着眼点があるかがわかり、更なる観察に役立つからである。
[植物研究雑誌76(5):306(2001)]
□国際園芸学会(著)・大場秀章(監)・栽培植物分類名称研究所(訳): 国際栽培植物命名規約第7版
A5版.159pp.2008.アボック社.¥14,286+税.
特定非営利活動法人栽培植物名称研究所(CULTA)の邦訳委員会(大場秀章(委員長)、今西英雄、大槻葉子、荻巣樹徳、與水肇、森弦一)が、わが国ではじめて全訳を行ったものである.前文(1-2頁)、第Ⅰ部:原則(3-4頁)、第Ⅱ部:規則と勧告(5-53頁)、第Ⅲ部:雑種属の名前(54-56頁)、第Ⅳ部:名前の登録(57頁)、第Ⅴ部:スタンダード標本(58-60頁)、第Ⅵ部:規約の修正(61頁)、附録Ⅰ~Ⅳ(63-99頁)、用語解説(101-128頁)、植物名索引(129-142頁)、事項索引(143-153頁)より成る。9章32条を含む第Ⅱ部が主体である。前文に先立って1995年の前版との異同比較表があるが、216件が示されている。一方1995年版に出ている1980年版との比較表では112件が挙げられており、今回の版で大幅な見直しが行われたことを示している。
第Ⅱ部第I章第1条は、国際植物命名規約との関係を述べている。第2条は、この規約の主対象となるcultivarの定義に関するものだが、この語に対して「栽培品種」という語が用いられている。これについては日本語版あとがきにあるように、本規約の対象範囲が作物も含むので、園芸品種という語よりも適当と思う。栽培品種はさまざまなオリジンや方法で作り出されるものなので、その定義づけと定義に外れるケースが16項目にわたって述べられている。第3条は、栽培植物独特の「グループ」に関するもので、栽培上や鑑賞上の特色から、一まとめに扱うことを認められた分類群で、わが国で「芸」と呼ばれるものに近いことが、フウランを例として示されている(実例8)。また、ランについては独特の品種作出技法が発達しているため、「グレックス」という分類群が特に認められている。第19条には栽培品種名の様式が提示されている。すなわちGeranium pratense ‘Mrs Kendall’のように、国際植物命名規約に則った学名の後に単引用符(‘ ’)で囲まれた先頭が大文字の形容語をつける。またCamellia ‘Shōjō-no-mai’のように、学名部分は属名だけでもよく、potato ‘Cara’のように、普通名が学名で示された植物と同等なものであればそれでもよい。栽培品種であることを示すランク名cv.は用いない。
栽培品種の学名の形容語は、いわゆる土名がそのまま用いられることが多いので、第29条:形容語の翻訳、30条:形容語の翻字、31条:形容語の書換え、32条:形容語の綴りなどの諸条でいろいろな制約が課せられているが、これには十分注意、というより警戒せねばならない。ここには米英語以外の文字をアルファベットに翻字するルールが規定されている。その基本は米国国会図書館発行のALA-LC Romanization Table現行版が基準とされているが、これはローマ字系以外の言語を対象としている。日本語の場合には(31条3項)、やはりこのTableに準拠した「研究社新和英大辞典第三版以後で用いられている修正へボン式ローマ字表記法」に『よらねばならない』としている。これの参考とするため、160頁(この部分は規約外のためか頁表記がない)に、「修正へボン式ローマ字表記一覧」が載せてあり、いくつかの事例が示されている。例えば注2の例として、東京はTōkyōであり、Tôkyô、Toukyouと綴らないと注意書きされている。同様に、si、tu、dzu、syoなども使えない。このヘボン式ローマ字表記には、いくつかの問題がある。
- 文字の上に短線を乗せることで長音を表現し、長音記号を単独で用いたり、文字の上に山形記号を乗せて長音を表す訓令式ローマ字や、長音を記号を用いずに表記する方法を排除していて、やむをえない面もあるが命名の自由度が制約される。
- 160頁の注釈では、東京は「トーキョー」であり「トウキョウ」ではないとしている。つまり、日本語の発音の仕方ばかりでなく、日本語の綴り方まで規定しているように見える。nに続く母音やyを、続けて読まないことを示す「’」記号の使い方についても同様である。これは異文化を否定することにならないだろうか。別にどんな綴りを使おうと、区別ができれば差し支えあるまい。160頁の注釈は勇み足と思う。へボン式でも東京をTokyo、Toukyouと綴れるのだから・・・。
- 長音記号を上乗せした文字は、和文のコード体系では、作字しなければ表現できないので、通用しないばかりか、他の文字に化けてしまう心配がある。欧米文字のコード体系なら可能だが、そのデータは日本国内で和文を交えたシステムで通用するのだろうか?汎用文字コードUNIXが一般化すれば可能になるといわれるが、UNIXの時代になったとき、それまでに作られたデータは生き残れるのか?上付き記号のある文字を使わねばならないような規約の容認は、わが国の当事者に不利益をもたらすのではないだろうか?この文の原稿も、上付き記号のある文字がないばかりか、単引用符も1バイト文字がないために、2バイト文字を使わざるを得なかった。
- 附録Ⅱの種苗登録行政機関一覧の日本関係では、農林水産省生産局種苗課が載っているのみだが、こういう政府機関が訓令式でなく、ヘボン式ローマ字を受け入れるのだろうか?
植物命名規約では学名だけが問題になるが、栽培植物では「学名」とはいえ和名の領域まで入り込んで干渉することになるので、問題が複雑である。ところが本来アルファベットを用いる語では、こういう制約はゆるい。たとえば3条3項(11頁)には、「grexの複数形はgregesであるがしばしばgrexesも書かれる」と、綴りの変異をごく自然に容認している。その上「言語習慣が要求する場合を除き」という前置きで、アポストロフィの使用を認めたり、ハイフンの途中の大文字を許したりしている。「アルファベット以外の文字を使われると印刷や記録が厄介だから、アルファベットで表記してくれ」だけにする方が公平だと思う。
栽培植物の名称は商標登録や特許の対象となるので、自然の植物のそれと違って大きな利益にからむため、名称の異同に神経質にならざるを得ない。上記のような制約は、中国語や韓国語やキリル文字についても規定されている。こういう規定はたぶん、栽培品種名を漢字やハングル文字や日本字で表記されて理解できないため、欧米の市場で勝手に適当な欧字名をつけて流通させる習慣があり、開発者がつけた品種和名の知的所有権が無視されるのを防ごうという思いやりに由来すると受けとめておこう。日本語についての制約事項に中華語や韓語よりも多くの字数を費やしているのは、日本の栽培植物市場の評価が高いことと、日本からの働きかけが多かった結果と思う。1995年の6版(とは書いてないが)では、「日本語にはヘボン式を使え」と書いてあるだけである(28条4項)。ただし日本の栽培品種名に頻出する「琴の糸」の「の」つまり「No」はたいへん目障りらしく、「Koto No Ito」ではなく「Koto-no-ito」と、ハイフンでつないで途中は大文字を使わないことにせよと、わざわざ例を挙げて念を押している。私はこの程度で十分だと思う。ただしそれならば、アルファベット圏の名前についても、同じルールを例外なく使わせる方が公平である。
栽培品種のタイプ標本にあたるものはスタンダード標本と名付けられ、付録にその保存場所のリストがある。しかし栽培品種のような、花の咲き方とか香りとか枝ぶりとかによる違いは、生きた実物を比較せねば判断し切れないだろう。だから、ローマ字名表記の方針はやむを得ないとしても、その綴りまで一々規定しても、それだけの効果があるとは思えない。それよりも、流行に流されながら次々と生産され、アッと言う間に消え去ってしまう「新品種」が流れる国内市場で、余計な規制のために登録手続きが煩雑になる不利益の方が大きいだろう。しかも消え去ってしまってもその栽培品種名はいつまでも残るし、スタンダード標本は上述の理由であまり頼りにならないから、付けられ易い名前が次第に品薄状態になって行くのではなかろうか。もっとも第27条には、名前の再使用の規定があり、もはや栽培されていない、育種素材や種子や遺伝子が保存されていない、その名前が出版物にほとんど用いられない、などの条件を満たせば、名前の再使用が認められることになっている。
栽培植物名をこの規定に沿って学名化するとき、日本名の単なるローマ字化では意味不明でインパクトがないだろう。外国人の感性に訴える名前を工夫する必要がある。われわれは「ポカリスェット」とか「コカコーラ」と聞くと、意味が分からなくてもなんとなく受け入れる習性がある。けれどもよその民族もそうだとは言えない。外国の文学、古典、伝説などの知識をもっと応用した命名を考えたらどうだろう。日本の雅名も、単なるローマ字化ではなく、意訳するような教養と工夫が必要である。園芸界で文学者や詩人や歴史家を動員して講習会をやったら、輸出に貢献するのではあるまいか。観察会や勉強会でも、名前の由来についての解説がよくなされるが、解説者が勉強して、もっとレベルアップすればよい。
あちこちに「第Ⅴ部参照」というような指示があるが、頁の肩の見出しは1-2頁は「前文」、3-4頁は「原則」(この場合Ⅰ部)、5-53頁は「条」(この場合II部)、54-61頁は「部」(この場合Ⅲ~Ⅵ部)、63-99頁は附録となっていて、慣れないとどこに何があるのかわかりにくい。
付録にはⅠ国際栽培品種登録機関、Ⅱ種苗登録行政機関、Ⅲ特定の適用分類群、Ⅳスタンダード標本が保持される場所、のリストがある。Ⅲを除いてはいずれも欧米の機関が圧倒的である。スタンダード標本が保持される機関は、オーストラリア、カナダ、オランダ、ニュージーランド、南アフリカ、英国、米国のみである。これは意思表示した機関が今のところそれだけだ、ということなので、こういう命名規約の必要性を認識するならば、積極的に意思表示をした上、実績を見せねばならないだろう。言うは易く行うは難しである・・・
国際植物命名規約よりはるかに煩雑で、かつ金銭的利害に影響の大きい国際栽培植物命名規約の和訳に取り組んだ、邦訳委員会のご苦労を多とすると共に、これが広く有効に利用されることを期待する。上記しただけでもわかるように、この命名規約自体がわが国の流通市場に与える影響が少なくないので、その改善に関係者がこぞって取り組む必要があるだろう。
[植物研究雑誌83(2):124-126(2008)]
『金井弘夫著作集 植物・探検・書評』コンテンツ一覧▼ 目次(青字)をクリックすると、各文をご覧いただけます
金井弘夫博士著作集に寄せて 東京大学名誉教授 大場秀章 / あとがき
第一部 時代の記憶・探険の記憶
最後の旧制高校生の自分史
理化館の焦げ茶のタイル
インドで見たこと聞いたこと
- はじめに
- 夏休みは4月
- 「古」新聞の値段
- 街頭の商人達
- 乞食
- ボクセス
- 良いお金と悪いお金
- 水
- お茶
- オナラ
- 立小便
- 近づくほど遠くなる
- 踏切に錠前
- 汽車
- バス
- 市電
- インド人という「民族」
- アッチャー
- タバコ
- お酒
- ビール
- ウイスキー
- ラム
- チャン
- マフア酒とヨーグルト
- 朝のお祈り
- 国境侵犯
- 二人のリエゾン・オフィサー
- シェルパたち
- アンプルパ
- トゥンドウ
- プルバ・ロブソン
- テンバ・シェルパ
- 女性たち
- ラマ教
- 山で一番こわかったもの
- お菓子
- 名前
- 宿屋
- インドの道の良さ
- フェリー
- 牛
- 交通法規
- カストムハウス
- 風呂
- 拍子木たたき
- バルカカナの日本人
- ボダイジュの借り倒し
- タテガミのあるブタ
- 封蝋
- 食いもの
- カースト(階級制度)
- デモ
- 鶏と卵
- 切符を買う
- 街路樹
- 事故
- インドの英語
再びインドの植物を求めて
- 悪路に悩む採集行
- ヒマラヤで見る段々畑
- 調査成果の一端
西北ブータンの山々
- 入国手続き、旅行許可など
- 入出国の経路
- 国内の輸送、通信、シェルパなど
- 物資の調達
- 気候
- 地図、コースについて
- チンプウ-トンサ
- 観察されたピーク
- 集落
- 通貨、賃金
フィニッシュの話
- 失せ物が出た
- 通関書類、フィニッシュ
- リエゾン・オフィサー、フィニッシュ
- ミソとストーブ、フィニッシュ
- スペース、フィニッシュ
- チニ、フィニッシュ
- サーダー、フィニッシュ
- ポーター、フィニッシュ
- 道路とジープ、フィニッシュ
- ブルカー、フィニッシュ
- 標本、フィニッシュ
- 道路、もうひとつのフィニッシュ
- シェルパ、フィニッシュ
- トラック、フィニッシュ
東ネパール調査(1963年)点描
- チャッシガレ!
- おまじない、ハチ
- 録音
- ハリー
- 食物
- こわいもの
ネパール通信1
- カトマンズ(1)
- フルチョウキ
- カトマンズ(2)
- チュリア・マハバラトの旅
- ゴサインクンデの旅
- ボダイジュのほこら
- カトマンズ(3)
- ロルカニの旅
- カトマンズ(4)
- チリメ、ランタンの旅
- チャンドラギリの旅
ビル・ニガントゥに見られる米の記事
ネパールの滝の数
ネパール通信2
- 自動車事故のはなし
- 創立記念パーティー
- カリンチョークの旅(1)
- インドラジャトラ
- カリンチョークの旅(2)
- チュリアの旅
ヒマラヤ植物調査の今昔
日本・ネパール協同植物調査史 1960-1980 [英文]
『冒険家族ヒマラヤを行く』訳者あとがき
パプア・ニューギニアの話
- 交通
- 食べ物
- 人々
- コトバ
- 古戦場
吉川英治文化賞受賞のことば
第二部 植物の観かた・残しかた
野外観察会のこと
日本植物の分布型に関する研究(2) ヒメマイヅルソウの分布型と変異
オゼコウホネの種子散布
ヤマモモの仁
クヌギの落枝
スベリヒユは対生
猪突猛進するチガヤの地下茎
ササの葉鞘
ケヤキの落葉現象はあったか
笹舟は沈む!
ミャンマーのドクウツギ属植物Coriaria terminalis Hemsley とその西限産地
ブータンのウルシ
植物の動きを見せる
尾瀬ケ原の池塘データベースによるヒツジグサとオゼコウホネの16年間の分布消長
群落の突然の交代
ツタの植物画
ツタの「雨」
国立科学博物館のサクラソウ生態展示
有毒植物を食べる
ミズバショウの果実の味
マムシグサのイモの「味」
ヌルデとネムノキは仲良し?
ビルマの植物学界の一端
部活動と自然観察会
普通な植物を記録しよう
ヒレハリソウ(ムラサキ科)の葉序
アイスマンの弓矢
ツュンベリーと日本のアマチュア植物学 [英文]
誰にでも利用できる標本のために
標本にはラベルを入れよう
標本ラベル論議へのながーいコメント
- 仮ラベルに関して
- 本ラベルに関して
- データベースに関して
ヒートシールによる標本貼付
おしば標本の新しい貼付法
おしば標本貼り付け用ヒートシールテープの自作法
移動式おしば標本棚の得失
- 改装工事前後の問題
- 運用上の問題
おし葉製作法の改良
携帯用植物乾燥機について
- 冨樫板
- 加圧法
- 加熱法
- 標本製作中の注意と標本の出来具合
- 研究室での使用法
教具教材としての植物パウチカード
生植物のラミネート標本
日本植物分類学文献目録・索引のデータ仕様と検索項目 [英文]
シンポジウム「標本データベースの将来」の感想
- Herbariumの体制
- 大学と博物館の違い
- どうやるか
- データベースを作ったあと
- 画像データベース
第三部 ナマエ・データ・ヒト
吉村衛氏による科の和名の新提案
命名規約とオフセット印刷
デチンムル科
「野草」に現れた植物の新名
新和名提示のいろいろなかたち
「ナマエ」を考える
モノの見え方について
東京消失
地名データベースの活用
- 住吉小学校の「住吉」研究
- 住吉小学校はいくつあるか
- 住吉神社はどのくらいあるか
- 住吉という地名はどうだろう
- IT化時代の学習
新日本地名索引の内幕
新日本地名索引のはなし
- どんなものか
- どうやって作ったか
- 索引のスタイル
- よみの問題
- 分布地図
- 「鐙」の分布
- JIS漢字表の問題
学術用語集植物学編(増訂版)の分類学用語改善のための資料
- 形を表す用語
- 花を表す用語
データベース仕様と植物学・動物学・農学に共通な植物用語
- データベース仕様
- データベース作成の方法
- 調整を要する用語の方針と方法
保育社・原色日本植物図鑑の観察
Index Kewensis 展開版前文
ネパールの本草書ビル・ニガントゥについて
岩槻邦男氏にエジンバラ公賞
英語教科書に載った西岡京治氏
大村敏朗氏の貢献
原寛博士への弔辞・追悼文
- 弔辞
- はじめてのヒマラヤ
若き日の原寛博士の日記
津山尚博士
「訓導」原襄さんの思い出
里見信生さんの思い出
里木村陽二郎先生
山崎敬さんの思い出
第四部 書を評す
地図・地名
- コンサイス地名辞典日本編
- 現代日本地名よみかた大辞典 1-6巻
- 知っておきたい災害と植物地名
- 日本湿地目録
- 日本山名総覧
- FD日本山名総覧「全国版」
- 数値地図 25.000(地名・公共施設)全国CD-ROM版
学名・用語など
- 植物学ラテン語辞典
- 国際植物命名規約1988
- 植物学名詞
- 菌学用語集
- 植物学名大辞典
- 植物の名前のつけかた植物学入門
- 日本苗字大辞典
- 図説植物用語辞典
- 国際栽培植物命名規約第7版
フィールドワーク
- 清瀬の自然フィールドガイド春
- 東京西郊野外植物の観察
- GPS全日本ロードマップ
- ヨコハマ植物散歩
- 東京樹木めぐり
- 巨樹・巨木
- ぐるっと日本列島野の花の旅
- 続巨樹・巨木
- 地べたで再発見「東京」の凸凹地図
- 東京大学本郷キャンパス案内
- 雷竜の花園
- 秘境・崑崙を行く
- 中国秘境に咲く花
- 青いケシの咲くところⅡ
- シルクロードに生きる植物たち
- ヒマラヤを越えた花々
- 幻の植物を追って
- ロンドンの小さな博物館
- ヒマラヤに花を追う
- ヒマラヤの青いケシ
人
- 白井光太郎著作集
- 進野久五郎植物コレクション
- 来し方の記8
- 横内齋著作集2
- 李永魯文集
- MAKINO80『植物同好会』八十年の歩み
- しだとこけ 服部新佐先生追悼記念号
- 小泉秀雄植物図集
- 籾山泰一先生論文集
- 私の研究履歴書-昭和植物学60年を歩む- [林孝三]
- 命あるかぎり-花と樹と人と-見明長門追悼集
- 中尾佐助文献・資料目録
- 牧野晩成
- 沼田真・著作総目録
- 牧野富太郎とマキシモヴィッチ
- 牧野富太郎著・植物一家言
- 誰がスーリエを殺したか1
- 展望河口慧海論
- 「イチョウ精子発見」の検証
- 牧野富太郎植物採集行動録
- 大雪山の父・小泉秀雄
- 大場秀章著作選Ⅰ
- 大場秀章著作選Ⅱ
- 小原敬先生著作集
- 植物文化人物事典
- 清末忠人研究集録
- 自然と教育を語る
文化
- 現代文明ふたつの源流
- 栽培植物の起源と伝播
- 江戸時代中期における諸藩の農作物
- 日本の植物園
- アジアの花食文化
- いのちある野の花
- 江戸参府随行記
- ボタニカルモンキー
- 菌類認識史資料
- 植物学と植物画
- 黒船が持ち帰った植物たち
- 日本植物研究の歴史
- 植物園の話
- バラの誕生
- 絵で見る伝統園芸植物と文化
- 江戸の植物学
- 現代いけばな花材事典
- 花の男シーボルト
- サラダ野菜の植物史
- すしネタの自然史
- シーボルト日本植物誌 文庫版
地域・フロラ
- 環境アセスメントのための北海道高等植物目録Ⅳ
- 宮城県植物目録 2000
- 秋田県植物分布図
- 秋田県植物分布図第2版
- 茨城県植物誌
- とちぎの植物Ⅰ,Ⅱ
- 日光杉並木街道の植物
- 渡良瀬川支流山塊の高等植物 類似植物の見分け方ハンドブック
- 渡良瀬川支流山塊の高等植物
- 群馬の里山の植物
- 群馬県タケ・ササ類植物誌
- 群馬県植物誌改訂版
- 館林市の植物
- 尾瀬を守る
- 1998年版埼玉県植物誌
- さいたまレッドデータブック
- 千葉県植物誌
- 千葉県の自然誌
- 富里の植物
- 続江東区の野草
- 小笠原植物図譜
- 神奈川県植物誌分布図集
- 横浜の植物
- Yato横浜 新治の自然誌
- 箱根の樹木
- 新潟県植物分布図集第6集
- 新潟県植物分布図集第7集
- 新潟県植物分布図集第10集
- 新潟県植物分布図集第1-10集登載植物および索引
- 石川県樹木分布図集
- 加賀能登の植物図譜
- 金沢大学薬学部付属薬用植物園所蔵標本目録 白山の植物
- 信州のシダ
- 長野県の植生
- 長野県植物研究会誌第20号
- 長野県版レッドデータブック維管束植物編
- 長野県植物ハンドブック
- 伊部谷の植物
- 植物への挽歌
- しなの帰化植物図鑑
- 37人が語るわが心の軽井沢1911-1945
- 近畿地方の保護上重要な植物
- 改訂・近畿地方の保護上重要な植物
- 近畿地方植物誌
- 高山市の植物
- 改定三重県帰化植物誌
- 兵庫県の樹木誌
- ひょうごの野生植物
- 播磨の植物
- 平成元年度箕面川ダム自然回復工事の効果調査報告
- 六甲山地の植物誌
- 淡路島の植物誌
- 奈良公園の植物
- 岡山県スゲ科植物図譜
- 広島県文化百選 花と木編
- 広島市の動植物
- 山口県の植物方言集覧
- 山口県の巨樹資料
- 徳島県野草図鑑〈下〉
- えひめの木の名の由来
- 福岡県植物目録 第2巻
- 熊本の野草〈上〉〈下〉
- 熊本の木と花
- 鹿児島県の植物図鑑
- 改訂鹿児島県植物目録
- 沖縄植物野外活用図鑑全6巻
- 沖縄県の絶滅のおそれのある野生生物
- 琉球列島維管束植物集覧
- 孤島の生物たち-ガラバゴスと小笠原
- ブラジル産薬用植物事典
- キナバル山の植物
- 韓国産松柏類
- 韓国植物検索便覚
- 韓国植物分類学史概説
- 中国人民共和国植被図
- 中国天山の植物
- 雲南の植物
- 雲南の植物
- 東北葯用植物
- ヒマラヤの自然誌
- ヒマラヤ植物大図鑑
- ネパール研究ガイト
- スイスアルプスの植物
調べる
<環境>
- 屋久島原生自然環境保全地域調査報告書
- 昭和63年度レアメタル賦存状況調査報告書
- 帰化植物のはなし
- レッドデータプランツ
- 植物からの警告・生物多様性の自然史
- エコロジーガイド・ウェットランドの自然
- 植物群落レッドデータブック
- 日本森林紀行
- 温暖化に追われる生き物たち
- 水生シダは生きる
- 侵略とかく乱のはてに
- 各都道府県別の植物自然史研究の現状
- 日本の絶滅危惧植物図譜
- 絶滅危惧植物図鑑レッドデータプランツ
<種類>
- 新しい植物検索法 離弁花類編
- 日本タケ科植物総目録
- 新しい植物検索法 合弁花類篇
- 北日本産樹木図集
- 動植物目録
- 日本件名図書目録⑨ 動・植物関係
- 山野草植物図鑑
- 植物目録
- 日本の高山植物
- 世界の針葉樹
- 検索入門樹木
- 葉による野生植物の検索図鑑
- 英語表現べからず辞典
- 日本イネ科植物図譜
- 改訂増補 牧野日本植物図鑑
- 日本の自生蘭
- 北本州産高等植物チェックリスト
- 日本水草図鑑
- 日本草本植物根系図説
- 日本のスミレ
- 日本で育つ熱帯花木植栽事典
- 植物の系統
- 日本タケ科植物図譜
- 日本の野生植物 コケ
- 日本花名鑑1
- 樹に咲く花 合弁花 単子葉 裸子植物
- 高山に咲く花
- 日本花名鑑2
- 日本の帰化植物
- ツバキとサクラ
- カエデの本
- 新日本の桜
- 日本のスゲ
- 日本の野菊
- 日本花名鑑4
- 日本海草図譜
<観察>
- 花と昆虫
- 樹木
- 平行植物
- 描く・植物スケッチ
- 植物観察入門
- 野草 1-15巻+別巻
- 折々草
- みどりの香り 青葉アルコールの秘密
- 誰がために花は咲く
- 草花の観察「すみれ」
- 人に踏まれて強くなる雑草学入門
- 花生態学入門 花にひめられたなぞを解くために
- ブナ林の自然誌
- 原寸イラストによる落葉図鑑
- 人里の自然
- 虫こぶ入門
- 森のシナリオ
- シダ植物の自然史
- 花と昆虫がつくる自然
- 文明が育てた植物たち
- 雑草の自然史
- セコイアの森
- 植物の私生活
- ツリーウォッチング入門
- 根も葉もある植物談義
- 花の観察学入門
- 野の花山の花
- ため池の自然
- 花と昆虫 不思議なだましあい発見記
- 道端植物園
- タンポポとカワラノギク
- どんぐりの図鑑
- 植物のかたち
- せいたかだいおう-ヒマラヤのふしぎなはな
- コケ類研究の手引き
- 虫こぶハンドブック
- 虫こぶ入門
- ひっつきむしの図鑑
- 樹木見分けのポイント図鑑, 野草見分けのポイント図鑑
- 植物生活史図鑑Ⅰ, Ⅱ
- 絵でわかる植物の世界
- 「野草」総索引
- 「野草」植物名総索引 第1巻~第70巻
- 標本をつくろう
- わたしの研究 どんぐりの穴のひみつ
- どんぐり見聞録
- ほんとの植物観察, 続ほんとの植物観察
- キヨスミウツボの生活
- 発見!植物の力1~10
- 帰化植物を楽しむ
- 花からたねへ
- 植物と菌類30講
<標本>
- 自然史関係大学所蔵標本総覧
- 国立科学博物館蔵書目録和文編
- デジタルミューゼアム
- 牧野植物図鑑の謎
- Systema Naturae 標本は語る
- 牧野標本館所蔵のシーボルトコレクション
- 牧野標本館所蔵シーボルトコレクションデータペース CD-ROM版
洋書
- Manual for Tropical Herbaria, Regnum Vegetabile
- The Asiatic Species of Osbeckia
- Biological Identification with Computers
- A Geographical Atlas of World Weeds
- Neo-lineamenta Florae Manshuricae
- Atlas of Seeds Part 3
- Alpine Flora of Kashmir Himalaya
- Botticelli's Primavera
- Index to Specimens Filed in the New York Botanical Garden Vascular Plant Type Herbarium
- Elsvier's Dictionary of Trees and Shrubs
- Medicinal Plants in Tropical West Africa
- Fodder Trees and Tree Fodder in Nepal
- Nepal Himalaya, Geo-ecological Perspectives
- Leaf Venation Patterns
- Development amid Environmental and Cultural Preservation
- The Lilies of China
- Kew Index for 1986
- Catalog of Moss Specimens from Antarctica and Adjacent Regions
- The mountains of Central Asia
- Trees of the southeastern United States
- A New Key to Wild Flowers
- Flora of upper Lidder Valleys of Kashmir Himalaya
- Systematic Studies in Polygonaceae of Kashmir Himalaya Vol.1
- Flowers of the Himalaya, a Supplement
- Plant Taxonomy and Biosystematics, 2nd ed.
- Plant Evolutionary Biology
- Lilacs, the Genus Syringa
- Ornamental Rainforest Plants in Australia
- Forest Plants of Nepal
- Plant Taxonomy, the Systematic Evaluation of Comparative Data
- Woody plants
- The Evolutionary Ecology of Plants
- The Forest Carpet
- Cryptogams of the Himalayas Vol.2., Central and Eastern Nepal.
- Pattern Formation in Plant Tissues
- Plant Genetic Resources of Ethiopia
- Leaf Architecture of the Woody Dicotyledons from Tropical and Subtropical China
- Palaeoethnobotany
- A Bibliograpby of the Plant Science of Nepal
- C.P. Thunberg's Drawings of Japanese Plants
- Temperate Bamboo Quarterly 2
- Index of Geogrphical Names of Nepal
- A Revision of the Genus Rhododendron in Japan, Taiwan, Korea and Sakhalin
- A Bibliography of the Plant Science of Nepal. Sipplement 1
- The Iceman and His Environment, Palaeobotanical Results
- The Cambridge Illustrated Glossary of Botanical Terms
- Handbook of Ayurvedic Medicinal Plants
- Ethnobotany of Nepal
- Himalayan Botany in the Twentieth and Twenty-first Centuries
- Meristematic Tissues in Plant Growth and Development
- Proceedings of Nepal-Japan Joint Symposium on Conservation and Utilization of Himalayan Medicinal Resources
- The Orchids of Bhutan
- Beautiful Orchids of Nepal
書籍詳細
-
元・国立科学博物館 金井弘夫 著
菊判 / 上製 / 904頁/ 定価15,715円(本体14,286+税)/ ISBN978-4-900358-62-1
〔花の美術館〕カテゴリリンク
- 第20回 『熱帯植物巡礼』
- 第19回 小山鐡夫追悼記念号『黒船が持ち帰った植物たち』より
- 第18回 小山鐡夫追悼記念号『植物園の話』より
- 第17回 『MAKINO 80』東京植物同好会・牧野植物同好会八十周年記念誌
- 第16回 ハマナスの語源を探る
- 第15回 金井弘夫追悼記念号『金井弘夫著作集 植物・探検・書評』より
- 第14回 『花のある風景』
- 第13回 坂嵜信之追悼記念号『日本で育つ・熱帯花木植栽事典』より
- 第12回 楽しい花観察108選『不思議な花々のなりたち』
- 第11回 川島榮生の《ヤマアジサイの世界》
- 第10回 渡辺健二『日本産ギボウシの世界』
- 第9回 『ユリノキという木』─ 魅せられた樹の博物誌
- 第8回 『北米インディアン悲詩』/ エドワード・カーティス写真集
- 第7回 江戸時代の花たち 書物に見る江戸時代の園芸文化
- 第6回 わが国初のボタニカルアーティスト 五百城文哉(いおきぶんさい)の世界
- 第5回 『ビル・ニガントゥ』 19世紀末ネパール秘蔵の本草図譜
- 第4回 植物画家 石川美枝子の作品
- 第3回 サイエンティフィック・イラストレーター 木村政司の作品
- 第2回 植物画家 中島睦子の作品
- 第1回 『PLANTAE ASIATICAE RARIORES』