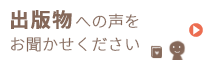モノの見え方について
ナマエを作ったり変えたり数えあげたりするより、ナマエの箱の中にいろんなものを放り込もうという私の説に賛成するとしても、一体何を入れればよいか、とまどう人も多いようだ。我々の見ている植物体はもう何もかもわかってしまっていて、微視的な見方を除けば調べることはなく、生態的な見方とか、どこに生えているとか、いつどうしたとかいうことにしか観察対象が無いと思っている人が、意外と多いのではなかろうか?そんなことは全然ないのであって、見て記録してゆくと、これ迄十把ひとからげに教科書で教わった(あるいは自分が現に教えている)形態学的事実でさえ、どうもそればかりではないらしいということがいくらもありそうである。そんな中から話の種を提供しておくのも、無駄ではあるまい。私自身こういうことを突込んで調べているわけではないので、他人のうけ売りや、ちょっと見ただけというものばかりだから、流し読みして、面白そうなら自分で調べていただきたい。多くは科学博物館へよせられる質問に発端がある。
「ヘチマのつるは右巻きか左巻きか?」ときかれたことがある。教科書会社が小学校向けの本にのせるのだそうだ。私の反問は「そんなクダラないことを、何故小学校で教えねばならないのか?」である。会社のコモンのえらい先生が、こういう基本的なことは早く教えるべきだというのだそうだ。私は回答しないことにした。つるの巻さ方には2通りあることはわかっていた方がよいだろうが、これは実は、あらゆるラセンの巻き方が2通りあるということであって、植物のテーマではない。ましてそれが右巻きか左巻きかということは、ナマエのつけ方の約束だけの問題であり、特に植物では確定しておらず、本質的な問題とは思われない。うっかり返事をすると「科博の先生がこう云った」と権威づけに利用されるだけだろう。会社の云うには「右か左かということのクダラなさはお説の通りかも知れないので、テキストを検討する。しかし、さし図をかくのに、どういう風に巻きついているのか知りたい」ということになった。時は冬の最中で、外へ行って見てこいと云うわけにはゆかない。ウリ科種物だから、つるは途中で反巻するだろうが、そもそもの始めのまきつき方がどうなっているのか私は知らない。そこで亘理氏の植物写真集だの、朝日植物百科だのをのぞいてみたが、どうもハッキリしない。そのうち「ヘチマのつるはみな同じ方向に巻く」のかどうかも心もとなくなって来た。へチマの巻きひげは基部で2〜5本に分かれている。もし異なる方向に巻くのなら、つるの位置と巻き方と関係があるのではないか?こんなことを考えたのだが、いざ確かめようとすると、なかなか適当な場面に行き当たらない。そのうちに時期が過ぎて、2・3年たってしまった。
今度この作文を書くので、近所に植えてあるのをつまんで来て調べたのだが、図1の通りで決まった巻き方などありそうにない。そのうえ、1本のつるの途中で何度も逆転が起こっている。「巻きひげは途中で1回巻き方が逆転しており、これはつるが一方向にのみねじられてねじ切られてしまわない合理的な方法だ」とよく書かれているが、こう何度もでたらめに逆転しているのをみると、それほど「理性的」とは思えなくなった。
[野草47(377):66-68(1980)]
(2)
「アサガオのつるは左巻き」というのが、近頃の大勢のようだ。その根拠は「生長方向から見て先端が時計廻りの方向にのびて行くのが右巻き」という定義による。一方、巻貝では「生長方向へ向かって時計方向に巻くのが右巻き」である。巻貝の見方でアサガオを見ると、これは右巻きである。つまりこういう定義のし方では、視点を変えるとナマエが違ってしまうのである。どちらにせよ「これこそ本質的で変えようがない」という確固たる根拠があるのならそれはそれでよいのだが、これは単なる申し合わせにすぎない。悪いことに、違うと云っても2通りしかないものだから、ひとつ違うと天地がひっくり返ったような大事件に感ぜられてしまう。こういう「感じ」が、この現象を「基本的」と思わせる理由なのだろう。
もし巻いた茎の一部分だけ持って来られると、芽のつき方や毛の生え方などで生長方向がわからない限り、どっち巻きか決められない。同様に、図1Bのように針金を巻いたラセンに矢印をつけたものは、Aの方から見ると(巻貝の見方)右巻き、Cの方から見ると(アサガオの見方)左巻きとなり、矢印をとり去ってしまうとどっちか決められないことになる。ところが、少しでも機械をいじったことのある人なら、矢印が無くともこのラセンは右巻きであると直ちに云うだろう。ということは、別な定義のし方があるということである。それは「右ネジと同じラセンは右巻き」というものである。これだと「生長方向」だの「時計廻り」などという高度の判定要素は必要なく、どこにでもころがっているネジとくらべればよいし、見る方向や角度でナマエが変わることもない。
ラセンというものは大変面白い研究テーマで、古来いろいろと論じられているが、巻き方のナマエのつけ方には何の根拠もあるわけではない。要するに、ふつうの人間の心臓のある側を何故左倒と云わねばならないかという問題と同じで、議論しても決着はつかないのである。何故そうなのかをここで論ずるのは『野草』にふさわしくないが、ガードナー『自然界における左と右』(坪井・小島訳 紀伊之国屋書店[紀伊国屋書店])という本があるので一読をおすすめする。木原均氏もこの問題に興味をもたれ、いろいろ論説したり実験されたりしておられる。例えば実験ではコムギの葉序のラセンの向きは、発芽の際に種子がどっちの側(種子にも前後左右がある)を下にして横たわっていたかで決まることを示している。またラセンの名付け方についてもネジとの対比に言及している。ラセンの名付け方については私もネジとくらべるのが最も簡単だと思うので、今後は従来の名付け方にとらわれず、断りなくネジの左右と同じ呼び方を用いる。つまりアサガオは右巻きである。「あまりいろいろな定義を出されても、単に右巻き左巻きと云った場合、どの定義によっているのかわからないで困る」と文句が出るに違いない。ここでも植物におけるナマエの問題と同じように、ナマエに著者名を付けないと解釈がわからないというようなことが起こるのである。だが、今の場合にはナマエを用いないで「右ネジと同じ巻き方」と云えば片付いてしまうだろう。
「生物学は遅れているから、こういう基本的なことがいつ迄も決まらない。そこへゆくと工学や物理化学は…」などと感心しなくてもよい。例えば旋光性だが、これは「平面波が進行方向から見て時計廻りに廻るのが右旋性」となっている。「アサガオは左巻き」と同じ決め方で、実際には右旋性の平面波が作るラセンは左巻きなのである。とにかくすべての立体ラセンの巻き方は、これで簡単に定義される。
ラセンの巻き方の名付け方は、これでみんな片付いたかというとそうではない。蚊取線香の巻き方はこれでは決められない。というのは、蚊取線香は裏返すと逆の巻き方になってしまうからである。高気圧周辺の風向は右巻きといわれる。これは天気図上、つまり地球を外から見下ろした時の話であって、地上からこれを見上げれば、風の作る渦は左巻きである。それどころか、「犬のシッポは上巻き」と云うことさえできる。たとえば、サルトリイバラの巻きひげがまだ若くて、巻きつく相手に出合っていない時などは、こういう呼び方をしても文句は云えないだろう。
[野草47(378):82-83(1980)]
(3)
植物において平面ラセン的なものに、花弁の重なり方がある。例えばAのような重なり方があると、ふつうは右巻きと呼ばれる。その定義は「花弁上を指でなぞって行って、反対側へぬけ出てしまわないような方向が時計廻りなら右巻」である。この花をつけ根から切って裏からなぞっても元通り右巻きで、蚊取線香のように逆にはならない。ところがこの花がつぼみの時に上の定義をあてはめると、これは左巻きということになる。
こういう違いは花式図を描いてみると理解し易い。(図−1)Aの並び方はCに相当する。花弁の並びをなぞるということは、その内側をなぞることである。つぼみをなぞるということは、外側をなぞることなので、向きは逆になる。花を裏返しにするということはDの図になるが、それをなぞることは外側をなぞることなので、逆の逆となって元と同じ巻き方ということになるのである。本来は同じラセン配置なのに、見方によって見え方が違ってしまうような定義のし方では、この種の現象の記録には不適当である。「花の開いたところを標準にして、常に上から見ることにすればよい」とする意見は強いだろうが、私には賛成できない。というのは前回で述べた通り、「上」だの「生長方向」だのというファクターは必ずしも対象に具わっているわけではなく、またあっても判断しにくいことがある。そのうえネジとくらべるという簡単明瞭な、しかも共通性の高い決め方があるからである。例えばアオミドロの葉緑体や、レンコンの糸の巻き方などは、こうでもしなければ決めようがあるまい。ついでながら、アオミドロの葉緑体を顕微鏡と虫めがねを用いて見たとき、両者の像は逆の巻き方に見える筈である。
花の諸器官は葉の変形であると教えられて来た。つまり、非常に短縮した茎に変形した葉がたくさん着いているということである。そうすると、葉の並び方(葉序)と同じ見方で花被の並び方をとらえられないだろうか?葉序は最も認識しやすいラセンなので、これと同じに解釈できれば記録にも理解にも楽なことだろう。1つそういう見方を試みてみよう。
その前に、記録に欠かせない用語について検討しておかねばならない。AやBはふつう回旋状とか片巻きとか呼ばれ、convolute(convoluta)という述語が当てられているが、Stearn『Botanical Latin』やDaydon&Jackson『Glossary of Botanical Terms』を見ると違う。AやBはtwisted(torsiva)と呼ぶべきで、これに対する日本語が存在しないようである。twistedはAやBの配置で、かつ花被にゆがみが無いものに用いられる。花被がゆがんでいるとcontorted(contorta)と呼ぶ。convoluteというのは1つのものが他のものを完全に巻き込む場合で、Eのようなものである。(図−2)その例として、アブラナ科のニオイアラセイトウ(Cheiranthus)やエゾスズシロ(Eythimum)の花弁があげられている。この他にも、我々が普通に用いられている形態用語には、本来のそれと異なった解釈で用いられているものがあることは、その都度注意することにしよう。ついでに云うと、「花被の重なり方」にはaestivationという語が用いられているが、この単語にはこの他に「芽の中の葉のたたまれ方」、「夏眠」などいろいろに用いられ、しかも「花被の重なり方」を意味する日本語の述語が無いのである。「葉のたたまれ方」に対して葉層、芽層、幼葉態などという語があり、「葉の並び方」に対しては葉序という立派な用語があるのにくらべると何とも淋しいことである。つまりあまり研究対象にされたことがないということなのだろう。
さて、葉序と同じ見方で花弁の重なり方を見るとどうなるか?先のA、Bは後廻しにした方が都合がよいので、かわら状(imbricate…これも後で説明し直さねばならない)の5弁花をとり上げる。まずどれか1番下に来る花弁を基準とし、これを1と名付けておく。(図−3、F)5枚の花弁が等しい角度で並ぶには1/5、2/5、3/5、4/5の4通りがあるが、4/5は1/5の逆廻り、3/5は2/5の逆廻りと思えばよいから、1/5と2/5だけ考えればよい。この内1/5はA、Bに似てくるので、後廻しにする。
さて右廻りのみ2/5だと、2番の花弁の位置はGのようになり、続いて3、4、5を加えるとそれぞれH、Ⅰ、Jとなる。こういう花冠では「指でなぞって裏側へ出ない」などという定義では調べようがないので、どっち巻きなどという問題は意識にのぼらないが、ちゃんとラセン配列として説明がつく。この配置は左ラセンとしても説明できる。1から始めて前と反対方向へ角度を3/5ずつとればよいのである。葉序でも同様に2通りの解釈ができる。こういう場合、「分子の小さい方をとる」と決めておけば一義的に決まる。
[野草48(379):2-4(1981)]
(4)
Jの並び方は2/5の葉序を押しつぶしたものと同じである。花式図で示せばKである。注意すべきは、いくら押しつぶされても花被のつく位置(節)の上下関係は保存されていることである。換言すれば、花被の発生に時間的な前後関係があることになる。
ところでこういう配列を何と呼ぶのだろうか?「かわら状」(imbricate)と何の気なしに呼んでいるだろう。ところが、大井『日本植物誌』や広川書店『最新植物用語辞典』ではimbricateはLのように示されている。Kでは1番下(外側)に来る花弁が2枚あるが、Lでは1枚しかない。imbricateというのは、1番外側と1番内側が1枚ずつのものをいう。つまりLである。「かわら状とは、花弁の隣同士との関係が、一方は上に、他方は下にあるような配列」と説明されている本が、我が国のにも外国のにもあるが、これではAかB(前回参照)になってしまうから、誤っていると云わねばならない。ところが、花弁数が5枚でなく、多数になるとこの定義は生きてくる。キク科の総苞片の並び方などは、明らかにこの意味での「かわら状」(imbricate)なのである。
さてKの並び方は何と呼ばれるか?quincuncialという聞きなれぬ術語を用いねばならない。久内清孝氏の御教示によると、この訳語として三輪・池田『植物用語新辞典』(1942)に交互覆瓦襞、五点性というのがあるとのことである。また佐竹『植物の分類』では梅花状となっている。いずれにしても聞いたことのある人は少ないだろう。五弁花の最も普通な並び方に対してこれである。
次にAやBのでき方の説明を試みよう。図を見ると1/5の葉序を押しつぶせばできそうである。試しにやってみると、Mのように今までとは異なったものとなる。MとCとでどこが違うかというと、1と5の重なり方だけである。Mをながめると先のimbricateの定義にあてはまることがわかる。従ってこれはimbricate「かわら状」と呼ぶべきだろう。ところが同じかわら状でもLとMは明らかに違うのに、これらを区別する術語が無いのである。
さて、MとCの違いは花弁1と5の重なり方の違いだけなのだが、これはささいな問題ではない。これ迄の話では、花被がつく節の上下関係が保存されることを前提とし、花被の重なり方はそれを表すものと解釈して来た。だから、Mの1と5は隣り合っていても、実際は5レベル違っていることになる(図N)。Cのように5が1の外側に来るためには、両者が同レベルか5の方が下位に位置しなければならない。下位にするのは無理だから同レベルと仮定すると、他の2、3、4の花弁も1、5と同レベルということになる。つまりAやBの5枚の花弁は、1/5の互生に由来するのではなく、すべて1つの節から出た輪生と考える方がよいことになる。(図O)換言すれば、発生に時間的前後関係がないと考えるのがよいのだろう。ラセン配置の説明としてとりつき易かったAやBには、実はラセン配置は無かったということになる。
[野草48(380):18-20(1981)]
(5)
「twisted(torsiva)やcontorted(contorta)は輪生に由来する」という解釈は、これだけで済ませるわけにはゆかない。もしOのように同じレベル5ケ所で同時に発生が起こり、花被片がそれぞれ横に成長すれば当然隣同士がぶつかることになる。その時どちらが外になるか内になるかは、偶然に支配されると考えるのが自然だろう。ぷつかる場所は5ケ所あるから、Cのようになる可能性は2の5乗回に1回(1/32)である。従ってある種の花がすべてCのような配置になるということは、それが偶然の結果とは考えられないので、何か説明を与える必要がある。私はPのように原基から発生が両側に一様に進むのではなく、Qのように片側へだけ(あるいは両側へ不平等に)進む結果だろうと推察している。野草同人には形態学専攻の方もおられるので、ぜひ御意見をうかがいたい。
それから、2/5の配置のところで示したquincuncial(梅花状)は、ラセン配列ばかりでなく、輪生配列からも偶然できることがある。だから梅花状だからこれは2/5配列のラセンに由来するのだと直ちに云うことはできない。こういうことを調べるには量を統計的にこなした観察が必要なのだが、こういう簡単なことがらでもちゃんと調べた人がないらしい。統計というとたくさん調べて何%とやれば片付くと思っている人が多いが、出た結果の解釈はなかなかむずかしい。この間題によく似た現象の観察が『採集と飼育』1977年9月号に報告されているが、現象aの出現数44、現象bの出現数64に対して、aとbは明らかに差があると結論されている。私はこの数値ではaとbに差があるとは云えない場合もまだあると思うのだが…。
一方、Pのような発生のし方をしてぶつかると、重なり合うものができる一方、互いに道をゆずらずに押し合ったままになったり、同じ方向に曲ったりする場合も起こるだろう(R、S、T)。これが「すり合せ状」(valvate)で、ブドウ科、フトモモ科、センニンソウ属などに例がある。この中でTのようなものはありそうに思えなかったが、カミさんが買って来たBubaliaのつぼみを見たら正にこれだった。
[野草48(381):34-35(1981)]
(6)
前回、5花弁の重なり方は32通りあると云った。重なりが起こる個所が5つあってそれぞれ2通りの重なり方があるから、2⁵で32通りである。もしある植物の花を観察の結果、これら32通りが一様に出現するならば、花被片の重なり方は偶然が支配するとみてさしつかえなかろう。これを確かめるには、これらの組み合わせの見本を作っておいて、実際とくらべればよい。32通りも作るのはシンドイと思うだろうが、やってみると大したことではない。使宜上見方を変えてやってみる。
まず5花弁のうち、1番下(外側)に来る(左右側とも隣の花弁の下にある)花弁が1枚もない型を考える。これは1、2であり互いに対称である。これらは既にA、B(又はC、D)で示したものである。これ以外の組み合わせはこの型にはない。
次に1番下に来る花弁が1枚だけある型を考える。これには3、4、5、6の4通りがあり、3と4、5と6は互いに対称である。そして3とM、5とLは同じである。
次に1番下に来る花弁が2枚ある型を考える。これには7と8の互いに対称な配置があるだけである。次に1番下に来る花弁が3枚ある型を考える、と云ってもこれは存在しない。従って5枚の花弁のあらゆる重なり方はこの8型で尽きている。32通りある筈のものが8通りになってしまった理由は…、これは教学の問題なので『野草』誌上に出そうとしてもボツになるだろう。簡単に云えば、見かけ上異なっていてもクルリと廻すと上のどれかと一致してしまうのである。
上の議論は5枚の花弁がすべて対等であって、廻してみてもよいということが前提となる。しかしながら花には向軸側と背軸側がある。これは花と茎との関係で生ずるもので、花式図上では上方に黒点が1つと下方に苞葉の記号が1つ書かれている。これを考えに入れると、花をクルリと廻すわけに行かなくなって、話がむずかしくて私の手に余るので、そこまでは考えないことにしておく。
このような見え方を得る為には、花を図式としてとらえねばならない。「ありのまま」を見ていたのでは、こういうことは分かりにくいのである。よく観察法や描画法の要諦として「見たままを描く」ことが強調される。これはもちろん結構なことで、例えば花と虫の関係だとか、葉の先の関係などは、自然のままの展開のし方や配置を記録しなければ意味はない。しかしそれとは別にこういう図式化した見方があり、こうすると別な見え方をするものだということにも留意してもらいたい。『野草』に現れる観察記録や図の中にも、もう少し図式化した見方や描き方をすれば面白いのにと思うものがある。図式化ということは標準化、一般化することで、個々別々な観察結果をまとめたり比較したりするのに役立つ。それにこういう見方は、観察対象の質をそろえるということに注意を向けるのにも役立つだろう。質をそろえておかないで、いくら量を多くしても統計的な処理とは言えない。
何もわざわざそんな見え方をするような見方をしなくても、自然のままに見ていれば、そのうちわかる筈ではないかと思う人もいるだろう。別にそれに異議をとなえるつもりはないが、身近な例をあげておく。
ミニスカートが「よく見える」条件は、視線が水平面となす角度(視角と呼んでおく)が最大の限定要素である。少なくともこれが水平より上(プラス)でなければならない。もう1つの限定要素は視線の長さ(距離と呼んでおく)であるが、これは第二義的である。従って「自然のまま」の水平な道路では「よい見え方」を得ることは決してない。「よい見え方」を得るためには、観察者はある程度以上の勾配の坂や階段の下に立ち、明視の距離になるべく近く対象をとらえる必要がある。もし勾配が十分でなければ、距離をギセイに(長く)してでも視角を大きくする方がよい。こんなことは誰でも心得ている。
植物はミニスカートとちがって、手にとって好きなような見方をすることができる。「よい見え方」というのは1つしかないわけではなく、見る角度や考え方によってたくさんの「よい見え方」が生じるので、各自で工夫すればよいのである。ところで冒頭に述べた、花弁の重なり方が偶然に決まるような場合が実際にあるのかというと、「アル」と云ってよいことを最近の観察結果から知った。
[野草48(382):50-52(1981)]
(7)
かわら状(imbricate)には2通りあると話した。最外の弁と最内の弁が隣り合う場合と、間に1つ他の弁がはさまる場合で、前者は3、4であり、後者は5、6である。5、6についてはまだラセン配置による解釈を与えていない。実をいうと、これについてはラセンによる説明を見つけることができなかったのである。対称像については一方の説明がつけば他も同様に片付くから、5について考えてみる。5にはラセン配列による規則は認められないが、花弁1または4を通る対称面を考えることができる。1を通る面を考えるとき、3と4の重なり方は対称性を失なわせているのだが、どうせどちらかに重ならねばならぬのだから、1ケ所はガマンすることにしてもらおう。こうするとPやQのように、発生の時間的関係を示すモデルを作ることができる。即ちUである。これはマメ科の一部にあてはまるだろう。
こういうモデルを思いつくと、その変形がすぐ出てくる。即ちV-Zの5型で、Uを入れて全部で6型である。各型の1番手前の2枚の花弁の重なり方が2通りあるから、総計12型となる。このうち隣り合う弁の内外関係という点から見ればVとYは同じであり、WとZも同じである。この4つはquincuncialである。換言すれば、この4つは相称としてもラセンとしても説明できるということになる。Xは少々異なって見えるが、実際に弁の重なりを描いてみればUを廻してできる型と同じであり、最外と最内の弁の間に他の弁が1つはさまったimbricateである。Xの型はスミレがこれに当たるだろう。
[野草48(383):70-71(1981)]
(8)
花のことばかり書いたから葉のラセンのことも書こう。ハコベの葉序は十字対生といわれるもので、ある節につく一対の葉とその次の節につく一対とは90°をなしている。これでは右巻きも左巻きもわからない。ところが都合のよいことに、ハコベの茎には一列の毛条がある。この毛条は葉腋に始まって上の節の対生葉の間に終わる。こういう云い方については後で説明し直さねばならないのだが、とにかくこうして対生葉が90°ずつズレるのに伴って、毛条も同じようにズレて行く。毛条は茎の片側にしかないので対生葉がどっち向きにズレるかは毛条のズレに現れてくることになる。実際、毛条は節ごとに一方向にズレるラセンをなしている。このラセンの向きは茎のどの部分でも同じかというと、そうではない。
ハコベの茎の分枝の型は2通りある。1つは主茎があって腋生の枝が出るという関係がハッキリしている場合で、これをAタイプとする。越冬中のハコベを見るとこのやり方をしている。もう1つは春になって花をつける為に盛んに生長している時見られる型で、みかけ上二叉分枝をしており(偽叉分枝)、茎と枝の区別がつかないもので、これをBタイプとしておく。いずれの場合にも、分岐点で毛条がどこについているかを調べると、2本の茎(或いは茎と枝)の向き合った側にある。さっき「毛条は葉腋に始まり」と記したが、これは分枝しない節での観察であって、正しく云おうとすると「毛条は葉腋の反対側に始まり」とでもせねばならない。
分枝がないかAタイプの分枝が起こる限り、主茎上の毛条のズレは一定の方向を維持している。Bタイブの分枝ではどちらが主茎と云いかねるから、むしろ毛条のズレが同じ方向の枝を主茎(主軸)とみなしておこう。こうすると、「枝」の上の毛条のラセンの向きは分枝したところからは逆向きとなる。だから、ハコベの毛条は枝によって右巻きのと左巻きのがあることになる。
断っておくが、ラセンの向きが維持される方が主軸だと云っているのではない。そういうことはチャンと形態学的、解剖学的に調べてから云うべきである。私は一応そのようにみなして話を進めようというだけのことである。
こうして茎を上へたどると花序となるが、ここで少々ちがったことが起こる。花序では枝が3出するのである。その中央のものは必ず花となって終わる。(Cタイプ)両側の枝は更に同様な分枝をくり返して遂に花となって終わる。そして左右に出る枝では、茎における分枝で見られたのと同じ毛条のラセンの規則がくり返される。一方、中央の花梗にも一条の毛条が走っているが、これは直下の節間の毛条の位置をそのまま踏襲する。つまりどちらへもズレないのである。
こういうことを見たうえで、これを学校で習った形態学の知識にてらすとどうもうまく説明がつかない。
Bのような分枝は見かけ上二叉分枝であるが、この分枝法はシダ類以下の下等植物に広く知られているものの、高等植物には無いことになっている。イチョウの葉脈がその名残りとして引用されるくらいだろう。
高等植物の分枝法には単軸分我と仮軸分枚があると教えられている。前者は主軸が発達しながら枝も伸ばすもので、Dのようになる。主軸と枝が同等に発達すればFである。仮軸分枝は主軸の伸長が止まって枝のみが発達するもので、Eである。これが極端になるとGのように、枝が主軸の延長のような見かけになる。以上は互生葉の場合だが、これを対生葉にあてはめるとH〜Kである。ハコベのBタイプの分枝はⅠでもJでも考えられる。そのいずれであるかは節のところにかくされた発達しない主軸や枝の原基がどちら側についているかを調べればわかる筈である。そこで節部をそいでルーペで調べたが、原基らしいものはどこにも見つからなかった。もっと高度な調べ方をしないとわからないものらしい。A、B、Cが同じ分枝法に由来するのなら、CはⅠに対応するのだから、この2本の枝の問に原基が見つかりそうに思えるのである。それではと茎の太いカーネーションを買ってみた。この茎でも枝分れは2又で、1つは太く、他方はいく分細いのがふつうである。マアBタイプと云ってよかろう。この茎を縦切りにして節を調べたが、茎の上方の分枝のない節に、伸びるべき枝に当たる小さな芽がある以外には、目的としていたものは見つからなかった。もっとも、以前の観察では太い茎をはさんで細い枝と反対側の葉腋にごく小さな芽の原基がついているのを見た記憶がある。苞の上方の花に近いところだった。従って元来は両方の葉腋から芽が出るタイブなのに、種類によって一方の葉腋の芽が退化したものとも考えられる。現にフシグロなどでは両方の腋から枝が出ている。一方が退化すると云ってもデタラメではなく、退化する側が決まっていて、これも節ごとにラセンをなしてズレて行くのである。ハコベのように片方の葉腋には全く芽が作られないとなると、その節の一対の葉について別な解釈をする余地も出てくる。
アカネの葉は4輪生とされているが、実はこの中の一対は本当の葉であり、他の一対は本当の葉の托葉が癒合して出来たものだということだ。このことは枝の出る葉腋が決まっていることで傍証されるし、解剖学的には維管束の配置から確かめられるそうである。ハコベの葉は実は対生ではなく、1/4の互生であり、その托葉が癒合して反対側に同じ葉の形を作ったと考えることもできないわけではあるまい。もちろんこれを云う為には解剖学的に確証を挙げねばならない。しかしもしそうならば、節の一方の葉腋からしか枝が出ないということはむしろ当たり前のこととなる。ただしこう仮定するとCタイプの説明はむずかしくなる。
[野草48(384):86-89(1981)]
(9)
これまでゴタゴタ並べて来た5枚の花弁の重なり方には、実はチャンとしたよび名がついていないものがいくつかある。ナマエがついていなかったり、定義がはっきりしていないと、情報交換が正確に行なわれないということは、植物名のときと変わりはない。そこでこれらに名前を与えたものを図1に示す。図における「おもて」、「うら」のよび方は回旋状(おもて)、メタ瓦状(うら)のようにカッコをつけて用いることにする。「おもて」「うら」を区別する必要がない場合には、カッコの部分をつけなければよい。花式図の中心に記したⅠa、Ⅲbなどの記号は説明の使宜上つけた略号で、型の名前として与えたものではない。日本女子大の相馬レイ子さんの卒業研究に、この8型がいろんな植物でどんなふうに出現するか統計をとってもらった。中学生の自由研究なみだと馬鹿にしないでもらいたい。中学生と大学生のちがいはデータのとり上げ方と処理のし方による。とにかく大変面白い結果が得られたのである。この研究は完結したものではないのでまだ調べなければならないことが山ほどあり、アマチュアのとりつき易い研究テーマの1つだと思う。
[野草49(385):2-3(1982)]
『金井弘夫著作集 植物・探検・書評』コンテンツ一覧▼ 目次(青字)をクリックすると、各文をご覧いただけます
金井弘夫博士著作集に寄せて 東京大学名誉教授 大場秀章 / あとがき
第一部 時代の記憶・探険の記憶
最後の旧制高校生の自分史
理化館の焦げ茶のタイル
インドで見たこと聞いたこと
- はじめに
- 夏休みは4月
- 「古」新聞の値段
- 街頭の商人達
- 乞食
- ボクセス
- 良いお金と悪いお金
- 水
- お茶
- オナラ
- 立小便
- 近づくほど遠くなる
- 踏切に錠前
- 汽車
- バス
- 市電
- インド人という「民族」
- アッチャー
- タバコ
- お酒
- ビール
- ウイスキー
- ラム
- チャン
- マフア酒とヨーグルト
- 朝のお祈り
- 国境侵犯
- 二人のリエゾン・オフィサー
- シェルパたち
- アンプルパ
- トゥンドウ
- プルバ・ロブソン
- テンバ・シェルパ
- 女性たち
- ラマ教
- 山で一番こわかったもの
- お菓子
- 名前
- 宿屋
- インドの道の良さ
- フェリー
- 牛
- 交通法規
- カストムハウス
- 風呂
- 拍子木たたき
- バルカカナの日本人
- ボダイジュの借り倒し
- タテガミのあるブタ
- 封蝋
- 食いもの
- カースト(階級制度)
- デモ
- 鶏と卵
- 切符を買う
- 街路樹
- 事故
- インドの英語
再びインドの植物を求めて
- 悪路に悩む採集行
- ヒマラヤで見る段々畑
- 調査成果の一端
西北ブータンの山々
- 入国手続き、旅行許可など
- 入出国の経路
- 国内の輸送、通信、シェルパなど
- 物資の調達
- 気候
- 地図、コースについて
- チンプウ-トンサ
- 観察されたピーク
- 集落
- 通貨、賃金
フィニッシュの話
- 失せ物が出た
- 通関書類、フィニッシュ
- リエゾン・オフィサー、フィニッシュ
- ミソとストーブ、フィニッシュ
- スペース、フィニッシュ
- チニ、フィニッシュ
- サーダー、フィニッシュ
- ポーター、フィニッシュ
- 道路とジープ、フィニッシュ
- ブルカー、フィニッシュ
- 標本、フィニッシュ
- 道路、もうひとつのフィニッシュ
- シェルパ、フィニッシュ
- トラック、フィニッシュ
東ネパール調査(1963年)点描
- チャッシガレ!
- おまじない、ハチ
- 録音
- ハリー
- 食物
- こわいもの
ネパール通信1
- カトマンズ(1)
- フルチョウキ
- カトマンズ(2)
- チュリア・マハバラトの旅
- ゴサインクンデの旅
- ボダイジュのほこら
- カトマンズ(3)
- ロルカニの旅
- カトマンズ(4)
- チリメ、ランタンの旅
- チャンドラギリの旅
ビル・ニガントゥに見られる米の記事
ネパールの滝の数
ネパール通信2
- 自動車事故のはなし
- 創立記念パーティー
- カリンチョークの旅(1)
- インドラジャトラ
- カリンチョークの旅(2)
- チュリアの旅
ヒマラヤ植物調査の今昔
日本・ネパール協同植物調査史 1960-1980 [英文]
『冒険家族ヒマラヤを行く』訳者あとがき
パプア・ニューギニアの話
- 交通
- 食べ物
- 人々
- コトバ
- 古戦場
吉川英治文化賞受賞のことば
第二部 植物の観かた・残しかた
野外観察会のこと
日本植物の分布型に関する研究(2) ヒメマイヅルソウの分布型と変異
オゼコウホネの種子散布
ヤマモモの仁
クヌギの落枝
スベリヒユは対生
猪突猛進するチガヤの地下茎
ササの葉鞘
ケヤキの落葉現象はあったか
笹舟は沈む!
ミャンマーのドクウツギ属植物Coriaria terminalis Hemsley とその西限産地
ブータンのウルシ
植物の動きを見せる
尾瀬ケ原の池塘データベースによるヒツジグサとオゼコウホネの16年間の分布消長
群落の突然の交代
ツタの植物画
ツタの「雨」
国立科学博物館のサクラソウ生態展示
有毒植物を食べる
ミズバショウの果実の味
マムシグサのイモの「味」
ヌルデとネムノキは仲良し?
ビルマの植物学界の一端
部活動と自然観察会
普通な植物を記録しよう
ヒレハリソウ(ムラサキ科)の葉序
アイスマンの弓矢
ツュンベリーと日本のアマチュア植物学 [英文]
誰にでも利用できる標本のために
標本にはラベルを入れよう
標本ラベル論議へのながーいコメント
- 仮ラベルに関して
- 本ラベルに関して
- データベースに関して
ヒートシールによる標本貼付
おしば標本の新しい貼付法
おしば標本貼り付け用ヒートシールテープの自作法
移動式おしば標本棚の得失
- 改装工事前後の問題
- 運用上の問題
おし葉製作法の改良
携帯用植物乾燥機について
- 冨樫板
- 加圧法
- 加熱法
- 標本製作中の注意と標本の出来具合
- 研究室での使用法
教具教材としての植物パウチカード
生植物のラミネート標本
日本植物分類学文献目録・索引のデータ仕様と検索項目 [英文]
シンポジウム「標本データベースの将来」の感想
- Herbariumの体制
- 大学と博物館の違い
- どうやるか
- データベースを作ったあと
- 画像データベース
第三部 ナマエ・データ・ヒト
吉村衛氏による科の和名の新提案
命名規約とオフセット印刷
デチンムル科
「野草」に現れた植物の新名
新和名提示のいろいろなかたち
「ナマエ」を考える
モノの見え方について
東京消失
地名データベースの活用
- 住吉小学校の「住吉」研究
- 住吉小学校はいくつあるか
- 住吉神社はどのくらいあるか
- 住吉という地名はどうだろう
- IT化時代の学習
新日本地名索引の内幕
新日本地名索引のはなし
- どんなものか
- どうやって作ったか
- 索引のスタイル
- よみの問題
- 分布地図
- 「鐙」の分布
- JIS漢字表の問題
学術用語集植物学編(増訂版)の分類学用語改善のための資料
- 形を表す用語
- 花を表す用語
データベース仕様と植物学・動物学・農学に共通な植物用語
- データベース仕様
- データベース作成の方法
- 調整を要する用語の方針と方法
保育社・原色日本植物図鑑の観察
Index Kewensis 展開版前文
ネパールの本草書ビル・ニガントゥについて
岩槻邦男氏にエジンバラ公賞
英語教科書に載った西岡京治氏
大村敏朗氏の貢献
原寛博士への弔辞・追悼文
- 弔辞
- はじめてのヒマラヤ
若き日の原寛博士の日記
津山尚博士
「訓導」原襄さんの思い出
里見信生さんの思い出
里木村陽二郎先生
山崎敬さんの思い出
第四部 書を評す
地図・地名
- コンサイス地名辞典日本編
- 現代日本地名よみかた大辞典 1-6巻
- 知っておきたい災害と植物地名
- 日本湿地目録
- 日本山名総覧
- FD日本山名総覧「全国版」
- 数値地図 25.000(地名・公共施設)全国CD-ROM版
学名・用語など
- 植物学ラテン語辞典
- 国際植物命名規約1988
- 植物学名詞
- 菌学用語集
- 植物学名大辞典
- 植物の名前のつけかた植物学入門
- 日本苗字大辞典
- 図説植物用語辞典
- 国際栽培植物命名規約第7版
フィールドワーク
- 清瀬の自然フィールドガイド春
- 東京西郊野外植物の観察
- GPS全日本ロードマップ
- ヨコハマ植物散歩
- 東京樹木めぐり
- 巨樹・巨木
- ぐるっと日本列島野の花の旅
- 続巨樹・巨木
- 地べたで再発見「東京」の凸凹地図
- 東京大学本郷キャンパス案内
- 雷竜の花園
- 秘境・崑崙を行く
- 中国秘境に咲く花
- 青いケシの咲くところⅡ
- シルクロードに生きる植物たち
- ヒマラヤを越えた花々
- 幻の植物を追って
- ロンドンの小さな博物館
- ヒマラヤに花を追う
- ヒマラヤの青いケシ
人
- 白井光太郎著作集
- 進野久五郎植物コレクション
- 来し方の記8
- 横内齋著作集2
- 李永魯文集
- MAKINO80『植物同好会』八十年の歩み
- しだとこけ 服部新佐先生追悼記念号
- 小泉秀雄植物図集
- 籾山泰一先生論文集
- 私の研究履歴書-昭和植物学60年を歩む- [林孝三]
- 命あるかぎり-花と樹と人と-見明長門追悼集
- 中尾佐助文献・資料目録
- 牧野晩成
- 沼田真・著作総目録
- 牧野富太郎とマキシモヴィッチ
- 牧野富太郎著・植物一家言
- 誰がスーリエを殺したか1
- 展望河口慧海論
- 「イチョウ精子発見」の検証
- 牧野富太郎植物採集行動録
- 大雪山の父・小泉秀雄
- 大場秀章著作選Ⅰ
- 大場秀章著作選Ⅱ
- 小原敬先生著作集
- 植物文化人物事典
- 清末忠人研究集録
- 自然と教育を語る
文化
- 現代文明ふたつの源流
- 栽培植物の起源と伝播
- 江戸時代中期における諸藩の農作物
- 日本の植物園
- アジアの花食文化
- いのちある野の花
- 江戸参府随行記
- ボタニカルモンキー
- 菌類認識史資料
- 植物学と植物画
- 黒船が持ち帰った植物たち
- 日本植物研究の歴史
- 植物園の話
- バラの誕生
- 絵で見る伝統園芸植物と文化
- 江戸の植物学
- 現代いけばな花材事典
- 花の男シーボルト
- サラダ野菜の植物史
- すしネタの自然史
- シーボルト日本植物誌 文庫版
地域・フロラ
- 環境アセスメントのための北海道高等植物目録Ⅳ
- 宮城県植物目録 2000
- 秋田県植物分布図
- 秋田県植物分布図第2版
- 茨城県植物誌
- とちぎの植物Ⅰ,Ⅱ
- 日光杉並木街道の植物
- 渡良瀬川支流山塊の高等植物 類似植物の見分け方ハンドブック
- 渡良瀬川支流山塊の高等植物
- 群馬の里山の植物
- 群馬県タケ・ササ類植物誌
- 群馬県植物誌改訂版
- 館林市の植物
- 尾瀬を守る
- 1998年版埼玉県植物誌
- さいたまレッドデータブック
- 千葉県植物誌
- 千葉県の自然誌
- 富里の植物
- 続江東区の野草
- 小笠原植物図譜
- 神奈川県植物誌分布図集
- 横浜の植物
- Yato横浜 新治の自然誌
- 箱根の樹木
- 新潟県植物分布図集第6集
- 新潟県植物分布図集第7集
- 新潟県植物分布図集第10集
- 新潟県植物分布図集第1-10集登載植物および索引
- 石川県樹木分布図集
- 加賀能登の植物図譜
- 金沢大学薬学部付属薬用植物園所蔵標本目録 白山の植物
- 信州のシダ
- 長野県の植生
- 長野県植物研究会誌第20号
- 長野県版レッドデータブック維管束植物編
- 長野県植物ハンドブック
- 伊部谷の植物
- 植物への挽歌
- しなの帰化植物図鑑
- 37人が語るわが心の軽井沢1911-1945
- 近畿地方の保護上重要な植物
- 改訂・近畿地方の保護上重要な植物
- 近畿地方植物誌
- 高山市の植物
- 改定三重県帰化植物誌
- 兵庫県の樹木誌
- ひょうごの野生植物
- 播磨の植物
- 平成元年度箕面川ダム自然回復工事の効果調査報告
- 六甲山地の植物誌
- 淡路島の植物誌
- 奈良公園の植物
- 岡山県スゲ科植物図譜
- 広島県文化百選 花と木編
- 広島市の動植物
- 山口県の植物方言集覧
- 山口県の巨樹資料
- 徳島県野草図鑑〈下〉
- えひめの木の名の由来
- 福岡県植物目録 第2巻
- 熊本の野草〈上〉〈下〉
- 熊本の木と花
- 鹿児島県の植物図鑑
- 改訂鹿児島県植物目録
- 沖縄植物野外活用図鑑全6巻
- 沖縄県の絶滅のおそれのある野生生物
- 琉球列島維管束植物集覧
- 孤島の生物たち-ガラバゴスと小笠原
- ブラジル産薬用植物事典
- キナバル山の植物
- 韓国産松柏類
- 韓国植物検索便覚
- 韓国植物分類学史概説
- 中国人民共和国植被図
- 中国天山の植物
- 雲南の植物
- 雲南の植物
- 東北葯用植物
- ヒマラヤの自然誌
- ヒマラヤ植物大図鑑
- ネパール研究ガイト
- スイスアルプスの植物
調べる
<環境>
- 屋久島原生自然環境保全地域調査報告書
- 昭和63年度レアメタル賦存状況調査報告書
- 帰化植物のはなし
- レッドデータプランツ
- 植物からの警告・生物多様性の自然史
- エコロジーガイド・ウェットランドの自然
- 植物群落レッドデータブック
- 日本森林紀行
- 温暖化に追われる生き物たち
- 水生シダは生きる
- 侵略とかく乱のはてに
- 各都道府県別の植物自然史研究の現状
- 日本の絶滅危惧植物図譜
- 絶滅危惧植物図鑑レッドデータプランツ
<種類>
- 新しい植物検索法 離弁花類編
- 日本タケ科植物総目録
- 新しい植物検索法 合弁花類篇
- 北日本産樹木図集
- 動植物目録
- 日本件名図書目録⑨ 動・植物関係
- 山野草植物図鑑
- 植物目録
- 日本の高山植物
- 世界の針葉樹
- 検索入門樹木
- 葉による野生植物の検索図鑑
- 英語表現べからず辞典
- 日本イネ科植物図譜
- 改訂増補 牧野日本植物図鑑
- 日本の自生蘭
- 北本州産高等植物チェックリスト
- 日本水草図鑑
- 日本草本植物根系図説
- 日本のスミレ
- 日本で育つ熱帯花木植栽事典
- 植物の系統
- 日本タケ科植物図譜
- 日本の野生植物 コケ
- 日本花名鑑1
- 樹に咲く花 合弁花 単子葉 裸子植物
- 高山に咲く花
- 日本花名鑑2
- 日本の帰化植物
- ツバキとサクラ
- カエデの本
- 新日本の桜
- 日本のスゲ
- 日本の野菊
- 日本花名鑑4
- 日本海草図譜
<観察>
- 花と昆虫
- 樹木
- 平行植物
- 描く・植物スケッチ
- 植物観察入門
- 野草 1-15巻+別巻
- 折々草
- みどりの香り 青葉アルコールの秘密
- 誰がために花は咲く
- 草花の観察「すみれ」
- 人に踏まれて強くなる雑草学入門
- 花生態学入門 花にひめられたなぞを解くために
- ブナ林の自然誌
- 原寸イラストによる落葉図鑑
- 人里の自然
- 虫こぶ入門
- 森のシナリオ
- シダ植物の自然史
- 花と昆虫がつくる自然
- 文明が育てた植物たち
- 雑草の自然史
- セコイアの森
- 植物の私生活
- ツリーウォッチング入門
- 根も葉もある植物談義
- 花の観察学入門
- 野の花山の花
- ため池の自然
- 花と昆虫 不思議なだましあい発見記
- 道端植物園
- タンポポとカワラノギク
- どんぐりの図鑑
- 植物のかたち
- せいたかだいおう-ヒマラヤのふしぎなはな
- コケ類研究の手引き
- 虫こぶハンドブック
- 虫こぶ入門
- ひっつきむしの図鑑
- 樹木見分けのポイント図鑑, 野草見分けのポイント図鑑
- 植物生活史図鑑Ⅰ, Ⅱ
- 絵でわかる植物の世界
- 「野草」総索引
- 「野草」植物名総索引 第1巻~第70巻
- 標本をつくろう
- わたしの研究 どんぐりの穴のひみつ
- どんぐり見聞録
- ほんとの植物観察, 続ほんとの植物観察
- キヨスミウツボの生活
- 発見!植物の力1~10
- 帰化植物を楽しむ
- 花からたねへ
- 植物と菌類30講
<標本>
- 自然史関係大学所蔵標本総覧
- 国立科学博物館蔵書目録和文編
- デジタルミューゼアム
- 牧野植物図鑑の謎
- Systema Naturae 標本は語る
- 牧野標本館所蔵のシーボルトコレクション
- 牧野標本館所蔵シーボルトコレクションデータペース CD-ROM版
洋書
- Manual for Tropical Herbaria, Regnum Vegetabile
- The Asiatic Species of Osbeckia
- Biological Identification with Computers
- A Geographical Atlas of World Weeds
- Neo-lineamenta Florae Manshuricae
- Atlas of Seeds Part 3
- Alpine Flora of Kashmir Himalaya
- Botticelli's Primavera
- Index to Specimens Filed in the New York Botanical Garden Vascular Plant Type Herbarium
- Elsvier's Dictionary of Trees and Shrubs
- Medicinal Plants in Tropical West Africa
- Fodder Trees and Tree Fodder in Nepal
- Nepal Himalaya, Geo-ecological Perspectives
- Leaf Venation Patterns
- Development amid Environmental and Cultural Preservation
- The Lilies of China
- Kew Index for 1986
- Catalog of Moss Specimens from Antarctica and Adjacent Regions
- The mountains of Central Asia
- Trees of the southeastern United States
- A New Key to Wild Flowers
- Flora of upper Lidder Valleys of Kashmir Himalaya
- Systematic Studies in Polygonaceae of Kashmir Himalaya Vol.1
- Flowers of the Himalaya, a Supplement
- Plant Taxonomy and Biosystematics, 2nd ed.
- Plant Evolutionary Biology
- Lilacs, the Genus Syringa
- Ornamental Rainforest Plants in Australia
- Forest Plants of Nepal
- Plant Taxonomy, the Systematic Evaluation of Comparative Data
- Woody plants
- The Evolutionary Ecology of Plants
- The Forest Carpet
- Cryptogams of the Himalayas Vol.2., Central and Eastern Nepal.
- Pattern Formation in Plant Tissues
- Plant Genetic Resources of Ethiopia
- Leaf Architecture of the Woody Dicotyledons from Tropical and Subtropical China
- Palaeoethnobotany
- A Bibliograpby of the Plant Science of Nepal
- C.P. Thunberg's Drawings of Japanese Plants
- Temperate Bamboo Quarterly 2
- Index of Geogrphical Names of Nepal
- A Revision of the Genus Rhododendron in Japan, Taiwan, Korea and Sakhalin
- A Bibliography of the Plant Science of Nepal. Sipplement 1
- The Iceman and His Environment, Palaeobotanical Results
- The Cambridge Illustrated Glossary of Botanical Terms
- Handbook of Ayurvedic Medicinal Plants
- Ethnobotany of Nepal
- Himalayan Botany in the Twentieth and Twenty-first Centuries
- Meristematic Tissues in Plant Growth and Development
- Proceedings of Nepal-Japan Joint Symposium on Conservation and Utilization of Himalayan Medicinal Resources
- The Orchids of Bhutan
- Beautiful Orchids of Nepal
書籍詳細
-
元・国立科学博物館 金井弘夫 著
菊判 / 上製 / 904頁/ 定価15,715円(本体14,286+税)/ ISBN978-4-900358-62-1
〔花の美術館〕カテゴリリンク
- 第20回 『熱帯植物巡礼』
- 第19回 小山鐡夫追悼記念号『黒船が持ち帰った植物たち』より
- 第18回 小山鐡夫追悼記念号『植物園の話』より
- 第17回 『MAKINO 80』東京植物同好会・牧野植物同好会八十周年記念誌
- 第16回 ハマナスの語源を探る
- 第15回 金井弘夫追悼記念号『金井弘夫著作集 植物・探検・書評』より
- 第14回 『花のある風景』
- 第13回 坂嵜信之追悼記念号『日本で育つ・熱帯花木植栽事典』より
- 第12回 楽しい花観察108選『不思議な花々のなりたち』
- 第11回 川島榮生の《ヤマアジサイの世界》
- 第10回 渡辺健二『日本産ギボウシの世界』
- 第9回 『ユリノキという木』─ 魅せられた樹の博物誌
- 第8回 『北米インディアン悲詩』/ エドワード・カーティス写真集
- 第7回 江戸時代の花たち 書物に見る江戸時代の園芸文化
- 第6回 わが国初のボタニカルアーティスト 五百城文哉(いおきぶんさい)の世界
- 第5回 『ビル・ニガントゥ』 19世紀末ネパール秘蔵の本草図譜
- 第4回 植物画家 石川美枝子の作品
- 第3回 サイエンティフィック・イラストレーター 木村政司の作品
- 第2回 植物画家 中島睦子の作品
- 第1回 『PLANTAE ASIATICAE RARIORES』