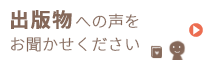「ナマエ」を考える
1976年11月11日付朝日新聞朝刊京葉版に載ったカタバミの八重咲き品についての記事は、私の云ったことと異なるニュアンスで書かれたところがあるので、本誌をかりて釈明しておく。この植物は雄しべの一部が弁化したもので、国立市の開邦子氏がおしば標本と写真を持参されたので、私の意見をのべたことがある。
朝日の記事では『……飯泉優氏は「完全な新品種だ。植物専門誌などに、正式に発表できる。」とみる。他方……金井弘夫氏は「……新品種ではないと思う。……奇形ではないか。……」と異論を唱えている。』となっている。
朝日の記者の電話取材では品種についての意見は求められなかった。記者の質問はこれが「突然変異」であるかどうかというものだったので、突然変異というよりは奇形というべきものだと返事をしたのである。何故ならば遺伝性についての調べがなされていなかったからである。新品種説に異を唱えるようなことは全く云っていないのである。従来の例からすれば、これを新品種として発表しても、手続きさえ誤らねば、それに異議を唱える者はいないだろう。
以前から気になっていることだが、分類学の目的は新植物の発見記載にあるという常識的な定義は本当なのだろうか?日本の顕花植物では種をかぞえ上げる仕事はあらかた終っている。この定義によれば日本国内では顕花植物の種のランクにおける分類学は仕事が無くなってしまい、研究は種以下のランク(変種や品種)をかぞえ上げるか、他の植物群(シダやコケ)の新種をさがすか、新らしくフロラに加わる植物(帰化など)に注目するかに方向が移って行くことになる。そして現状は正にそのような傾向が見られるように思う。私はこのような定義に疑問を持っている。
フロラを調べるのにその構成種を数え上げる作業は不可欠である。その過程で未知なものが出て来ればこれに名前をつけるのは当然の手続きである。何故ならば名前がないと他の人問とそれを対象として議論することができないし、そのタクソンについての情報を集積する場がないからである。誰が何時その名前を用いても同一の植物を指すことを保証する為にいろいろ複雑なルールが作られている。
しかし名前をつけるということは、もの事を整理する手段又は過程であって目的ではないだろう。それは例えて云えば、空箱を持って来て「文房具」。とか「衣類」とかいう字を書き込む作業に相当する。文房具や衣類というものの実体は別に存在しているのだが、我々が利用できるのは「知り得た事柄」だけなので、我々の知識の豊かさというか、その箱の利用度の高さは、その中にどれだけ多くの情報を放り込めるかにかかっている。
文房具の中には鉛隼も消ゴムも物差もあり、夫々形も色も用途も異る。しかしこれらを一々別な箱に入れようとしたならば、空箱ばかり沢山できてしまって、目的の品物がどこにあるか、手にした品物をどこに入れるかわからなくなり、整理も利用もできなくなることは明らかである。つまり箱の数はホドホドがよいのである。もちろん、文房具屋では鉛筆と消ゴムと物差は別な箱に入れた方がよいし、鉛筆を色ものと黒に分ける必要もできるだろう。つまり箱の種類や数は整理の目的や用途で異なる。
先に述べたことをここに当てはめれば、日本の顕花植物の種の名前を書いた箱がズラリと出そろっているということだ。サテ箱の中身はどんなものであろうか?どうもいっぱいつまっているとは思えない。例えば日本の蝶や蜂ではその1つ1つの生活史がアマチュアによって丹念に調べられ、記録されている。日本の顕花植物でこれに相当する情報蓄積が行われた種があるだろうか?箱の中身をふやすよりも箱の数をふやしたり、「コレをどの箱に入れるべきか!」という議論の方が盛であるように思える。我々が手にする「モノ」は、それをどの箱に入れるべきかを一々議論せねば入れ場所がわからないものばかりではあるまい。だからそういう「モノ」をセッセと箱に入れて中身をふやす行き方がもっと盛になって欲しいものだと思う。こういう「モノ」の1つ1つは断片的な観察結果にすぎないが、1つの箱の中に集められればその種についての知識の体系を組立てるのに無くてはならぬ部品となるに違いない。そしてこの部品集めは無数のアマチュアの努力無しには為し得ないのである。空箱作りよりこの方がよほどやり甲斐のある仕事ではあるまいか!
こういう観点からすると、分類学についての先の「常識的」な定義は影のうすいものとなる。分類学は種についてのすべての知識を集積し、体系化する研究分野とでも定義したらよかろう。
[野草44(357):30-31(1977)]
(2)
名前をつけることは空箱に字を書くことと同じだなどというと、何だかその仕事をケイベツしていると思う人もあるだろう。特に私のような、タクソンについての意見を発表したことのない者が云えばなおさらである。しかしそんなつもりは全くない。「この箱に文房具を入れるのダ」と宣言するには、何が文房具であり何がそうでないかが周知されていることが前提となる。文房具の箱にズボンを入れられては困るのである。ところが文房具というものが何かをみんなが知らない時には、それがどんな特徴をもち、どんなかっこうをしているかをなるべくくわしく、わかりやすく記してこれを箱に貼り付けておかねばならない。これが記載文に相当する。こうやって貼紙をすると、それを見た者が「ソイツはこの間作った箱と同じでよいじゃないか」とか「それは衣類の隣よりは工具の箱のそばに置く方がよい」とか云い出す。これがいわゆる「分類学上の議論」である。こういう議論はきわめて重要である。余計な箱がいっぱいあれば、先に述べたようにモノを入れる先もとり出す先もわからなくなるし、モノを持って来る度に箱の置場が変っていては整理などできるものではない。大いに議論して早く箱の置場を確定しなければならない。そうこうしているうちにアチコチの箱に入れるべきモノがどんどん持込まれる。箱の位置や数が決らないからといってモノを床に放り出しておくことはない。何らかの目安のもとにどれかの箱に入れた方が片付くし、そうすることによって箱の置場を決めやすくなるだろう。どれに入れてよいか決めかねるからといって新しい箱を作るのは、事をゴタつかせるだけである。例えばナイフは文房具の箱へ入れておいて、工具の箱へはそのことを書いた紙片を入れておけばよい。ナイフとスプーンがセットになっているからといって「スプーンつきナイフ」という箱を作る必要はあるまい。
我々がある努力の結果何がしかの情報を手に入れ、これを共通の知識としようとする時には、このような箱のどれかにそれを入れねばならない。つまりどの箱に入れるかを決めねばならない。これが同定である。実を云えば同定は研究しようとする材料を手にした時、目にした時にはじまる。何故ならそれに名前がついていようといまいと、その人はその材科を他の何物とも区別して認識しているにちがいないからである。どの箱に入れるかを決めるとき、その認識は一般化される。私は箱の数や置場を決めるのが分類であり、どの箱にモノを入れるかを決めるのが同定であると考えている。従来この2つは「分類」という言葉の中でマゼゴゼにされて用いられているが、全く異質のものだと思う。異質というよりは表裏の関係と云う方がよいだろう。
同定というのは「コレはシソである」と決めることだ。シソの箱がシソ科の棚にあろうと野菜の棚にあろうと香料の棚にあろうと一向かまわない。ところが自然分類という面からみるとシソの箱はシソ科の棚にあってスズコウジュの隣くらいに置かれていないと困るのである。一方家事分類(こんな単語があるかどうか知らないが)の立場からはシソは野菜の棚にあってジャガイモのそばよりホウレンソウの隣にあった方がよいだろう。つまり同定という作業は自分の手にしたモノが森羅万象の中のどの1つと同じかがわかればよいので、それが他の「森羅万象マイナス1」の1つ1つとどんな関係にあるかなどということはどうでもよいのである。いずれにせよこの作業はモノを扱う以上避けて通ることはできない。これは生物に限ったことではなく、物質科学で云えば定性分析に当る。定性分析ならその手法が確立しており、誰もがそのやり方を我がものとしていて、同じ操作で同じ結論を導くことができる。そうできる理由は物質というものの定義が比較的確固としているからである。だから化学の研究者が自分の研究材料を「コレ何ですか?」と他人にたずねるようなことはあるまい。そんなことをしたら研究能力を教われてしまう。生物となると種の定義がまだ確立していないから、そこにアイマイさが多分に残されており、同定という作業を困難にしている。生物学を物質科学であるかの如くいう人があるが、その人は自分の扱う材料の同定基準がどんなに不安定なものであるかを認識していないのではあるまいか?このことはまた分類学という生物学特有の分野が発達している由縁でもある。このあたりの根本問題の解決には情報の蓄積と周辺諸科学の進歩をまつ他はない。その為にも箱にモノを入れる仕事に精出してもらいたいのである。こう考えるとふつう人々が「分類」と云っている仕事は「同定」という作業に相当することが理解されよう。図(①②③④)でわかるようにナマエgは種の実体Gに対する情報の受皿でGそのものではない。我々が作り出せる種Gのイメージは受皿の中身を組み立てたGⅠに過ぎない。GⅠをGに近づけるには受皿gの中身が多いほどよい。従って分類学の1つの目標はgの中身を増やすことにあると云ってよい。
分類学というと系統や進化を論じないと意味がないという人が多いが、私は必ずしもそうは思わない。誰もがダーウィンやエングラーになろうとする気持ちはわかるが、情報の集積なしには進化論も分類体系も論じられまい。中身のつまった箱が多ければ多いほど、ある日能力のある人がそれらを用いて立派な理論や体系を組み立ててくれるだろう。その為にはヤタラに箱の数をふやすよりは、どんな小さなことでもよいから箱の中に営々とため込む仕事を軽く見てはならない。そういうことは「学」ではないと云う人には云わせておけばよい。そういう人でも時が来れば、箱の中身をだまって使うに違いないのだから。
▼ 同定作業
[野草44(358):42-44(1977)]
(3)
新名、特に新学名を作ることが、分類学にたずさわらない人達から何となくもてはやされる理由の1つは、著者名をそえることができるということにあるだろう。真摯な研究の末、新名を発表しつつある方々にはこのような云い方をするのは大変申し訳ないが、私の云わんとするところはこの文を読んでいただければわかってもらえると思う。
学名にそえる著者名とは伺だろうか?高校の生物の授業で「著者名は命名者の名誉の為にそえるものだ」と教師が云ったのを私は記憶している。これは今でも大方の人々が理解しているところと同じだろう。
先に述べたようにナマエをつける手続きとしては、まず空箱を持ってくること、そこへナマエを書くこと、そこへ入れるべきモノの定義を張紙することをせねばならない。ところがこの張紙は必らずしも箱に張りつけられてはおらず、むしろ別にまとめてしまってあることの方が多い。その方がナマエを調べたり、張紙の整理に便利だからである。これが文献である。文献といっても植物研究雑誌も、あれば野草もあれば少年ジャンプもあれば英和辞典もある。その中に含まれる個々の論文は無数といってよい。その中から目的のものを探し出すには著者名を手がかりに探すのが最も有効である。そのわけは、文献の整理は著者名を最優先にして行われているからである。
こういう次第で、学名の著者名はその出典を見つけ出す手がかりとしてそえられていることがわかるだろう。本当は学名の著者名の後に文献名が続いているのだが、あまり長いと符丁としての学名の意義がうすれるので省略されているだけである。従って出典の探索を問題にする必要のない、例えば単なる採集品リストのような場合には、著者名など無くても一向さしつかえない。むしろ和名だけの方が「正確」な場合が多い。「著者名を落としたら命名者に失礼だ」などと考えるのは、ナマエが符丁であることを忘れ、まるで命名者の所有物であるかのような錯覚である。こういう考え方を払拭しない限り、新名を作ってうれしがるという有害無益な一部の風潮はなくならないだろう。動物の分野で規約によって亜種以下のナマエは無視することになっているのは、無用な新名作り競争に歯止めをかける賢明な策である。一方命名者の倒から見れば、著者名は自分の作ったナマエに対してトコトンまで責任をもち、面倒をみるということを意味する。
著者名が無くても種名や科名から原典を見つけ出せるではないかと考える人もいるだろう。理屈としては確かにその通りである。しかしながら文献整理に当たってその内容にまで立ち入って整理の手をのばすということはあまり行われない。たとえば雑誌の目次は頁順か著者順で、項日別索引を作ることは例外的である。しかし本当をいうと、著者名からしか目的の文献を探し出せないというのは、不便をみんながガマンしているだけの話しで、いろいろな角度から文献検索ができる方が良いに決まっている。ある分野ではアブストラクトの形式や長さを規定し、検索用キーワードを指定するなどして多角検索を行なえるようにとり決められている。我国の分類学でもこういう工夫をしないと、折角たくさんの文献がありながら有効な利用ができないので、研究が立ち遅れることになるだろう。私の編集している植物分類学関係文献総目録は、この線にそうものなのだが、採録する報文の方がそういう作業に対する理解の上に立って書かれていないので、項目配分に苦労するものが少なくない。
[野草44(359):54-55(1977)]
(4)
前号でわずかにふれたが、ナマエというのはある実体Qをさし示す符丁である。だから何か他と違った記号がついていればよい。分類学をケイベツする人がよく口にする「名前をイジクリ廻している」という言葉の中には、前から述べているナマエというものに対する恐るべき認識不足の他に、符丁であるべき名前に意味のあるでき合いの単語を流用するよりは、数字でも使えば簡単でしかも順序だったナマエがつけられるのにという皮肉がこめられている。私はこの意見にはくみしない。
たしかにナマエは符丁であるから簡単な方が良さそうだ。たとえば植物が一万種あるとしよう。これを10進数字を用いて区別するには、5桁あれば十分である。だから26文字もあるアルファベットを用いて20桁も30桁も字を並べてナマエを作る必要はないというのである。だがもし桁教が少ない方がよいというのなら私はこれを2桁で表す方法を知っている。漢字を100個集めてこれを2字ずつ組合せればよいのである。漢字は順序づけができていないというかも知れないが、辞書にはちゃんと順序づけてのっているのでこの序列を利用すればよい。漢字は国際性が無いというなら別のどんな字でも記号でもよい。要するに桁数を少なく表現しようとすれば字母の数がふえるのである。字母の数は10進数なら10個、16進数(0−9にA−Fをつないで作る)なら16個、アルファベットなら26個、かな文字なら濁音半海音も入れて73個、漢字なら14,000個ほどである。ナマエがこれらの字母の単なる組合せによって作られるならば、桁数は字母の教によって決る。字母が少ない方がよいというなら2進数(0と1の2個の字母より成る)を用いればよい。その代り1万の表現には14桁を必要とする。16進数を用いれば4桁、アルファベットなら3桁が必要である。
このように、単語を流用するのは合理的でないから数字(10進数)を使えというのは何の根拠もない。数字を使えというなら2進数の方が合理的である。2進数を使うナマエは憶えにくいと合理主義者は云うだろう。それなら10進数のナマエは憶え易いかというとそんなことはない。誰でも√3をヒトナミニオゴレヤと覚えた経験があるだろう。これは数字は憶え易さの点でコトバにはかなわないという好例である。もう1つ例を挙げると、ジュゲムジュゲム……を暗記することはそんなにむずかしいことではない。でもその人に円周率を同じ字数(約140字)憶えろと云ってもまず出来ないだろう。このことは極めて重要な2つのことを含んでいる。
1つはそのナマエを誰が使ったり憶えたりするのかということである。人間が使うならコトバの方が断然すぐれていることは前述の通りである。ところが機械が使うのならば2進数を用いるのが最も効率がよい。欧米では学名を電算機に記憶させていろいろな情報処理に用いる試みがなされており、この為に1つ1つの種に特有の数を割り当てる作業が行われている。この数はもちろん10進数である。何故2進数を用いないかというと、普通の人間は2進数に馴れていないからにすぎない。別の云い方をすれば電算機はコトバを解するほど頭が良くないので、人間側が機械が何とか理解できる10進数に変えてやっているだけの話である。アルファベットは26進数なのだが機械はまだこれを消化できないのである。一方人間は2進数より16進数よりコトバの方がずっと使いよい。何を好んで間違い易い数字をナマエに用いる必要があろうか。
もう1つ重要なことは、ナマエの正確さを保つのに数字よりコトバの方がすぐれているのである。情報がやりとりされている間にいろいろな原因でその内容がこわれたり無くなったりする。例えばあるナマエ(一つながりの記号の列)の中の1字が無くなったとしよう。そこに何かがあったことはわかっているものとする。その空白に入るべきものは2進数なら2つのうちどちらか、10進数なら10に1つ、アルファベットなら26に1つだからアテズッポに字をあてはめるなら前者の方が当たる率は高い。ところが例えば「オオイヌノ□グリ」という記号の列があれば、この空所に「フ」が来るべきことは殆ど間違いない。つまりこの情報を正しく復元できる可能性は1/73ではなく100%と云ってさしつかえないのである。何故そうなるかというと、この単語を構成する字母の間にはアル関係(連接性)があることがわかっており、それを利用して欠損した部分を復元して情報の正確さを維持することができるからである。ナマエをコトバでなく数字や記号で表現するとこの相互関係は存在しないから、欠損部分を復元できる可能性は前述の如くセイゼイ50%止まりである。50%というのはデタラメの代名詞のようなものだから、部分の欠損した情報はもはや価値を持たないと云ってよい。
オオイヌノフグリという単語は8桁の単位から成っている。これと同じ桁数を10進数字で作ったら1億個の異なった情報を表現できる。もし48進数という意味でのかな文字(清音)を用いれば約28兆の異なった表現ができる筈である。ところが、辞書を調べたわけではないが、かな文字8字から成るコトバは1万もありはしないだろう。つまり我々は情報の表現に、その構成要素の相互閏に関係のない数字や記号を使わず、相互関係のあるコトバを用いていることで、表現の可能性という点ではモノスゴイ無駄使いをしているのである。だが反面その無駄使いのおかげで前記のように情報の正確さ、安定性が確保されているのである。人間の頭脳のようにきわめて不安定な環境条件の下で運行される記憶装置に於いて、情報の表現にこのような復元性の高い方式が用いられていなければ文化の発達はおぼつかなかったに違いない。機械に於いてはまだこのような無駄使いを許すほど記憶装置は安価ではない。そこで数字を用いた記憶がこわれないように、細心の注意を払わねばならないのである。以上によって√3をヒトナミニ……と読み変えたり電話番号をマルイマルイと憶えたりする理由は説明されたと思う。同時に既成のコトバを流用してナマエを作るやり方は、人間の情報処理の方式としてきわめて好都合で信頼性の高いものであることも説明したつもりである。
[野草44(360):66-67(1977)]
(5)
分類学をやる者が他分野の者からよく聞かされる批判の1つは「標本ばかり作って、あれは生物学ではなく死物学ではないか」というものである。我々は何故標本を作り残そうとするのだろうか?そんなことをしなくても必要な時にまた採ってくればよいではないか。これに対する普通の返事は「絶滅した時困るから」というものだろう。それでは絶滅しないように植物園で必ず生かして保存すれば標本はいらないのか?どうもそうではない。1つは植物園という培養条件では自然の状態とは色々な点で異なった様相を呈することが考えられる。もう1つは唯一株の生植物が生き残っていても「種」を扱う研究には不充分である。と云って、一種についてできるだけ多数の生標本を保存することは不可能である。それをやろうとすれば「種」全部の面倒をみなければならない。多年生のものはこういう問題だけで済むが、一年生のものは種子をとって播かねばならない。そうすると親植物の如何によっては元と同じでなくなるかも知れない。
我々がある実体(種)Gに対してナマエgをつけるのは、その名を称えれば、何時でも何処でも同じモノをさし示すことを念願している為である。もし同じモノをさし示さないのならナマエの意義は無くなる。一方我々が知覚し得るGのイメージは箱gの中身を組立てたGⅠである。我々はGⅠがGの実体にほど遠いものであることをよく心得ており、そういう不十分な情報に基づくgというナマエが時間空間をへだてて同じ実体Gを指し示すのかどうかということに疑問を抱いている。おまけにGは生き物の集合だから、一寸考えても何時でも何処でも同じであるとは考え難いのである。そこで我々はgという箱に情報を集積するだけでなく、実体Gの一部を切取って来てこれを保存する。これが標本GSである。GSは実体Gの一部だから、知られた情報の他に未知の部分をいっぱい含んでいる。従ってGSはGに代わって研究の対象にすることができるし、必要に応じて問題となる個所をチェックして新しい情報をとり出すことができる。切り取るという操作と保存という目的の為にGSはGの持っていた形質のかなりの部分を失っている。大マカに云えば形は残るが機能や作用は失われ、部分は残るが全体は失われるのである。しかし標本の利点はGの一部をある時点で固定してしまうことにある。実体Gは生きているのだから時々刻々変ってゆくだろう。従ってある時刻tにおけるG(G1)と次の時劾t+aにおけるG(G2)は同じでないかも知れない。これをどうやって知ることができるだろうか?時刻t+aにおいてはG1はもはや存在しないのだから較べることはできない。G2に於いて目標とされたある形質がたまたまG1についても調べられて箱gの中に入っていた時にのみ比較検討ができる。調べられていなければお手あげである。標本はこの欠陥をある程度カバーする。G1の標本G1SとG2をつけ合わせれば時間aの間に起こった、または起こらなかった変化を知りうる可能性がある。
標本を作らないで同一性をナマエgにだけ頼っていたらどうなるか?微生物などでは生物体を継代培養することによって種(と云って悪ければ株)を保存している。そのナマエは培養管に記された、例えばB. coli 007として受けつがれてゆく。そうすると5年前のB. coli 007と今のB. coli 007が同じものだろうかという疑問が出たときどうやってそれを確かめるのだろうか? 5年前の標本が無ければそれは箱に入った情報に頼るしかない。つまり前記のように標本G1Sを調べ直して新しい情報を得るという手段はとれないのである。そうするとB. coli 007というナマエは情報の入れ物としての名前ではなく、培養株の入れ物としてのガラス管の名前に過ぎないことになる。つまり「B. coli 007の情報はこの箱に入れる」のではなく「この箱に入っているのがB. coli 007の情報だ」ということになる。前者では箱に入れる前に同定という作業が行われているのに対して後者ではそれが行われたかどうかは保証されない。さっき「疑問が出たとき」と書いたのは、そういう疑問は万に一つしか出ないのではなく、モノを手にする時には常に出るべきものなのだと云いたかった為である。
似たようなことだが「俺の使っているB. coli 007アイツの使っているB. coli 007は同じものだろうか?」という疑問が出たらどうするか。両方を同じところへ持って来て気の済むまで較べてみればよいだろう。しかし一方が過去のものなら前の場合と全く同じことである。よく考えると「同じところへ持ってくる」という操作には時間の経過が含まれるので、本当は較べることができないのである。つまり時間、空間をへだててモノ(特に生きもの)を比較する場合には、固定された標本が無ければ同一性の判定はきわめて稀な偶然に頼るしかないことになる。標本があればその可能性をいく分でも大きくすることができる。
▼ 標本
[野草45(361):2-4(1978)を一部修正]
(6)
標本GSは実体Gの一部を切り取って固定したものである。このシリーズのはじめから私は「実体G」という言葉を用いているが、そういう明確な実在があると思ってもらっては困る。「実体G」は張り子の達磨のように、はっきりした界面をもってある領域を占有しているものではない。ある領域を占めてはいるけれど、その界面ははっきりしないのである。これはGの定義がアイマイな為である。しかしこれは命名者の定義がいい加減だということではない。Gはこの場合「種」を意味するから、種の定義の仕方が確立されていない為に、Gの領域が確定しないということである。図でGの輪郭を破線で描いているのはそのためである。Gを認識しgと名付けた者は自分なりにGの定義を下すが、共通の客観的基準がない以上、他人は彼が期待したとおりに理解しないかもしれないし、ご当人でも研究が進むに連れて、最初の定義ではうまくないということも起こってくる。極端に言えば、Gの定義は一人一人の好みで異なる。だから「牧野先生はこう言ったが中井博士はこう同定した」というようなはなしがよくおこるのである。このことは他分野の人からよく分類学の非科学性として批判されることであるが、これは分類学のセイではない。科学の水準が、種の定義を下せるほどに進んでいないだけの話である。それにもかかわらず生物にはいろいろな種があることは明らかなので、不完全でもなんでも定義を下さざるをえないのである。その損な役割を受け持つのが分類学という分野であるにすぎない。錬金術の時代に、元素を地水火風空と定義したのと同じである。
こういうわけで、Gの全貌は命名者自身ですら掴んでいない。従っていろいろな人が箱gの中へ情報を入れてゆくにつれて、Gの領域ははじめの期待とは異なった方向へふくらんだり縮んだりする。その結果、ナマエgのさし示す実体Gが、出発点とはずっと離れたところへ行ってしまうおそれもある。どこへ行こうと構わないようなものだが、Gの領域が無制限に動いてしまっては、ナマエgが同じ実体を指し示すという保証がアヤフヤになってしまう。そこでそれに制限を加えておこうというのが、基準標本の役割である。基準標本と種の領域の関係を例えて言えば、釘にひっかかった輪ゴムである。輪ゴムがどんなに変形しようとも、釘のある位置とその太さは常にその領域の中に含まれている。輪ゴムがどんなに縮んでも、釘の太さより小さくはならない。釘がなければ輪ゴムはどこへ行ってしまうか分からないし、縮んで無くなってしまうかもしれない。輪ゴムの囲む範囲をGとし、釘を基準標本GSTとすれば、近頃はやりの集合論で言えば、GST⊂Gが常に成り立ち、Gが最小になった場合でもGST=Gである。基準標本を複数にした場合、Gの最小領域はいくつかの釘を結んだ多角形の領域となる。この領域は釘(基準標本)の占める領域とそれ以外の空間とより成る。先に記したように、定義の解釈は人によって異なるので、領域の界面が基準標本群の中の空間を通る可能性は否定できない。1個の標本はひとつながりの個体だから、この中を種の界面が通ることは考えないでよい。だから複数の基準標本を作って前記のような矛盾の起こる危険を冒すよりも、基準標本を1個だけにしておくほうが安全である。この一個の基準標本が正基準標本(ホロタイプ)と呼ばれるもので、1本の釘に相当するものである。
基準標本という呼び名の感じからして、種Gのすべての平均値または標準的様相を具えているかのように思う人もいるようだが、それは当たっていない。ナマエgを記載した者は注意して標準的なものを選ぶだろうが、その標準とは、彼がその時手にし目にした限りのことであって、彼は実体Gの全体を掴んでいるわけではない。だから情報が増えるにつれて、Gの標準値はもっと別なところにあることがわかるという事態は少なくない。形質は無数にあるのだから、そのすべての標準値が1つの標本の中に具現しているということはむしろあり得ない。そうすると唯一つの正基準標本を「種」Gの標準と考えるのは無理である。正基準標本とは、ナマエgが初めて付けられた標本であると考えるべきである。この考え方では、正基準標本は「種」の標準でも何でもない。他の標本との唯一の違いは、ナマエgと正基準標本は針金で結ばれていて、切っても切れない関係にあるということである。どういうことかというと、次のようなことである。
もしGの領域が変形していって、他の実体Fの領域と重なったとしよう。そうする1つの領域に対して、gとfの2つのナマエがつくことになる。時間空間を隔てて独立に研究が進められれば、こういうことはしばしば起こる。ナマエがある特定の実体をさし示し、逆に1つの実体を指し示すナマエは1つしかないという状態を保つには、こういうことが起こったときに、どちらの名前を用いるかの判定基準ができていなければならない。これは命名規約でもっとも意を用いている問題であり、主として先取権と有効出版という規範に照らして決着が付けられる。その結果gと呼ばれていたものはfと呼ぶべきであると決まったとしよう。そうするとgという箱はなくなって、その中身はfの箱の中にあけられる。その際gの名札と人相書きは、Gの正基準標本(今やFの単なる標本の1つに過ぎない)全体を指し示す情報としてfの中に入れられる。ただしこの人相書きはGの正基準標本のみを対象に書かれたものではないから、上の言い方は正確ではないが、この情報はもはや使われることはないのでどうということはない。少なくともgの名札はGのホロタイプに死ぬまでくっついている臍のようなものとなる。逆にgのナマエが生きる場合にはGSTはもとのGとFの領域の和の実体の正基準標本となる。この場合でもGSTは領域のどこかの一角を占めるだけで、「中心」にいるとは限らないことは前記のとおりである。
[野草45(362):16-18(1978)]
(7)
近頃植物の観察や研究をする人が増え、同好会や植物目録の刊行が盛んになっているのは喜ばしいことである。それに伴って新しいタクソンの発見や新名の発表が多くの人によって行われるようになったことも、またご同慶の至りである。新しい分類群の発見や命名は、分類学の専門家でなければ行ってはいけないなどというものではない。誰がやっても手続きとモラルを逸脱していなければ問題はない。ところが新名の発表者の範囲が拡がるにつれて、発表の仕方に問題のある例が増えているのは残念なことである。ルールに外れたナマエは命名者のせっかくの努力を無駄にするばかりか、発表者の研究態度や、ひいては我が国の分類学の国際的信用にかかわるおそれがある。これは特に新学名の発表について問題が多いのだが、新和名の発表についても困った例が見られるのである。植物分類学文献総目録の作成の際、気づいたことを中心に以下に述べる。以下の各項のほとんどについて、それぞれ最近の実例があるのだが、それを挙げることは避ける。また指摘する事例については、国際植物命名規約の裏付けがあるものもあるし、私の個人的見解にすぎないものもある。
- 新学名を作るには正基準標本が実在することが必要である。ー 正基準標本なしに、目撃や伝聞だけで新学名を作ってはならない。
- 新名は1つのタクソンを指し示すものだから、これに対応する正基準標本は常識的な標本の形を具えているべきである。ー 斑入りの新品種の基準標本が、葉1枚だけというのではよくないということ。
- 正基準標本は永久保存ができ、国際的に利用できる公的機関の標本室に納める。ー 基準標本を秘宝の如く私蔵しないでもらいたい。
- 副基準標本はなるべく多くの標本室に分散させる。ー 副基準標本は正基準標本のデュープリケートである。通常の場合、副基準標本は正基準標本と同じくらいの価値を持っているので、これが各地に分けられていれば、研究者は正品を見ないで済むことが多いし、正品も傷まないで済む。災害などで正品が失われたときには、副基準標本の1つがこれに代わるものとなる。
- 命名の際に利用し、同じタクソンと同定した標本は、著者の見解の理解のため、なるべく正基準標本と同じ所に置く。
- 新学名発表の形式は、国際植物命名規約にてらして適合したものでなければならない。
- 新名発表の場所は、国際性のあるサーキュレーションのよい専門誌を選ぶ。ー これについては植物研究雑誌26:31-32(1951)「国内有効出版物に関する植物分類学会の申し合せ」があるが、その後の学界情勢の変化や印刷技術の進歩のため、新たな見直しが必要と思う。
- 新名の引用は、発表されたこと確かめてから行う。ー「新種、ーー== sp. nov. 」という表題の下に「某々専門家に標本を送ったところ、『ーーという名前で発表しようと思う』という返事をもらった。故にここに新種の発見をお知らせする。本種は…」という報文が少なくない。この sp. nov. の著者(==)は某々氏となっている。これは某々氏にとって大変迷惑なことである。発表もしていない学名を発表してあるかの如く引用され、親切に返事を出したことを後悔しているに違いない。研究の結果、意見が変わるかもしれないし、材料がそろうまでにまだ時間がかかるかもしれない。勝手に引用してしまった人は、どう責任をとるつもりだろうか?
- 正式に発表していない学名は使わない。ー 前項と同じであるが、まずとりあえず裸名で発表しておいて、いずれ正式に記載しようというような新名は、名のある研究者の立派な著書にも散見される。先取権を確保しようとするのだろうか。とくにその学名が正式発表ではないことを断ってない場合には、見る者はその出典を探そうと無駄な努力をさせられる。これは迷惑千万である。何の目的でそんなにあわてて発表せねばならないのか、理解しがたい。前項が著者にとって大迷惑だと言ったのは、このような自己の信用を落とす行為を、他人が勝手にやってしまうという点にある。
- 二重投稿をしない。ー 新名を早く発表しようと、ほとんど同じ内容の投稿を、複数の雑誌に行ったとしか思えない報文がある。これが高じると、他人の発表を出し抜こうとして、実在しない刊行物に新名を発表したことにして引用したという、某大家のことが思い出される。
- 和名には交雑品や中間型を表す「a×b」という表現が非常に多く、これがあたかも独立のタクソンに対する和名であるかの如く記録通用している。学名でさえ、こういう表現を「学名項目」に記録する人が少なくない。これらはナマエではなく、ノートに属するものである。したがってこういう表現をナマエとして用いる習慣が拡がれば、タクソンの認識が次第に甘くなり、ナマエの意義が失われるだろう。
以上挙げたことは、発表者本人の自覚にまつことはもちろんだが、各誌の編集者が十分注意せねばならないことである。
[野草45(363):31-32(1978)]
(8)
このシリーズの(2)で、同定と分類は別物で、ふつうに分類と呼ばれている行為は同定という作業に当たると記しておいた。近頃は大井氏や北村氏の著書をはじめ、大変多くの立派な植物誌や図鑑が出まわっているので、植物の名前を調べるということは、誰もが自分でやることが出来るはずと考えてよかろう。これらの本は、著者の意図はともかく、ほとんどの場合、名前を調べるということを目的に購入されているのだから、それができなければ購入の目的は達せられないことになる。ところが私のようなモノを知らない男のところにも、名前を教えてもらいたいと来られる方があとを絶たず、同好会の集会でも標本の鑑定が大きな内容を占めていると聞く。中には「こういうことはもう自分のやることではない」と、ゴウを煮やしておっしゃる先生もおられるそうで、私もこれに同感である。こんなに同定用(と思われる)図書が出回っているのに、どうして各自が自分で名前を見つけ出すことができないのだろうか?実を言えば、私自身もこれらの本を用いて的確に名前を見つけ出すことが出来ないのである。つまりこれらの本は、多くの利用者についてはその目的を満たしているとは言いがたい。我々はもう一度、同定という作業をどうやるべきかを考える必要がある。同定という作業は誰もが身につけるべきテクニックであって、誰か物知りに聞かないと分からないという、無形文化財みたいなものであってはならないはずだ。そもそも高等植物の研究に「同定法」という分野がないのは不思議ではなかろうか?とくに、研究を行う者が、自分の仕事の最も重要な情報の1つである材料の名前を、共同研究者でもない他人に聞いて片づけてしまうのはうなずけない。これは1つには「同定法」というものが確立されていないからだろう。
名前を知るには普通は検索表が用いられる。これは一方の端から始まって通常は二又分枝的に進み、他端に達するとそこに名前が記されている。二又分枝のどちらをとるかは、そこに記された背反的な2つの形質のどちらを標本が具えているかで判断される。1つの極端な例として、大井:日本植物誌(初版)のヤナギ属の検索表をたどってバッコヤナギに至る経路をたどってみよう。そこに現れる検索用形質はつぎのとおりである。
- 芽鱗は枝の腹面で癒合し深帽状。
- 雄しべは1−2個。
- 雄花の腺は1個、苞は宿存し上方は通常濃色。花穂は通常無梗又は稍無梗で側芽上に直接して生ずる。
- 雄しべは2個。離生又は稍離生。
- 花柱は甚だ短く、柱頭より短いか又は0。子房は有柄。
- 子房有毛。低地乃至山地の植物。
- 喬木又は大形灌木。葉は稍幅広くて大形、長さ4−8cm、幅2−4 cm、柄は長さ1−2.5 cm。花序は稍太し。
- 小枝の皮を除くと木質部に著しい縦の隆起線条がある。葉は下面多少毛あり。
この検索表を用いて1枚の標本の同定ができないことは明白である。ヤナギは雌雄異株なのに、この検索表は雌花と雄花の形質を調べることを要求しているのである。いま♀花の標本があるとすると、♂花の株とくらべるには、少なくともこの2つが同一種であることが分かっていなければならない。その為には前もって検索表で調べておいて…ということになるのだろうか?そればかりでなく、同定しようとする標本は、上の検索表に記されたすべての形質を必ず具えていなければならないのである。葉だけの標本はこれでは同定できない。ヤナギ属の花は原則として葉前性である。成葉を具え、雌雄花序をもつ標本でないと、この検索表を通過できないのである。そんなヤナギの標本があるだろうか?またHにある、木部の縦条という形質が標本に見いだされたとしても、これで直ちにバッコヤナギと決めつけることはできない。というのは、検索表全体を見回しても、さらに種の個々の記述を見ても、縦条の記事があるのはエゾノバッコヤナギとタライヤナギのみで、他はこの形質があるのかないのかわからないからである。記事がないからこの形質は持たないとは言えまい。毛の多少とか、葉の幅が稍広いとか、花序が太いとかいう相対的な形質は、検索表が意図する相手と比べなければ何にもならない。比べようとしても、手にする標本はただ1つなのである。長さの形質などは、背反的でない場合の方が多い。
こういうことを書いたからといって、私は大井氏をはじめ多くの著者がいい加減だと言っているのではない。検索表を使えば同定ができると思い込むほうが間違っていると言いたいのだ。近頃、植物名を調べるには検索表を使うのだということを、教科書に載せようと意図する人がおられるようだが、ちょっと考え直してもらいたい。
検索表というものは、ヤナギ属ならヤナギ属の全体が分かっているとき、その成員を近似または類型に従ってどの様に整理したかを示すもので、著者の分類学的見解の表明である。だから観察されるすべての形質が動員されており、それが1つの標本の中に共存し得るか否かは考慮されない。
前にも述べたことがあるように、これは分類であって、箱の並べ方をどうするかを示すものであり、手にしたモノをどの箱に入れるべきかを示すものではない。従ってこれを同定に用いて行き詰まったところで、著者の責任ではない。検索表を同定に使うこと自体が間違っているのだ。検索表を用いて行き詰まらないでたどれる人は、すでに全体を知っており、結果についての予断を持てる人なのだ。そうでなければ検索すべき形質を標本が持っていないのに、そこを跳び越えて先へ行けるはずがない。跳び越えができるのなら、検索表などいらないのである。検索表では少なくとも標本1点ではなく、その枝分かれごとに、比較すべき別な標本が必要なのである。さもなければ「広い」とか「長い」とか、比較用語を用いることは出来ない。
それでは同定という作業はどんなやり方をすればよいのか?残念ながらまだ確定した方法はない。私が以前から考えているのは以下のようなことである。
バッコヤナギの木部の縦条の有無は、3種についてしか記されていないから、縦条があっても直ちにバッコときめるわけにゆかないと記した。もしすべての種について縦条の有無が調べあげられて一覧表にしてあれば、標本のこの点1つをチェックするだけで、同定範囲をいくつかの種に絞ることが出来る。雄しべの数や癒合の状態がすべての種について一覧できれば、その形質だけでまた別に同定範囲を限定できる。こういうことをいろんな形質について各々独立にやっていくと、目指す種の名は、各々の範囲の重なり合った部分に入っていることになる。こうして絞り出されたいくつかの種は、もう1つ2つの形質について同じことをやれば簡単に分離できるか、分けても分けなくてもいいような近い種だろう。こういうやり方だと、標本の持っている形質に応じて、同定のコースを変えることができる。二分式検索表だと相手かまわずコースが1つしかとってないので、先に記したような障害がおこる。だから私は、同定の為には二分式検索表よりは、ここに述べた一覧表形式の方が適していると考えている。
このような一覧表の一般的な形はつぎのようになる。表の左端に種をすべて縦に並べ、上端には横に検索形質を並べる。形質の一つ一つについて、形質ごとにそれを持つか否かを〇✕で印をつけておく。同定しようとする標本について、形質の欄を見ながら、標本の持つ属性(〇か✕か空白か)を表とおなじ形式で記録する。標本に備わっていない形質は空白にしておけばよい。それが終わったときこの記録のパタンを一つ一つの種のパタンと比較し、一致する種の名前がその標本の名前となる。一致するものが複数あったり1つも無かったりする時には、見方を変えて、あるいは重要でないと思われる形質を落として、もう一度やってみればよい。
こういう一覧表は簡単には出来ない。例えばヤナギ属の検索表では枝の数は74ある。1本の枝に平均 3個の検索形質が含まれているとし、これを一覧表形式に合うように書き換えると、項目数は2−3倍になるだろう。従ってヤナギ属の同定用一覧表を作るには、少なくとも 500の形質を40ほどの種について調べねばならない。これは実に退屈な仕事だろう。例えば「葉の下面は粉白」という形質は、誰でも記録するに足ると思うだろう。しかし「粉白でない」という形質は当たり前なので、誰も記録しないから空白になっている。この空白にハッキリ✕印を入れるのは、誰が考えても気の進む仕事ではあるまい。誰でも「重要な」形質には興味を持つが、「重要でない」形質には興味を引かれない。しかし一覧表を作るには、重要であろうが無かろうが、とにかく空白は埋めておかねばならないのだ。このシリーズの始めに、箱の数は多いが中身はタップリあるとは思えないから、箱の数を増やすより中身を増やす方にセイ出したらどうだろうと言ったその「中身」には、こういう一見くだらないものがたくさん含まれているのである。こういうことはいくら一生懸命やっても、「研究」だとか「学問」だとかとは関係ないと見なす空気も残念ながらないわけではない。つまり「本質的」ではないのである。ヤナギは手ごわいにしても、手始めにもっと小さなグループから手をつけて、まだしっかりしていない同定法というものを確立するする人が出ないものだろうか?どんな小さなグループでも、検索表を上記の一覧表形式に書き換えてみると、埋めるべき空白がいかに多いかにため息が出ることだろう。大井:日本植物誌(初版)のクワガタソウ属の検索表から、タチイヌノフグリ、オオイヌノフグリ、フラサバソウ、イヌノフグリの部分を一覧表形式に書き換えたものを示しておこう。この場合、形質はハッキリ分離できるような区分で仕切りなおす方がよいので、長さのような連続量はいくつかの適当な区切りを設けなければならない。「大きい」とか「狭い」という、もう1つ比べるものがなければ成り立たない用語は使えない。まして「いちじるしく」とか「やや」という表現は役に立たない。?のところはこの本から記入できなかったもので、これから調べなおして埋めるべきところである。この表を利用して名前を調べるにもそれなりの注意が必要で、葉の幅と長さが等しいからといってすぐ2031にしてしまうより、2032の極限形もありうると考えておかねばならない。また1031、1032の萼の長さは6.0-6.9mmの範囲は重複しているから、この範囲に当たる標本ではこの項は同定手段として使えない。イヌノフグリの類の形質はこの他にもいろいろあるから、気がついた人はこの表に付け加えてゆけば、かなり不完全な標本でも何とか名前を見いだせるような同定表ができるのではないか。ただし形質をつけ加えるには、4種すべてについて調べることが要求される。またこの表をVeronica属全体に拡張するには、新しく加わる種類と形質について、それぞれすべての項目をチェックし直さねばならない。
▼ 一覧表形式
種名 タチイヌノフグリ オオイヌノフグリ イヌノフグリ フラサバソウ 項目番号 検索項目 1011
1012小梗長 ≪ 萼長
小梗長 ≫ 萼長〇
✕✕
〇✕
〇✕
〇1021
1022小梗長 < 萼長
小梗長 > 萼長〇
✕✕
〇〇
✕〇
✕1031
1032萼長 ≦ 7mm
萼長 ≧ 6mm〇
✕✕
〇〇
✕〇
✕1041
1042萼は草質
萼は膜質?
??
?✕
〇〇
✕1051
1052萼片の縁毛著しい
萼片の縁毛微か?
??
?〇
✕✕
〇1061
1062花は碧青、青紫
花は淡紅紫〇
✕〇
✕〇
✕✕
〇1071
1072花冠径 < 5mm
花冠径 > 5mm〇
✕✕
〇〇
✕〇
✕1081
1082花柱長 > 2mm
花柱長 < 2mm?
?〇
✕✕
〇✕
〇1091
1092
1093一果実中の種子数 16
一果実中の種子数 10
一果実中の種子数 04?
?
?✕
〇
✕✕
✕
〇〇
✕
✕1101
1102種子径 < 1mm
種子径 < 1mm〇
✕✕
〇✕
〇✕
〇1111
1112種子表面平滑
種子表面シワがある〇
✕✕
〇✕
〇✕
〇2011
2012葉は対生
葉は互生〇
✕〇
✕〇
✕〇
✕2021
2022上方の葉は苞状で
下葉と異型
下葉と同型〇
✕✕
〇✕
〇✕
〇2031
2032下葉は幅 ≧ 長
下葉は幅 < 長✕
〇✕
〇〇
✕〇
✕2041
2042下葉は3~4浅裂
下葉は5~7浅裂?
??
?〇
〇✕
〇今述べたやり方は数量分類学という分野の手法と似ている。違うところはこれは同定であって分類ではないということと、判断を人間がやるということだろう。こういう同定法を研究しているのは、我が国では石戸忠氏唯一人である。同定に一覧表による手法を取り入れると、紙上に作られた表を用いる同定の他に、カードを用いた同定とか、電卓を使ってテレビと対話しながらやる同定とかができる可能性がある。後者は医学の分野では自動診断としてすでに実用されている。近頃このはなしを聞かなくなったので、生き残っているかどうか知らないが...。検索表式の同定ではこういう応用はきかない。
一覧表式の同定で困るのは、種や形質がふえるにつれて、表が縦横に際限なく大きくなってしまうことである。これは紙の上では適当なグルーピングをすることで解決できるだろう。カード式や電卓式ではこういうサイズを気にする必要はない。そのやり方がどんな物になるかはアイデアとしてはあるが、まだ具体的なものではない。興味のある方は考えていただきたい。
後記:その後、大川ち津る氏が、生物教育の教材として、膨大な形質マトリクスを使った同定ソフトを開発し、教育現場で実用している
[野草45(364):46-49(1978)]
(9)
分類学からナマエの問題を切り離すことは出来ない。その為に知らない人達は分類学とはナマエをいじくる学問だと思っているようだ。そうでないことはこれまで述べたつもりだし、ナマエは分類学だけの問題ではないということも述べたつもりである。それでも何でこんなにナマエのことを気にしなければならないのか腑に落ちないのではあるまいか。もう一度そもそもの発端から考えて見よう。
カナイさんという人が、庭の植物を調べたとする。彼は植物の名前は全然知らないとしよう。また本も読まなければ人にも尋ねない不精者で、それでも調べようとする気持ちだけは殊勝にも持ち合わせているとしよう。
庭にいくつかの異なった種類の植物が生えていることは馬鹿でも分かる。これは実は重大なことである。つまり調べなくとも「種」というものが実在することが誰にでも分かってしまうのである。また生えている1本ずつが全部異なっているわけではなく、何本かは同じもので、別な何本かはまた異なった同じものだということもすぐ分かることである。とにかく彼には、いつかの「種」が認識されたのだ。彼の頭のなかではそれらは「コレ」とか「ソレ」とか「アレ」とか「ナニ」とかいう代名詞で区別されているだろう。しかしこれを記録する段になると、代名詞では用が足りなくなるので、A、B、C、D…などという固有名詞をつけることになる。ここではじめて植物にナマエが付けられたことになる。つまり知識を入れる為のA、B、C…という箱ができたことになる。この箱のなかに、春でも秋でも、とにかく異なった時点、観点における庭の植物AならAの情報が入れられてゆく。
次に彼は高尾山の植物を調べたとする。ここでも彼は「高尾山」という整理棚にA、B、C…という箱を作って記録を蓄積するだろう。こうやって知識が増えてゆくにつれて、彼はある日、自分の庭で見つけたことのある植物が高尾山にもあることに気づく。庭でBと名付けておいた植物は、高尾山でDと名付けた植物と同じではないか!そこで彼の頭の中では(庭のB=高尾のD)という関係式が成り立つことになる。こうやってことが進んで行くと、(庭のA=高尾のH)、(庭のQ=江ノ島のD)、(高尾のI=江ノ島のA)などといろんな関係式ができてきて、しまいにはつき合いきれなくなってしまう。これを切り抜けるには「等式の成り立つ『種』は同じナマエで呼ぶ」ことにして整理しなおすことになる。つまり(庭のB=高尾のD=B)、(庭のA=高尾のH=M)、(高尾のI=江ノ島のA=PQ)…という具合に、ナマエを付け替えるのである。こうすればどこに生えていようと、同じ「種」には同じナマエがつくので、仕事も整理もやり易くなる。どう言うふうにナマエを付け替えるかは、自分の好きにやればよい。とにかくこんがらがらなければよいのである。これでとにかく、1人の人間にとって場所や時期に関係のない、安定したナマエが確立したわけである。
これとは別に、マキノさんという人がいて、同じようなことをやっていたとする。ある日2人が出会ってAという植物の話をはじめたとする。ところがどうも話が食い違う。カナイさんはAに紅い花が咲くというのにマキノさんは黄色い花だという。そこでAという植物をそれぞれ持ち寄ってみたら、全然違うものだった。カナイさんのAと呼ぶものはマキノさんがBと呼ぶものであり、マキノさんのAはカナイさんのHであった。つまりA・Kanai=B・Makinoであり、H・Kanai=A・Makinoである。お互いに話しを通じやすくする為には、カナイさんが自分のコレクションの中でやったように、2人の間でナマエを統一すればよい。
自分自身の問題として片づけるのはやさしい。ナマエをどっちにするかとかどんな新しいナマエにするかとかは、気分まかせにやればよいからである。ところが他人同士となるとそうはいかない。誰だって自分の使っているナマエを捨てて他人の付けたナマエにするのは気乗りがしない。そんなことをすればこれ迄の自分の記録を全部書き換えねばならないのに、むこうは何もしないでよいのだから不公平な感じがする。何か納得できる理屈がなければ、互いに譲るわけには行くまい。その理屈は今後3人目4人目の同類が出てきたときにも説得力があるものである必要がある。こうして命名規約というものが出来上がるのである。とにかくこれで、他人同士でも通用するナマエというものが出来上がり、情報の交流が間違いなく行われるようになるのである。
これで問題が片づいたかというとマダマダで、少々次元の異なった問題が起こってくる。1つの標本に対してカナイさんはPと名付け、マキノさんはQと名付けることが起こる。これは先のP・KanaiとQ・Makinoの問題とは本質的に異なる。例えば(P・Kanai=P・Makino+Q・Makino)とか、もっとややこしくすると(O・Kanai+P・Kanai=P・Makino+Q・Makino)という関係である。つまり種の認識が異なることによって起こる問題である。これはナマエのような人為的な問題ではないから、話合いでは片づかない。種の客観的定義がなければ、水掛け論か権威主義になってしまう。現状は後者で、「何々先生ご同定」というお墨付きが効果を持つ所以である。
種に対する確立した定義がないことについては、これまで「科学がそこまで進歩していないから」と片づけてきたが、もう少し突っ込んで書いてみよう。問題は2つあると思う。
まず生物は「種」という単位から成り立っているという仮説は、認めてよかろう。何事も不連続な単位の集積として考えるのが、近代科学の基本的な考え方である。物質の場合、たとえばショ糖という「種」をこまかく分けていって分子に達しても、それはショ糖と呼ばれるに足る形質を保持しているだろう。ところが生物の「種」を、その構成単位である個体まで分けたとき、それは「種」と同じ形質を持っているだろうか?どうも少々違っていそうな気がする。そのわけは個体は「種」の示す大きな変異のなかのある1点しか示さないので、それで種を代表させることはむずかしいからではあるまいか?物質にも変異というものはあるにはある。異性体もあるだろうし、同位元素の組み合わせも違うだろう。しかしこういうものは通常の測定法では引っ掛かってこないか、誤差の範囲内のものだから、「個体」の集合である「種」としての物質は厳密な測定法ではっきり他と区別することが出来る。生物は一目見て分かるほど個体間の形質の差が大きいから、「種」を区別するための定量的な測定の対象とはなりにくい。従って客観的な測定値を基にした種の定義がやりにくいのである。
もう1つの問題、とくに植物における問題は個体性がハッキリしていないことにある。1本のケヤキの木から5枚の標本を作ったとする。これは重複標本(Duplicate)と呼ばれ、採集番号は同じものが与えられるのが通常である。もしこの標本を基準標本とする場合には、その1つがホロタイプに選ばれ、他はイソタイプとなり、研究上は同格に扱われる。イヌノフグリを同じ日に同じ場所で5本採っても、おそらく同じように処理されるだろう。ところがこの5本は別個体で、従って別な遺伝子組成を持っている筈である。だからさっきのケヤキの5枚の標本と同じように扱うのは本当はおかしいのである。マイズルソウの場合はどうか?これは地下茎で殖えてゆくのと種子で殖えるのとがあるだろう。ところが殆どの場合、地上へ出た1本1本が別個体と見なされ、研究される。用心深い人でも、地下茎のつながっているものは同一個体と見るが、離れていれば別と見なすだろう。しかし地下茎はそういつまでもつながっているものではないから、独立していても以前はつながっていたものもあるし、種子から芽生えたものもあるはずである。それらを区別する方法は知られていない。ササの場合はどうか?これは言うまでもあるまい。ササの名前の多さとわかりにくさが、それを如実に物語っている。もしかするとわれわれは、ササの一個体のいろんな部分に、別な名前を付けているかも知れないのである。
このように植物では、別個体も同一株も、有性繁殖体も無性繁殖体も区別がむずかしく、同格の標本として扱われてしまうことに、研究上のむずかしさがあると見てよい。動物では多くの場合、個体性が明確であるし、例外が多いにしても、有性繁殖体が通常の状態なのでまだ救われている。植物のように個体の一部だけが標本として研究されるというようなこともあまりないのである。植物分類学の研究には、これは大きなハンディキャップとなっている筈である。
[野草45(365):62-64(1978)]
(10)
このシリーズもそろそろ終わりにしたい。気のきかないことを延々と書いても、読む人がソッポを向くだけだろう。その前にそもそもの発端であるクニタチカタバミに、もう一度立ち返ることにする。私はこれ迄に「新名」を作るほどの勉強をしてこなかったし、学名にせよ和名にせよ新名を作るやり方というものが、どうもスッキリ理解できないで来た。その私が新名を作ることに表立ってコントしたような新聞記事には、ビックリさせられたのである。第一こんなことが新聞記事の対象になり得るとは、私は思っていなかったのである。私は別にクニタチカタバミの是非を論ずるつもりはなく、ナマエを作ること一般について話をしているので、「クニタチ」のナマエはもう使わないことにする。ただしカタバミは議論に適当な相手なので、これに架空のナマエをつけて話を進める。
ナマエをつけるにはその元になる存在が必要で、この場合カタバミというモノがちゃんと存在していなければならない。うるさく言えば前に書いたとおり、この存在は周りがボケているのだが、少し遠くから見ればそのボケは問題あるまい。この中にたとえば「ヤエカタバミ」というナマエを作るには、それに相当する永続性のあるモノが存在せねばならない。つまり代を重ねても変わらないことが必要である。「ヤエカタバミ」が木本で何百年生きようとも、それだけではtaxonにはならないだろう。ところが実際にはこういうものにタクソンとしてのナマエがつけられたものがいくらもあって、それなりの理由があるのだから、私のは空論かもしれない。たとえば「薄墨桜」という「種」があると思っている人は少なくないだろう。
次に「ヤエカタバミ」というタクソンを作ったとする。これは既述のとおり、そういう名前の空き箱を作って置くということである。
その置き場はカタバミの箱の中になるだろう。そうするとその小箱に入らない部分は何だろうか?カタバミというのは大箱全体の名前から、この部分はカタバミではない。「ヤエカタバミ」に対して「タダノカタバミ」とでも言うべきものである。「ヤエカタバミ」を作った人は、これを「狭義のカタバミ」と呼ぶのが普通である。これに対して元の大箱は「広義のカタバミ」と呼ばれる。
ナマエを作る人は「ヤエカタバミ」を作ると「タダノカタバミ」が必然的に生まれることに気がついてくれなくては困る。しかしこれまでナマエを作った人は、みんな「ヤエカタバミ」を作っただけで、「タダノカタバミ」があることに気がつかないで放り出してあるように思う。ナマエを作るとき「通常のものに対して八重咲きのものを『ヤエカタバミ』と呼ぶ」というような記述がなされるが、これはとりもなおさず「カタバミ」のナマエを八重咲きでないものに対してのみ適用するという宣言で、彼は「ヤエカタバミ」ばかりでなく元来あった「カタバミ」の方にも枠をはめたことになる。ところが彼の一瞬前の解釈では、カタバミは八重も一重も含んでいたはずである。そうでなければ「ヤエ」をカタバミの品種なり変種なり、とにかく種以下のランクで呼ぶ理由がなくなる。「カタバミ」の名を「ヤエ」と対立したものとして残すなら、両方は同格であるべきなのだ。「カタバミ」が種の名なら「ヤエカタバミ」も種の名でなければならない。「ヤエカタバミ」の名を「カタバミ」の品種として認めるのならば「カタバミ」の名は八重も一重も含んだものとして認めていることになる。こうなると「原記載に無かったから新しいタクソンを作るのだ」という根拠もあやしくなってしまう。まさか彼は、種全体の呼び名である「カタバミ」を抹殺して、一重咲きの品種の呼び名にしてしまうつもりはあるまい。やはり「『カタバミ』というタクソンには常識的に八重のものも含まれているのだが、必要あって八重の方にだけ名をつけるのだ」ということになるのではあるまいか?それならば「ヤエカタバミ」が「カタバミ」の品種であることの説明はつく。だがそれと同時に、その補集合である「タダノカタバミ」というものも規定したのだと自覚してもらいたい。「ヤエ」の方だけ馬鹿にはっきり定義して、残りの方をあいまいにするものだから、「カタバミ」の適用範囲があやしくなり、「狭義の」などといい加減な名前で呼ばねばならなくなるのだ。種より品種の方がタクソンを作りやすいというおかしな先入観があるようだが、こういうことを考えると、決してそんなものではないと分かるだろう。こうして1つ種内にタクソンを作ると、自動的にその補集合であるもう1つのタクソンが規定され、種の中身全体に再編成が起こる。このことは、後で分かるが、大変重要でややこしい問題につながっている。
さてこれとは別に、白花のカタバミがみつかったとする。八重咲きにナマエがつくくらいだから、これにも当然「シロバナカタバミ」とナマエが付けられるに違いない。そしてこれに対して前と同様に自動的に「タダノカタバミ」ができる。ところで先の「タダノカタバミ」と今度の「タダノカタバミ」は同じものだろうか?明らかに別物である。前者は「八重でないカタバミ」であり、後者は「白花でないカタバミ」である。ナマエを作るとき、自分の作ったナマエのことだけしか考えていないと、上記のようなおかしなことになっていることに気がつかない。それなら解釈を統一して「先にあった『タダノカタバミ』の領域から新しいナマエの領域を取り去ったものが『タダノカタバミ』である」とすれば片づくように思える。ちょっとこれで話しを進めてみよう。
「カタバミ」の中に「ヤエ」を認めたとき、これは八重でありさえすればよいのだから、花の色は何でもよい。これに伴う「タダ」(これを「タダ①」とする)は、「八重咲きでないカタバミ」である。これも花の色は問わない。ここに更に「シロバナ」を認めるとき、上の解釈では「シロバナ」には八重咲き品は含まれない。このとき生まれる「タダ②」は「八重咲きでないカタバミの中で白花でないもの」である。一方「カタバミ」の中にさきに「シロバナ」を作ったときの「タダ③」は「白花でないカタバミ」である。ここに更に「ヤエ」を認めると、これには白花は含まれない。そしてこの時の「タダ④」は「白花でないカタバミのうちで八重でないもの」をいう(図1)。上の解釈では、ナマエをつける順序によって中身が変わってしまうのである。ここに4つ出現した「タダノカタバミ」のうち、「タダ②」と「タダ④」は同じものだろう。合計3種類の異なった「タダノカタバミ」が現れる。そればかりか「シロバナ」とか「ヤエ」とかの中身も、ナマエをつけるときにそれ以前にどんなナマエがあったかによって中身が異なってしまうのである。従ってそれらすべてがわからない限り、ナマエの示す実体の同一性は保証されない。
この「タダノカタバミ」というナマエは私の創作ではない。命名規約によって、種内に1つのタクソンを作ったとき、それに対する補集合(母変種とか母品種と呼ばれるもの)は、変種なら指種名を、変種の下の品種なら母変種のエピセットをそのランクのもとに繰り返したものである。ただし著者名はつけない。例えばOxalis corniculata L.の中にHaraという人がf. rubrifoliaという品種を作った場合、Oxalis corniculata L. f. rubrifolia Haraというナマエと共に Oxalis corniculata L. f. corniculataというナマエが自動的に誕生する。この、エピセットを繰り返すことによって「タダ」の方の表現をするというアイデアは良いのだが、残念ながら先に記したように「タダ①」「タダ②」「タダ③」「タダ④」などを区別することはできないので、不備と言ってよい。だからといって和名をつける時に、こういうことを考えないでよいという理由にはなるまい。特に和名は我が国では学名より遙かに多くの人々によって用いられ、情報交換の担い手とされているのだから、自分の創作したナマエによって、既存のナマエの解釈まで変わってしまわないように、万全な注意を払ってほしいのだ。
さて八重と白花は独立して起こる現象と思ってよいから、八重で白花というものも出現する可能性がある。今までの伝で行くと、これは「シロバナヤエカタバミ」とでもナマエがつけられるだろう。そしてこれも1つの品種として位置づけられるに違いない。だがちょっと待ってもらいたい。「シロバナ」と「ヤエ」を別々に認識した場合、その関係は図1のようなもので、ここですでに問題があることは前に書いた。「シロバナヤエ」が認識されるということは、関係が図2のようなものであることを意味する。このことは図1のような関係は正しくなく、図3のようなものであることを意味する。
図2によると「シロバナヤエ」というのは「シロバナ」の部分集合であり、また「ヤエ」の部分集合である。したがって「シロバナ」や「ヤエ」を、「カタバミ」の品種と規定したセンスから言えば「シロバナヤエ」は「シロバナ」や「ヤエ」と同格ではあり得ない。亜品種にもならない低位のタクソンである。「シロバナ」を規定した者は「白花のものは何でも」というつもりでナマエをつけたのだろう。そして「ヤエ」を作った者も「八重咲きのものは何でも」というつもりで領土宣言をしたに違いない。ところが気がついてみたら、他人の領土までウッカリ取り込んでいた…と思ったらそうではなくて、いつの間にか自分の土地を他人に取られていたということになり、結局中間地帯はどちらでもないとして、また別に領土宣言する羽目になったというわけである。カタバミには他にアカカタバミだのタチカタバミだのウスアカカタバミだのが認識されている。こういうものが話しに加わってきたら、状況は正に支離滅裂と言わねばならない。独立した一つ一つの形質にのみ注目してナマエを製造していったら、形質の数がふえるほどその組み合わせに対するナマエが増え、そのナマエの指し示す実体の中身は貧弱になるばかりだろう。ナマエを作る者が周囲に及ぼす影響に十分気を配ってくれているのかどうか、残念ながら疑問である。ここまでナマエを作ったことのある人なら、それに伴ってどれほどの「タダ」ができたかを考えれば、ことの重大さは分かるに違いない。
文房具の箱の中にエンピツとケシゴムとモノサシの箱を作り、更に「ケシゴムつきエンピツ」と「モノサシつきケシゴム」と「モノサシつきエンピツ」の箱を作るのだと言ったら、大抵の人は「そんな無駄なことは止めろ」と言うに違いない。作ったところでそれらの箱にモノが入るのは始めのうちだけだろう。そればかりでなく、文房具の整理全体に重大な悪影響をおよぼす。そんなヤヤコシイ区分けをした箱では、整理しようという意欲はしぼんでしまうだろう。
カタバミの箱の中に「ヤエ」、「シロバナ」、「シロバナヤエ」があって「タダ①」、「タダ②」、「タダ③」、「タダ④」の小箱がある。もし「アカ」を加えれば、小箱の数はもっと増える。「カタバミ」の中にこれだけ小箱があったら、誰でもどこへ入れたらよいかと考えるのが面倒くさくなるだろう。そうなると折角の小箱は利用されないで、別に「ナンデモカタバミ」という箱を作ってとりあえずそこにみんな入れておこうということになりはしないか?この「ナンデモカタバミ」は、もとの「カタバミ」と同じものである。ちがうところは「中身にコレコレのバラエティがあるぞ」という認識を伴っていることである。
こういう細かいナマエをつけることを、私は一概に否定するものではない。園芸や農業では、ホンの僅かな形質の違いでも、そのタクソンの価値に天地の差が生ずるのだから、そういう目的ならいくら細かいナマエでも十分有用である。しかし自然分類で類縁や系統を扱ったり、種の認識の手段にするためには、こういうナマエの付け方はなじまないのではないだろうか?まして「とにかく違うのだからナマエをつけておこう」という付け方は、特許の先願争いによく似ている。なにがタクソンであるかについて定説がないにしても、ナマエだけ先取りしておこうというやり方は、今に風が吹くかも知れないから猫でも集めておこうかという感じがする。1・2匹三味線に売れれば、あとは野良猫にしてしまってもよいというのでは近所迷惑である。せめて鼠をとる猫くらいにはしておいてもらいたい。
1つの形質だけに注目してナマエを作るのは控えたらどうだろうか?そういう形質は原記載には出ていないかも知れないが、記載を付け加えれば片づいてしまうだろう。例えば原記載に「花は黄色」と書いてあるのに白花が存在するのなら、記載文に「白い花もたまにはある」と一行付け加えれば済むのである。先の「ナンデモカタバミ」の認識はまさにこれである。
複数の独立な形質がつねに相伴って出現して、はじめてナマエをつける最低基準に達したと考えたらどうだろうか?例えば葉の赤いカタバミは必ず石灰岩地に現れるということになれば、そういう箱を作ってもカタバミ全体の中で領土争いが起こる恐れは少ないだろう。先の例で言えば、白花や八重では基準以下だが、白花で八重が必ず現れるなら基準に達したことになる。「シロバナヤエ」があって「シロバナ」や「ヤエ」が無いのは気に食わぬと思うだろう。それならば「シロバナヤエ」などというナマエもついでに気に食わぬと思えばよい。べつに基準に達したからといって、ナマエをつけなくてもよいのである。
ナマエというものは人為的なもので、しかも主観的要素を多く含んでいる。特に植物においては種の定義が確立していないので、それに対するナマエの根拠も不安定である。ナマエを共通なものとするルールも複雑なわりに抜け穴がある。従ってナマエをつけるという行為には、分類学についての深い認識と、まわりのナマエに対する周到な配慮が要求される。何か違っていればすぐにナマエをつけてしまうというやり方は、和名だろうと学名だろうと、分類学にとって有益とは思えない。目的と手段、過程を取り違えると、分類学自体を掘り崩す恐れさえある。ゴッドファーザーになる為には、それなりの実力の裏付けと、まわりからの信頼感がなければならない。
[野草45(366):78-82(1978)]
(11)
このシリーズは先号で終わるつもりだったが、原稿を書いているうちにまだ書くことがあることに気がついた。こういう下らぬ物語りは、しまっておいても陽の目を見ることはないので、野草同人の我慢強さに甘えて、もう少し続けさせてもらうことにする。
新種を作るよりも新品種を作る方がやさしいという錯覚があると前に書いた。私もこの文を書く前まで、何となくそう思っていた。ところが「タダノカタバミ」の存在を書いているうちに、錯覚どころか大間違いだと感じはじめた。種の中に下位のタクソンを作るほうが、種をもう1つ作るよりはるかに面倒な問題が起こるのである。今回はこれについて考えてみる。
「カタバミ」の中に「ヤエカタバミ」を作ると、自動的に「タダノカタバミ」ができ、これが騒ぎの元だということは説明した。ところが「カタバミ」の外に「ミヤマカタバミ」を作っても、このような問題は起きない。何故起きないのかよくわからないのだが、どうやら「タダノカタバミ」に相当する「タダノ Oxalis」というものが存在しないためらしい。
属というものは種を寄せ集めたものである。したがって種が1つ増えれば、属の縄張りはそれにつれて拡がる。種という下位のタクソンがなければ属は成り立たない。ところが種というものはそれ自身で存在できるもので、変種や品種のような下位のタクソンがなくても成り立ちうるし、上位のタクソンの属がなくても種は存在している。もし属の中に何かあるカタマリ(Section)を作ると、そのカタマリは構成要素であるいくつかの種の外側をなぞったものとなる。そして残りの部分もいくつかの種の外側をなぞったものである。Section をどう作っても、その境界が1つの種を二分するようなことは起こらない。つまり属の中には種レベルに於いて分からないものは存在しない。Oxalisの中にカタバミという囲いを作れば、その残りはタチカタバミ+ミヤマカタバミ+オオヤマカタバミ+……というような、分かったものの集合であって、「タダノ Oxalis」と言わねばならぬようなあいまいなものはない。いやむしろカタバミという種は属をもとにして定義されているのではなく、いくつかの形質を兼ね備えた個体の集合なのだから、その補集合は「タダノ Oxalis」などではなく、宇宙の森羅万象あらゆるものなのである。そんなものをカタバミの補集合として議論する必要はあるまい。「タダノ Oxalis」というものが存在しないという意味は、こういうことである。
いま述べたように、種というものはいくつかの形質を目安として、それらを兼ね具えている個体の集合である。それらを兼ね具えた個体ということが重要である。個体は目安とされた形質だけで成り立っているのではない。それよりはるかに多くの、無数のよくわからない構成要素で成り立っている。しかもこれ迄に知られている個体ばかりでなく、これから知られるであろうすべての個体を含むのである。そういう集まりのなかに新しく1つの形質を目安として「ヤエカタバミ」という縄張りを作る。これで大丈夫なのだろうか?タクソンというのは個体の集合だから、個体と個体の間を綱が通ってくれないと困る。ところが大分前に書いたとおり、このやり方を繰り返してゆくと、個体の中を綱が通ってしまうおそれがある。縄を1本張った本人はオニギリ弁当のつもりでも、実際にはオニギリは独立していないで五輪マークのように食い込み合っていはしないか?そうするとあるナマエで呼ばれる個体が、同時に同等の他のナマエでも呼ばれ得るということが起こる。これではナマエというものが意味を持たなくなってしまう。生物の種の規定があいまいであるからこういうことは常に起こりうることではあるが、なるべく起こらぬように努力するに越したことはない。そういう努力なしにナマエを作ってゆくと、認識の手段としてのナマエが混乱の元となるばかりか、結局我々が使うナマエの信頼性を掘り崩す結果となるに違いない。
数学で「連続」の概念を説明するとき1本の紐に例えることがある。この紐が連続であるならば、これをどこかで切ると一方の切れ端には端があるがもう一方の切れ端には端というものが存在しない。種というものもこんなものだろう。われわれは種というものを形質上不連続なものとして認識している。つまり一つ一つの種の紐はちゃんと両端を持っている。そして種の内部はある形質レベルでは、1つの連続したものとして認識している。このことはもしこれを2つに切って一方にハッキリした端を認めるならば、他の切片には端がないことを意味する。ヤエタタバミを区別すればタダノカタバミには端がなくなるのである。紐の連続性ということは、構成要素をいくらでも小さくとり得るという点に本質があるのに対して、種の場合は構成要素である形質に未知のものがいくらでもあり得るという点に違いがあるにすぎない。もし種という紐を2つに切りたければ、それが2つの互いに不連続な連続体から成り立っていること、つまりどちら側にも端があるということ、を言わねばならない。そのためには片一方のタクソンだけを記述していたのでは片手落ちであって、もう片方の独自性も同じくらい強調する必要がある。
ところで種を作り上げている形質はたくさんあって、それらが多次元的にかかわり合って1つの種を作り上げているものと私は思っている。この塊を2つに分けるということは、その中にある1つの面を作るということである。こう考えるとたった1つの形質でもって種を二分することは出来そうにない。先に述べた紐のように、形質のつながり方が一次元的なものならば、1個の形質を取り上げて紐を切断することが出来る(たとえ片方に端がないにしても)。しかしそんな簡単なものとは誰も思うまい。もし形質の構成する空間が三次元的であるとすると、これを最も単純な面である平面で切断するには、少なくとも3個の点を規定せねばならない。もし3次元空間を2個の点を通る面で切ろうとすれば、その切り方は無数にあって決定できない。n次元空間なら少なくともn個の点を指定する必要がある。従ってそういう空間をただ1個の形質のみで二分しようとする人は、種というものをオソロシク簡単な構造と考えているか、さもなければその1個の形質が原爆級の重大な形質であると確信しているかのどちらかなのだろう。
原爆級というのはいわゆる「重要な」形質のことである。こういう形質は見かけは1つでもそれに紐がついていて、引っ張るとあちこちでベルが鳴りだすといったものである。そのたくさんのベルの場所が、タクソンを分ける面を決定するのに十分な根拠を与えるのだ。これに対して「重要でない」形質というのは紐の数が少なく、引っ張ってもあまりベルが鳴らないということである。従ってそれらが作る面はアイマイで、全体に与える影響は弱い。こういう強弱がランクとして反映されるのだろう。
分子の下部構造として原子があるのだから、種の下部構造として亜種や品種があっても差し支えなかろう。こういう観点からタクソンを作るなら、やはりその補集合の概念をハッキリさせねばならない。水の構成要素として水素だけ定義して、あとは知らんというのは片手落ちである。
他の面から言えば、そういうナマエを用いて何を論ずるかによって、必要とする細かさの程度が異なる。分子運動論をやるには、水の分子はただの粒でよく、中身のことなどどうでもよい。そんなことにまで一々水は酸素と水素で出来ていて、水素は電子1個と中性子1個と陽子1個で出来ていて…などという必要はサラサラない。それどころか普通に「水」と言えばそれで十分実用上の概念となるのであって、その中に15Oでできた水の「品種」がいくらか混じっていても、ちっとも気にすることはないのである。種の定義がかなり厳密に規定できる物質でも、この程度である。まして定義がアイマイな生物の種について、何でもかんでも細かく区別せねばならぬ理由は見つけにくい。まして細かく区別するほうが正確だなどということにはならない。そんな考え方は、物差しの目盛りが0.1mm までしか読めないのに、掛け算や割り算をやって小数点以下10桁まで答えを出して、この方が正確だというのに似ていると思う。
[野草46(367):2-4(1979)]
(12)
ここでランクの表示について気になっていることを記す。生物のタクソンは階級的な構造を取るものと理解されている。つまり会社の中に部があり、部の下に課があり、課の下に係があり、その中に人がいるという形である。これをナントカ社の販売部仕入課書籍係の金井さんというように表現する。ナントカ社の金井さんでは、その人がどんな組織の中でどんな役割を持っているかはわからない。それでもこういう表現が普通に用いられるのは、途中が分かっているので省略しても差し支えないからである。
学名に付けられたランク名も、こういう位置づけを表している。よく用いられるものに、ssp. var. form. などある。この他にもsubvar. subform. も稀に用いられる。これらがそれぞれ種の中での役割というか兵隊の位を示しているわけである。ところで学名の属名、示種名にはランク名は示されていない。これは学名の第1番目のナマエは属を示し、2番目のナマエが属と組み合って種を示すことが誰にも分かっているから、それらの表示を省くことが出来るのである。ところが種内のタクソンには、ナマエの前に必ずランク名がついている。これは上のような慣行が種内では確立していないからである。したがって品種を示すにはformaとかf.とかのランク名をつけねばならない。ある品種は種の下にいきなり出てくる。別な品種は同じ種の中のある変種の下に示される。これは少々おかしなことではあるまいか。さきのナントカ会社の金井さんと同じに、途中で何か省略されていると思うべきだろう。どういうものが省略されているかが問題である。
種というものは1つの単位であるから、一応互いに同じ認識レベルの上にあると考えねばならない。その中のいろいろなランクも、それぞれ同じレベルにあるはずである。そうでなければ同じランク名で呼ぶ意味はない。A社の係とB社の部長が対等だなどというとはあり得ない。種の中で用いられるランク名には亜種(ssp.)、変種(var.)、亜変種(subvar. )、品種(forma)、亜品種(subforma)などがある。こういうものがみんな有意なランクであるかどうかについては議論が分かれるところだが、一応みんなあるものとすると、ナントカ社の金井さんを正式に書いたように、タダノカタバミはOxalis corniculata ssp. corniculata var. corniculata subvar. corniculata f. corniculataとなる。こんなに長いナマエが必要とは誰も思うまい。これを短く表すために、例えば Oxalis corniculata f. corniculataと途中が略される。ところが別にOxalis corniculata var. corniculataという表現があり、この2つは別なタクソンであることを示している。つまりvar. というランク名はこれに続くエピセットが種の中で2番目のランクであることを示し、f. は4番目のランクであることを示している。
まだ別な略し方もある。こんなにたくさんの種内のランクは不要だから、削ってしまえというものである。例えば「課長補佐」的な役は無くもがなだから定削の対象とし、subのつくランクは削ってしまう。すると種の中に残るのは var. とf. だけである。こうすると「乱暴だ」という声が聞こえてきそうだ。subvar. やsubformaを削るのはあまり異論はないはずだが、subsp. を消そうとすると抵抗が大きい。というのは近頃はvar. の上にssp. を認める研究者がふえている、つまり種の中をssp. 、var. 、f. の3段階に区切るのが一般化しているようなのである。そこでこの3つを残してみよう。この3つのランクを皆が認めるなら、もはやランク名を示す必要はない。学名の1番目の綴りは属、2番目の綴りは種のランクを示していることは先刻承知しているから、同様に3番目は亜種、4番目は変種、5番目は品種だと思えばよい。ssp. だのvar. だのf. は大小関係、上下関係を示す記号だから、位置が確定すればランク名というものは不要となる。そうするとヤエカタバミに対するタダノカタバミはOxalis corniculata corniculata corniculata corniculataとなる。これでもジュゲムジュゲム……の感がないでない。もっと簡単にしたければ、切り捨てるのはシッポの方であることは明らかである。Oxalis corniculata f. corniculataと書いてあると、切り捨てるのが何だか恐れ多いように思うが、上のように書いてあると、シッポの先をちょっと切っても大したことはないし、むしろ切ったほうがスッキリすることが自ずと分かるだろう。
こういうナマエは、前に述べた動物の学名とよく似てくる。動物では第3のエピセット(ssp. )までを公式に認め、これ以下の名はつけてもよいが学名としての扱いは受けない。植物では何番目まで認めるかについて議論の多いところだろうが、全部認めてもどうということはない。それよりもタクソンの表示がみんな同じ形式になるということの方が大事である。ナマエが冗長なら、自然に使われないで短くなるに違いない。金井さんがセーターを着たときと背広を着たときで、別なナマエで呼ばれる必要はない。彼がセーターと背広を持っているということの方が大事なのである。
[野草46(368):18-19(1979)]
(13)
学名の話しはこれくらいにして、今度は和名の話しに入ろう。和名と学名の大きな違いは、規則がないということのほかに、ランクが示されないということである。だからハナグルマがモチツツジの品種だということはわからない。
博物館に入るといろんな質問の応対をせねばならないが、時々あるのが植物名の表示が正しくないというものだ。たとえばある教科書にタンポポというナマエが使われている。しかしタンポポという植物は存在しない。ゆえにこの教科書は誤っており、カントウタンポポとかセイヨウタンポポとか「正確な」ナマエを用いるべきであるというのだ。
タンポポ一般を示すには学名でTaraxacumと言えば済むが、和名でタンポポと言ってもみんな承知しない。だから我々も「タンポポ属」とか「タンポポの類」とかぎごちない呼び方をせねばならないのでどうも落ちつかない。和名にランクがないというのはこういうことである。こういうのはまだ我慢できるが、ランクが無いために名は一つ一つがみな対等の位にあるかのごとく錯覚され、つけなくても済むのにナマエをつけることが流行し、つけられたナマエはその大小軽重にかかわらず使うほうが正確であるように思い込まれ、ナマエをつけるのが分類学の仕事であるかの如く勘違いされるのである。これには良いことは1つもない。いずれにせよタンポポ一般を呼ぶナマエが必要なことはわかってもらえるだろう。つまり属レベルの呼び名である。もともとタンポポというナマエはTaraxacumに対応させてよいのだから、みんなでそのように了解すればよい。そうすると当然いろいろなレベルに対応したナマエが必要となる。種レベルのナマエは属レベルのナマエの前につけるとしよう。カントウタンポポとかセイヨウタンポポのたぐいである。もっと下のレベルのナマエは更にその前にくっつければよい。和名にはルールがないから誰でも勝手に命名できてよいという人がいるが、この位のルールはあった方が便利ではあるまいか?それよりも、ナマエが違えば夫々対等であるとか、細かいナマエをつける方がより正確だとかいう錯覚を無くすことは、分類や同定をする者にとって大切なことだと思う。細かく分けたい人はいくらでもナマエを付け加えればよい。シロバナヒロハノカントウタンポポとかフイリキレハノナガバノサツキヒナノウスツボとか好きなだけ付け加えればよいのである。長いナマエほどその示す範囲は小さく、取るに足らないのだということが分かっていればよいのだ。
このように先へ先へ(左へ左へ)とナマエを付け足してランクを示すのだから、後(右)へナマエを付け足さないほうがよい。カントウタンポポに近いからカントウタンポポモドキなどとするとわけがわからなくなる。
こんな考え方で見直すと、多くの和名は上のようなセンスに従った形をしている。だからセンスに合わないいくつかのナマエを作り変えればよい。こういうとすぐナマエの付け変えに熱中する人が現れるとかなわないのであわてて付け加えるが、和名には先取権を認めるべきではない。学名に複雑なルールがある1つの大きな理由は先取権にあるのだから、そういう規則に縛られたくない和名に先取権を云々するのは筋が通らない。それにこういうセンスでの新和名は、既成のもののシッポにリボンをつけるようなものだから、それをつけている猫は俺のものだというわけにゆかないだろう。和名の混乱を心配して古い和名を尊重しようと提唱する機運が時々起こるが、これはとりもなおさず先取権問題そのものであり、厳重なルールなしに実行できるものではない。従ってその実現には、自己規制が必要であるという認識が広く行き渡るような、分類学やナマエに対する考え方の転換を十分にPRする必要があるだろう。
繰り返して言うが、私はナマエをつけることが悪いというのではない。ナマエはある実体を指し示す抽象なのだから、その細かさについてはある程度で打ち切るのがよいと考えるのである。リンネが二名法を作ったことについて多とされている所以は、二名法の発明にその本質があるのではなく、いくら記述してもしきれない実体に対して、思い切って記述的な呼び名をやめて、抽象的な短いナマエを与えて身代わりにしたということにある。それまでは例えば「黄色い花が咲いて赤くて食べられる実が成って体に毛が生えていて青臭い匂いがして葉が細かく切れているナスビ」というようなナマエが用いられていたのである。近頃のように細かい変化に対して一々ナマエをつけていると、いっそのこと記述文をそのままナマエにすればよいということになる。これではリンネ以前に退行してしまうではないか。「金井さん」というナマエでは中身がよく分からなくて「不正確」だからといって「ナントカ社の……部…課…係でセーターと背広を持っていて男の子が2人いて女房の尻に敷かれている金井さん」というナマエをつけたところで、不正確なことに変わりはない。そういうものは金井さんの属性なのだから、「金井さん」というナマエのついた箱のなかに入っていて、誰でも見ることが出来さえすればよい。学校の先生はその中から子供の偏差値とオヤジの月給の情報を取り出して、進学先を判断すればよい。銀行のセールスマンはボーナスを預金させるにはダンナとワイフのどちらを攻めればよいかを考えればよい。そういうことは利用者各自がそれぞれの利用法に応じて自前の箱を作ればよいのであって、「金井さん」の箱と別に「子供の偏差値35、進学先私立 Cクラスの金井さん」という箱を作って、みんなにこれを利用しろというようなことはしない方がよかろう。
書くタネが尽きたのでここらでおしまいにする。空き箱をこれ以上たくさん作ることと、空き箱に中身を詰めることと、どっちがやりがいがあるか、考えるきっかけになれば幸いである。
[野草46(369):34-35(1979)]
(14)
カタバミという種のなかにヤエカタバミを作ると、その補集合であるタダノカタバミが自動的にでき、これが問題をはらんでいるとしてこれまで議論を進めてきた。ところがこの話しをTさんにしたら、私の論拠はおかしいのではないかと言う。私はヤエカタバミというものはもともとカタバミの部分集合であったのを、あらためてハッキリ認識して垣根を作ったものと考えていた。しかしTさんの言うには、元来カタバミの中にはヤエは含まれていなかったので、ヤエカタバミはカタバミの外側に付け加えられたものだという。今回はこの見方で話しを進めてみる。
ある標本をカタバミと同定する根拠は、基準標本や原記載と比べてみて得られる。基準標本と原記載に矛盾があったり、調べたい形質について原記載が言及していないときは、基準標本が頼りになる。前に記したとおり、記載文は「知りえたことがら」だけしか書けないのであって、それを書いた者は実体Gやタイプ標本GSTのすべての情報を並べたわけではない。それができるのなら標本など保存する必要はない。従ってこちらが必要とする情報を記載文が提供してくれないのなら、基準標本を調べるしかないのである。
見たことはないけれど、カタバミの基準標本は一重の黄色い花のものだろう。いや、そうであるとして話を進めよう。そうすると、カタバミという種は一重の黄色い花をつけるものであって、八重のものは含んでいないと考えるべきである。リンネは、カタバミという種を認知したとき、知ってか知らずか八重咲きのものを疎外してしまったのである。ところが炯眼な某氏が、カタバミであるのに八重咲きのものを見つけてしまったのである。これは虚空の星々の中から彗星を発見するような大仕事である。この八重咲きのカタバミは「カタバミ」ではない。なぜなら原記載とも基準標本とも合わないからである。しからば別種かというと、とてもそうだと言うだけの勇気を与えるほど「カタバミ」とは違っていない。要するにリンネがウッカリしていたものだから迷子を作ってしまい、それが200年あまりたって見つかったというわけである。この迷子の復帰には大変なトラブルが伴う。
別種にはならないからカタバミに入れるしかない。カタバミの定義は基準標本と原記載で規定されていて、この迷子を受け入れる余地はない。そこでこの迷子をヤエカタバミというカタバミの品種(でも変種でも何でもよい)として、カタバミの外側にそっとくっつけてやる。そうするとおそろしいカタストロフが起こる。
カタバミという種の範囲は、原記載や基準標本がどうであろうと、この新参者のくっついた範囲までいやでも拡大する。そうするとリンネさんのいうカタバミはもはや種ではあり得ない。それは「新カタバミ」の一部分にすぎなくなるのだから、種以下のランクになってしまう。そうするとカタバミという種はどこに行ってしまったのか?もちろん、ヤエカタバミと「元カタバミ」の合わさったものである。だが、このタクソンを示す原記載も基準標本もナマエも存在しないではないか。
さっき八重咲きのものを見つけたとき、「これは原記載や基準標本と合わない」という理由でカタバミの外にヤエカタバミを作ったのである。今になってあわてて「元カタバミ」の原記載と基準標本を「新カタバミ」のそれに据え直そうというのなら矛盾している。さっきの標準でやれば「新カタバミ」の基準標本は一重と八重の花を持っていなければならない。基準標本は1枚で、それも1個体であるべきなのだから、「新カタバミ」の基準標本は同じ株に一重と八重の花が付いていなければならない。そうすると一重の花のみをつけたカタバミは「新カタバミ」ではないのだから、さっきのやり方では「新カタバミ」の外に「一重カタバミ」を作ってくっつけてやらねばならないことになる。これではイタチごっこである。
標本というものは、実体Gのホンの一部分のホンの一瞬の姿のそのまたホンの一部を保っているにすぎない。基準標本の役割は前に述べたように、ナマエgと実体Gをつなぐものであって、実体Gの標準でも模範でもない。代表ではあるけれど、それはたとえば、カナイさんがアフリカへ行けば日本人の代表になるようなものである。カナイさんが日本人の基準標本と思っている人の前に、もう1人日本人らしい人物が現れたとき、「カナイはシングルの背広を着ているのにコイツはダブルを着ている。故にコイツは日本人ではない」と思うのは馬鹿げていると誰でも思うだろう。ところが基準標本中心主義を金科玉条とすると、こういうことが実際起こるのである。標本1枚では、少なくとも変化の幅については何も示せないのである。こういう不都合を補うのが記載文の役割で、コトバによる抽象的な記述に大きな意義が出てくる。
[野草46(370):50-51(1979)]
(15)
「三角形」という種を記載文と基準標本で周知させるにはどうしたらよいだろう?まず三角形の基準標本を決めねばならない。これに三角定規を使うとしよう。三角定規には二等辺のと不等辺のとがある。その中の不等辺のものを基準標本としよう。そうすると二等辺のものは三角形ではないのか?これも三角形である。だからこれもタイプに指定しておこう。これはアイソタイプ(副基準標本)である。しかしこんなことではとても片づかない。ミヤマタニソバの葉は?扇子を広げた形は?オデンのコンニャクは?ビキニの水着は?ときりがなくなる。要するに標本というものは具体的であるだけに包括性に乏しいのである。これを補うために抽象的なコトバによる記載文が必要となる。曰く「三角形とは3本の線分より成る多角形である」ここで線分だの多角形だのという用語は、既に他で厳密に定義されているものとする(これがクセモノであるのだが)。これで一般的にどんな三角形でも定義できそうである。例えば 6.3、1.8、5.0cmのものでも、2.0、2.0、3.0cmのものでもよい。しかし 6.3、1.0、5.1cmというのはダメである。これでは三角形は出来ない。もっとも、定義の中には「…より成る…」という言葉がある。最後の組み合わせでは三角形は「成らない」から、あらかじめ除外されていると解釈することもできよう。
さてこの記載文は、基準標本を正しく表現しているだろうか?否である。三角形は平面図形なのに、三角定規は立体である。いくら大目に見ても、原記載に合うところは定規の稜の上でしかない。ミヤマタニタデの葉やオデンのコンニャクでは、一致するところは1つもない。それでもこれらのものを三角形と称して通用するのは、記載文と基準標本のもつ情報群を利用者が適宜取捨選択したうえ、自分の知識を加味して解釈するからである。標本は具体的でありすぎ、文章は抽象的でありすぎるので、利用者の総合判断が必要となる。
さて、迷子を受け入れた結果起こった騒ぎは、まだ片づいていない。「新カタバミ」という種を示す基準標本も記載文も存在しないのである。あるのは「元カタバミ」のそれだけである。この「元カタバミ」の形質は「新カタバミ」のそれと大部分共通であるし、種と種以下のランクのタクソンが全く異なる形質ばかりで成り立つとは思われない。だからこの「元カタバミ」の記載文と基準標本を、「新カタバミ」を示せるように作り直せばよい。 まず、花が一重という記載があるなら削除する。何か書いてあれば、今度のようにそれと異なったものが見つかったとき、また騒ぎが起こるからである。花の色も削除する。白花やピンクが見つかる可能性が大いにあるから。葉の色も書かないことにする。赤い葉のがあるし、斑入りだってないわけではない。記載文はそれくらいにして、基準標本も「厳密に」調べたとき問題がないようにする。まず花はとりのぞいてしまう。ついていると花が黄色だの一重だのと1つに決まってしまうからである。同じ理由で葉も取り去っておく。
冒頭のような立場に立って記載文や基準標本を作った結果は以上のようになる。これで何かの役に立つだろうか?花や葉のついたカタバミはこの基準標本と一致しないのだから、カタバミではないことになってしまう。
そもそも八重のカタバミは「カタバミ」ではないとしながらも、カタバミにくっつけてしまった理由は何だろう?ヤエカタバミの大部分の形質が、カタバミのそれと一致したためである。それにもかかわらずカタバミの中に取り込まなかったのは、たった1つの形質が一致しなかったためである。これは適切な処置だろうか?記載文や基準標本の解釈が厳密に過ぎて、引っ込みが付かなくなった感じである。
リンネは我々がカタバミと思っているものすべてをOxalis corniculataとナマエをつけたのであって、少々つけ落しがあっても、人間のやることだから大目に見て融通をきかせようという気になった方が、万事丸く収まりそうである。この植物は花が八重である点は違うが、カタバミの原記載や基準標本の大部分と合うから、カタバミに入れておこうという考え方である。重要でない形質が違うだけだからというのではない。一重の花ということはきわめて正常で重要な形質である。けれどもたった1つの形質だけ違って、あとはすべて同じとき、「だから違う」とはなかなか言えない。ハコネコメツツジは葯が裂開するという、ツツジ属にあるまじき重大な特徴があるのに、これをRhododendron属でなくTsusiophyllum属にすることには、見解が一致しないのである。
上の考え方では、八重のカタバミはカタバミの外で迷子になっていたのではなく。もともとカタバミの中にあって、たまたま眼のよい人が見つけてしまったのである。それは、スカートは膝下10cmと決まっているのに、膝下5cmにした子がいて、うるさい補導係の教師につかまったようなものである。その子をどういう処分にするかは、違反の程度によるばかりでなく、その子が翌日どんな恰好で来るかという、その子の性格によって決まることの方が多いだろう。それに、つかまえた教師の性格によるところも大きい。
こういうふうに考えると、迷子が戻ったときのような騒ぎは起こらない。カタバミの縄張りは八重が見つかっても安泰である。その代わり、ヤエカタバミを作るには、同じランクのタダノカタバミの始末をせねばならないが、迷子のときのようなカタバミ全体の始末をせねばならないのよりは楽だろう。
Tさんの考え方は、カタバミの外へ別な種を作るときには何も問題はないとする私の考え方と相通じるものがあったので、うまくゆくかと思ったが駄目だった。そのわけは、ヤエカタバミをカタバミから離せないで、くっつけざるを得なかったことにある。種というものは原記載や基準標本とは関係なく、何だかわからないある共通な理解があるためだろう。それがわかれば、種の定義は出来たことになる。
[野草46(371):66-67(1979)]
(16)
ある実体Gを指し示す名は1つしかないことになっている。即ちgである。もし何かの拍子にGを指し示す名がgとfの2つ出来てしまったときには、どっちの名を使うべきか、つまりどっちの名が「正しい」名でどっちが「誤った」名かを、命名規約にてらして判定する。もしfの方が「正しい」となれば、gは異名に「落とされ」る。ここでいくつかの単語にカッコをつけたのは、こういう言葉づかいがきわめて誤解を招きやすく、実際招いているということである。
もしgもfも過不足無く実体Gを指し示しているのなら、どっちを使おうと一向差し支えないと考えてはなぜいけないのだろうか?この場合はどっちを使おうと、本質的な問題ではないはずだ。とこかにこの2つは同じものを指し、カドある時にはどっちを使うかという対応表ができていればよい。ナマエが2つあろうと10あろうと同じことである。つまり、g→f、a→f、p→fという表があればよい。近頃のように電算機でナマエを処理しようという時代になると、こんなことは朝飯前である。実際、こういう対応表(この頃の言葉でシソーラスという)を作っておかなければ、古い文献に出てくるナマエを最新の知識の下に利用するわけにゆかない。
ただ、1つの論文の中で同一の植物を2通りのナマエで呼ぶのは無駄である。筋が通らないとかみっともないとか言ってないことに注意してもらいたい。Gという実体に対してgとfの2通りの名を使って何か言うためには、その論文のどこかにgとfは同じものを指すことを注釈する必要がある。それが無駄だというのである。同じ理由でいろんな人が同じ実体Gを呼ぶのにいろんなナマエを使うのは無駄である。だから便宜上1つのナマエで呼ぶ方が都合がよいから、どれか1つを選ぶのである。したがってこれを選び出す操作において「誤った」とか「正しい」とか「落とす」という差別用語は誤解の元なのである。
前に書いたとおりナマエの本体はエピセットまでで、著者名は出典検索の目的以外の何者でもないのだが、著者名がエピセットの方にくっついていて、ナマエの所有権を示すもののように思われがちである。私は分類研究者のハシクレなのに、こういうことをする見識も勇気も持ち合わせていないのであるが、他人の作ったナマエを変えたりつぶしたりすることは、大変勇気のいることらしい。先人の作ったナマエを変更しようとする者が、前もってその「所有者」の了解を求めたり、やったあとでアイサツしたりするというはなしは何度かきかされたことがある。そうかと思うと「俺の作ったナマエをツブした」と、うらまれる人もいるらしい。また、権威ある著者によって作られたナマエが「誤って」いるにもかかわらず、誰も手をつけないで通用して来た例もあるようだ。どうもこのあたりはもっとクールにゆかないと困る。それよりも、gとfが同じものを指すのなら、どっちを使ったって誤りではないじゃないかという思いが、私には先に立つのである。
gとfの示す範囲が一部しか重なっていないとどうなるか?例えばGの一部のみがFに含まれてfと呼ばれることになるとしよう。この場合、fの異名としてg pro parteとして示される。示されるけれどもこの対応表は実際の役に立たない。gのどのparteがFに入りどのparteが入らないかが、ナマエでは示されないからである。だからむしろgとfを対応させることは出来ないというほうがよい。gのナマエは2つのタクソンを含むことになってしまったので、これこそ「誤って」いると言ってよいだろう。
これとよく似ていてしばしば問題になるのは、1つの種に対して2つの「正当な」ナマエがあって、どちらを使うべきかとものである。イヌザンショウにはZanthoxylum schinifoliumとFagara schinifoliaという2つの「正当な」ナマエがある。ヤミクモに規約に当てはめれば前者が「正しい」ナマエである。しかしこれでは問題の次元を取り違えている。この問題は
- ① Zanthoxylumと呼ばれていた属はFagaraとZanthoxylumの2つの属に分けねばならない。
- ② Fagaraとされるグループの特徴は、属を分けるほどの重要さは認められない。
という、2つの意見の反映である。①の見解を表すのがFagara schin.であり、②の見解を示すのがZanthoxylum shin.である。これは分類学的見解の差であって、規則に当てはめても決着は付かない。本当はこういうことも一定のルールに当てはめて決められるとよいのだが、種の定義が確立していないので、そんなルールは作りようがないのである。先のハコネコメツツジもこの例である。植物を研究する分類学以外の研究者からこの点をただされることがよくあるが、返事に困ってしまう。こういうことについては一般的な判断の基準がないから「どっちにせよ」などと言えるはずがない。これについてはむしろ使おうとする人の方に誤解があることが多い。
彼は「誤った」ナマエを使いたくないから、どっちが「正しい」のかを知りたいのである。そういう人に「どっちも正しい」などと言っても当惑するだけである。こういう場合には「成書に従え」ということにしている。それがたまたまFagaraであろうとZanthoxylumであろうと、同じものを示している正当なナマエなのである。ちょうど入口は違っても奥でつながっている、田舎の温泉みたいなものである。物知りで詮索好きな人は「何故Fagaraを使わないでZanthoxylumを使ったのか? FagaraとZanthoxylumの特質の重要性は如何?」などと尋ねるかもしれない。しかしこの場合のナマエは、そんな分類学上の見解の問題ではあるまい。ただイヌザンショウを示す手続きにすぎないのだから、相手がお気に召さなければZanthoxylumをFagaraに付け替えてもかまったものではないのである。それは「シソ」がシソ科の棚にあろうと野菜の棚にあろうと、シソ以外の何者でもなければよいのと同じである。この場合のナマエの目的は「同定」であって、湯船につかることが目的だから、どっちの入口から入ったなどということは気にしなくてよいのである。ただし「分類」という観点に立てば話しは別である。この場合には、入口を間違えると大事件になるのである。
[野草46(372):82-83(1979)]
(17)
変種だの品種だのという分類群は、種の内部において階級構造をなしているという考え方に異議を唱える人もある。これらのランク名は違いの程度を示すもので、上下関係はないという意見である。だから種の下にいきなり品種が作られたり、亜種の次に品種が付いていたりするのは当然で、私の言うように一々亜種、変種、品種という順序にみんな並べなければならないと考える必要はないというものである。
ランク名は違いの程度を示すという考え方は正しいと思う。それはタクソンの境目の強さを示すと言い換えてもよかろう。亜種はブロック塀、変種は生け垣、品種は歩道の縁石とでも言おうか。こうなると種の境目は刑務所の塀くらいだろう。
さて刑務所の壁に囲まれた種という広場があって、そこにいろんな人がテンデに境目を作ると考えよう。これにはルールが必要となる。もっとも重要なルールは「境目は交わってはならない」というものである。あるタクソンの中を別なタクソンの境目が横切れば、どっちかのタクソンは成り立たなくなるのだから、これは当然である。このことは、種の中にあるタクソンを作ろうとする者は、すでに存在する他のタクソンを無視して作ることはできないということを意味する。さてこのルールだけに則って境目を作るやり方は、見かけ上図に示したA、B、Cの3通りある。
Aの表現は不正確で、実際には二分した一方をタクソンとして認めることなので、正しくはA′である。したがってA′はBと同じである。Cは囲んだ中には他のタクソンを含まないが、囲わなかった方には含んでいるのでBの裏返しである。こういうやり方で造園してゆけば何の不都合も無いように思えるのだが、結果はちょっと困ったことが起こるのである。ブロック塀に囲まれた生垣が出来るのはよいが、Dのように縁石に囲まれたブロック塀もできる。つまり品種の中に亜種ができるようなことが起こる。
ランクに上下関係がないというはじめの人の意見なら、こういうことが起こっても一向差し支えない。つまり、
- ー var. stenophylla f. albiflora と
- ー var. macrosepala f. albiflora があるとき、同類項をまとめて
- ー f. albiflora var. stenophylla
- ー f. albiflora var. macrosepala
とする方が、片づくではないかというものである。最初のペアでalbifloraとalbaの2通りの表現をしているのは、同一種内ではランクのいかんにかかわらず同じエビセットは使えないからである。またこういう考え方では、品種の中にまた別な品種があっても一向差し支えないことになる。実際には命名規約上からいうと、最初のペアは成り立たない。同じ属の中では異なるタクソンを表すのに、既に他で使われている小名は使えないからである。
冒頭の意見の人はこれを認めるだろうか?おそらく否である。つまり縁石の中にはブロック塀も生垣も縁石さえも含まれてはならず、生垣の中にはもう1つの生垣やブロック塀を造ってはならないというルールがあることになる。このことはこれらのランクに階級構造を認めることにほかならない。しかしながらこれは「縁石は生垣の中になければならず、石垣はブロック塀の中になければならない」ということにはならないので、私の意見が通ったことにはならない。
ところで「違いの程度」の「違い」というのは何だろうか?「違いがわかる」と言ったってNessばかり飲んでいたのでは違うか同じかわかろう筈がない。Maxwellと比べてみるからわかるのである。2つ以上のものがないと「違い」というものは存在しえないのである。
「シロバナ」というものを1つのランクと認めて囲うということは、もともと黄色い花だけと思っていた広場の片隅に白い花がみつかったので、黄色い花と白い花とをそれぞれ寄せ集めて、その間に縁石で境目を作ったのである。したがってこの境目は「シロバナ」のためにだけあるのではない。当然「キバナ」の方も囲っていることになる。つまりA′の図はまだ不完全でA″が本当の姿なのである。「シロバナ」を作った人は、自分が囲ったのは白花だけで、それ以外のものはみんな残りのところへ入っているものと考えているようだ。「タダノカタバミ」の一般的理解もそのようであるが、これは正しくないと思う。「タダノカタバミ」には黄花しか含まれていないのである。従って万一「アカバナ」が見つかったら、それは「タダ」の方からだけ出たのではなく、「シロバナ」の方からも出ているかも知れないのである。
さてこう考えると、一方を縁石で仕切れば、自動的に残りも同じ縁石で仕切られることになる。これを図でやってみるとC′のようになる。この場合「残り」というのは「タダノカタバミ」であり、その中にもvar.もssp.も含まれ得る。だから縁石に囲まれたブロック塀や生垣ができてしまうのである。これは先の第2のルールに反する。ただしこのことは作図のしかたが議論に忠実でないから起こることである。種の中に変種でも亜種でも作れば、それに応じて「タダノ」に当たる変種や亜種が自動的にできるから、Cの図は正しくないのであって、A″のようになるべきである。このような図式を考えれば話が片づいたように見える。
ところがまだ先がある。異なったランクのタクソンを作る順序によって話が変わってくるのである。
Eに於いて種の中が変種で2分されている。ここに何か品種レベルのタクソンを作るのは何でもない。Fのようになるだけである。ところがGのように、はじめに品種レベルで分割されているところへ上位のランクの亜種を作ろうとすると厄介なことになる。第2のルールによってブロック塀は縁石より外側に作らねばならない。ブロック塀を縁石に全く合わせて作らねばならないということは、まず起こるまい。そんなものはあってもなくても同じである。上位のタクソンを作るからには、下位のチャチなタクソンを無視しなければならないほどの強い理由があるに違いない。そうするとHのようになり、これは第1のルールに反する。したがって2つのルールに反しないためには、まず縁石を無視してブロック塀を作ったうえ、それぞれの囲いのなかで縁石を元通りに作りなおさねばならない。即ちIのようになる。つまり種の中にあるタクソンを作ろうとするときには、既にできているすべてのタクソンに気を配るだけでは済まず、自分が作ろうとしているのより下位のタクソンがあれば、それらをすべて作り変えねばならないということになる。「タダノカタバミ」を認めなければこういうことはあまり気にしなくてもよかろう。その代わり新しく作ったタクソンが、他のタクソンの縄張りを侵しているかどうかに、配慮が行き渡らないだろう。
[野草47(373):2-5(1980)]
(18)
私がなぜこんな意見になったか説明しよう。1975年植物分類学文献目録を電子計算機(当時はまだパソコンという単語はポピュラーでなかった)を用いて作ったとき、新名のリストも作った。このリストの配列順序はまず属のABC順、属の中は種のABC順である。ここまではやさしい。種以下の配列も同様にできるかというとそうは行かないのである。学名では第1のナマエは属で、第2のナマエは属の中の種を示すことは決まっている。ところが第3番目にくるナマエは、亜種のこともあれば変種もあれば品種の場合もある。それに第3で終わることもあれば第4、第5と続くときもある。品種のエピセットが第3番目のこともあるし第5番目のこともある。これらのナマエはランクによって格付けが違うので、それに応じた序列を与えねばならない。植物研究雑誌の総索引を見ると、こういう序列決めが苦もなく行われているように見えるが、これは人間業だから出来るのであって、電算機ではこのままでは至難の業というより不可能なのである。電算機はエピセットやランク名では階級序列を判断できないからである。それを判断してもらうためにいろいろとひねくり回したあげく、ランクによってナマエの出現する位置を決めてしまった。それは升席を6つ並べ、第1の席は科、第2の席は属、第3は種、第4は亜種、第5は変種、第6は品種のナマエの入る席と決めてしまったのである。たとえ品種のナマエが種のすぐ後に出てきても、それは第6の席に押し込んでしまう。第4第5の席は空席である。電算機はナマエの入っている席の位置でその格付けを判断できるので、序列をつけて並べることが出来るのである。今の場合、第4と第5の席は空席である。この空席が「タダノ~」に当たる。この場合タクソンのランクは「違いの程度」を示すのではなく、数字で表された階級的強さを示すものとなる。つまり種は第3ランクで変種の第5ランクより2階級上位ということを示す。こういう考え方ならvar.の代わりに5と表現してもよいし、エピセットの前に2とついていれば属のナマエであることがわかる。実際こういう表現をプログラムの中で用いている。植物研究雑誌の総索引を作ったhuman computerも、同じことをやったに違いない。実は私もある時期この総索引を作った1人なのだ。したがって私の考え方は、決して異端のものではないと言いたいのである。
さて実際にナエマを書くときには、さきの空席をそのまま出すと間が抜けて見えるし冗長だから省略すると言うのなら話しは分かるけれど、存在しないと見なすのは賛成できない。0(ゼロ)は存在しないのではなく、そういう値が存在しているということである。ましてこの空席は、本来ならば規約によって1つ上位のナマエがそのままの形で入っているべき席なのである。それを省略してしまうのは、冗長さを避けるためというより、冗長さを覚られないためという気がしないでもない。
「俺は亜種を認めないから、こういう並べ方は気に食わん」と言われる方は多い、だが誰が考えても亜種というランクは、もし存在するならば、変種よりも上位で種よりも下位である。これは亜種を認めない人でもうなずかざるをえないだろう。だからその場所は、使う人のために空けておいて、使いたくなければ使わねばよいのである。ただ索引を作る側から言わしてもらえば、亜種を認めた人のつけたナマエと認めない人のつけたナマエを、別建てで索引にするわけには行かないのである。そんなことをしたら索引の便利さは失われてしまう。そうすると、ありそうなランクはみんな使えるようにしておくのがよいということになってしまう。上記のほかに亜変種だの亜品種だのcultivar.だのもあるが、データカードのサイズの関係で、ほとんど出現しないランクのために席を予約するほど余裕がなかったのである。これらのことは便宜上の問題だけなら簡単なのだが、「タダノ~」の問題とからんでphilosophyと関係してくるので厄介なのである。
[野草47(374):18-19(1980)]
(19)
電子計算機を使うようになって、ナマエというものについてそれまで漠然と信じていたことを、再考せざるをえないことになった。つまり、ナマエというものは受皿であって、その中身を入れるには別な努力をしなければならないということである。
S=A+B …①
という式がある。ふつうこの式の意味は、「AとBを足せばSになる」あるいは「AとBを足したものがSである」あるいは「SはAとBの和である」ということである。ところが計算機の解釈は少々違う。この式の意味は、「Aというナマエのついた記憶場所に入っている値(中身)と、Bというナマエのついた記憶場所に入っている値(中身)を取り出してきて足し合わせ、その結果をSというナマエのついた記憶場所を作ってそこへしまう」というものである。したがって「Aという記憶場所」の中身を取り出そうとしたとき、そこがカラッポであったら、計算機は仕事が出来なくなって放り出してしまうのである。そうさせないためには、この足し算をやる前にたとえば
- A=1.2 …②
- B=3.5 …③
というように、AやBに数値を入れる仕事をやっておかねばならない。この式の意味は「Aというナマエのついた記憶場所を作り、そこへ 1.2という数値をしまう」というものである。この場合のカラッポとは、その値が0(ゼロ)であるということではなく、Aという場所だけあるけれど、ホントに何も入っていない(null)、あるいは何が入っているか分からないということである。Aがゼロであるというのならば、A=0.0という作業をしておかねばならない。
ここまで書けば、私が前から言っている「空き箱」と「中身」の関係が理解できるのではなかろうか。Aというナマエは空き箱(記憶場所)に対応し、 1.2がその中身なのである。もしS=A+Bのように、箱の中身を利用して何か仕事(研究)をしようとしても、それらがカラッポだったら仕事にならない。だからその前に②や③のような仕事(これも研究である)をしておかねばならないのである。
種の記載は②や③の仕事の一部には違いないのだが、これはむしろAとはどんな箱でその中にどんなデータを入れればよいかという、箱の定義(Aという記憶場所を作ること)の方に重点がある。フォルトランという計算機言語の中では、Aというナマエのついた記憶場所の中へ入れることが出来る数値は実数のみという約束があり、整数や文字は入れられない。それをしたければ特別な宣言をしなければならないのである。記載というのはどうもこういう約束や宣言に相当するものが主体となるようだ。だから種のナマエをつけ、記載しただけでは、箱の中身はほとんど入らないと思わなければならない。②や③の仕事をするためには、自分が手にした数値(情報)が入れようとする受皿に合っているかどうかを判断しなければならない。Aに5という整数を入れようとすれば、これはAを作ったときの約束によって誤りなのである。こういう判断をするのが「同定」という作業に当たるのだろう。
ナマエがあると、我々はそれが実体そのものと思いがちである。ところが、ナマエをつけただけでは、その名がどの実体を指し示すかを宣言しただけである。我々はその実体から何か情報を取ってきて、ナマエのついた箱に入れてやらないかぎり、箱の中はカラッポなのである。中身の入っていない重箱を、積み替えてみたり中仕切りをつけたりをいくらやってみたところで、中に入れるゴチソウは別に作られねばならないのである。
[野草47(375):34-35(1980)]
(20)
「ヤエカタバミ」を「カタバミ」の外へくっつけた時起こる騒ぎを書いたら、これにも異議が出た。「ヤエカタバミ」というのは「八重」以外はみんなカタバミと同じだから、わざわざ記載する必要はない。カタバミの原記載には「八重」ということだけ欠けていたので、品種のランクでこういう記載を付ければ、種の記載を補足したことになるのだから、私の言うような騒ぎにはならないというものである。
そうすると、種の記載文というものはその中に含まれるすべてのタクソンの記載文の合計ということになるのだろうか?それから、種のタイプもその中に含まれるあらゆる種内タクソンのタイプを合わせたものになるのだろうか?少なくとも後の場合は明らかに違う。種のタイプは種の正基準標本1つだけである。そうするとたとえば「ヤエカタバミ」の正基準標本とは何だろうか?これもレッキとした1つのタクソンのタイプなのだから、全身全霊でもって基準標本でなければならない。ところが「ヤエカタバミ」は花が八重であるということ以外は「母種と同じ」とされ、記載文もそう書かれるだろう。このことは、「八重」以外の形質については母種の正基準標本に準拠するということであり、「ヤエカタバミ」の正基準標本はこの点についてはタイプの役を果たさないことを示している。つまり「ヤエカタバミ」の正基準標本というのは「八重」であることだけが実在であり、他のいかなる形質も基準標本として実在してはならないのである。これではまるで幽霊ではないか!もしそうでなくて「ヤエカタバミ」のタイプは体全体でもってタイプなのだとすると、カタバミの「一重」と「八重」という以外の部分について、全く同じ実体に対して2つの正基準標本が存在することになる。これは今まで気づかないで来たが、私にとって大変重大な発見である。つまり種の中に現行のタイプメソッドに基づく下位のタクソンが作れるのか、という問題となる。カタバミの中に「ヤエ」を区分して「タダ」と両立させればよいという私の考え方も、タイプについての上の矛盾を解決してくれない。
タクソンというものは種がそうであるように、全身全霊でもって他と異なっているべきである。そうでなければどの程度の垣根であれ、これを囲い込むことは出来ない。種内のタクソンはその種なり上位のタクソンなりをはっきり二分するものとして話を進めてきたのだが、種内のタクソンの認識がその基準の一部(というより大部分)を「母種」に求めている以上、これは種を二分していることにはならない。つまりAでなくBのような形である。したがってこの下位群は、種と同じ意味でのタクソンとは認められない。「ヤエカタバミ」の正基準標本は単に「花が八重である」ことの見本にすぎない。なぜならば、その形質以外はタイプとしての役目を放棄しているからである。だいぶ前に「斑入りの新品種のタイプが葉1枚だけというのはよくない」と書いたが、種内のタクソンのタイプではみんなこういうことが起こっているのではあるまいか?種内のタクソンが全身全霊で「母種」と異なっているのでなければ、葉1枚をタイプにしても一向差し支えなさそうである。
種というものは1つの単位で原子のようなものであり、変種や品種はその下位の構成単位で、電子や中性子のようなものと考えてきたが、そうではなさそうである。種も変種も同じくtaxonと呼ばれるので、同じように独自性があると思っていたが、ずいぶん違うらしい。種というものは1つのatomだから、それを分割するには何か別な概念による要素を持ち出さねばならない。変種や品種はこれに値しない。何故ならば、そのよって立つ基盤を種に依存しているからである。電子や中性子は原子がなくなっても存在できるが、亜種や変種は種がなくなれば一緒に消えてしまうのである。むしろ種内のいろいろなタクソンは、水が氷や水蒸気になるように、種の存在様式の1つのあり方と見るのがよかろう。
したがって種の下位群に対して、種と同じルールを適用するのは誤りではなるまいか?これらのランクは、前に否定した違いの程度を示す目安にすぎないと考えるのがよかろう。つまり、Bの切れ込みの深さと厚さを示すだけである。こういうものに種と同じルールを当てはめて、原記載や基準標本を決めて同等のタクソン扱いをすると、先に述べたようなルール違反が自然におこる。これはルールが悪いのではなく、独自性のない種の下位群を、種と同じ「タクソン」として認めようとするところに無理があるのだと思う。
[野草47(376):50-51(1980)]
『金井弘夫著作集 植物・探検・書評』コンテンツ一覧▼ 目次(青字)をクリックすると、各文をご覧いただけます
金井弘夫博士著作集に寄せて 東京大学名誉教授 大場秀章 / あとがき
第一部 時代の記憶・探険の記憶
最後の旧制高校生の自分史
理化館の焦げ茶のタイル
インドで見たこと聞いたこと
- はじめに
- 夏休みは4月
- 「古」新聞の値段
- 街頭の商人達
- 乞食
- ボクセス
- 良いお金と悪いお金
- 水
- お茶
- オナラ
- 立小便
- 近づくほど遠くなる
- 踏切に錠前
- 汽車
- バス
- 市電
- インド人という「民族」
- アッチャー
- タバコ
- お酒
- ビール
- ウイスキー
- ラム
- チャン
- マフア酒とヨーグルト
- 朝のお祈り
- 国境侵犯
- 二人のリエゾン・オフィサー
- シェルパたち
- アンプルパ
- トゥンドウ
- プルバ・ロブソン
- テンバ・シェルパ
- 女性たち
- ラマ教
- 山で一番こわかったもの
- お菓子
- 名前
- 宿屋
- インドの道の良さ
- フェリー
- 牛
- 交通法規
- カストムハウス
- 風呂
- 拍子木たたき
- バルカカナの日本人
- ボダイジュの借り倒し
- タテガミのあるブタ
- 封蝋
- 食いもの
- カースト(階級制度)
- デモ
- 鶏と卵
- 切符を買う
- 街路樹
- 事故
- インドの英語
再びインドの植物を求めて
- 悪路に悩む採集行
- ヒマラヤで見る段々畑
- 調査成果の一端
西北ブータンの山々
- 入国手続き、旅行許可など
- 入出国の経路
- 国内の輸送、通信、シェルパなど
- 物資の調達
- 気候
- 地図、コースについて
- チンプウ-トンサ
- 観察されたピーク
- 集落
- 通貨、賃金
フィニッシュの話
- 失せ物が出た
- 通関書類、フィニッシュ
- リエゾン・オフィサー、フィニッシュ
- ミソとストーブ、フィニッシュ
- スペース、フィニッシュ
- チニ、フィニッシュ
- サーダー、フィニッシュ
- ポーター、フィニッシュ
- 道路とジープ、フィニッシュ
- ブルカー、フィニッシュ
- 標本、フィニッシュ
- 道路、もうひとつのフィニッシュ
- シェルパ、フィニッシュ
- トラック、フィニッシュ
東ネパール調査(1963年)点描
- チャッシガレ!
- おまじない、ハチ
- 録音
- ハリー
- 食物
- こわいもの
ネパール通信1
- カトマンズ(1)
- フルチョウキ
- カトマンズ(2)
- チュリア・マハバラトの旅
- ゴサインクンデの旅
- ボダイジュのほこら
- カトマンズ(3)
- ロルカニの旅
- カトマンズ(4)
- チリメ、ランタンの旅
- チャンドラギリの旅
ビル・ニガントゥに見られる米の記事
ネパールの滝の数
ネパール通信2
- 自動車事故のはなし
- 創立記念パーティー
- カリンチョークの旅(1)
- インドラジャトラ
- カリンチョークの旅(2)
- チュリアの旅
ヒマラヤ植物調査の今昔
日本・ネパール協同植物調査史 1960-1980 [英文]
『冒険家族ヒマラヤを行く』訳者あとがき
パプア・ニューギニアの話
- 交通
- 食べ物
- 人々
- コトバ
- 古戦場
吉川英治文化賞受賞のことば
第二部 植物の観かた・残しかた
野外観察会のこと
日本植物の分布型に関する研究(2) ヒメマイヅルソウの分布型と変異
オゼコウホネの種子散布
ヤマモモの仁
クヌギの落枝
スベリヒユは対生
猪突猛進するチガヤの地下茎
ササの葉鞘
ケヤキの落葉現象はあったか
笹舟は沈む!
ミャンマーのドクウツギ属植物Coriaria terminalis Hemsley とその西限産地
ブータンのウルシ
植物の動きを見せる
尾瀬ケ原の池塘データベースによるヒツジグサとオゼコウホネの16年間の分布消長
群落の突然の交代
ツタの植物画
ツタの「雨」
国立科学博物館のサクラソウ生態展示
有毒植物を食べる
ミズバショウの果実の味
マムシグサのイモの「味」
ヌルデとネムノキは仲良し?
ビルマの植物学界の一端
部活動と自然観察会
普通な植物を記録しよう
ヒレハリソウ(ムラサキ科)の葉序
アイスマンの弓矢
ツュンベリーと日本のアマチュア植物学 [英文]
誰にでも利用できる標本のために
標本にはラベルを入れよう
標本ラベル論議へのながーいコメント
- 仮ラベルに関して
- 本ラベルに関して
- データベースに関して
ヒートシールによる標本貼付
おしば標本の新しい貼付法
おしば標本貼り付け用ヒートシールテープの自作法
移動式おしば標本棚の得失
- 改装工事前後の問題
- 運用上の問題
おし葉製作法の改良
携帯用植物乾燥機について
- 冨樫板
- 加圧法
- 加熱法
- 標本製作中の注意と標本の出来具合
- 研究室での使用法
教具教材としての植物パウチカード
生植物のラミネート標本
日本植物分類学文献目録・索引のデータ仕様と検索項目 [英文]
シンポジウム「標本データベースの将来」の感想
- Herbariumの体制
- 大学と博物館の違い
- どうやるか
- データベースを作ったあと
- 画像データベース
第三部 ナマエ・データ・ヒト
吉村衛氏による科の和名の新提案
命名規約とオフセット印刷
デチンムル科
「野草」に現れた植物の新名
新和名提示のいろいろなかたち
「ナマエ」を考える
モノの見え方について
東京消失
地名データベースの活用
- 住吉小学校の「住吉」研究
- 住吉小学校はいくつあるか
- 住吉神社はどのくらいあるか
- 住吉という地名はどうだろう
- IT化時代の学習
新日本地名索引の内幕
新日本地名索引のはなし
- どんなものか
- どうやって作ったか
- 索引のスタイル
- よみの問題
- 分布地図
- 「鐙」の分布
- JIS漢字表の問題
学術用語集植物学編(増訂版)の分類学用語改善のための資料
- 形を表す用語
- 花を表す用語
データベース仕様と植物学・動物学・農学に共通な植物用語
- データベース仕様
- データベース作成の方法
- 調整を要する用語の方針と方法
保育社・原色日本植物図鑑の観察
Index Kewensis 展開版前文
ネパールの本草書ビル・ニガントゥについて
岩槻邦男氏にエジンバラ公賞
英語教科書に載った西岡京治氏
大村敏朗氏の貢献
原寛博士への弔辞・追悼文
- 弔辞
- はじめてのヒマラヤ
若き日の原寛博士の日記
津山尚博士
「訓導」原襄さんの思い出
里見信生さんの思い出
里木村陽二郎先生
山崎敬さんの思い出
第四部 書を評す
地図・地名
- コンサイス地名辞典日本編
- 現代日本地名よみかた大辞典 1-6巻
- 知っておきたい災害と植物地名
- 日本湿地目録
- 日本山名総覧
- FD日本山名総覧「全国版」
- 数値地図 25.000(地名・公共施設)全国CD-ROM版
学名・用語など
- 植物学ラテン語辞典
- 国際植物命名規約1988
- 植物学名詞
- 菌学用語集
- 植物学名大辞典
- 植物の名前のつけかた植物学入門
- 日本苗字大辞典
- 図説植物用語辞典
- 国際栽培植物命名規約第7版
フィールドワーク
- 清瀬の自然フィールドガイド春
- 東京西郊野外植物の観察
- GPS全日本ロードマップ
- ヨコハマ植物散歩
- 東京樹木めぐり
- 巨樹・巨木
- ぐるっと日本列島野の花の旅
- 続巨樹・巨木
- 地べたで再発見「東京」の凸凹地図
- 東京大学本郷キャンパス案内
- 雷竜の花園
- 秘境・崑崙を行く
- 中国秘境に咲く花
- 青いケシの咲くところⅡ
- シルクロードに生きる植物たち
- ヒマラヤを越えた花々
- 幻の植物を追って
- ロンドンの小さな博物館
- ヒマラヤに花を追う
- ヒマラヤの青いケシ
人
- 白井光太郎著作集
- 進野久五郎植物コレクション
- 来し方の記8
- 横内齋著作集2
- 李永魯文集
- MAKINO80『植物同好会』八十年の歩み
- しだとこけ 服部新佐先生追悼記念号
- 小泉秀雄植物図集
- 籾山泰一先生論文集
- 私の研究履歴書-昭和植物学60年を歩む- [林孝三]
- 命あるかぎり-花と樹と人と-見明長門追悼集
- 中尾佐助文献・資料目録
- 牧野晩成
- 沼田真・著作総目録
- 牧野富太郎とマキシモヴィッチ
- 牧野富太郎著・植物一家言
- 誰がスーリエを殺したか1
- 展望河口慧海論
- 「イチョウ精子発見」の検証
- 牧野富太郎植物採集行動録
- 大雪山の父・小泉秀雄
- 大場秀章著作選Ⅰ
- 大場秀章著作選Ⅱ
- 小原敬先生著作集
- 植物文化人物事典
- 清末忠人研究集録
- 自然と教育を語る
文化
- 現代文明ふたつの源流
- 栽培植物の起源と伝播
- 江戸時代中期における諸藩の農作物
- 日本の植物園
- アジアの花食文化
- いのちある野の花
- 江戸参府随行記
- ボタニカルモンキー
- 菌類認識史資料
- 植物学と植物画
- 黒船が持ち帰った植物たち
- 日本植物研究の歴史
- 植物園の話
- バラの誕生
- 絵で見る伝統園芸植物と文化
- 江戸の植物学
- 現代いけばな花材事典
- 花の男シーボルト
- サラダ野菜の植物史
- すしネタの自然史
- シーボルト日本植物誌 文庫版
地域・フロラ
- 環境アセスメントのための北海道高等植物目録Ⅳ
- 宮城県植物目録 2000
- 秋田県植物分布図
- 秋田県植物分布図第2版
- 茨城県植物誌
- とちぎの植物Ⅰ,Ⅱ
- 日光杉並木街道の植物
- 渡良瀬川支流山塊の高等植物 類似植物の見分け方ハンドブック
- 渡良瀬川支流山塊の高等植物
- 群馬の里山の植物
- 群馬県タケ・ササ類植物誌
- 群馬県植物誌改訂版
- 館林市の植物
- 尾瀬を守る
- 1998年版埼玉県植物誌
- さいたまレッドデータブック
- 千葉県植物誌
- 千葉県の自然誌
- 富里の植物
- 続江東区の野草
- 小笠原植物図譜
- 神奈川県植物誌分布図集
- 横浜の植物
- Yato横浜 新治の自然誌
- 箱根の樹木
- 新潟県植物分布図集第6集
- 新潟県植物分布図集第7集
- 新潟県植物分布図集第10集
- 新潟県植物分布図集第1-10集登載植物および索引
- 石川県樹木分布図集
- 加賀能登の植物図譜
- 金沢大学薬学部付属薬用植物園所蔵標本目録 白山の植物
- 信州のシダ
- 長野県の植生
- 長野県植物研究会誌第20号
- 長野県版レッドデータブック維管束植物編
- 長野県植物ハンドブック
- 伊部谷の植物
- 植物への挽歌
- しなの帰化植物図鑑
- 37人が語るわが心の軽井沢1911-1945
- 近畿地方の保護上重要な植物
- 改訂・近畿地方の保護上重要な植物
- 近畿地方植物誌
- 高山市の植物
- 改定三重県帰化植物誌
- 兵庫県の樹木誌
- ひょうごの野生植物
- 播磨の植物
- 平成元年度箕面川ダム自然回復工事の効果調査報告
- 六甲山地の植物誌
- 淡路島の植物誌
- 奈良公園の植物
- 岡山県スゲ科植物図譜
- 広島県文化百選 花と木編
- 広島市の動植物
- 山口県の植物方言集覧
- 山口県の巨樹資料
- 徳島県野草図鑑〈下〉
- えひめの木の名の由来
- 福岡県植物目録 第2巻
- 熊本の野草〈上〉〈下〉
- 熊本の木と花
- 鹿児島県の植物図鑑
- 改訂鹿児島県植物目録
- 沖縄植物野外活用図鑑全6巻
- 沖縄県の絶滅のおそれのある野生生物
- 琉球列島維管束植物集覧
- 孤島の生物たち-ガラバゴスと小笠原
- ブラジル産薬用植物事典
- キナバル山の植物
- 韓国産松柏類
- 韓国植物検索便覚
- 韓国植物分類学史概説
- 中国人民共和国植被図
- 中国天山の植物
- 雲南の植物
- 雲南の植物
- 東北葯用植物
- ヒマラヤの自然誌
- ヒマラヤ植物大図鑑
- ネパール研究ガイト
- スイスアルプスの植物
調べる
<環境>
- 屋久島原生自然環境保全地域調査報告書
- 昭和63年度レアメタル賦存状況調査報告書
- 帰化植物のはなし
- レッドデータプランツ
- 植物からの警告・生物多様性の自然史
- エコロジーガイド・ウェットランドの自然
- 植物群落レッドデータブック
- 日本森林紀行
- 温暖化に追われる生き物たち
- 水生シダは生きる
- 侵略とかく乱のはてに
- 各都道府県別の植物自然史研究の現状
- 日本の絶滅危惧植物図譜
- 絶滅危惧植物図鑑レッドデータプランツ
<種類>
- 新しい植物検索法 離弁花類編
- 日本タケ科植物総目録
- 新しい植物検索法 合弁花類篇
- 北日本産樹木図集
- 動植物目録
- 日本件名図書目録⑨ 動・植物関係
- 山野草植物図鑑
- 植物目録
- 日本の高山植物
- 世界の針葉樹
- 検索入門樹木
- 葉による野生植物の検索図鑑
- 英語表現べからず辞典
- 日本イネ科植物図譜
- 改訂増補 牧野日本植物図鑑
- 日本の自生蘭
- 北本州産高等植物チェックリスト
- 日本水草図鑑
- 日本草本植物根系図説
- 日本のスミレ
- 日本で育つ熱帯花木植栽事典
- 植物の系統
- 日本タケ科植物図譜
- 日本の野生植物 コケ
- 日本花名鑑1
- 樹に咲く花 合弁花 単子葉 裸子植物
- 高山に咲く花
- 日本花名鑑2
- 日本の帰化植物
- ツバキとサクラ
- カエデの本
- 新日本の桜
- 日本のスゲ
- 日本の野菊
- 日本花名鑑4
- 日本海草図譜
<観察>
- 花と昆虫
- 樹木
- 平行植物
- 描く・植物スケッチ
- 植物観察入門
- 野草 1-15巻+別巻
- 折々草
- みどりの香り 青葉アルコールの秘密
- 誰がために花は咲く
- 草花の観察「すみれ」
- 人に踏まれて強くなる雑草学入門
- 花生態学入門 花にひめられたなぞを解くために
- ブナ林の自然誌
- 原寸イラストによる落葉図鑑
- 人里の自然
- 虫こぶ入門
- 森のシナリオ
- シダ植物の自然史
- 花と昆虫がつくる自然
- 文明が育てた植物たち
- 雑草の自然史
- セコイアの森
- 植物の私生活
- ツリーウォッチング入門
- 根も葉もある植物談義
- 花の観察学入門
- 野の花山の花
- ため池の自然
- 花と昆虫 不思議なだましあい発見記
- 道端植物園
- タンポポとカワラノギク
- どんぐりの図鑑
- 植物のかたち
- せいたかだいおう-ヒマラヤのふしぎなはな
- コケ類研究の手引き
- 虫こぶハンドブック
- 虫こぶ入門
- ひっつきむしの図鑑
- 樹木見分けのポイント図鑑, 野草見分けのポイント図鑑
- 植物生活史図鑑Ⅰ, Ⅱ
- 絵でわかる植物の世界
- 「野草」総索引
- 「野草」植物名総索引 第1巻~第70巻
- 標本をつくろう
- わたしの研究 どんぐりの穴のひみつ
- どんぐり見聞録
- ほんとの植物観察, 続ほんとの植物観察
- キヨスミウツボの生活
- 発見!植物の力1~10
- 帰化植物を楽しむ
- 花からたねへ
- 植物と菌類30講
<標本>
- 自然史関係大学所蔵標本総覧
- 国立科学博物館蔵書目録和文編
- デジタルミューゼアム
- 牧野植物図鑑の謎
- Systema Naturae 標本は語る
- 牧野標本館所蔵のシーボルトコレクション
- 牧野標本館所蔵シーボルトコレクションデータペース CD-ROM版
洋書
- Manual for Tropical Herbaria, Regnum Vegetabile
- The Asiatic Species of Osbeckia
- Biological Identification with Computers
- A Geographical Atlas of World Weeds
- Neo-lineamenta Florae Manshuricae
- Atlas of Seeds Part 3
- Alpine Flora of Kashmir Himalaya
- Botticelli's Primavera
- Index to Specimens Filed in the New York Botanical Garden Vascular Plant Type Herbarium
- Elsvier's Dictionary of Trees and Shrubs
- Medicinal Plants in Tropical West Africa
- Fodder Trees and Tree Fodder in Nepal
- Nepal Himalaya, Geo-ecological Perspectives
- Leaf Venation Patterns
- Development amid Environmental and Cultural Preservation
- The Lilies of China
- Kew Index for 1986
- Catalog of Moss Specimens from Antarctica and Adjacent Regions
- The mountains of Central Asia
- Trees of the southeastern United States
- A New Key to Wild Flowers
- Flora of upper Lidder Valleys of Kashmir Himalaya
- Systematic Studies in Polygonaceae of Kashmir Himalaya Vol.1
- Flowers of the Himalaya, a Supplement
- Plant Taxonomy and Biosystematics, 2nd ed.
- Plant Evolutionary Biology
- Lilacs, the Genus Syringa
- Ornamental Rainforest Plants in Australia
- Forest Plants of Nepal
- Plant Taxonomy, the Systematic Evaluation of Comparative Data
- Woody plants
- The Evolutionary Ecology of Plants
- The Forest Carpet
- Cryptogams of the Himalayas Vol.2., Central and Eastern Nepal.
- Pattern Formation in Plant Tissues
- Plant Genetic Resources of Ethiopia
- Leaf Architecture of the Woody Dicotyledons from Tropical and Subtropical China
- Palaeoethnobotany
- A Bibliograpby of the Plant Science of Nepal
- C.P. Thunberg's Drawings of Japanese Plants
- Temperate Bamboo Quarterly 2
- Index of Geogrphical Names of Nepal
- A Revision of the Genus Rhododendron in Japan, Taiwan, Korea and Sakhalin
- A Bibliography of the Plant Science of Nepal. Sipplement 1
- The Iceman and His Environment, Palaeobotanical Results
- The Cambridge Illustrated Glossary of Botanical Terms
- Handbook of Ayurvedic Medicinal Plants
- Ethnobotany of Nepal
- Himalayan Botany in the Twentieth and Twenty-first Centuries
- Meristematic Tissues in Plant Growth and Development
- Proceedings of Nepal-Japan Joint Symposium on Conservation and Utilization of Himalayan Medicinal Resources
- The Orchids of Bhutan
- Beautiful Orchids of Nepal
書籍詳細
-
元・国立科学博物館 金井弘夫 著
菊判 / 上製 / 904頁/ 定価15,715円(本体14,286+税)/ ISBN978-4-900358-62-1
〔花の美術館〕カテゴリリンク
- 第20回 『熱帯植物巡礼』
- 第19回 小山鐡夫追悼記念号『黒船が持ち帰った植物たち』より
- 第18回 小山鐡夫追悼記念号『植物園の話』より
- 第17回 『MAKINO 80』東京植物同好会・牧野植物同好会八十周年記念誌
- 第16回 ハマナスの語源を探る
- 第15回 金井弘夫追悼記念号『金井弘夫著作集 植物・探検・書評』より
- 第14回 『花のある風景』
- 第13回 坂嵜信之追悼記念号『日本で育つ・熱帯花木植栽事典』より
- 第12回 楽しい花観察108選『不思議な花々のなりたち』
- 第11回 川島榮生の《ヤマアジサイの世界》
- 第10回 渡辺健二『日本産ギボウシの世界』
- 第9回 『ユリノキという木』─ 魅せられた樹の博物誌
- 第8回 『北米インディアン悲詩』/ エドワード・カーティス写真集
- 第7回 江戸時代の花たち 書物に見る江戸時代の園芸文化
- 第6回 わが国初のボタニカルアーティスト 五百城文哉(いおきぶんさい)の世界
- 第5回 『ビル・ニガントゥ』 19世紀末ネパール秘蔵の本草図譜
- 第4回 植物画家 石川美枝子の作品
- 第3回 サイエンティフィック・イラストレーター 木村政司の作品
- 第2回 植物画家 中島睦子の作品
- 第1回 『PLANTAE ASIATICAE RARIORES』