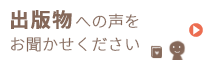- ホーム
- ネイチャーコンテンツ
- Aboc Museum
- 花の美術館
- 第15回 金井弘夫追悼記念号『金井弘夫著作集 植物・探検・書評』より
- 第一部 時代の記憶・探険の記憶: 最後の旧制高校生の自分史
第一部 時代の記憶・探険の記憶: 最後の旧制高校生の自分史
成蹊学園の尋常科(中学)へ入ったのは昭和18年である。出身の盈進学園の丸山鋭雄校長は、もとは成蹊の教師だったので、入試は受けたものの推薦入学のようなものだったのだろう。一学年わずか5-6人の寺子屋のような小学校から、一組30人の普通の規模の学校に入ったのだが、私にはなにもかも巨大で異質だった。日米の戦争はすでに昭和16年から始まっていたが、まだそれほどの切迫感はなかった。
小金井の家は駅から1.5kmほど南で、小金井村のはずれ、府中町との境目にあった。物心ついた頃には周囲は一面の畑と栗林とアカマツの疎林で、家の門から富士山が直接見えた。今のオートバックスのあたり(小金井街道と新小金井街道の交叉点)に蛇窪という葦に囲まれた小さな沼があり、そこから出た小川が家のそばを流れていて、よく笹舟を流して遊んだ。今は遊歩道になっている中倉さんの前の通りである。バスはなく、乗り物としては駅前に人力車が1台、タクシーが1台あるだけで、父(英一)は家から駅まで歩いて、神田の店(絵本出版の金井信生堂)に通っていた。なんでこんな不便なところに住んだのかというと、もともとここは別荘地として売り出されたが、見込み外れで買い手がなく、祖父(直造)がまとめて土地を買ったものらしい。家は建てたものの頻繁に来るような所ではなく、子供の多い長男の父に住まわせたもののようだ。父は三井物産に勤め、台北に家族ぐるみで赴任していたが、直造が家業を継がせようと呼び戻したのである。建築の際には、電気を引くための電柱を何十本だか買ったと聞いている。近くには小山商店という藁葺きの小さな雑貨店(今のスリーエフの前身)があるだけで、買い物はすべて駅前まで行かねばならなかったが、八百屋や魚屋は御用聞きが毎日やってきて、午後には品物が届けられた。祖父と祖母(とよ)は年末年始の数日、泊まりにくるだけで、その間は家中はすごく緊張していた。官立学校の嫌いな父は、子供の小学校には1つ隣の武蔵境駅(東小金井駅はまだなかった)から北へ1kmほどにある盈進学園を選んでいた。天気の悪い日には駅までの道はつらかった。ある年には台風の大雨で野川が氾濫し、道路が1週間ほど水没したこともある。野川のまわりは一面の田圃で、蛙の大合唱が聞こえ、夏には蛍が家の庭まで入って来た。昭和12年頃、すぐ近くに横河電気の工場が建つことになり、工事が始まった。家の前の畑には工員のための青年学校が建てられ、府中街道(今の小金井街道)までの道沿いには職員住宅が並んだ。バスが通るようになったのは、戦後だったと思う。戦争が進むにつれて灯火管制が強化され、街灯がつかなくなった。そうすると夜遅く帰る父は暗夜には道が見えず、「上を向いて歩くと、両側の樹木の隙間がわずかに暗さが違うので見当がつけられる」と言っていた。
同じクラスに後藤英一(ユニークな計算素子パラメトロンの発明者、綽名三角おむすび)と槇原稔(後の三菱商事会長、綽名マキドン)がいて、どういういきさつか覚えていないが、3人で「共同研究」をしようということになった。カエルにどのくらい電流を流せば死ぬか、というテーマである。エーコン(加藤藤吉・物理の教師)から昇圧型のトランスを借り出し、ノミ(鈴木豊、生物の教師)に頼んで日曜日に生物実験室のドアを開けておいてもらい、校庭で運の悪いガマガエルを1匹つかまえてきた。トタンの解剖皿では漏電するので、板の上にじかにカエルを載せ、麻酔してから腹を開いて両腕に針金を巻いて通電するという、残酷きわまる実験である。ところがいくら電気を通しても、カエルの心臓は止まらなかった。半日くり返したあげくあきらめて、花壇の縁にカエルを埋葬して引き上げた。この昇圧型のトランスというのは、われわれの当初の目標は、真空放電に使う感応コイルだったのだが、大きくて重いうえに危険と思われたか断られ、次善の選択として提示実験用の通常型のトランスを借りた。それでもコイルや端子はむき出しで、やっと持ち上げられるほどの重さだった。後藤のもくろみでは、1次コイルと2次コイルを逆に使えば、充分な高圧が出るという。そんなことをすればコイルが焼き切れるか電源ヒューズが飛んだはずなのだが、彼は何か細工をしたらしく、そういう事故は起こらなかった。電圧計は借りなかったので何ボルト出たか知らないが、ウッカリ感電したらただではすまなかったろう。
戦局の深刻化につれて、学校の本館は航空軍に接収され、軍人軍属たちが我が物顔に横行し、遊びに夢中でウッカリ隊列を横切った生徒が、こっぴどく怒鳴りつけられたりした。陸上競技の400mグラウンドは工事の車両に踏みにじられ、見るかげもなくなった。「公認グラウンドなので荒らさないでください」という小さな立て札が、ゾル(Soldat:軍人に対するわれわれの蔑称)に対するせめてもの抵抗だった。学校の裏手には高射砲陣地が築かれ、発砲するのを一度だけそばで見た。砲口の炎は焦げ茶色をしていた。通学の途上で高射砲弾の破片を拾って見せあった。破片は熟れたニガウリ(ゴウヤ)の裂片に似ていた。昭和19年(1944年)サイパン島が陥落すると、B29 による空襲が本格的となった。昼間爆撃の彼らの目標の第1は、学校のそば(いまの武蔵野市緑町)にある中島飛行機製作所の大工場だった。編隊は高々度で八王子の方向からやってきて爆弾を落とした後、学校の北側を通り抜けていった。空襲警報が鳴ると授業は中止となり、下校させられたが、吉祥寺駅に行っても電車は動いていなかった。そこで近くの井の頭公園で、空襲が終わるのを待った。編隊が爆弾を放つと、空一帯に「カラカラカラ… 」と荷車を引き回すような音が響きわたり、目標から2kmも離れているのに怖ろしさに思わず身を伏せた。爆風を防ぐために、小指を歯の間に挟み、親指で耳を、残る指で目をふさぐ動作を自然に身につけた。やがて「ドン・ドン」という爆発音と地響きが伝わってくると、やっとホッとして立ち上がった。焼夷弾ではなく、破壊力の強い爆弾なので、地響きはすごかった。遠いからといって、爆弾がこないとは限らない。ある日警報が遅れて、駅に着く前に爆撃が始まってしまった。近くの藤村女学校の校庭で見上げていたら、なんの前触れもなく「スパッ」という音と共に20mほどのところに着弾した。あわててそばの防空壕に飛び込んだが、爆発しなかったからよかったもののさもなければ手遅れだった。不発弾か時限爆弾か知らないが、しばらくの間は、道路脇の小さな穴に立入禁止の縄張りがあるのを横目に通学していた。戦争が終わってから井の頭公園に行ってみたら、池のそばに大穴があいており、ここにも爆弾が落ちたことを知った。
やがて夜間の空襲も頻繁になり、この場合には敵機は小金井のわが家の上空を通って東京に向かった。3月10日の大空襲では、大火災に照らし出された銀色のB29の大編隊が低空で通過するのを眺めた。近くの調布飛行場は東京の防衛戦闘機の基地だったが、1機も迎撃にこなかった。敵は南方洋上から直進するように見せかけ、戦闘機を飛び立たせた後で近海で旋回して時間をつぶし、戦闘機の燃料が切れて着陸したころを見計らって進入したという。
昭和20年(1945年)4月に硫黄島が陥落すると、戦闘機の空襲が始まった。これは機関砲の弾が先に飛んできて、それから轟音と共に低空で飛行機がやってくるので逃げようがない。クラスでは、空襲による死傷者はなかったようだが、別な犠牲者が出た。大輪田が北鎌倉駅で死んだのだ。当時は空襲を避けて、鎌倉の疎開先から吉祥寺まで2時間かけて通学する者が多かった。昭和19年だったと思うが、電車は超満員の殺人電車で、窓から乗り降りするのは当たり前、連結器や屋根の上にまで人が乗っていた。大輪田は連結器に乗ろうとして足を踏み外し、電車とホームの間に挟まれて即死した。彼の墓は北鎌倉の寿福寺にある。
3年になるとすぐ、学校疎開のはなしが持ち上がり、われわれ3年生は箱根の寮に行くことになった。当時は中3(学校によっては中2)は勤労動員の対象だったが、成蹊では4年生からで、一部は軍需工場に働きに出かけ、一部は雨天体操場を工場として通信機のコイル巻きをしていた。軍需工場は空襲の対象になるので命の危険がある。学校は早晩避けられない勤労動員に対して、疎開によって勉学の場を確保しようとしたのだろう。小学生はともかく、中学高学年生の学校疎開は例外的だったと思う。なお中2年は福島県の二本松に疎開した。7月2日、約60名の生徒は箱根登山鉄道の小涌谷駅から重い荷物を背に、延々と歩いて芦ノ湖畔の寮に入った。引率は鈴木先生(数学、綽名ウルフ)、清水先生(英語、綽名シミッタレ)、谷岡先生(OB、国語、漢文、綽名タニオカ)で、川上先生(数学、綽名サンタロウ)もいたかもしれない。寮は箱根神社の西隣の高台にある東西に細長い平屋で、中央の洗面所を挟んで左右に二室づつあり、3班に分かれた生徒が東側から3部屋に入り、西端の部屋は職員室だった。われわれの班は東端の部屋で、その隣は便所になっていた。
ここで晴耕雨読の生活が始まった。「耕」は裏のゴルフ場の芝生を掘り返して畑を作り、蕎麦や大豆をまいた。「読」は各班の居室を使って、先生方が交代で担当科目を教えた。鈴木先生の数学はむつかしかった。谷岡先生は国士風の雰囲気で、忠君愛国の精神を鼓吹した。鈴木先生はまた作業の方の指導者でもあり、暇があれば薪割りに精出していて、割りにくい二股になった薪の割り方のコツをわれわれに伝授した。この技術はあとで虹芝寮で合宿したとき役立ち、先輩面をすることができた。加藤先生(物理、綽名エーコン)は東京とかけ持ちで、ときどき現れては授業をしたが、あるとき分光器を背負ってきて、太陽スペクトルのフラウンホーファー線のD線がナトリウムの輝線に一致することを、アルコールランプを使って見せてくれた。
箱根の夏は雨が少なく、せっかくまいた蕎麦や大豆はなかなか芽が出ず、芦ノ湖から水を運び上げてかけたりした。ところが芽が出ると、カラスに端から食べられてしまった。毎日の食事が、われわれの最大の関心事だった。別棟の炊事場から当番が鍋に入れて運んできて、各自の食器に盛り分けるのを、一同目を皿のようにして見守り、ちょっとでも少ないと文句をつけた。配膳されてからも、左右の者の食器の盛り具合を横目で観察し、スバシコイ奴は目にもとまらぬ早業で取り替えてしまう。一同気がつかないふりをしているが、実はみんなシッカリ見ていて、夜になると蒲団むしの制裁となる。職員室の隣の班ではあまり騒ぐわけには行かないので、われわれの部屋まで遠征して蒲団むしを執行した。蒲団持参で来るものだから、われわれの蒲団と混ざって天井近くまで積み上がった。でもこういう制裁はそのとき限りで、翌日はみんな元通りだった。他の学校疎開の思い出話にあるような、ボスができて手下と共に横行するというようなことは起こらなかった。作業や授業のない休日は、あたりを歩いたり、カッター(訓練用のボート)で湖に乗り出したりしたが、雨の日はみんなでトランプやゼスチャーをして時間をつぶした。「箱根ヤナとこ二度とは来ない・・・ 。」と、草津節の替え歌を作って憂さばらしをした。このとき採集したウメバチソウが私の作った標本第1号で、東大の標本室に入っている。1番時間を使ったのは食い物の話である。みんな腹を空かしていたから・・・ 。職員室への食事はわれわれが届けることになっていたが、腹いせに飯に草の葉や虫(大きな銀蠅)を混ぜ込んだりした。そういう中で起こったのが缶詰紛失事件である。職員室に保管してあった缶詰が多量になくなったのだ。これには複数の人がかかわっていたようだが、わが班に関する限りこれは共同謀議で、私も犯人の1人である。
学校側でも、開墾の収穫は期待できず、配給だけではとても足りないことは分かっていたのだろう。その対策として、吉祥寺の学校農園から野菜を運ぶ仕事が、生徒数名づつ順番に割り当てられた。教師の引率はもちろん無しである。帰宅して親に顔を見せてやろうという配慮もあったのだろう。私も2回その当番に指名された。帰宅できるといっても、小田急の沿線には厚木基地があり、しょっちゅう空襲されていて、そのたびに電車が止まって車外へ退避せねばならず、ときには銃撃されることもあるので、安全ではなかった。寮から小涌谷駅までは、間道を通って約7kmあるが、われわれは遠回りの国道を選ぶことが多かった。たまに通る軍のトラックの荷台に便乗できる可能性があるからだ。運よく小田原まで運んでもらったときもある。1回目のときはさしたるトラブルもなく、夕方学校に着いたら夕食を出してくれた。飯は高粱入りの赤黒いものだったが、食べていたらドアの外に兵隊が大勢集まってのぞいていた。「こんな子供に飯を食わせるなんて」というような、穏やかならぬ雰囲気で、食堂の係も「早く食べてしまえ」と、隠すようにしていた。戦争末期で、軍隊といえどもまともな食事にありつけなかったのだろう。
家で一日二日過ごしてから、学校農場のイモや野菜をいっぱい背負って箱根に向かった。当時の買い出しとは逆の風景である。小涌谷駅からの道では、トラックは期待できなかった。馬力が弱くて坂道を登れないのだ。重い荷物を背負って間道を歩いた。帰宅した生徒はなにがしかの「おみやげ」(つまり食い物)を班のみんなに配るのが、暗黙の仁義だった。これを怠ったり隠したりすれば、やはり蒲団むしの制裁で酬いられた。連合艦隊司令長官の息子の小沢が持ち帰った海軍乾パンは、最高の御馳走だった。後年、ヒマラヤ調査の食品調達で、偶然この製造元に行き当たったときには、とても懐かしい思いがした。私の場合は、大豆の塩煎りを茶筒に1本がセイゼイだった。
敗戦の8月15日は偶然にも運搬当番で、終戦の放送を自宅で聞いた。戦争が終わったことだけはわかったが、それ以外の感慨はなかった。良く晴れたとても暑い日だったこと、夕方外へ出たら、調布飛行場の方角で盛大な黒煙が上がっていたことを記憶している。多摩墓地は飛行機の退避場所だったので、翌年になっても双発機が放置されたままになっていた。戦争末期には長距離旅行の切符は許可制で、あらかじめ申請書を出して、前日に駅長の判断を仰ぐ必要があった。
季節は秋に入り、朝夕は冷たい露が降りるようになっていた。みんなホームシックで、清水先生が英語で教えてくれたホームスイートホームをよく歌った。後になって音楽の時間にこの歌が課題として出され、私は草川信先生(夕焼け小焼けの作曲者)に「君の発音は正しい」とほめられた。私が外国語でほめられたのは、この時だけである。栄養状態が悪いので、みんな虫刺されのあとが治らず、掻きつぶして手足に潰瘍を持つ者が多くなっていた。湖畔には成蹊小学校の生徒が疎開しており、そこの保健室で診てもらうのだが、消毒薬を塗る以外の手当てはできなかった。私はその結果、顔が西瓜のように膨らみ、足は大根のように水膨れになった。急性腎炎なのだが、その時は誰もわからなかった。朝起きてみると、横になっていた顔の下側は風船のように膨らんでいる一方、反対側は普通の顔で、自分ではわからないが、みんなには不気味に見えたらしい。私は小学校5年のときにも急性腎炎の前歴があるが、その時は手当てが早かったので、こんなになるとは知らなかった。さすがに休養を命ぜられ、1日中蒲団にくるまって寝ていた。皆はそれでも邪魔扱いはせず、何かと世話をやいてくれた。授業や食事は私の寝ている枕元で行われた。
霜が降りようとする10月15日、とうとう帰京することになった。結局、疎開は終戦前1ヶ月半、終戦後2ヶ月ということになる。しかし私は寝たままで、みんながいそいそと帰り支度をするのを、黙って見ているほかはなかった。そして誰もいなくなってガランとなった部屋に1人取り残され、蒲団の中からボンヤリ天井を見上げていた。悲しいとか、これからどうなるとかいう感情は湧かなかった。やがて事務担当の浜田先生が現れ、一緒に帰ることになった。彼は後始末の要員を引き連れていた。小涌谷までどうやって行ったのか覚えていない。長距離を歩けるはずはなかったから、トラックにでも便乗したのだろう。超満員の小田急を乗り継ぎ、新宿で別れて、夕方暗くなってから1人で小金井の家に帰り着いた。先に帰京した班長の片山透が、家まで来て様子を話してくれていたので、家人はどうしたものかと思案しているところだった。私は反抗期の最中だったので、疎開先から手紙を1度も出しておらず、様子がわからなかったのだ。疎開が冬まで続いたら、私は生きていなかったろう。昭和18年に長兄の謹一郎を長患いの末に亡くしたばかりなので、親は深刻な思いだった違いない。湖畔の小学生の疎開につき添っていた滑川道夫先生は教育評論家で父と顔見知りで、ときどき私の様子を書き送ってくれていたらしい。翌日からお茶の水の杏雲堂病院に2月まで入院していた。食料品の配給制度はまだ続いていたし、敗戦でそういうシステムが最も混乱した時期だったので、上野の東京薬専女子部に通う姉の澄子が、毎日おにぎりを運んできて、それで食いつないだ。だから私は、敗戦直後の世間や校内の混乱を、見ないでしまった。
新学期になって、私は長期欠席のため留年して新しいクラスに入った。吉祥寺の駅前は盛大な闇市場となっていて、人でゴッタ返していた。電車はとにかく動いていたが、超満員という言葉以上の混雑で、乗り降りにはラグビーなみの力業が必要だった。乗ってしまうと身動きがとれず、足の上に体があることはほとんどなかった。窓ガラスはみんな破れて雨や寒風が吹き込み、座席が空いても坐ると前の人が押されてのしかかってきて危険なため、みんな座席の上に立っていた。東中野と大久保の間で、乗客の圧力で走行中の急行のドアがはずれ、数人が神田川に転落死亡したのもこの頃である。一番楽なのは、ドアと座席の端の間の空間だった。だから私は、今でもそこへ立つことが多い。けれども進行方向側は危険だった、しばしばかかる急ブレーキで座席の側板に圧しつけられ、骨折する人さえいたのである。食料事情が悪くて、アメリカが恵んでくれた飼料のトウモロコシ粉や大豆粉の粉食が多いので、そういう中でガスの放出をする奴が少なくなく、臭いが消散するまで長い間我慢せねばならなかった。中野から先の沿線は焼け野原、中野から手前で焼けていないところでも、線路から数十メートルの間は戦争末期に行われた強制疎開のため、家がなかった。これは空襲による火災から鉄道を守るために、建築物を取り壊したことによる。
小金井の家は居間だけでも九室ほどある大きな日本家屋で、空襲で焼け出されたり、子供だけでも安全なところへという親戚など、多いときには30人近い人数が生活していた。親が近所の農家と親しかったので、食料はかなり融通してもらえたから、買い出しに走り回ることはなかった。しかしいくつもの家族が1つ屋根の下に住むことはトラブルを生みやすく、新聞紙上にはそのための悲劇がしばしば報道されていた。とくに食料の配分についてが、その原因となりやすかった。台所は1つしかないので、それぞれの家族が交代で使い、食料のストックはオープンにして、それぞれ別な食事を作っていたらしい。この結果、少なくとも表立ったトラブルはおこらなかったようだ。母親たちは神経を使ったことだろう。空襲の翌日には、被害に遇ったと思われる親戚や知人のところへ、自転車に食料を積んで届けたこともあるが、一面の焼け野原で目印がなく、行き着くのが大変だった。
戦争が終わったのに犠牲者が出た。黒田が米軍放出のガソリン焜炉を使っていて爆発、家が全焼したうえ彼は焼死したのだ。片山透の父親は成蹊のドイツ語教師だったが、出征したまま未帰還で、家は収入が途絶え、彼と2人の弟は吉祥寺の駅前で新聞売りに立っていた。しまいには母親も見かけた。父親が帰還復職してからも、この立ち売りは続いていた。彼らはこれを1つの人生修行として続けたのだろう。制帽をかぶったまま、平然と仕事をしていた。私は腎炎の後遺症もなく、生物部と蹴球部で楽しんでいた。
敗戦により、日本の教育制度は目まぐるしく変わった。旧来なら中学5年、高校3年のところを、成蹊のような7年制高校では、一貫教育を理由に中学(尋常科)4年、高等科3年で通過する仕組みだった。ところが尋常科4年はとにかく修了したものの、高等科(旧制)は1年で新制大学受験となってしまい、高等科へ入ったトタンに受験勉強をせねばならなくなった。だから同窓会名簿を見ると、われわれ24回生は昭和24年修了なのに対して、1年早く入学した23回生(私がもといたクラス)は、昭和25年修了となっている。当時のクラスには、敗戦で行き場を失った海軍兵学校や陸軍幼年学校出身の、成績優秀な(これらの学校には国内最優秀の人材が集まっていた)人たちがたくさん入っていた。彼らは年齢も上で人生経験豊富なので、子供っぽいわれわれとは雲泥の差があった。こういう人達と受験競争をしても、とても勝ち目はない。だが、入試制度そのものも大きく変わり、大学受験の前にアチーブメントテストという全国一斉テストが導入された。今日のセンター試験と似ているが、内容は大いに異なる。たとえば積み木を立方体に組んだ見取り図があって、それを構成する積み木の数を答えるというような、直観重視の問題が多かった。これは旧来の理詰めの勉強では間に合わない。ところが私にはこのテストが性に合っていた。というのは盈進学園には幼稚園があり、そこで遊んだ積み木にソックリだったのだ。立方体の箱に収まっているのを取り出して遊んだ後、その箱へ戻すのだが、箱へ直接戻すのはむつかしい。だから外で立方体に組んでおいて、箱をかぶせて収めていたのだ。おかげでアチーブメントテストは好成績で、いつも平均点附近をうろうろしている私がクラスで2番の成績をとり、みんなを驚かせた。
大学入試の最初は学芸大だった。これには腕試しを兼ねて志願者が殺到し、驚異的な倍率となった。東大の入試はその次だったが、大学側の準備が遅れてしばらく待ち時間があり、間がもたない。そこで小海線沿線で2-3泊の採集旅行をしてガス抜きをした。こういう旅行は、前年にも京都で旧制高校最後のインターハイに参加して緒戦敗退した後、1人で紀伊半島を1周して体験ずみだった。鈍行で行ってフラリと降りて、駅前旅館(かつてはどの駅にもあった)へ飛び込みで泊まるのである。はじめのうちは米を持参せねばならなかったが、その頃になるとかなり融通がきくようになっていた。当時は偏差値というものがなかったから、学校側は「受けたい」と言えば誰がどの大学を受けようと、内申書を作ってくれた。陰でなんとうわさしていたかは知らない。試験の前日の夕方、父が「明日は雪の予報なので、交通機関が止まるかも知れないから、今夜のうちに牛込の叔父の家へ行って泊めてもらえ」と言う。私はなんとなく反発したが、結局不承不承それに従い、もう寝支度をしていた敬吉叔父を煩わせた。翌朝は重たい雪が10cmほど積もっていて、国鉄は動かなかった。市電は動いていたので試験場へは定刻前に着けたが、試験開始は数時間延期された。試験問題は覚えていないが、数学については解法がわからないので、あてずっぽにピタゴラスの定理の応用と見当をつけて答えを先に決めてしまってから逆にたどったら、解法がわかったものがあった。東大の次は教育大の入試だったが、印象に残っていない。結果は学芸大は「否」、東大は「合」、教育大は「合」だった。入試制度の変更で、いわゆる秀才タイプが失敗する例が多かった中、高校側としてはかなり番狂わせな結果だったようだ。しかし東大教養学部に入ってみたものの、やはり背伸びしたことは争えず、2年後の専門課程への進学は、単位不足 (とくに語学)で留年し、翌年理学部植物学科に進んだ。語学の弱さは、その後も私の弱点だった。もっとも留年しなかったら、成績の関係で農学部に振り分けられたはずだから、将来は全く違ったものとなっただろう。2度の留年が、将来を分けるキーとなったことは否めない。
これで高校生活は終わったわけだが、通学路が吉祥寺経由だったので、帰途に成蹊に寄って生物部の部室でとぐろを巻いたり、蹴球部の練習に加わったりした。採集会や合宿にもよく参加し、新制高校の連中ともなじみになった。戦争の影響で諸先輩の多くは連絡がとれなくなり、せいぜい2-3年前の先輩しか知らなかったので、自然とわれわれの世代がOBとして部の世話をやくことになった。スプトニークが打ち上げられたときには、理化館屋上で天文気象部がエーコンの指導で観測(成蹊は正式の測候所と認められており、この観測も全国的に行われた事業の一環である)するのを見学した。あのときが人工衛星を見た最初で最後である。アルバイトで高校の生物の授業をやったこともあるが、教科書を教えることは私の気質に合わなかった。そのうち自分の仕事が忙しくなり、高校と中学が別な校舎に移ったこともあって疎遠になった。その次に接触ができたのは、ヒマラヤ植物調査に使う大量の新聞紙を、生物部を通じて調達してもらったときである。1回の遠征で、半頁に畳んで重ねた新聞紙が10mほど必要なのである。これは2-3年おきに4回ほど世話になり、大変助かった。
(2007年11月20日記)
『金井弘夫著作集 植物・探検・書評』コンテンツ一覧▼ 目次(青字)をクリックすると、各文をご覧いただけます
金井弘夫博士著作集に寄せて 東京大学名誉教授 大場秀章 / あとがき
第一部 時代の記憶・探険の記憶
最後の旧制高校生の自分史
理化館の焦げ茶のタイル
インドで見たこと聞いたこと
- はじめに
- 夏休みは4月
- 「古」新聞の値段
- 街頭の商人達
- 乞食
- ボクセス
- 良いお金と悪いお金
- 水
- お茶
- オナラ
- 立小便
- 近づくほど遠くなる
- 踏切に錠前
- 汽車
- バス
- 市電
- インド人という「民族」
- アッチャー
- タバコ
- お酒
- ビール
- ウイスキー
- ラム
- チャン
- マフア酒とヨーグルト
- 朝のお祈り
- 国境侵犯
- 二人のリエゾン・オフィサー
- シェルパたち
- アンプルパ
- トゥンドウ
- プルバ・ロブソン
- テンバ・シェルパ
- 女性たち
- ラマ教
- 山で一番こわかったもの
- お菓子
- 名前
- 宿屋
- インドの道の良さ
- フェリー
- 牛
- 交通法規
- カストムハウス
- 風呂
- 拍子木たたき
- バルカカナの日本人
- ボダイジュの借り倒し
- タテガミのあるブタ
- 封蝋
- 食いもの
- カースト(階級制度)
- デモ
- 鶏と卵
- 切符を買う
- 街路樹
- 事故
- インドの英語
再びインドの植物を求めて
- 悪路に悩む採集行
- ヒマラヤで見る段々畑
- 調査成果の一端
西北ブータンの山々
- 入国手続き、旅行許可など
- 入出国の経路
- 国内の輸送、通信、シェルパなど
- 物資の調達
- 気候
- 地図、コースについて
- チンプウ-トンサ
- 観察されたピーク
- 集落
- 通貨、賃金
フィニッシュの話
- 失せ物が出た
- 通関書類、フィニッシュ
- リエゾン・オフィサー、フィニッシュ
- ミソとストーブ、フィニッシュ
- スペース、フィニッシュ
- チニ、フィニッシュ
- サーダー、フィニッシュ
- ポーター、フィニッシュ
- 道路とジープ、フィニッシュ
- ブルカー、フィニッシュ
- 標本、フィニッシュ
- 道路、もうひとつのフィニッシュ
- シェルパ、フィニッシュ
- トラック、フィニッシュ
東ネパール調査(1963年)点描
- チャッシガレ!
- おまじない、ハチ
- 録音
- ハリー
- 食物
- こわいもの
ネパール通信1
- カトマンズ(1)
- フルチョウキ
- カトマンズ(2)
- チュリア・マハバラトの旅
- ゴサインクンデの旅
- ボダイジュのほこら
- カトマンズ(3)
- ロルカニの旅
- カトマンズ(4)
- チリメ、ランタンの旅
- チャンドラギリの旅
ビル・ニガントゥに見られる米の記事
ネパールの滝の数
ネパール通信2
- 自動車事故のはなし
- 創立記念パーティー
- カリンチョークの旅(1)
- インドラジャトラ
- カリンチョークの旅(2)
- チュリアの旅
ヒマラヤ植物調査の今昔
日本・ネパール協同植物調査史 1960-1980 [英文]
『冒険家族ヒマラヤを行く』訳者あとがき
パプア・ニューギニアの話
- 交通
- 食べ物
- 人々
- コトバ
- 古戦場
吉川英治文化賞受賞のことば
第二部 植物の観かた・残しかた
野外観察会のこと
日本植物の分布型に関する研究(2) ヒメマイヅルソウの分布型と変異
オゼコウホネの種子散布
ヤマモモの仁
クヌギの落枝
スベリヒユは対生
猪突猛進するチガヤの地下茎
ササの葉鞘
ケヤキの落葉現象はあったか
笹舟は沈む!
ミャンマーのドクウツギ属植物Coriaria terminalis Hemsley とその西限産地
ブータンのウルシ
植物の動きを見せる
尾瀬ケ原の池塘データベースによるヒツジグサとオゼコウホネの16年間の分布消長
群落の突然の交代
ツタの植物画
ツタの「雨」
国立科学博物館のサクラソウ生態展示
有毒植物を食べる
ミズバショウの果実の味
マムシグサのイモの「味」
ヌルデとネムノキは仲良し?
ビルマの植物学界の一端
部活動と自然観察会
普通な植物を記録しよう
ヒレハリソウ(ムラサキ科)の葉序
アイスマンの弓矢
ツュンベリーと日本のアマチュア植物学 [英文]
誰にでも利用できる標本のために
標本にはラベルを入れよう
標本ラベル論議へのながーいコメント
- 仮ラベルに関して
- 本ラベルに関して
- データベースに関して
ヒートシールによる標本貼付
おしば標本の新しい貼付法
おしば標本貼り付け用ヒートシールテープの自作法
移動式おしば標本棚の得失
- 改装工事前後の問題
- 運用上の問題
おし葉製作法の改良
携帯用植物乾燥機について
- 冨樫板
- 加圧法
- 加熱法
- 標本製作中の注意と標本の出来具合
- 研究室での使用法
教具教材としての植物パウチカード
生植物のラミネート標本
日本植物分類学文献目録・索引のデータ仕様と検索項目 [英文]
シンポジウム「標本データベースの将来」の感想
- Herbariumの体制
- 大学と博物館の違い
- どうやるか
- データベースを作ったあと
- 画像データベース
第三部 ナマエ・データ・ヒト
吉村衛氏による科の和名の新提案
命名規約とオフセット印刷
デチンムル科
「野草」に現れた植物の新名
新和名提示のいろいろなかたち
「ナマエ」を考える
モノの見え方について
東京消失
地名データベースの活用
- 住吉小学校の「住吉」研究
- 住吉小学校はいくつあるか
- 住吉神社はどのくらいあるか
- 住吉という地名はどうだろう
- IT化時代の学習
新日本地名索引の内幕
新日本地名索引のはなし
- どんなものか
- どうやって作ったか
- 索引のスタイル
- よみの問題
- 分布地図
- 「鐙」の分布
- JIS漢字表の問題
学術用語集植物学編(増訂版)の分類学用語改善のための資料
- 形を表す用語
- 花を表す用語
データベース仕様と植物学・動物学・農学に共通な植物用語
- データベース仕様
- データベース作成の方法
- 調整を要する用語の方針と方法
保育社・原色日本植物図鑑の観察
Index Kewensis 展開版前文
ネパールの本草書ビル・ニガントゥについて
岩槻邦男氏にエジンバラ公賞
英語教科書に載った西岡京治氏
大村敏朗氏の貢献
原寛博士への弔辞・追悼文
- 弔辞
- はじめてのヒマラヤ
若き日の原寛博士の日記
津山尚博士
「訓導」原襄さんの思い出
里見信生さんの思い出
里木村陽二郎先生
山崎敬さんの思い出
第四部 書を評す
地図・地名
- コンサイス地名辞典日本編
- 現代日本地名よみかた大辞典 1-6巻
- 知っておきたい災害と植物地名
- 日本湿地目録
- 日本山名総覧
- FD日本山名総覧「全国版」
- 数値地図 25.000(地名・公共施設)全国CD-ROM版
学名・用語など
- 植物学ラテン語辞典
- 国際植物命名規約1988
- 植物学名詞
- 菌学用語集
- 植物学名大辞典
- 植物の名前のつけかた植物学入門
- 日本苗字大辞典
- 図説植物用語辞典
- 国際栽培植物命名規約第7版
フィールドワーク
- 清瀬の自然フィールドガイド春
- 東京西郊野外植物の観察
- GPS全日本ロードマップ
- ヨコハマ植物散歩
- 東京樹木めぐり
- 巨樹・巨木
- ぐるっと日本列島野の花の旅
- 続巨樹・巨木
- 地べたで再発見「東京」の凸凹地図
- 東京大学本郷キャンパス案内
- 雷竜の花園
- 秘境・崑崙を行く
- 中国秘境に咲く花
- 青いケシの咲くところⅡ
- シルクロードに生きる植物たち
- ヒマラヤを越えた花々
- 幻の植物を追って
- ロンドンの小さな博物館
- ヒマラヤに花を追う
- ヒマラヤの青いケシ
人
- 白井光太郎著作集
- 進野久五郎植物コレクション
- 来し方の記8
- 横内齋著作集2
- 李永魯文集
- MAKINO80『植物同好会』八十年の歩み
- しだとこけ 服部新佐先生追悼記念号
- 小泉秀雄植物図集
- 籾山泰一先生論文集
- 私の研究履歴書-昭和植物学60年を歩む- [林孝三]
- 命あるかぎり-花と樹と人と-見明長門追悼集
- 中尾佐助文献・資料目録
- 牧野晩成
- 沼田真・著作総目録
- 牧野富太郎とマキシモヴィッチ
- 牧野富太郎著・植物一家言
- 誰がスーリエを殺したか1
- 展望河口慧海論
- 「イチョウ精子発見」の検証
- 牧野富太郎植物採集行動録
- 大雪山の父・小泉秀雄
- 大場秀章著作選Ⅰ
- 大場秀章著作選Ⅱ
- 小原敬先生著作集
- 植物文化人物事典
- 清末忠人研究集録
- 自然と教育を語る
文化
- 現代文明ふたつの源流
- 栽培植物の起源と伝播
- 江戸時代中期における諸藩の農作物
- 日本の植物園
- アジアの花食文化
- いのちある野の花
- 江戸参府随行記
- ボタニカルモンキー
- 菌類認識史資料
- 植物学と植物画
- 黒船が持ち帰った植物たち
- 日本植物研究の歴史
- 植物園の話
- バラの誕生
- 絵で見る伝統園芸植物と文化
- 江戸の植物学
- 現代いけばな花材事典
- 花の男シーボルト
- サラダ野菜の植物史
- すしネタの自然史
- シーボルト日本植物誌 文庫版
地域・フロラ
- 環境アセスメントのための北海道高等植物目録Ⅳ
- 宮城県植物目録 2000
- 秋田県植物分布図
- 秋田県植物分布図第2版
- 茨城県植物誌
- とちぎの植物Ⅰ,Ⅱ
- 日光杉並木街道の植物
- 渡良瀬川支流山塊の高等植物 類似植物の見分け方ハンドブック
- 渡良瀬川支流山塊の高等植物
- 群馬の里山の植物
- 群馬県タケ・ササ類植物誌
- 群馬県植物誌改訂版
- 館林市の植物
- 尾瀬を守る
- 1998年版埼玉県植物誌
- さいたまレッドデータブック
- 千葉県植物誌
- 千葉県の自然誌
- 富里の植物
- 続江東区の野草
- 小笠原植物図譜
- 神奈川県植物誌分布図集
- 横浜の植物
- Yato横浜 新治の自然誌
- 箱根の樹木
- 新潟県植物分布図集第6集
- 新潟県植物分布図集第7集
- 新潟県植物分布図集第10集
- 新潟県植物分布図集第1-10集登載植物および索引
- 石川県樹木分布図集
- 加賀能登の植物図譜
- 金沢大学薬学部付属薬用植物園所蔵標本目録 白山の植物
- 信州のシダ
- 長野県の植生
- 長野県植物研究会誌第20号
- 長野県版レッドデータブック維管束植物編
- 長野県植物ハンドブック
- 伊部谷の植物
- 植物への挽歌
- しなの帰化植物図鑑
- 37人が語るわが心の軽井沢1911-1945
- 近畿地方の保護上重要な植物
- 改訂・近畿地方の保護上重要な植物
- 近畿地方植物誌
- 高山市の植物
- 改定三重県帰化植物誌
- 兵庫県の樹木誌
- ひょうごの野生植物
- 播磨の植物
- 平成元年度箕面川ダム自然回復工事の効果調査報告
- 六甲山地の植物誌
- 淡路島の植物誌
- 奈良公園の植物
- 岡山県スゲ科植物図譜
- 広島県文化百選 花と木編
- 広島市の動植物
- 山口県の植物方言集覧
- 山口県の巨樹資料
- 徳島県野草図鑑〈下〉
- えひめの木の名の由来
- 福岡県植物目録 第2巻
- 熊本の野草〈上〉〈下〉
- 熊本の木と花
- 鹿児島県の植物図鑑
- 改訂鹿児島県植物目録
- 沖縄植物野外活用図鑑全6巻
- 沖縄県の絶滅のおそれのある野生生物
- 琉球列島維管束植物集覧
- 孤島の生物たち-ガラバゴスと小笠原
- ブラジル産薬用植物事典
- キナバル山の植物
- 韓国産松柏類
- 韓国植物検索便覚
- 韓国植物分類学史概説
- 中国人民共和国植被図
- 中国天山の植物
- 雲南の植物
- 雲南の植物
- 東北葯用植物
- ヒマラヤの自然誌
- ヒマラヤ植物大図鑑
- ネパール研究ガイト
- スイスアルプスの植物
調べる
<環境>
- 屋久島原生自然環境保全地域調査報告書
- 昭和63年度レアメタル賦存状況調査報告書
- 帰化植物のはなし
- レッドデータプランツ
- 植物からの警告・生物多様性の自然史
- エコロジーガイド・ウェットランドの自然
- 植物群落レッドデータブック
- 日本森林紀行
- 温暖化に追われる生き物たち
- 水生シダは生きる
- 侵略とかく乱のはてに
- 各都道府県別の植物自然史研究の現状
- 日本の絶滅危惧植物図譜
- 絶滅危惧植物図鑑レッドデータプランツ
<種類>
- 新しい植物検索法 離弁花類編
- 日本タケ科植物総目録
- 新しい植物検索法 合弁花類篇
- 北日本産樹木図集
- 動植物目録
- 日本件名図書目録⑨ 動・植物関係
- 山野草植物図鑑
- 植物目録
- 日本の高山植物
- 世界の針葉樹
- 検索入門樹木
- 葉による野生植物の検索図鑑
- 英語表現べからず辞典
- 日本イネ科植物図譜
- 改訂増補 牧野日本植物図鑑
- 日本の自生蘭
- 北本州産高等植物チェックリスト
- 日本水草図鑑
- 日本草本植物根系図説
- 日本のスミレ
- 日本で育つ熱帯花木植栽事典
- 植物の系統
- 日本タケ科植物図譜
- 日本の野生植物 コケ
- 日本花名鑑1
- 樹に咲く花 合弁花 単子葉 裸子植物
- 高山に咲く花
- 日本花名鑑2
- 日本の帰化植物
- ツバキとサクラ
- カエデの本
- 新日本の桜
- 日本のスゲ
- 日本の野菊
- 日本花名鑑4
- 日本海草図譜
<観察>
- 花と昆虫
- 樹木
- 平行植物
- 描く・植物スケッチ
- 植物観察入門
- 野草 1-15巻+別巻
- 折々草
- みどりの香り 青葉アルコールの秘密
- 誰がために花は咲く
- 草花の観察「すみれ」
- 人に踏まれて強くなる雑草学入門
- 花生態学入門 花にひめられたなぞを解くために
- ブナ林の自然誌
- 原寸イラストによる落葉図鑑
- 人里の自然
- 虫こぶ入門
- 森のシナリオ
- シダ植物の自然史
- 花と昆虫がつくる自然
- 文明が育てた植物たち
- 雑草の自然史
- セコイアの森
- 植物の私生活
- ツリーウォッチング入門
- 根も葉もある植物談義
- 花の観察学入門
- 野の花山の花
- ため池の自然
- 花と昆虫 不思議なだましあい発見記
- 道端植物園
- タンポポとカワラノギク
- どんぐりの図鑑
- 植物のかたち
- せいたかだいおう-ヒマラヤのふしぎなはな
- コケ類研究の手引き
- 虫こぶハンドブック
- 虫こぶ入門
- ひっつきむしの図鑑
- 樹木見分けのポイント図鑑, 野草見分けのポイント図鑑
- 植物生活史図鑑Ⅰ, Ⅱ
- 絵でわかる植物の世界
- 「野草」総索引
- 「野草」植物名総索引 第1巻~第70巻
- 標本をつくろう
- わたしの研究 どんぐりの穴のひみつ
- どんぐり見聞録
- ほんとの植物観察, 続ほんとの植物観察
- キヨスミウツボの生活
- 発見!植物の力1~10
- 帰化植物を楽しむ
- 花からたねへ
- 植物と菌類30講
<標本>
- 自然史関係大学所蔵標本総覧
- 国立科学博物館蔵書目録和文編
- デジタルミューゼアム
- 牧野植物図鑑の謎
- Systema Naturae 標本は語る
- 牧野標本館所蔵のシーボルトコレクション
- 牧野標本館所蔵シーボルトコレクションデータペース CD-ROM版
洋書
- Manual for Tropical Herbaria, Regnum Vegetabile
- The Asiatic Species of Osbeckia
- Biological Identification with Computers
- A Geographical Atlas of World Weeds
- Neo-lineamenta Florae Manshuricae
- Atlas of Seeds Part 3
- Alpine Flora of Kashmir Himalaya
- Botticelli's Primavera
- Index to Specimens Filed in the New York Botanical Garden Vascular Plant Type Herbarium
- Elsvier's Dictionary of Trees and Shrubs
- Medicinal Plants in Tropical West Africa
- Fodder Trees and Tree Fodder in Nepal
- Nepal Himalaya, Geo-ecological Perspectives
- Leaf Venation Patterns
- Development amid Environmental and Cultural Preservation
- The Lilies of China
- Kew Index for 1986
- Catalog of Moss Specimens from Antarctica and Adjacent Regions
- The mountains of Central Asia
- Trees of the southeastern United States
- A New Key to Wild Flowers
- Flora of upper Lidder Valleys of Kashmir Himalaya
- Systematic Studies in Polygonaceae of Kashmir Himalaya Vol.1
- Flowers of the Himalaya, a Supplement
- Plant Taxonomy and Biosystematics, 2nd ed.
- Plant Evolutionary Biology
- Lilacs, the Genus Syringa
- Ornamental Rainforest Plants in Australia
- Forest Plants of Nepal
- Plant Taxonomy, the Systematic Evaluation of Comparative Data
- Woody plants
- The Evolutionary Ecology of Plants
- The Forest Carpet
- Cryptogams of the Himalayas Vol.2., Central and Eastern Nepal.
- Pattern Formation in Plant Tissues
- Plant Genetic Resources of Ethiopia
- Leaf Architecture of the Woody Dicotyledons from Tropical and Subtropical China
- Palaeoethnobotany
- A Bibliograpby of the Plant Science of Nepal
- C.P. Thunberg's Drawings of Japanese Plants
- Temperate Bamboo Quarterly 2
- Index of Geogrphical Names of Nepal
- A Revision of the Genus Rhododendron in Japan, Taiwan, Korea and Sakhalin
- A Bibliography of the Plant Science of Nepal. Sipplement 1
- The Iceman and His Environment, Palaeobotanical Results
- The Cambridge Illustrated Glossary of Botanical Terms
- Handbook of Ayurvedic Medicinal Plants
- Ethnobotany of Nepal
- Himalayan Botany in the Twentieth and Twenty-first Centuries
- Meristematic Tissues in Plant Growth and Development
- Proceedings of Nepal-Japan Joint Symposium on Conservation and Utilization of Himalayan Medicinal Resources
- The Orchids of Bhutan
- Beautiful Orchids of Nepal
書籍詳細
-
元・国立科学博物館 金井弘夫 著
菊判 / 上製 / 904頁/ 定価15,715円(本体14,286+税)/ ISBN978-4-900358-62-1
〔花の美術館〕カテゴリリンク
- 第20回 『熱帯植物巡礼』
- 第19回 小山鐡夫追悼記念号『黒船が持ち帰った植物たち』より
- 第18回 小山鐡夫追悼記念号『植物園の話』より
- 第17回 『MAKINO 80』東京植物同好会・牧野植物同好会八十周年記念誌
- 第16回 ハマナスの語源を探る
- 第15回 金井弘夫追悼記念号『金井弘夫著作集 植物・探検・書評』より
- 第14回 『花のある風景』
- 第13回 坂嵜信之追悼記念号『日本で育つ・熱帯花木植栽事典』より
- 第12回 楽しい花観察108選『不思議な花々のなりたち』
- 第11回 川島榮生の《ヤマアジサイの世界》
- 第10回 渡辺健二『日本産ギボウシの世界』
- 第9回 『ユリノキという木』─ 魅せられた樹の博物誌
- 第8回 『北米インディアン悲詩』/ エドワード・カーティス写真集
- 第7回 江戸時代の花たち 書物に見る江戸時代の園芸文化
- 第6回 わが国初のボタニカルアーティスト 五百城文哉(いおきぶんさい)の世界
- 第5回 『ビル・ニガントゥ』 19世紀末ネパール秘蔵の本草図譜
- 第4回 植物画家 石川美枝子の作品
- 第3回 サイエンティフィック・イラストレーター 木村政司の作品
- 第2回 植物画家 中島睦子の作品
- 第1回 『PLANTAE ASIATICAE RARIORES』