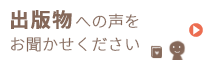再びインドの植物を求めて
日本の植物の起源や類縁関係を理解するためには、同じ祖先から出たとみられるアジア大陸東部に存在する近縁な植物の知識が必要である。ことに最近では、日本の植物はかなりよく調べられてきたので、大陸側の近縁植物を調査することがますます必要になってきている。
東京大学では、1960年春に第1次インド植物調査隊をシッキム・ヒマラヤに送り、このような立場から調査をおこなったが、1963年には第2次調査隊を送って、東部ヒマラヤの秋の植物を調査した。最近の国際情勢のため前回の地域に入るのが困難であったので、そのすぐ西隣のタムル川流域に入ることになった。隊員6人のうち、紅一点の黒沢幸子さんのほかは、第1次調査隊のメンバーである。先発の原寛隊長、金井、黒沢の3人は9月初旬に東京を出発し、手続きや交渉をおこなった後、10月13日にビラトナガルで後続の津山尚、村田源、冨樫誠と落ちあった。ネパール政府はわれわれの隊の性格を考慮して、王立植物園のウパディヤ氏をリエゾン・オフィサーにつけてくれた。
〇悪路に悩む採集行
10月16日、ビラトナガルをバスで出発し、ダランからは徒歩で、シェルパ9人、人夫約50人とともに2ヶ月の旅にかかった。われわれのとったコースのうち、ダランからワルンチュンゴラまでは、近年多くの日本隊が通過しており、コースに問題はないと聞いていたが、あいにく9月に大洪水があり、タプレジュン以北の川沿いの道路は全く破壊されてしまっていて、1日に何度となくけわしい上下をくり返しながら、足場の悪い仮設の道を歩かねばならなかった。橋もすっかり流されていて、両側から竹をさし出し、フジヅルでつないだV字型のつり橋をキモを冷やしながら渡らされた。ガケくずれを横断中に、落石にあい、リエゾン・オフィサーをはじめシェルパ数人が負傷したこともある。またイラムから南はジープが使えると思っていたのだが、行ってみたらそんな道路はなく、しかも行先の情報が不確実で、明日はジープに乗れると毎日あてにしながら、とうとうビラトナガルまで1週間歩かされてしまった。イラムからビラトナガルまで歩いたのは、日本人でははじめてであるし、ネパール人でもあまり多くはあるまい。彼らはイラムからダージリンに出て、インドの鉄道を利用するのが普通なのである。
われわれは秋の植物を採集するのが目的だったのだが、ビザの申請や入域のコースなどについて許可をもらうのに手間どり、予定が1ヶ月近く遅れ、高地では冬にかかってしまい、また10月、11月というのに季節はずれの雨に悩まされた。しかし幸い予期以上に豊富な植生にめぐまれて十分に現地で調査をおこなうことができ、約40,000点の種子植物のおしば(腊葉)標本をはじめ、多数の地衣、コケ、種子などを採集することができた。
一口に40,000点と言っても、人夫約30人分に当り、それも乾いた後でのことだから、採集したての重量はその数倍あり、いやがる人夫にこれを背負わせるのは毎朝ひと仕事だった。日中は手あたり次第採集して、幅50cm、長さ1mのポリ袋につめこむ。それがいっぱいになるとシェルパに背負わせてまた新しい袋に採集する。シェルパが背負いきれなくて、隊員もそれを背負わねばならぬほど採集したこともある。キャンプ地につくと、毎晩おそくまで標本の整理乾燥にあたった。用意した新聞紙の量は、半ページ大で積重ねて10mに達する。特別に作った金属製のプレートに標本をはさみ、炭火の上で加熱するので、早いものは半日で乾ききってしまう。こうしてできあがった標本は、別に人夫をやとって後送しておいた。日本へ送り返す荷造り包装を終ってみたら、大型トラック1台分あり、日本を出発する時より量がふえていた。採集コースは海抜200mから4,000mにわたり、亜熱帯から亜高山帯におよぶ。高山帯は時期的にも、日程の関係からも、ゆくことができなかった。
タムル川やカンカイ川下流はかなり湿潤で温度が高く、いろいろな種類の常緑広葉樹の密林であるが、少し土地が乾燥したところではサラソウジュの林が見られる。800m以上になるとSchima wallichii(ヒメツバキ)が多くなり、これにCastanopsis indicaが混じる。1,500m以上はCastanopsis hystrixやC. tribuloidesのシイ類のほか、ハイノキ科やクスノキ科の木本の暖帯常緑広葉樹林となり、2,300mくらいになるとQuercus pachyphylla、Q. lamellosa、Q. semecarpifolia、Q. glaucaなど、常緑カシ類が主となる。2,600m以上はシャクナゲ林で、Rhododendron arboreumの純林が続く。亜高山帯の針葉樹林はヒマラヤツガ(Tsuga dumosa)とヒマラヤモミ(Abies spectabilis)の2種からなり、2,700~2,800mでTsugaが現れ、3,000mを越すとAbies林となる。Tsuga林の下にはそれより一段下位のシャクナゲ林やカシ林の植物がまじっているが、Abies林ではそういうものはなく、Rhododendron barbatum、Rh. falconeri、Rh. hodgsoni、Juniperus、Betula utilisなどが一緒に生えている。
ヒマラヤには日本のブナ帯に当る落葉広葉樹林が欠けており、われわれの地域もその例外ではなかった。ただ、ところどころ特に尾根の北斜面のようなところではAcer(モミジ)、Betula(カバノキ)、Viburnum(オオカメノキ)、Sorbus(ウラジロノキ)のような落葉広葉樹がかなり広い面積を占めている。
特殊な植生としては、岩盤の露出した日当たりの良い斜面では、Schima−Castanopis帯ではサラソウジュ(Shorea robusta)、シイ−カシ帯ではQuercus incanaが生えている。マツの林は暖帯のやせ尾根の上や谷の出合いの突角地にみられた。バンドケバンジャンの東西に走る尾根筋は、遠望するとシャクナゲ林のようだが、実際はユズリハの森林におおわれており、奇異の感にうたれた。
森林の樹木は着生植物にビッシリとおおわれており、とくにセン(蘚)類、ラン、シダが豊富である。低い高度の所では植物の繁茂が目立った。秋から春にかけて雨はほとんど降らないが、霧がよくかかるので空中からの水分の供給がかなりあるらしい。ゴルワで経験したところでは、日が上って霧が晴れる際に、それが樹木の葉に凝結して木雨となり、30分ほど夕立のようにパラパラと降ってくるのだった。
〇ヒマラヤで見る段々畑
耕地についてみると、約2,200m以下はほとんど全部耕されているといってよい。作物の主なものはトウモロコシ、ジャガイモ、シコクビエ、ソバ、イネ、アブラナなどである。イネは約2,000m以下にみられ、急な山腹に階段状に作られた大小無数の水田は立体地図をみているような気がする。イネのできは日本とはくらべものにならず、熟しても穂が直立している。穀粒が非常に落ちやすく、稲束を3回ほど地面にたたきつけるだけで、きれいに脱穀がすんでしまう。そのかわり運搬中の脱粒がひどく、刈入れのすんだ水田には一面にモミが落ちている。
ヒマラヤの農民の畑作りの努力は、だれも感嘆させられるが、地味の悪くなった畑はそのまま放置されており、造林も全くおこなわれていないので、急速に侵食されていることが気にかかる。この地域が地すべり地帯であることを考えると、耕地の経営や森林の造成に適当な手を打つことは急務と思われる。われわれが至るところで出会った大地すべりも、適当な森林行政が行われればある程度防止できたであろう。
われわれは秋から冬にかけて旅行したわけであるが、日本での季節感とはだいぶん違った場面に出会い、めんくらわされた。11月なかばの3,000m附近では、毎朝真白に霜が降り、月はじめに降った雪が根雪となって残っている。日本ほどみごとではないが、紅葉もみられる。ところが1,500~2,000mでは12月のはじめなのに、日本なら早春に咲くツノハシバミの花がみられ、サクラやアブラナが満開である。水田にはトンボが飛んでイネの取入れの最中であり、ソバが花盛りで、シコクビエは取入れを待つばかり。夜になるとテントの周囲をホタルがとびまわり、草むらではクツワムシやキリギリスが鳴いている。美しい星空を人工衛星がとぶのもみえる。もっと低いところでは日ざしは真夏のよう、マラリヤ・カもずいぶんいる。われわれがいそがしく登ったり下ったりしたせいもあるが、日本とは季節の移り変わりの仕方が違うようにみえる。
〇調査成果の一端
われわれの採集品はまだ整理が始まったばかりであるが、特に注目すべき発見としては、Tetracentronとカワゴケソウ科を、ヒマラヤではじめて採集したことをあげられよう。
Tetracentronはカツラに近縁な1科1属1種の樹木で、双子葉植物の中で材に導管をもたない特異なものであり、きわめて古い起源をもつものと考えられている。これまでは中国中西部とビルマ最北部にしか知られていなかったが、われわれはこれをバンドケバンジャンと他1ヶ所で実のついた枝を採集した。冬で木の葉が落ちていたからこそ、遠くにある果穂を発見できたのだが、そうでなければとても採集はできなかったろう。中国からネファ、ブータン、シッキムをとびこえて東ネパールでみつかったので、今後この中間地域でも発見の可能性がある。ヒマラヤ植物と東部アジア温帯植物の関連を示す1つの重要な証拠である。
カワゴケソウ科はこれまでインド東部のアッサムで知られていたが、われわれはタプレジュン地区の2ヶ所でこれを発見した。この植物は浅い水流に洗われる石の上にへばりつく種子植物であるが、その形態は一見、タイ(苔)類を思わせる。アジアの南方地域に点々と分布しており、わが国でも九州の一部に産して天然記念物に指定されている。第1の産地はたんぼの灌漑(かんがい)用水が道床を洗っているところで、路上の石の上にビッシリとついていた。数人の隊員は気がつかずにその上を踏んでいってしまったが、後続のメンバーが発見した。ちょうどよい時期だったので、花も実もある標本をとることができた。
そのほか特異なものとしては、ヒナノシャクジョウ科、ツチトリモチ科、アキノギンリョウソウ属などの寄生植物を採集した。ヒナノシャクジョウ科の植物は、厚く積った落葉の中にはえ、真白で菌類のような感じのするものである。わが国にも数種を産するが、熱帯地方に多い。ツチトリモチ科は樹木の根に寄生し、小さな花をつけた太い穂状花序を地中からもち上げ、何とも珍妙な形をしている。われわれの採集品は数種類で、寄主はウルシ科、ブナ科などであった。雌雄異株であるが、雌株と雄株が下部でつながっている標本も得られた。われわれが苦労しながら見つけ出そうとしているところへ、土地の人が通りかかり、そのへんの土をかきまわすと、まだ小さい株がつぎつぎところがり出てきて驚かされた。アキノギンリョウソウ属は腐葉に寄生する植物で、日本でもギンリョウソウ属とともに山地でよくみられる。これらの両者はよく似ているが、アキノギンリョウソウ属は秋に開花して“さく果”を作り、ギンリョウソウ属は初夏に開花して“液果”を作る。1960年にわれわれはダージリンでギンリョウソウ属を採集している。
日本植物に近縁な植物はシイ・カシ林とシャクナゲ林の中に多い。アオキ、ハナイカダ、マツカゼソウ、ズダヤクシュ、ゲンノショウコ、キヅタ、ドクダミ、ウマノミツバ、タニソバ、キブシ、アセビ、ネジキ、ミヤマシキミなど、数えあげるには紙数が足りない。ズダヤクシュのように日本のものとどこも違わないものもあるが、たいていは少し異なっている。ハナイカダの実は日本では黒緑色であるが、ヒマラヤのは赤味をおびているし、ミヤマシキミは日本では赤い実をつけるのにヒマラヤのは黒い実をつけるといったふうである。
ヒマラヤといっても広大な地域なので、1度や2度の調査ではなかなか調べきるというわけにはいかない。何かの機会にヒマラヤに足を入れる方々があれば、少しでもよいから資料をもち帰ってくださるようにお願いする。
[科学朝日1964年6月号を加筆]
『金井弘夫著作集 植物・探検・書評』コンテンツ一覧▼ 目次(青字)をクリックすると、各文をご覧いただけます
金井弘夫博士著作集に寄せて 東京大学名誉教授 大場秀章 / あとがき
第一部 時代の記憶・探険の記憶
最後の旧制高校生の自分史
理化館の焦げ茶のタイル
インドで見たこと聞いたこと
- はじめに
- 夏休みは4月
- 「古」新聞の値段
- 街頭の商人達
- 乞食
- ボクセス
- 良いお金と悪いお金
- 水
- お茶
- オナラ
- 立小便
- 近づくほど遠くなる
- 踏切に錠前
- 汽車
- バス
- 市電
- インド人という「民族」
- アッチャー
- タバコ
- お酒
- ビール
- ウイスキー
- ラム
- チャン
- マフア酒とヨーグルト
- 朝のお祈り
- 国境侵犯
- 二人のリエゾン・オフィサー
- シェルパたち
- アンプルパ
- トゥンドウ
- プルバ・ロブソン
- テンバ・シェルパ
- 女性たち
- ラマ教
- 山で一番こわかったもの
- お菓子
- 名前
- 宿屋
- インドの道の良さ
- フェリー
- 牛
- 交通法規
- カストムハウス
- 風呂
- 拍子木たたき
- バルカカナの日本人
- ボダイジュの借り倒し
- タテガミのあるブタ
- 封蝋
- 食いもの
- カースト(階級制度)
- デモ
- 鶏と卵
- 切符を買う
- 街路樹
- 事故
- インドの英語
再びインドの植物を求めて
- 悪路に悩む採集行
- ヒマラヤで見る段々畑
- 調査成果の一端
西北ブータンの山々
- 入国手続き、旅行許可など
- 入出国の経路
- 国内の輸送、通信、シェルパなど
- 物資の調達
- 気候
- 地図、コースについて
- チンプウ-トンサ
- 観察されたピーク
- 集落
- 通貨、賃金
フィニッシュの話
- 失せ物が出た
- 通関書類、フィニッシュ
- リエゾン・オフィサー、フィニッシュ
- ミソとストーブ、フィニッシュ
- スペース、フィニッシュ
- チニ、フィニッシュ
- サーダー、フィニッシュ
- ポーター、フィニッシュ
- 道路とジープ、フィニッシュ
- ブルカー、フィニッシュ
- 標本、フィニッシュ
- 道路、もうひとつのフィニッシュ
- シェルパ、フィニッシュ
- トラック、フィニッシュ
東ネパール調査(1963年)点描
- チャッシガレ!
- おまじない、ハチ
- 録音
- ハリー
- 食物
- こわいもの
ネパール通信1
- カトマンズ(1)
- フルチョウキ
- カトマンズ(2)
- チュリア・マハバラトの旅
- ゴサインクンデの旅
- ボダイジュのほこら
- カトマンズ(3)
- ロルカニの旅
- カトマンズ(4)
- チリメ、ランタンの旅
- チャンドラギリの旅
ビル・ニガントゥに見られる米の記事
ネパールの滝の数
ネパール通信2
- 自動車事故のはなし
- 創立記念パーティー
- カリンチョークの旅(1)
- インドラジャトラ
- カリンチョークの旅(2)
- チュリアの旅
ヒマラヤ植物調査の今昔
日本・ネパール協同植物調査史 1960-1980 [英文]
『冒険家族ヒマラヤを行く』訳者あとがき
パプア・ニューギニアの話
- 交通
- 食べ物
- 人々
- コトバ
- 古戦場
吉川英治文化賞受賞のことば
第二部 植物の観かた・残しかた
野外観察会のこと
日本植物の分布型に関する研究(2) ヒメマイヅルソウの分布型と変異
オゼコウホネの種子散布
ヤマモモの仁
クヌギの落枝
スベリヒユは対生
猪突猛進するチガヤの地下茎
ササの葉鞘
ケヤキの落葉現象はあったか
笹舟は沈む!
ミャンマーのドクウツギ属植物Coriaria terminalis Hemsley とその西限産地
ブータンのウルシ
植物の動きを見せる
尾瀬ケ原の池塘データベースによるヒツジグサとオゼコウホネの16年間の分布消長
群落の突然の交代
ツタの植物画
ツタの「雨」
国立科学博物館のサクラソウ生態展示
有毒植物を食べる
ミズバショウの果実の味
マムシグサのイモの「味」
ヌルデとネムノキは仲良し?
ビルマの植物学界の一端
部活動と自然観察会
普通な植物を記録しよう
ヒレハリソウ(ムラサキ科)の葉序
アイスマンの弓矢
ツュンベリーと日本のアマチュア植物学 [英文]
誰にでも利用できる標本のために
標本にはラベルを入れよう
標本ラベル論議へのながーいコメント
- 仮ラベルに関して
- 本ラベルに関して
- データベースに関して
ヒートシールによる標本貼付
おしば標本の新しい貼付法
おしば標本貼り付け用ヒートシールテープの自作法
移動式おしば標本棚の得失
- 改装工事前後の問題
- 運用上の問題
おし葉製作法の改良
携帯用植物乾燥機について
- 冨樫板
- 加圧法
- 加熱法
- 標本製作中の注意と標本の出来具合
- 研究室での使用法
教具教材としての植物パウチカード
生植物のラミネート標本
日本植物分類学文献目録・索引のデータ仕様と検索項目 [英文]
シンポジウム「標本データベースの将来」の感想
- Herbariumの体制
- 大学と博物館の違い
- どうやるか
- データベースを作ったあと
- 画像データベース
第三部 ナマエ・データ・ヒト
吉村衛氏による科の和名の新提案
命名規約とオフセット印刷
デチンムル科
「野草」に現れた植物の新名
新和名提示のいろいろなかたち
「ナマエ」を考える
モノの見え方について
東京消失
地名データベースの活用
- 住吉小学校の「住吉」研究
- 住吉小学校はいくつあるか
- 住吉神社はどのくらいあるか
- 住吉という地名はどうだろう
- IT化時代の学習
新日本地名索引の内幕
新日本地名索引のはなし
- どんなものか
- どうやって作ったか
- 索引のスタイル
- よみの問題
- 分布地図
- 「鐙」の分布
- JIS漢字表の問題
学術用語集植物学編(増訂版)の分類学用語改善のための資料
- 形を表す用語
- 花を表す用語
データベース仕様と植物学・動物学・農学に共通な植物用語
- データベース仕様
- データベース作成の方法
- 調整を要する用語の方針と方法
保育社・原色日本植物図鑑の観察
Index Kewensis 展開版前文
ネパールの本草書ビル・ニガントゥについて
岩槻邦男氏にエジンバラ公賞
英語教科書に載った西岡京治氏
大村敏朗氏の貢献
原寛博士への弔辞・追悼文
- 弔辞
- はじめてのヒマラヤ
若き日の原寛博士の日記
津山尚博士
「訓導」原襄さんの思い出
里見信生さんの思い出
里木村陽二郎先生
山崎敬さんの思い出
第四部 書を評す
地図・地名
- コンサイス地名辞典日本編
- 現代日本地名よみかた大辞典 1-6巻
- 知っておきたい災害と植物地名
- 日本湿地目録
- 日本山名総覧
- FD日本山名総覧「全国版」
- 数値地図 25.000(地名・公共施設)全国CD-ROM版
学名・用語など
- 植物学ラテン語辞典
- 国際植物命名規約1988
- 植物学名詞
- 菌学用語集
- 植物学名大辞典
- 植物の名前のつけかた植物学入門
- 日本苗字大辞典
- 図説植物用語辞典
- 国際栽培植物命名規約第7版
フィールドワーク
- 清瀬の自然フィールドガイド春
- 東京西郊野外植物の観察
- GPS全日本ロードマップ
- ヨコハマ植物散歩
- 東京樹木めぐり
- 巨樹・巨木
- ぐるっと日本列島野の花の旅
- 続巨樹・巨木
- 地べたで再発見「東京」の凸凹地図
- 東京大学本郷キャンパス案内
- 雷竜の花園
- 秘境・崑崙を行く
- 中国秘境に咲く花
- 青いケシの咲くところⅡ
- シルクロードに生きる植物たち
- ヒマラヤを越えた花々
- 幻の植物を追って
- ロンドンの小さな博物館
- ヒマラヤに花を追う
- ヒマラヤの青いケシ
人
- 白井光太郎著作集
- 進野久五郎植物コレクション
- 来し方の記8
- 横内齋著作集2
- 李永魯文集
- MAKINO80『植物同好会』八十年の歩み
- しだとこけ 服部新佐先生追悼記念号
- 小泉秀雄植物図集
- 籾山泰一先生論文集
- 私の研究履歴書-昭和植物学60年を歩む- [林孝三]
- 命あるかぎり-花と樹と人と-見明長門追悼集
- 中尾佐助文献・資料目録
- 牧野晩成
- 沼田真・著作総目録
- 牧野富太郎とマキシモヴィッチ
- 牧野富太郎著・植物一家言
- 誰がスーリエを殺したか1
- 展望河口慧海論
- 「イチョウ精子発見」の検証
- 牧野富太郎植物採集行動録
- 大雪山の父・小泉秀雄
- 大場秀章著作選Ⅰ
- 大場秀章著作選Ⅱ
- 小原敬先生著作集
- 植物文化人物事典
- 清末忠人研究集録
- 自然と教育を語る
文化
- 現代文明ふたつの源流
- 栽培植物の起源と伝播
- 江戸時代中期における諸藩の農作物
- 日本の植物園
- アジアの花食文化
- いのちある野の花
- 江戸参府随行記
- ボタニカルモンキー
- 菌類認識史資料
- 植物学と植物画
- 黒船が持ち帰った植物たち
- 日本植物研究の歴史
- 植物園の話
- バラの誕生
- 絵で見る伝統園芸植物と文化
- 江戸の植物学
- 現代いけばな花材事典
- 花の男シーボルト
- サラダ野菜の植物史
- すしネタの自然史
- シーボルト日本植物誌 文庫版
地域・フロラ
- 環境アセスメントのための北海道高等植物目録Ⅳ
- 宮城県植物目録 2000
- 秋田県植物分布図
- 秋田県植物分布図第2版
- 茨城県植物誌
- とちぎの植物Ⅰ,Ⅱ
- 日光杉並木街道の植物
- 渡良瀬川支流山塊の高等植物 類似植物の見分け方ハンドブック
- 渡良瀬川支流山塊の高等植物
- 群馬の里山の植物
- 群馬県タケ・ササ類植物誌
- 群馬県植物誌改訂版
- 館林市の植物
- 尾瀬を守る
- 1998年版埼玉県植物誌
- さいたまレッドデータブック
- 千葉県植物誌
- 千葉県の自然誌
- 富里の植物
- 続江東区の野草
- 小笠原植物図譜
- 神奈川県植物誌分布図集
- 横浜の植物
- Yato横浜 新治の自然誌
- 箱根の樹木
- 新潟県植物分布図集第6集
- 新潟県植物分布図集第7集
- 新潟県植物分布図集第10集
- 新潟県植物分布図集第1-10集登載植物および索引
- 石川県樹木分布図集
- 加賀能登の植物図譜
- 金沢大学薬学部付属薬用植物園所蔵標本目録 白山の植物
- 信州のシダ
- 長野県の植生
- 長野県植物研究会誌第20号
- 長野県版レッドデータブック維管束植物編
- 長野県植物ハンドブック
- 伊部谷の植物
- 植物への挽歌
- しなの帰化植物図鑑
- 37人が語るわが心の軽井沢1911-1945
- 近畿地方の保護上重要な植物
- 改訂・近畿地方の保護上重要な植物
- 近畿地方植物誌
- 高山市の植物
- 改定三重県帰化植物誌
- 兵庫県の樹木誌
- ひょうごの野生植物
- 播磨の植物
- 平成元年度箕面川ダム自然回復工事の効果調査報告
- 六甲山地の植物誌
- 淡路島の植物誌
- 奈良公園の植物
- 岡山県スゲ科植物図譜
- 広島県文化百選 花と木編
- 広島市の動植物
- 山口県の植物方言集覧
- 山口県の巨樹資料
- 徳島県野草図鑑〈下〉
- えひめの木の名の由来
- 福岡県植物目録 第2巻
- 熊本の野草〈上〉〈下〉
- 熊本の木と花
- 鹿児島県の植物図鑑
- 改訂鹿児島県植物目録
- 沖縄植物野外活用図鑑全6巻
- 沖縄県の絶滅のおそれのある野生生物
- 琉球列島維管束植物集覧
- 孤島の生物たち-ガラバゴスと小笠原
- ブラジル産薬用植物事典
- キナバル山の植物
- 韓国産松柏類
- 韓国植物検索便覚
- 韓国植物分類学史概説
- 中国人民共和国植被図
- 中国天山の植物
- 雲南の植物
- 雲南の植物
- 東北葯用植物
- ヒマラヤの自然誌
- ヒマラヤ植物大図鑑
- ネパール研究ガイト
- スイスアルプスの植物
調べる
<環境>
- 屋久島原生自然環境保全地域調査報告書
- 昭和63年度レアメタル賦存状況調査報告書
- 帰化植物のはなし
- レッドデータプランツ
- 植物からの警告・生物多様性の自然史
- エコロジーガイド・ウェットランドの自然
- 植物群落レッドデータブック
- 日本森林紀行
- 温暖化に追われる生き物たち
- 水生シダは生きる
- 侵略とかく乱のはてに
- 各都道府県別の植物自然史研究の現状
- 日本の絶滅危惧植物図譜
- 絶滅危惧植物図鑑レッドデータプランツ
<種類>
- 新しい植物検索法 離弁花類編
- 日本タケ科植物総目録
- 新しい植物検索法 合弁花類篇
- 北日本産樹木図集
- 動植物目録
- 日本件名図書目録⑨ 動・植物関係
- 山野草植物図鑑
- 植物目録
- 日本の高山植物
- 世界の針葉樹
- 検索入門樹木
- 葉による野生植物の検索図鑑
- 英語表現べからず辞典
- 日本イネ科植物図譜
- 改訂増補 牧野日本植物図鑑
- 日本の自生蘭
- 北本州産高等植物チェックリスト
- 日本水草図鑑
- 日本草本植物根系図説
- 日本のスミレ
- 日本で育つ熱帯花木植栽事典
- 植物の系統
- 日本タケ科植物図譜
- 日本の野生植物 コケ
- 日本花名鑑1
- 樹に咲く花 合弁花 単子葉 裸子植物
- 高山に咲く花
- 日本花名鑑2
- 日本の帰化植物
- ツバキとサクラ
- カエデの本
- 新日本の桜
- 日本のスゲ
- 日本の野菊
- 日本花名鑑4
- 日本海草図譜
<観察>
- 花と昆虫
- 樹木
- 平行植物
- 描く・植物スケッチ
- 植物観察入門
- 野草 1-15巻+別巻
- 折々草
- みどりの香り 青葉アルコールの秘密
- 誰がために花は咲く
- 草花の観察「すみれ」
- 人に踏まれて強くなる雑草学入門
- 花生態学入門 花にひめられたなぞを解くために
- ブナ林の自然誌
- 原寸イラストによる落葉図鑑
- 人里の自然
- 虫こぶ入門
- 森のシナリオ
- シダ植物の自然史
- 花と昆虫がつくる自然
- 文明が育てた植物たち
- 雑草の自然史
- セコイアの森
- 植物の私生活
- ツリーウォッチング入門
- 根も葉もある植物談義
- 花の観察学入門
- 野の花山の花
- ため池の自然
- 花と昆虫 不思議なだましあい発見記
- 道端植物園
- タンポポとカワラノギク
- どんぐりの図鑑
- 植物のかたち
- せいたかだいおう-ヒマラヤのふしぎなはな
- コケ類研究の手引き
- 虫こぶハンドブック
- 虫こぶ入門
- ひっつきむしの図鑑
- 樹木見分けのポイント図鑑, 野草見分けのポイント図鑑
- 植物生活史図鑑Ⅰ, Ⅱ
- 絵でわかる植物の世界
- 「野草」総索引
- 「野草」植物名総索引 第1巻~第70巻
- 標本をつくろう
- わたしの研究 どんぐりの穴のひみつ
- どんぐり見聞録
- ほんとの植物観察, 続ほんとの植物観察
- キヨスミウツボの生活
- 発見!植物の力1~10
- 帰化植物を楽しむ
- 花からたねへ
- 植物と菌類30講
<標本>
- 自然史関係大学所蔵標本総覧
- 国立科学博物館蔵書目録和文編
- デジタルミューゼアム
- 牧野植物図鑑の謎
- Systema Naturae 標本は語る
- 牧野標本館所蔵のシーボルトコレクション
- 牧野標本館所蔵シーボルトコレクションデータペース CD-ROM版
洋書
- Manual for Tropical Herbaria, Regnum Vegetabile
- The Asiatic Species of Osbeckia
- Biological Identification with Computers
- A Geographical Atlas of World Weeds
- Neo-lineamenta Florae Manshuricae
- Atlas of Seeds Part 3
- Alpine Flora of Kashmir Himalaya
- Botticelli's Primavera
- Index to Specimens Filed in the New York Botanical Garden Vascular Plant Type Herbarium
- Elsvier's Dictionary of Trees and Shrubs
- Medicinal Plants in Tropical West Africa
- Fodder Trees and Tree Fodder in Nepal
- Nepal Himalaya, Geo-ecological Perspectives
- Leaf Venation Patterns
- Development amid Environmental and Cultural Preservation
- The Lilies of China
- Kew Index for 1986
- Catalog of Moss Specimens from Antarctica and Adjacent Regions
- The mountains of Central Asia
- Trees of the southeastern United States
- A New Key to Wild Flowers
- Flora of upper Lidder Valleys of Kashmir Himalaya
- Systematic Studies in Polygonaceae of Kashmir Himalaya Vol.1
- Flowers of the Himalaya, a Supplement
- Plant Taxonomy and Biosystematics, 2nd ed.
- Plant Evolutionary Biology
- Lilacs, the Genus Syringa
- Ornamental Rainforest Plants in Australia
- Forest Plants of Nepal
- Plant Taxonomy, the Systematic Evaluation of Comparative Data
- Woody plants
- The Evolutionary Ecology of Plants
- The Forest Carpet
- Cryptogams of the Himalayas Vol.2., Central and Eastern Nepal.
- Pattern Formation in Plant Tissues
- Plant Genetic Resources of Ethiopia
- Leaf Architecture of the Woody Dicotyledons from Tropical and Subtropical China
- Palaeoethnobotany
- A Bibliograpby of the Plant Science of Nepal
- C.P. Thunberg's Drawings of Japanese Plants
- Temperate Bamboo Quarterly 2
- Index of Geogrphical Names of Nepal
- A Revision of the Genus Rhododendron in Japan, Taiwan, Korea and Sakhalin
- A Bibliography of the Plant Science of Nepal. Sipplement 1
- The Iceman and His Environment, Palaeobotanical Results
- The Cambridge Illustrated Glossary of Botanical Terms
- Handbook of Ayurvedic Medicinal Plants
- Ethnobotany of Nepal
- Himalayan Botany in the Twentieth and Twenty-first Centuries
- Meristematic Tissues in Plant Growth and Development
- Proceedings of Nepal-Japan Joint Symposium on Conservation and Utilization of Himalayan Medicinal Resources
- The Orchids of Bhutan
- Beautiful Orchids of Nepal
書籍詳細
-
元・国立科学博物館 金井弘夫 著
菊判 / 上製 / 904頁/ 定価15,715円(本体14,286+税)/ ISBN978-4-900358-62-1
〔花の美術館〕カテゴリリンク
- 第20回 『熱帯植物巡礼』
- 第19回 小山鐡夫追悼記念号『黒船が持ち帰った植物たち』より
- 第18回 小山鐡夫追悼記念号『植物園の話』より
- 第17回 『MAKINO 80』東京植物同好会・牧野植物同好会八十周年記念誌
- 第16回 ハマナスの語源を探る
- 第15回 金井弘夫追悼記念号『金井弘夫著作集 植物・探検・書評』より
- 第14回 『花のある風景』
- 第13回 坂嵜信之追悼記念号『日本で育つ・熱帯花木植栽事典』より
- 第12回 楽しい花観察108選『不思議な花々のなりたち』
- 第11回 川島榮生の《ヤマアジサイの世界》
- 第10回 渡辺健二『日本産ギボウシの世界』
- 第9回 『ユリノキという木』─ 魅せられた樹の博物誌
- 第8回 『北米インディアン悲詩』/ エドワード・カーティス写真集
- 第7回 江戸時代の花たち 書物に見る江戸時代の園芸文化
- 第6回 わが国初のボタニカルアーティスト 五百城文哉(いおきぶんさい)の世界
- 第5回 『ビル・ニガントゥ』 19世紀末ネパール秘蔵の本草図譜
- 第4回 植物画家 石川美枝子の作品
- 第3回 サイエンティフィック・イラストレーター 木村政司の作品
- 第2回 植物画家 中島睦子の作品
- 第1回 『PLANTAE ASIATICAE RARIORES』