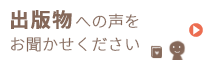- ホーム
- ネイチャーコンテンツ
- Aboc Museum
- 花の美術館
- 第10回 渡辺健二『日本産ギボウシの世界』
第10回 渡辺健二『日本産ギボウシの世界』
【解説】
葛田一雄(随筆家・作家)
渡辺健二氏を御殿場にたずねて
紫に魅せられた男がいる。男にとって富士の裾野は紫野である。10億株のギボウシが富士の裾野を紫に染めあげていく。その男、渡辺健二が大いなるキャンパスに描く、壮大な自然画の世界である。
払暁の富士は静寂に包まれて、紫煙に揺らめいていた。渡辺が逃げるようにして故郷の御殿場に戻ってきた翌朝、昭和22年初秋のことである。
渡辺は、中国大陸に男一生の夢を残し、捕虜の苦い体験を胸に収めて東京の土を踏んだ。渡辺は東京で仕事がしたかった。大陸でやり残した仕事を東京でしなければならないと思ったのである。ところが、身体がそれを許さなかった。焼け野原となった東京で病に侵されたのである。
前夜、渡辺は、寝ようにも寝つかれなかった。あの韓国人が私を救ってくれた。戦時中、俺は中国人も韓国人も決して虐待しなかった。しかし、それは俺の論理だ。終戦を機に立場が逆転し、日本人であれば、誰彼となく攻撃の対象にされた。
でも、彼の俺に接する態度は変わらなかった。それどころか、手持ちの金をはたいて俺を収容所から貰い受けてくれた。人間として対等な付き合いをしてきた気持ちが通じたからなのか。
「渡辺さん、大丈夫ね、富士山があるよ」、引き上げ船に乗り込む時のあの男の言葉が渡辺の頭の中を駆け巡っていた。
初秋の明け方に御殿場から見る富士は秀麗である。沈むような闇が緩やかに、しかし確実に白み始めると、富士は漆黒の稜線を描き出していく。やがて、山全体が濃藍に変わり、そして、そぼふるように紫に煙る。日本は生きている。俺は生きている。富士山に対峠したときの渡辺の心の叫びだった。紫に生の悦びとやさしさを見たのである。渡辺の脳裏に藤が、紫陽花が、葛が、岩煙草が、桔梗が、紫の木花や紫の草花が次から次に浮かんでいた。渡辺の紫の、紫の花への巡礼の始まりである。
富士に息づく木々や草花そして小動物と渡辺との出会いは、生きとし生けるもの同士の生への確認なのかも知れない。春浅き日、渡辺に語りかけてきた木立があった。芽吹きを待つ富士桜だった。渡辺は、一帯の森の中で一本の富士桜と語らったのである。富士桜を庭に移植しよう。「家に庭がなければ、家庭は出来ない」、父親の渡辺に対する教えである。敗戦ですさみきった日本人に勁さと暖かさを与えられるのは富士山しかない。富士山の香りを体現している桜に渡辺はそうした願いを込めた。来る日も来る日も、富士桜の園芸種へ開発の日々が続く。一心に一つのことに心を砕く者を神はもはや見放しはしなかった。小振りの富士桜は日本の庭に良く似合った。
渡辺の人格形成に深く係わった人物のひとりが尋常小学校の国語の教師だった。6年生の時にその国語の教師に触発されたのか、6年生の時に渡辺は御殿場で発刊されていた児童文芸誌に投稿をしている。国語の教師に纏わる話を主題としたその作文は、特席を得た。「先生が坂道を下りていく。女の先生と一緒に坂を歩いている。先生と女の先生の肩と肩が少し触れる。少し触れて、少し離れる」。その女教師は、楚々とした感じの人でした。渡辺の述懐である。
富士桜の改良が一段落した年の、昭和50年の暑い夏が去ろうとする日、御殿場に秋の風が抜けた。翌朝、渡辺は、自衛隊の戦車によって地肌の露になった富士山の中腹で、鮮やかな紫に朝露を宿す桔梗に目を止めた。富士桜で園芸家としての地歩を固めた渡辺が確固たる地位をしめるに到る桔梗との出会いであった。紫の艶やかさが、渡辺の育てた桔梗として首都圏で評判を取るにいたるのである。桔梗の紫と凜とした花姿に楚々とした女教師の面影を見た渡辺が、ギボウシに仏の心を見出したのは、彼女がその後、自ら命を断ったことと関係があるかも知れない。ギボウシは、五重の塔の九輪の上部に位置するギボウシに花の形が似ているから名付けられたという。
ギボウシは、欧米で、HOSTA(ホスタ)と言われている。HOSPITALITY(ホスピタリティ)と言う言葉がある。ねんごろなお持てなし、という意味であり、ホテルやホスピタル(病院)は、このホスピタリティを抜きにしては語れない。ホスピタリティの違った言い回しが旧約聖書にある。HOME AWAY FROM HOMEである。旅人を、さながら我が家にいるようにくつろがせて差し上げなさい、ということである。園芸種として庭に植えられて、広く愛好されている植物の名前がHOSTAというのは、むしろ当然のことなのだろう。あるいは、渡辺が仏の心を感じたごとくに、欧米人の名付け親も神が宿っているような啓示を受けて、HOSTAと名付けたのだろうか。
渡辺は、ギボウシと時折り対話をするそうだ。ギボウシの花穂に父や母や兄の姿を見出すという。渡辺が中学1年の時に世を去った父、その後の家計を女手で支えてきた母、生計の足しにするために少年の時から働いていた兄、母も兄もとうにみまかっている。ギボウシは、家族を結ぶ絆なのかもわからない。家族の絆ならば、園芸種として庭に移植するのも道理だ。しかし、道理であっても、自然界の法則には及ばないようだ。
渡辺は、多くのギボウシを世に出してきたのだけれども、いまだ原種を凌ぐことが出来ないという。欧米で盛んに移植されているHOSTAにしても同様であるという。ギボウシは日本が原種である。ところが、日本の野生種は、制約された野山にしか成育できなくなってきたために、人はギボウシを欧米産とも思うようになってきたのである。渡辺が、日本の野生種を保護し育成しようという念に囚われたのは、日本原産の草花が死に絶えていくという実態に直面したからではなかったか。日本古来の花として根づいてきた紫の花を絶やしてはならないという熱い想いが、桔梗の花の哀惜を引き継ぐ草花として、渡辺の心を虜にしたからではないか。
日本を代表する野にある植物研究者、渡辺健二は新種改良の園芸家として優れているだけに止まらず自然回帰を基調とした自然種の保護者として名高い。ここに、渡辺の秀なるすごさがある。今、富士の原野にギボウシが群生している。渡辺が渡辺の子息ともども確認した富士の原野に成育するギボウシは10億株を優に超える。
渡辺の俳号は紫峰である。若き日に、紫は高貴の色、峰は秀峰富士の山、から名付けたそうだ。ギボウシを小さい富士に見立てた命名といわれたとしても違和感がない。淡い紫色の花の蕾を峰に譬えるようにという、神の思し召し、というのは穿ちすぎだろうか。
「私は人との戦いに破れたような気もする。人生に負けたのかもわからない。誇りといえばなんだが、齢70余年の大半を植物と共に過ごしてきた。だからこそ、神は、私を僕(しもべ)にお加えなさった。神はギボウシの番人の役目を私に与えて下さったのではないか。」
朝霧にもやる富士の裾野に紫花のギボウシが群れる原野をかくしゃくとした足取りで歩を進める渡辺の声が柔らかい風に乗って私の耳元に届いた。
1990.July 15
葛田一雄
渡辺健二 プロフィール
(※準備中)
渡辺健二氏よりの書簡
コンテンツ一覧▼ 目次(青字)をクリックすると、各文をご覧いただけます
第一部
Ⅰ はじめに 渡辺健二の世界 文:葛田一雄
Ⅱ 富士山の自生の群落から 写真:榊原速雄
- オオバギボウシの大群落
- オオバとコバの自然雑種
- イワギボウシ 樹幹につく、地上
Ⅲ 富士山の自生の状況と特徴 文:渡辺健二
Ⅳ ギボウシの大群生を見た感動 文:毛藤圀彦
- 自然の中の変異の帯化品なども
Ⅴ 岩壁のイワギボウシ 写真:榊原速雄
第二部
Ⅰ 日本産ギボウシの名称と園芸的分類
- A. ギボウシの名称
- B. ギボウシの分布
- C. 園芸的分類
Ⅱ 園芸品種とその形態
Ⅲ 園芸品種紹介
- A. 従来からの品種
- B. 自生種の変異
- C. 改良品種
- D. 育種こぼればなし-亜細亜の平和を願う夢-
Ⅳ ギボウシ文化史
- A. 古文献
- B. 近代(渡辺健二 ギボウシ歴)
〔花の美術館〕カテゴリリンク
- 第19回 小山鐡夫追悼記念号『黒船が持ち帰った植物たち』より
- 第18回 小山鐡夫追悼記念号『植物園の話』より
- 第17回 『MAKINO 80』東京植物同好会・牧野植物同好会八十周年記念誌
- 第16回 ハマナスの語源を探る
- 第15回 金井弘夫追悼記念号『金井弘夫著作集 植物・探検・書評』より
- 第14回 『花のある風景』
- 第13回 坂嵜信之追悼記念号『日本で育つ・熱帯花木植栽事典』より
- 第12回 楽しい花観察108選『不思議な花々のなりたち』
- 第11回 川島榮生の《ヤマアジサイの世界》
- 第10回 渡辺健二『日本産ギボウシの世界』
- 第9回 『ユリノキという木』─ 魅せられた樹の博物誌
- 第8回 『北米インディアン悲詩』/ エドワード・カーティス写真集
- 第7回 江戸時代の花たち 書物に見る江戸時代の園芸文化
- 第6回 わが国初のボタニカルアーティスト 五百城文哉(いおきぶんさい)の世界
- 第5回 『ビル・ニガントゥ』 19世紀末ネパール秘蔵の本草図譜
- 第4回 植物画家 石川美枝子の作品
- 第3回 サイエンティフィック・イラストレーター 木村政司の作品
- 第2回 植物画家 中島睦子の作品
- 第1回 『PLANTAE ASIATICAE RARIORES』