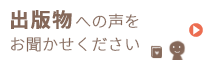- ホーム
- ネイチャーコンテンツ
- Aboc Museum
- 花の美術館
- 第9回 『ユリノキという木』─ 魅せられた樹の博物誌
- 第三章 アパラチア山麓のユリノキ
第三章 アパラチア山麓のユリノキ
詩は私のような愚か者がつくる
しかし樹は ただ神のみがつくりうる――。
ユリノキの古里は北米大陸のアパラチア山麓にあって
詩人ジョイス・キルマーの愛した森だ。
開拓とユリノキ天然林の結末を
一篇のファンタジー「チューリップの木の花かご」からはじめる。
一、チューリップの木の花かご
今から一二〇年ばかり前のことです。
アメリカのペンシルベニア州の東海岸から五〇キロメートルほど入ったところに、ランカスターという小さな町がありました。
この町のはずれに、ことし一〇歳になるリッキーという元気な子供がいました。リッキーのお父さんの名はロバート、お母さんの名はテニーといいました。
リッキーの家には、もう一人、昔から働き手として雇われているカールじいやがいます。
リッキーのお父さんは養蜂家だったので、蜜蜂たちが住む巣箱を家のまわりにいっぱいおいていました。
春がやってくると、雪の下で冬を越したナタネの黄色い花が畑をおおい、町の人たちの家の花壇にもいろいろな美しい花が咲きみだれました。また、近くの森や林のなかの木々もたくさんの花を咲かせます。そして、リッキーの家の蜜蜂たちはいっせいに飛び立っていって、おいしい蜜を巣箱に運んできました。
しかし、ランカスターは一年ごとに町に住む人がふえて、森や畑は、住宅になり、工場がたち、黒い煙を吐きだす煙突が立ちならぶようになりました。町が大きくなるにつれて、リッキーの家の蜜蜂が集めてくる蜜は、毎年のように少なくなるいっぽうでした。
ロバートとテニーは心配顔で話し合いました。
「こんなことになってきては、もうこの町で蜂を飼いつづける仕事ができなくなるなあ」そうロバートが言うと、テニーも悲しげに、
「といっても、亡くなったお父さんが残した蜜蜂を、ここで捨てるわけにはいきません。どうしたらいいのかしら………」ロバートは妻に向かってきっぱりと言いました。
「もちろん、この仕事をやめるわけにはいかないんだよ。蜜蜂たちが思いきり慟いてくれるような土地を探そう、テニー」花の多い四月と五月が過ぎました。蜜蜂たちが集めた花蜜は、去年にくらべて半分にも達しませんでした。
カールが巣箱の手入れをしながら、ロバートに話しかけました。
「ことしの花もおわったというのに、このしまつでは、ここはもう蜜蜂の住む場所じゃありませんな。こうなったら、巣箱をここより高い土地の森のなかに移して、遅れて咲く花の蜜を集めること、これしかない……、そう思っているんですがね」
「そうだ。私もそう考えていたんだ」このときです。山のように荷物を積んだ二頭立ての馬車が近づいてきました。
「やあ、ロバート、カール、いつも元気で、いいなあ」この老人は毛皮商人のデックでした。
ここランカスターの町から、さらに七〇キロメートルも奥によこたわるアパラチア山脈には、野生の動物を追う狩人たちがいます。デックは、その狩人たちから買い取った野牛や鹿などの毛皮を売るために、フィラデルフィアにある毛皮市場へむかう途中でした。
デックは、ロバートの亡くなった父親の昔友達でしたから、そのころの思い出話を聞くことをロバートもカールも楽しみにしていました。その夜もデックを囲んで思い出話がはずんでいました。
そのうちロバートがデックに、ランカスターが養蜂家の住む場所でなくなったことや、蜜の多いところを探して移ろうと思っていることなどを相談しはじめました。
すると、デックがどこか遠くを見ているような目をして語りはじめました。
「二日前だったよ。長々とつづく大きい森の途中で、疲れた馬を休ませていたんだ。……よく晴れていて、とても静かな昼だったな。と、わずかな風が、私のまわりに、とてもよい香りを運んでくる……。それが、あんまりいい匂いだったから、どの木の花の匂いかと探しはじめたんだ……。香りの花を探しあてるのに苦労しなかったね。山道のすぐ近くに、あまり目立たないがチューリップの形をした花をたくさんつけた、大きな木があったんだよ」カールは、いきなり体を乗り出して言いました。
「それはチューリップの木だ」
「そこは、オハイオ川の本流にサンデー川が合流するあたりでな。付近一帯はなだらかな、広い森におおわれていて、その近くには狩人たちの仮小屋があるんだ……。そこからランカスターに向かって馬の足で二時間くらいの間には、山道の両側にも、その奥のほうにも、同じ木があっちにもこっちにもあるんだな。それはいま、カールが言った、チューリップの木なんだろう。……というのは、ほかのどんな木よりも、この木は高く伸びているから、一目でそれとわかるんだよ」いつか洗いものをすませたテニーもその話を聞いていました。
次の日の朝早く、デックは別れをつげ、フィラデルフィアに向かいました。
それを見送ったロバートは、急いで旅の支度をはじめました。
「いまからサンデー川に出かける。四日もしたら帰ってくるから、蜜蜂の世話はテニーとカールに頼んだよ……。さあ、リッキー、私のそばに乗るんだ」ロバートとリッキーがサンデー川の合流点の近くに着いたのは、翌日のちょうど昼ごろでした。デックの話のとおり、今を盛りと咲きはこっているチューリップの木の花が、あたりいっぱいによい香りをただよわせていました。すこし奥のほうに、狩人たちの丸太小屋がポツンと建っているのが見えました。
ここに積んできた巣箱をおろして、出入口を次々に開けました。蜜蜂たちは、いっせいにチューリップの木の花に向かって飛び立っていきました。
あとは、甘い蜜をたくさん集めて、花から帰ってくる蜜蜂たちを待つだけです。ロバートは、蜜蜂たちが巣箱に帰ってくる様子をよく見るようにとリッキーに言いつけて、奥の丸太小屋に出かけていきました。
しばらくして、丸太小屋からロバートの帰ってくる姿が見えると、リッキーは大声で叫びながら駆けよりました。
「お父さん! 早くこっちへきて、見て! 蜜蜂たちがさっぱり帰ってこないの……」驚いてロバートが巣箱の中をのぞくと、リッキーの言うとおり、巣箱にはいつもの半分しか蜂がもどっていません。
「夕暮れまでには、みんな帰ってくるだろうよ。それまで待つことにしよう……」
と、リッキーは何を考えたのか、いきなり走り出しました。
「何をするんだ! どこに行く、リッキー!」リッキーは走りながら大声で叫びました。
「蜜蜂を探しに行くんだ!」リッキーがめざしたチューリップの木は、大人が二人で手をつないでも抱えきれないような大木でしたが、幸いなことに、リッキーの太ももほどもある太いつる性の植物が、根元から巻き上っていました。
リッキーは、いちばん下の枝の分かれめまで太いつるの幹を登りつめると、こんどは枝をまたいで、小枝のほうに進んでいきます。
「リッキー、あまり先のほうまで行かずに戻るんだぞ!」すると、葉かげからリッキーの叫ぶ声が聞こえました。
「お父さん、蜜蜂たちが、花の中でおぼれているんだ。花の蜜が、体や羽根にベタベタとくっついて、花の底からはい出せないでいるんだ!………」太陽が落ちて、あたりはだんだん暗くなりはじめました。ロバートとリッキーは、巣箱のふたを開けて中の様子を調べはじめました。巣箱にもどっている蜜蜂は多いものでも半数くらいでした。二人はがっかりしましたが、それでも最後の一箱まで調べてみることにしました。
あと数箱で終ろうとしたときです。「これも、だめか」と思いながら箱のふたをとるなり、二人はびっくりしました。
その箱の蜜蜂たちは、全部巣に戻っていて、元気に体を寄せ合っているのでした。
すぐに、ロバートは巣板の一枚を取り出して調べました。ランカスターで蜂たちが集める蜜にくらべて、はるかにすばらしい花蜜が巣板にいっぱい詰まっていました。
ロバートは、傍らのリッキーの手を固く握りながら、
「よし、わかった! このあとは、この巣の中の蜜蜂を増やしていけばいいんだ!」
と力強い声で叫びました。
「ここが、これから私らの暮らす場所だ。さっそくテニーとカールを呼びよせて、家を建てる仕事から取りかかろう」やがて、ロバートたちが新しい家づくりをはじめると、近くの狩人たちは、斧や鋸などを用意しておおぜいで手伝いにやってきました。
男たちはさっそく仕事にかかり、森の奥深くに、木を切る音がこだましてひびきはじめました。それから三日目には、木の肌も美しい丸太小屋ができあがりましたので、お祝いをすることになりました。
テニーは、ここでとれたチューリップの木の花蜜を使って、料理の支度にとりかかりました。男たちは、小屋の中に張りめぐらす小旗づくりをはじめました。
リッキーは、何を考えたのか、だれにも知られないように外へ出ました。
しばらくして帰ってきたリッキーは、小枝つきのチューリップの木の花を両手に抱え切れないほど持ってきて、台所にいるテニーを喜ばせました。
やがて、美しく飾りつけた部屋の中央のテーブルには、テニーの手づくり料理がならび、一同は明るい顔で席につきました。
このとき、テニーがロバートに、なにか耳打ちをしました。すると、ロバートは笑顔で立ちあがり、リッキーの手を引いて台所に行きました。
少しの間をおいて、チューリップの木の花をいっぱいに盛った大きい花かごを持ったリッキーがニコニコして入ってきました。皆がいっせいに拍手で迎えました。
花籠がテーブルのまんなかに置かれると、楽しい食事がはじまりました。
二週間ほどたったある日、ロバートはカールと二人で森の中に出かけました。チューリップの木の花がおわったあとが心配だったからです。森には、あまり品質の良くない蜜を出すクリの木の仲間がわずかにあるだけで、奥深く入るほどチューリップの木が多いので安心しました。
なおも進むと、少し樹木がまばらになっている森がつづいていました。このあたりの木と木の間には、これから秋までの季節に次々と花を咲かせる丈の低い木や、つるを出してこれにからむ植物が一面にはびこっていました。さらにうれしいことには、このあと、あとからあとからと咲くさまざまな小さな草花が地面をおおっていたことでした。
二人は喜び勇んで引き返しました。
ロバートは、心配しながら待っていたテニーとカールに森の様子をくわしく話して聞かせ、皆でいっしょに喜び合いました。
ロバートは、チューリップの木の花蜜を集めるのが上手で、病気にも強い蜜蜂の群れづくりの研究に取り組みました。リッキーもカールも一緒になって手伝いました。そして、ロバートたちの蜜蜂とチューリップの木の花蜜とは、いつのまにか人々の評判になって、養蜂家や蜂蜜屋たちが遠くからわざわざ蜂群や蜂蜜を買いにくるようになりました。
毎年、チューリップの木の花が真っ盛りになる六月、ロバート家では丸太小屋が出来上がった日を記念してパーティを開きます。このパーティでは、いつもチューリップの木の花を、大きいかごいっぱいの盛り花にしてテーブルを飾るのでした。
いま、ペンシルベニア州をはじめ、アパラチア山脈をとりまく広大な地域にひろく飼われている蜜蜂たちは、ロバートとリッキーとが一生をかけて改良したものだといわれています。
コンテンツ一覧▼ 目次をクリックすると、各記事をご覧いただけます
第一章 ユリノキという木
一、化石のなかの「ユリノキ」 村井貞允
- ユリノキ属の出現
- わが国におけるユリノキ化石発見の歴史
- 琵琶湖よりも大きかった古雫石湖
- ユリノキ化石の仲間たち
- ユリノキの繁茂した古環境
- ユリノキの仲間のうち、興味ある種類
二、北米産ユリノキのこと 四手井綱英
- 東部森林の代表者ユリノキ
- 外国樹種の導入
- 導入の失敗と成功例
- ユリノキへの期待
三、シナユリノキのこと 毛藤圀彦
- シナユリノキ発見の記録
- リリオデンドロン・キネンセ
- シナユリノキの天然分布
- 樹齢一〇〇〇年の最大樹発見
- ユリノキとシナユリノキの関連
四、ユリノキの名前
- 呼び名いろいろ
- ハンテンボク
- イエローポプラ
- チューリップツリー
- カヌーウッド
- サドルツリー
- カナリーウッド
- バスウッド
- ホワイトウッド
- ユリノキの学名
- リリオデンドロン・ツリピフェラ
第二章 ユリノキのふしぎな形態
一、花
- 原始の花
- 緑色の花冠
- 古代花の形質
二、葉
- 葉先のない珍しい葉形
- 難解な葉の表現
- 発見した小さな突起物
三、生長
- どのくらい大きくなるのか
- 生長迅速
- 容姿端整
四、寿命
- 樹高六〇・四メートルの巨木
- 枝と幹と樹皮
五、ユリノキの薬効と成分 指田豊
- 北米インディアンの薬木
- 抗癌作用のあるユリノキ成分
- 辺材が示す抗菌物質と香りの成分
六、花蜜
- 一花に小匙一杯ほどの
- 蜂を呼ぶ
- 蜜の品がら
第三章 アパラチア山麓のユリノキ
一、チューリップの木の花かご
二、幻のユリノキを訪ねて
- 手当たりしだいの伐採
- 神々の樹との出会い
三、天然林に生きる
- 天然更新できない理由
- 世紀末をむかえたユリノキ
四、ユリノキ天然林の植物相
- 山岳天然林
- 低地天然林
- 丘陵地天然林
- 河床地天然林
- ユリノキの食害
五、伐りつくした材
- 「光沢の白材」と呼ばれて...
- 木材としての価値
- 材の堅さと強度
第四章 ユリノキ・ニッポン物語
一、日本渡来考
- 伊藤圭介説と田中芳男説
- 不発芽に終った第一号
二、長岡苗木について
- 初代の並木たち
- 公園設計の父・長岡安平
- 御苑ユリノキを母樹として
三、小泉苗木について
- ユリノキ二世のルーツ
- 啄木と同期の小泉多三郎
- 造園業のパイオニア藤村「豊香園」
四、横山苗木について
- 造林の先駆者・横山八郎
- 小泉苗木を継いだ横山苗木
五、ロウソクノキの林
- 紺野ツマさんの林
- 半世紀後のみごとな林分
六、新宿御苑のシンボル
- 御苑の来し方
- 寄せ植えした三本
七、上野・銀座のユリノキ
- 牧野富太郎の設計
- この木なんの木
- 銀座のユリノキ
八、受難のユリノキ二題
- 三菱爆破事件の顛末
- 「宮沢賢治の母校並木」の顛末
- 植栽用途と生育状況の把握
第五章 都市と田園のユリノキ
一、植えたい人へのメッセージ
- 「田園の幸福」の花ことば
- 植栽上の七つのポイント
- 北限および南限と適地
- 防火樹としての効果と萌芽力
- 枝折れ
- 冬の小苗管理法
- アメリカシロヒトリ
二、ユリノキの優れた園芸品種
- 樹形変わりと葉の変化
- 新品種への期待
- 現在の園芸品種
三、世界の国のユリノキ事情
- 九カ国の生態学者に聞く
第六章 ユリノキ実験考
一、移植
- 成木移植はむずかしい
二、三年生株と幼苗の移植実験
三、実生苗
- ユリノキ苗木の量産法
- 種子のカーペット
- 樹下採苗
- 四〇パーセントに近い硬実歩合
- 五〇〇メートルも飛ぶ翼果
- 一樹から採れる種子数
書籍詳細
-
毛藤勤治 著 / 四手井綱英・村井貞允・指田 豊・毛藤圀彦 寄稿
四六判 / 並製 / 304頁(カラー24頁) / 定価1,885円(本体1,714+税)/
ISBN4-900358-23-1
〔花の美術館〕カテゴリリンク
- 第19回 小山鐡夫追悼記念号『黒船が持ち帰った植物たち』より
- 第18回 小山鐡夫追悼記念号『植物園の話』より
- 第17回 『MAKINO 80』東京植物同好会・牧野植物同好会八十周年記念誌
- 第16回 ハマナスの語源を探る
- 第15回 金井弘夫追悼記念号『金井弘夫著作集 植物・探検・書評』より
- 第14回 『花のある風景』
- 第13回 坂嵜信之追悼記念号『日本で育つ・熱帯花木植栽事典』より
- 第12回 楽しい花観察108選『不思議な花々のなりたち』
- 第11回 川島榮生の《ヤマアジサイの世界》
- 第10回 渡辺健二『日本産ギボウシの世界』
- 第9回 『ユリノキという木』─ 魅せられた樹の博物誌
- 第8回 『北米インディアン悲詩』/ エドワード・カーティス写真集
- 第7回 江戸時代の花たち 書物に見る江戸時代の園芸文化
- 第6回 わが国初のボタニカルアーティスト 五百城文哉(いおきぶんさい)の世界
- 第5回 『ビル・ニガントゥ』 19世紀末ネパール秘蔵の本草図譜
- 第4回 植物画家 石川美枝子の作品
- 第3回 サイエンティフィック・イラストレーター 木村政司の作品
- 第2回 植物画家 中島睦子の作品
- 第1回 『PLANTAE ASIATICAE RARIORES』