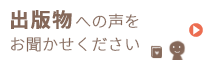- ホーム
- ネイチャーコンテンツ
- Aboc Museum
- 花の美術館
- 第9回 『ユリノキという木』─ 魅せられた樹の博物誌
- 第一章 ユリノキという木
第一章 ユリノキという木
二、北米産ユリノキのこと
○東部森林の代表者ユリノキ
ユリノキは、アメリカ合衆国東部の山地の落葉広葉樹林で、主要林木をなす巨木にまで生長する樹木である。アメリカ東部の山地の温帯林上部の冷温帯には、日本の冷温帯の落葉樹林と同様にブナが主林木として出てくるが、下部の暖温帯では、日本の森林なら照葉樹(常緑広葉樹)林になっていて、落葉広葉樹の出現頻度はきわめてすくなくなっている。この気候帯がアメリカでは全部、落葉広葉樹林に変わっているのである。
この理由は現在のアメリカの気候では説明がむずかしく、むしろ過去の時代の気候の影響が現れているのだといわれている。すなわち今から六〇〇〇年ほど前の後氷河期に、アメリカのこの地帯には著しい乾期が入り、乾燥に耐えられぬ湿潤を好む照葉樹類の高木が絶滅し、低木のシャクナゲ類のような常緑でも乾燥に耐えられるものだけが残ったという。
私が見学旅行にいったグレートスモーキーマウンテンは、バージニア州とテネシー州の境にある国立公園であるが、この周辺の暖温帯林もすべて落葉広葉樹林であって、落葉性のナラ類が多く、スズカケノキやユリノキも多く混生している。なかでもユリノキが大木になり最上層林冠を形成しているので、森林植生の代表者としてユリノキがあげられている。この種の森林には、直径一メートル以上、樹高四〇メートルにもなるユリノキが混生しているのである。
アメリカ合衆国の気候は大西洋側と太平洋側とで極端に変わる。
前者は日本の太平洋岸に近い気候で、どちらかといえば夏雨、冬乾燥型といえる。夏は暖流が海岸沿いに北進して暖雨をもたらすが、冬は寒流が南下して寒気と寡雨の気候を出現する。これに反し、北米太平洋岸の気候はまったく逆で、夏はオホーツク海から寒流が南下して暖流の北上がおさえられ、海霧は発生するが雨はほとんど降らず、冷涼で乾燥した気候になる。冬は暖流が北上して多雨となり、寒流の南下が阻止されるので、温暖多雨な冬気候になるのである。すなわち大西洋側は夏雨、太平洋側は冬雨という相反した気候が出現している。
このことは、アメリカの大西洋岸気候と日本の太平洋岸気候とが近似し、アメリカの太平洋岸気候は、どちらかというとヨーロッパ大陸西部の気候に近似しているということになる。
○外国樹種の導入
近年、とくに第一次世界大戦後、日本の林業では外国樹種の意欲的な導入が企画されて、林木育種の一環として盛んに行われ、研究もされた。その当初には、ほとんど無差別的に優良と思われる針葉樹種が手当たり次第に持ち込まれたといっても過言ではない。
こういう外国樹種の導入は古くから行われていて、今では、いつ、どうして運び込まれたか不明なものすら多い。
例えば、日本に現存する果樹の類の大半は外国産で、日本の原産種から改良されたと考えられるものは、まずないといってよい。しかも、古い時代のものの大部分は中国渡来のもので、新しい時代のものは北米大陸原産のものが多い。
街路樹に広く用いられているスズカケノキは、アジア大陸原産のものと北米大陸原産のものが入り混じり、今ではその雑種が広く用いられているのはその好例であろう。
最近、アメリカ大陸からもたらされたもので、いちおう日本でよい生長を示しているものは、前記のようにその気候の近似した北米大西洋岸産のものである。マツ属で、日本でよい生長を示しているものは、スラッシュマツ( Pinus eliottii )とテーダマツ( Pinus taeda )、それにストローブマツ( Pinus strobus )があるが、すべて大西洋岸の山地産であり、ストローブマツは北海道でも育つが、他の二種は暖温帯に適している。広葉樹でもニセアカシアやタイサンボクなどは、やはり北米大西洋岸産である。
また逆に、日本産や東洋産の植物も、北米大西洋側には種々導入されている。林木としてではないが、庭園樹になっているものが多い。シダレヤナギが各地の庭園にみられる。
これは樹木ではないが、今次大戦後に日本からTVA(テネシー・バレー・オーソリティ)が傾斜地の土壌侵食防止用に大量に導入したクズは、テネシー州を中心として侵食防止には役立ったが、その後各地で大繁殖をつづけ、国道沿いに林内空地に侵入して、今や加害性つる植物としてその処置に困っていることなども面白いエピソードであろう。ちょうど逆に、北米西部の原野から意識的にもたらされたかどうかは不明であるが、わが国でセイタカアワダチソウの旺盛な生育に悩んでいることと軌を一つにしている。
北米太平洋岸産のものは日本ではよく育たない。いちおう公園などでよく育つのはセンペルセコイアのみであろう。この点、ユリノキやプラタナスが日本でよい生長をし得るのは、いちおう類似した気候の所からもたらされたからだと考えてよいようである。
ヨーロッパではまったく逆で、北米太平洋側のものはよく育つ。日本ではどうしても一メートル以上の高さに育たない(これは主にスギと同じ赤枯病にかかるからであるが)といわれるギガントセコイアも、かなりの巨木に育っているし、ダグラスファー(米松)は森林をつくり、天然更新すら容易にしているのである。その他、シトカトウヒなども十分に成林している。
このことからみると、気候の類似性ということが、外国樹種の導入にはまず考えられねばならない条件である。
○導入の失敗と成功例
次に、現在までの世界各地のそういった外国産植物の導入で、うまくいっている例をみると、北半球から南半球へ、南半球から北半球へという、地球の南北両半球間の交流がある。
両半球は赤道を中心として、気流・海流がともにほとんど完全に二分されているため、おのおのの半球の生物には交流なしに独立して進化発達したものが多い。とくにオーストラリア・ニュージーランド・南米のように、現在ほとんど陸上でつながっていない土地では、著しく特異な生物が独立して分化した例が多い。こういった場合、同じような気候帯への南北両半球の植物の交換には、案外うまくいく例がある。
林業では、オーストラリアやニュージーランドヘ導入された数種の北米大西洋岸産のマツ属が旺盛な生育を示し、現在では外国へもマツ材が輸出されているほどで、主要な林業樹種となっている。また、コーヒーやゴムが、両半球間に移動されたり、大陸間に移動されたりして成功しているのも、このような例として考えられてもよかろう。オーストリア原産のアカシアが、わが国の南部でかなりよい生長を示しているのは、その一例といえよう。
しかし、日本は台風国であって、強風のすくない南半球産の樹種は風倒の危険が著しく大で、アカシアも熊本県沿海や天草島のやせ地に大量に植栽されているが、生育はよいものの、台風のたびに風倒したり風折したりしている。
一般に樹木のような高等植物では、このような移動をおこなってたとえ個体の移動に成功しても、森林として山地に大きな群落を造成することは、なかなか成功しないのが普通である。一本の木を育てるということと、ある種の木で林分を造りあげることとは、かならずしも一致しない。
これには色々な理由があるだろうが、今は決め手になるようなはっきりした理由をあげることはできない。しかし、例えば一本の木を植える環境と、林分を造る環境とには、かなりの差がある。平地に植えられる木の場合は、農業同様の耕土に植栽され、林地のように天然の土壌構造がそのまま残されたものではない。また、住居近くに植えられた木は、なんとなく絶えず人手が保育作業として入れられているが、山地の場合は、いくら力を入れて保育されたとしてもその度合は著しく低く、大部分が自然まかせである。
さらに、一本の孤立した木は、枝葉を自由にのばせるし、生長するにつれて、自分の生育に必要な生育面積を自由に獲得できるが、林分となると、互いに他の生育面積を制限する作用が加わり、各個体の自由な枝葉の伸長がおさえられ、各個体に分けられる光合成に必要な陽光量も限定されてしまうので、個体としての生長は常に制限されているといってよい。
そのため、住居地近くの耕地や屋敷内で、ある種の木がよく育ったからといって、林にして大きく育つという保証はないのである。今までも、こういった個体としての生育と、集団あるいは群落としての生育とが混同され、個体の生育がよいから林にすればよいだろうと、単純に信じ込んで失敗した例が著しく多い。
近年では、オーストラリア特産のユーカリが、日本の南西部各地で個体として立派に生育していることから、ただちに林分を造って林業に持ち込もうとして失敗した例がある。
ココノエギリといわれる台湾産のキリも同様で、山地に集団植栽して失敗している。また、ある製紙会社の社長が、自宅の庭で旺盛に生育するアオギリを見て、これを山地に植えれば林分としての生長もきっとよいであろうと考え、山林部に命じて植栽させたという話があるが、どうなったであろうか。
イタリアポプラの改良種の植栽がひところ盛んであったが、この場合もまだ成功した例は聞かない。大きくなっているのは、農地の周辺や山麓地帯に単木的に植えちれたものだけであろう。しかし、これも虫害などに弱く、うまくいった例はきわめて少ないものと思っている。
外来樹種で林分として生育しているのは、今のところニセアカシアぐらいで、他はほとんど失敗しているように思う。
奈良の奥山の原生林保護地域(天然記念物)の、いわゆる春日杉をまじえた照葉樹林は、先年、台風に直撃されて著しい破壊を受けたが、その風害地へ、小鳥の運んだと思われるナンキンハゼが急速に侵入して林分を造りはじめているなどは、外国樹種としてわが国では異例であろう。ナンキンハゼは、奈良市で街路樹として植えられたものである。
ヨーロッパの植生はすこぶる単純であることで有名である。これの原因は、後氷河期以降に、スイスアルプスなどのほぼ東西に走る氷河を残す高山脈地帯が、植物の復帰をさえぎったからで、現気候としては、多くの植物の種が生育し得る土地をふくめた環境があるにかかわらず、その環境を満たすに十分な植物の種類が現存していないともいえる。
極端な例では、イギリスの島々は氷河期が後退して森林が回復し得るようになった時に、北海は開氷してしまっていたという。そのため、例えば針葉樹種は、三種類のヨーロッパアカマツ・イチイ・ネズミサシしか天然には侵入成立していない。アカマツは種子に羽根があり、イチイとネズミサシは鳥に食べられて運ばれる種子をもっているから、開氷した海を越えることができたのである。
ヨーロッパ大陸に天然分布するトウヒやモミのように、種子に羽根がなく、小鳥に食べられると消化してしまうような樹種は、イギリスの諸島へは自然に分布し得なかったのである。
生態学では、おのおのの種が生育し得る場(立地)をニッチェと呼んでいる。ヨーロッパには、なお多くの現在分布していない種類の木や草の入り得るニッチェはあるが、そのニッチェを満たす木や草がないという言い方もできる。そのためニッチェを満たす植物が人為でもたらされると、その植物は容易に林分としても繁殖し得ることになる。
イギリスへもたらされた外来種で、ニッチェに合ったものはよく繁殖している。そのよい例にシャクナゲがある。シャクナゲは、チベット・ネパールなどの乾燥地帯の寒冷地から、イギリスへ多様の種類が導入された。今では全島にわたり森林の下草として旺盛に繁殖し、その防除に手をやいているほどである。
日本列島は、高山以外は氷河におおわれた経験がまったくない。寒冷気候時から温暖気候に移行した場合、植物の移動をさまたげる地形的な障害も、何もなかった。その結果、氷河にさまたげられず、樹種が豊富で、ニッチェを占める種が十分にそろっているわけである。この点からも、日本に外来樹種の導入を考える場合、人為的に破壊されたニッチェ以外へ、庭園とか農地とかへ導入することの他は、著しく困難であるともいえるであろう。それゆえ私は、外国産樹種は市街地や公園、農地への導入を考え、林業樹種としては用いないほうが良いと思っている。
○ユリノキへの期待
ユリノキの場合は、前記のようにおおまかな気候的環境条件は、日本に導入し、よい生育を示す可能性が、個体としては確かにある。しかし、森林として育成するとなると、そのニッチェを占めて天然分布する樹種がわが国には十分に存在しているので、おそらくユリノキの入り得る余地はないと考えてよいのではなかろうか。
里山で、よほど保育が行きとどかないと、在来種との競争に負けてしまうに違いないであろう。あるいは、著しく破壊された箇所には小群状に入り得るかもしれない。
ユリノキは落葉広葉樹であるが、気候的にみると、むしろ暖温帯の照葉樹林帯の樹種であることは、前記の原産地の気候からも分かるであろう。プラタナスも同様だと思われる。
以上で、要するにユリノキは、日本では森林としての植栽の可能性はきわめて少なく、公園などの木としては用いられる可能性が多いということを述べたつもりである。
さらに外来樹種が成功する場合、もう一つの重要な条件として、それを侵害する病菌や昆虫がいないことがよく挙げられている。
前記したオーストラリアで、アメリカ原産の数種のマツの造林に成功しているのも、類似の植物がなく(南半球にはマツ属が分布していない)、原産地から病虫害が侵入していないことが成功のもとであったともいわれる。日本では、すでにマツ属が天然生で広く分布しているので、外国産マツにもシンクイムシと総称される蛾類が侵害していて、抵抗力の強いテーダマツやスラッシュマツでも、あらかた侵されている。また、前記のイギリスのシャクナゲも、やはり同国にこれを侵す病虫害がないので、旺盛な生育を示しているのだといわれている。
ユリノキは、関東地方では広葉樹の根の病害であるムラサキモンパ病に侵され、根が腐るので風害に弱くなり、林業試験場にあつたユリノキの老大木の並木は次々と倒れて、今では一本を残すのみになってしまった。病虫害については、今のところムラサキモンパ病以外には大害を与えるものが知られていないらしい。
私の住む京都には、古くから烏丸通りに街路樹としてユリノキが植栽され、毎春きれいな特徴のある花を咲かせていた。烏丸通りは、京都駅から下鴨へと市街の中央を南北に走る大通りであり、京都市を東西に二分する幹線道路でもあるが、その街路樹がユリノキであることは、当事者のほかは案外認識されていなかったように思う。すくなくとも私の学生時代の昭和一〇年ごろまでは、まだ両側とも圧倒的にユリノキが多かったと思うが、今ではごくわずかに古木が残っているだけで、ほとんどがスズカケノキに変えられてしまっている。これも街路樹の常として、過度の刈り込みと、根部の過湿などの悪条件により病害に侵されて、次々と枯れていったのではないかと考えている。舗装道路下は蒸発がおさえられて、意外に過湿のことが多いらしく、根の呼吸に必要な土壌中の酸素欠乏の状態のほうが多いという。
そして、枯れた後へは再びユリノキが植えられることはなく、スズカケノキの並木に変わってしまった。現在ではほんのわずかしか残っていないが、スズカケノキの幹の淡色なのに対し、ユリノキが黒い濃色であるので、自動車で走っていてもすぐに見分けがつく。スズカケノキは、どうも自動車の排気ガスなどの大気汚染に強いらしい。東洋産と北米大陸産の両種があり、今では世界各国でこの両種が混じってしまって雑種ができているせいか、そのうちに世界中の温帯都市の街路樹が、ほとんどスズカケノキに変わってしまうのではないかという気がする。
京都大学農学部の旧館正面にもユリノキの並木があり、理学部植物園の一隅にも、同時に植えたとみられるユリノキが数本ある。すくなくとも五十数年はたつているものと思われる。
京都大学農学部は、東山の白川から排出されたと考えられる花崗岩砂(白川砂といわれる)のデルタ上にあるので、排水がよいせいか病害にもかからず、よく生育している。農学部旧館のユリノキ並木は、近年に一度だけ台風で倒されたことがあり、その前後から刈り込みが毎年行われて生育はとまっているが、その姿のうつくしさは卒業生にも認められていて、農学部の各学科の卒業生会の一つには「ゆりのき会」というのがあるくらいである。
自国にはない外来樹種は、どの国民でも興味が湧くらしく、私のまわった北半球の国々で、外来樹種を見かけない国はなかった。わが国でも、前にちょっとふれたように、戦後の意識的な導入ばかりでなく、かなり古くから海外の樹種がもたらされて、色々と植栽が試みられたようである。
北海道などの明治以降の林業は、林業用外国樹種の導入の歴史とみてもよい。旧御料林や旭川の外国樹種見本林は、その好例であろう。当時、北海道産のエゾマツ・トドマツはともに育苗が困難であったので、主として林業先進国のドイツで林業に用いられている樹種が導入され、試植された。今でも旅行中に、ヨーロッパアカマツの小さな林分が車窓から見えたり、鉄道防雪林にヨーロッパトウヒが使われていたりしているのも、みな往時の名残りである。しかし、これらの外国産樹種から、森林として造成されたものは、おそらくないのではなかろうか。
日本には温帯産樹種として、どの国の木材にも負けないスギやヒノキのような、生長・材質ともにすぐれた造林樹種があるが、亜熱帯林には、カラマツ以外に適当な造林樹種が見当たらない。そのカラマツも、造林木となると材質不良で用途がせまく、戦後に盛んに植えられた東北や北海道、それに原産地長野県地方のカラマツ造林も、用途の点で色々と問題をおこしている。
私はやはり、現産する針葉樹による造林を、人工・天然更新を通してもっとよく研究すべきだと信じている。ようやくうまく人工造林されるようになった北海道のエゾマツやトドマツも、まだ十分な成果をあげているように思えない。内地の亜高山帯になると、カラマツ以外の樹種では、育苗も満足に行えていないのが現状である。スギ・ヒノキ造林のみに集中して技術開発が行われすぎた感がある。
このことは冷温帯の落葉広葉樹林でも同様であって、針葉樹人工造林に変える、いわゆる拡大造林は行われるが、広葉樹の造林方法については著しく知識が不足している。
現状では、広葉樹丸太は南洋材として大量に輸入できているが、これは、私の考えではそれほど永くは続かない。というのは、現在広く用いられるようになったフタバガキ科の大径木は、いわゆるエマージェント・ツリーであって、林冠相を抽出して長々とそびえている木の一部であるから、単位面積当たりの出材量はきわめて少量なのである。
やはり、私は根本的には、自国原産の樹種による更新をまず研究して完成すべきで、外国産樹種の利用は造園的利用であると思っている。
(四手井綱英)
コンテンツ一覧▼ 目次をクリックすると、各記事をご覧いただけます
第一章 ユリノキという木
一、化石のなかの「ユリノキ」 村井貞允
- ユリノキ属の出現
- わが国におけるユリノキ化石発見の歴史
- 琵琶湖よりも大きかった古雫石湖
- ユリノキ化石の仲間たち
- ユリノキの繁茂した古環境
- ユリノキの仲間のうち、興味ある種類
二、北米産ユリノキのこと 四手井綱英
- 東部森林の代表者ユリノキ
- 外国樹種の導入
- 導入の失敗と成功例
- ユリノキへの期待
三、シナユリノキのこと 毛藤圀彦
- シナユリノキ発見の記録
- リリオデンドロン・キネンセ
- シナユリノキの天然分布
- 樹齢一〇〇〇年の最大樹発見
- ユリノキとシナユリノキの関連
四、ユリノキの名前
- 呼び名いろいろ
- ハンテンボク
- イエローポプラ
- チューリップツリー
- カヌーウッド
- サドルツリー
- カナリーウッド
- バスウッド
- ホワイトウッド
- ユリノキの学名
- リリオデンドロン・ツリピフェラ
第二章 ユリノキのふしぎな形態
一、花
- 原始の花
- 緑色の花冠
- 古代花の形質
二、葉
- 葉先のない珍しい葉形
- 難解な葉の表現
- 発見した小さな突起物
三、生長
- どのくらい大きくなるのか
- 生長迅速
- 容姿端整
四、寿命
- 樹高六〇・四メートルの巨木
- 枝と幹と樹皮
五、ユリノキの薬効と成分 指田豊
- 北米インディアンの薬木
- 抗癌作用のあるユリノキ成分
- 辺材が示す抗菌物質と香りの成分
六、花蜜
- 一花に小匙一杯ほどの
- 蜂を呼ぶ
- 蜜の品がら
第三章 アパラチア山麓のユリノキ
一、チューリップの木の花かご
二、幻のユリノキを訪ねて
- 手当たりしだいの伐採
- 神々の樹との出会い
三、天然林に生きる
- 天然更新できない理由
- 世紀末をむかえたユリノキ
四、ユリノキ天然林の植物相
- 山岳天然林
- 低地天然林
- 丘陵地天然林
- 河床地天然林
- ユリノキの食害
五、伐りつくした材
- 「光沢の白材」と呼ばれて...
- 木材としての価値
- 材の堅さと強度
第四章 ユリノキ・ニッポン物語
一、日本渡来考
- 伊藤圭介説と田中芳男説
- 不発芽に終った第一号
二、長岡苗木について
- 初代の並木たち
- 公園設計の父・長岡安平
- 御苑ユリノキを母樹として
三、小泉苗木について
- ユリノキ二世のルーツ
- 啄木と同期の小泉多三郎
- 造園業のパイオニア藤村「豊香園」
四、横山苗木について
- 造林の先駆者・横山八郎
- 小泉苗木を継いだ横山苗木
五、ロウソクノキの林
- 紺野ツマさんの林
- 半世紀後のみごとな林分
六、新宿御苑のシンボル
- 御苑の来し方
- 寄せ植えした三本
七、上野・銀座のユリノキ
- 牧野富太郎の設計
- この木なんの木
- 銀座のユリノキ
八、受難のユリノキ二題
- 三菱爆破事件の顛末
- 「宮沢賢治の母校並木」の顛末
- 植栽用途と生育状況の把握
第五章 都市と田園のユリノキ
一、植えたい人へのメッセージ
- 「田園の幸福」の花ことば
- 植栽上の七つのポイント
- 北限および南限と適地
- 防火樹としての効果と萌芽力
- 枝折れ
- 冬の小苗管理法
- アメリカシロヒトリ
二、ユリノキの優れた園芸品種
- 樹形変わりと葉の変化
- 新品種への期待
- 現在の園芸品種
三、世界の国のユリノキ事情
- 九カ国の生態学者に聞く
第六章 ユリノキ実験考
一、移植
- 成木移植はむずかしい
二、三年生株と幼苗の移植実験
三、実生苗
- ユリノキ苗木の量産法
- 種子のカーペット
- 樹下採苗
- 四〇パーセントに近い硬実歩合
- 五〇〇メートルも飛ぶ翼果
- 一樹から採れる種子数
書籍詳細
-
毛藤勤治 著 / 四手井綱英・村井貞允・指田 豊・毛藤圀彦 寄稿
四六判 / 並製 / 304頁(カラー24頁) / 定価1,885円(本体1,714+税)/
ISBN4-900358-23-1
〔花の美術館〕カテゴリリンク
- 第19回 小山鐡夫追悼記念号『黒船が持ち帰った植物たち』より
- 第18回 小山鐡夫追悼記念号『植物園の話』より
- 第17回 『MAKINO 80』東京植物同好会・牧野植物同好会八十周年記念誌
- 第16回 ハマナスの語源を探る
- 第15回 金井弘夫追悼記念号『金井弘夫著作集 植物・探検・書評』より
- 第14回 『花のある風景』
- 第13回 坂嵜信之追悼記念号『日本で育つ・熱帯花木植栽事典』より
- 第12回 楽しい花観察108選『不思議な花々のなりたち』
- 第11回 川島榮生の《ヤマアジサイの世界》
- 第10回 渡辺健二『日本産ギボウシの世界』
- 第9回 『ユリノキという木』─ 魅せられた樹の博物誌
- 第8回 『北米インディアン悲詩』/ エドワード・カーティス写真集
- 第7回 江戸時代の花たち 書物に見る江戸時代の園芸文化
- 第6回 わが国初のボタニカルアーティスト 五百城文哉(いおきぶんさい)の世界
- 第5回 『ビル・ニガントゥ』 19世紀末ネパール秘蔵の本草図譜
- 第4回 植物画家 石川美枝子の作品
- 第3回 サイエンティフィック・イラストレーター 木村政司の作品
- 第2回 植物画家 中島睦子の作品
- 第1回 『PLANTAE ASIATICAE RARIORES』