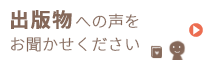花の手帖
○花の季節
花には季節がある。春の花、夏の花、秋の花、冬の花と、だいたい季節に応じて咲く花がきまっている。春といってもウメ、スイセン、セツブンソウ、ミスミソウのように早春に咲くものもあれば、アマドコロ、ヤマツツジ、クサノオウのように晩春に咲くものもある。この花の季節は植物の種類ごとにきまっていて、同じリンドウのなかまでも、春咲く種類にはハルリンドウがあり、秋咲く種類にはリンドウがある。
春夏秋冬の四季ばかりでなく、一年をいくつかに区分し、そのおりおりに咲く花をあてはめることができる。これをこまかく月別に区分して花を配列したものが花暦である。花暦は国によってちがい、同じ国のなかでも地域によってちがう。日本でも北海道と本州、九州では同じ種類でも花の咲くのは一月ずつくらいのちがいがある。
わが国に昔から花カルタというカード遊びがある。ふつうは花札といっているが、一月から十二月までに季節の花を配し、各月四枚の札(カード)、四八枚からなるものである。これは、一月―松、二月―梅、三月―桜、四月―藤、五月―花菖蒲、六月―牡丹、七月―萩、八月―薄、九月―菊、十月―紅葉、十一月―雨、十二月―桐となっている。八月の札には山と月と雁があるがススキの絵はなく、十月のモミジは、花は春であるのに紅葉をもってこれにかえ、鹿を配している。十一月の雨札にも花がなく、十二月の桐札には花の代りにホウオウを配し、日本人好みのしゃれたものである。しかし、これはあきらかに花暦である。一六〇〇年代の末頃にできたというから、およそ本州中部、江戸付近の花が中心になっているのではあるまいか。
それはともかく、春咲く花は秋には咲かないし、秋咲く花は春には咲かない。これはなぜであろうか。これはその植物自身にそなわった性質であるが、太陽の照射時間に深い関係があることがわかったのはそう古いことではない。春から初夏に開花する植物は、日が長くなる、つまり日照時間が長くなることが条件であり、秋から初冬に開花する植物は日が短くなる、いいかえると日照時間が短くなることが花を咲かせる条件である。これを利用して園芸家は、ときならぬ花を花屋にだすようになった。たとえば、キクの花は十月から十一月に咲くのが正常である。しかし早くから日覆いなどして日照時間を短くしてやると夏に開花するようになる。また逆に、春から初夏にかけて咲く花を電燈などでふつうより長い時間光をあててやると、冬の間から開花するようになる。
同じ植物でも、地域によって開花期にずれのあることは前にものべた。たとえばソメイヨシノというサクラは九州では三月下旬、東京付近では四月上旬、東北地方では四月下旬から五月上旬に開花する。これは気温の相違によるものである。同じ東京付近でも暖い年は早く、寒い年はおそく咲き、一週間ぐらいのずれがある。
このように、開花には日照と気温とが深い関係をもっているから、この条件をうまく処理すると、同じ植物で一年中花を咲かせることができる。この頃、花屋にでている花を見ると季節感を忘れ、ちぐはぐな気持になることが多い。
一方、季節にあまり関係なく、春から秋までつぎつぎに開花しつづけるものがある。トキワハゼ、カタバミ、ノボロギクなどがそうである。開花に日照時間の長いことを条件とするものを長日植物、日照時間の短いことを条件とするものを短日植物とよぶのに対し、カタバミなどは中日植物とよばれる。しかし、短日植物であれ、長日植物であれ、同じ場所で同じ種類の花が全く同時に咲くとはかぎらない。開花ばかりではなく、紅葉、落葉の現象にも同じことがいえる。個体の差によるものであろう。私の家の庭に、一〇メートルも離れていないが、雌木と雄木の二株のイチョウがある。ある秋に雄木の方が二週間ほど早く落葉したことに気がついた。その後毎年そうかと注意しているが、必ずしもそうでない。自然の微妙さに考えさせられたことである。
○花の美しさ
花は美しい。真紅のバラ、カーネーション、チューリップ、黄色のヤマブキ、レンギョウ、キク、紫色のオダマキ、アサガオ、ジギタリス、みなそれぞれの美しさをもっている。山野に自生するいろいろな野の花もそれなりの個性をそなえて美しい。
では花のどこが美しいのだろう。ときにはトリカブトのように萼が美しいとか、ホトトギスのように雄蕊と雌蕊が美しいこともある。しかし、一般に美しいと思われているのは花弁の集合である花冠であろう。ひとつひとつの花びらをとって見てもそれほど美しいとはいえないが、それらが集まってつくるひとつの構造物(花冠)としてはじめて花の美が強調される。人工的に改良された園芸植物の花は花冠が大きく色もはでで美しい。しかし、野山に咲く小さな花でも手にとって拡大鏡で見れば、その構造は同じであるから美しさには変りはない。
しかし、花の美しさは大きさや形にもよるであろうが、なんといっても豊かな色彩によるといえよう。花弁の色は白、黄、赤、青、紫、しかも濃淡ばかりでなく、その中間の微妙なニュアンスのちがいがあることはだれでも知っている。このような花弁の色の多彩さは何によるものであろうか。それは一言でいえば、花弁の細胞中にふくまれる色素のちがいなのである。
花弁の色素はアントシアン系、カロチノイド系、クロロフィル系の三つになるという。アントシアン系は花青素といわれ、花弁はもちろん、リソゴの果実の外皮、葉などにふくまれ、赤、青、紫色系統の色はみなこの色素による。この色素は細胞液にとけていて、液が酸性になると赤~紅色になり、アルカリ性になると青色に変る。秋の紅葉はこのよい例で、山々の木の葉の細胞液が酸性化しアントシアンが赤~紅色に発色すると、昔の風流人はもみじ狩りと称してくり出したのである。
カロチノイド系色素は花弁のほかに果実や葉、ときには根にふくまれ、それらが黄色から深黄~黄赤色を呈するのはこのせいである。
クロロフィルは一般によく知られているように葉緑素といい、ふつうは葉に多くふくまれているが、ときには花びらにもあらわれる。クルマバツクバネソウのような緑色の花がそうである。白色の花びらに少量ふくまれ、緑色のすじや斑点としてあらわれることもある(例、ウコンザクラ)。
咲きはじめと咲きおわりとで花びらの色が変ることがある。これは花びらの中にある色素の増減によるためであるが、これが気温と光線の微妙な変化によるらしいというほかくわしいことはわからない。ハコネウツギの花は咲いたときは白色であるが、終りに近づくと紅色になる。フヨウの一品種にスイフヨウ(酔芙蓉)というのがある。午前中に開いた花びらは純白であるが、午後になると徐々に赤みを増して、ほんのり顔に赤みをあらわした美女を思わせるのである。
さて、われわれは花弁の色を美しいと見る。しかし、花本来の生殖という機能から考えればよそおいの目的は人間相手ではない。では花に集まる昆虫には花の色がわかるだろうか。個々の生活をする昆虫ではよくわからないが、集団生活をすることで有名なミツバチではかなりのことがわかっている。ミツバチは赤色に感じない。つまり赤色盲であるが、黄色から青緑色、青色によく感じ、面白いことに人間の眼には見えない紫外線にもよく感ずるといわれる。しかし、われわれのように美しいとしてではなく、蜜や花粉を集めるときのシグナルとして見るものらしい。一般に、風で花粉が媒介される風媒花には花びらのないものや、あっても色の地味なものが多いのに、虫媒花には華やかな色をもつものが多いということは何か因果関係がありそうである。しかし、花が花粉を運んでもらうために昆虫の眼をひくように色をもつことになったというのはあまりにも目的論にすぎる。多種多様な色彩をもつことが生物学的にどんな意義があるのか、まだ十分にわかっていないのである。
○花の香り
美しい花を見るとたいていの人はつい匂いをかいでみる。そして「いい香り……」とうっとりしたり、香りのないのにがっかりしたり、ときには「いやな香り……」とすてたりする。
よい香りの花といえば、ふつうだれでも、クチナシ、ジンチョウゲ、ウメ、キンモクセイ、ライラック、バラ、スズラン、ヤマユリなどをあげる。大きな美しい花が必ずしもよい香りをもつとはかぎらず、目立たない花でもすばらしい香りをもつものもある。まれには美しい花でありながらたえられない臭気をだすものもある。一口によい香り、いやなにおいといっても感ずる人の個性によりちがいがあるわけで、一般には、花の香りと美しさはあまり関係はないといってよい。
ところで、いやなにおいでは、クリの花は青臭くていやなにおいと感ずることはだれでも知っている。クロユリといえば伝説にまつわる高山植物として登山者はあこがれるが、花にいやなにおいがあるのでかいでみた人はがっかりする。日本には堪えられないほどの悪臭をもつ花はないが、外国にはある。多肉植物のスタペリアの花がそれで、肉が腐敗したような臭気をだす。
また、とくによい香りというほどではなくても、キクの花にはキクの、サクラの花にはサクラの特有の香りがある。いってみれば個性的な香りということになろう。
このように花にはさまざまな香りがあるが、空気の温度や湿度、昼と夜、感ずる人の肉体的・心理的条件によって感じ方がちがってくる。一般に、空気に湿気の多いときが乾いているときより、風のないときがあるときより、夜の方が昼より、健康なときが病気のときより、安らいでいるときが騒がしいときより香りをよく感ずる。庭に植えたウメ、クチナシ、キンモクセイの花の香りが、昼間はそれほど感じないのに、夜間びっくりするほど強く感じられたり、夜、戸をしめたとき花瓶にいけたヤマユリのはげしい香りに困惑させられるのはよくあることだ。
さて、花びらの色が色素によると同じように、花の香りもその中にふくまれる成分による。よく知られているように、優雅な芳香で愛されるジャスミンの香水は、天然のものはモクセイ科のジャスミンの花を集めてその成分をとり出したものである。花の香りの成分としては、シトロネロール、ゲラニオール、リナロール、ジャスモンなどが主なものであり、水や油にとけた揮発性の物質である。これらの物質からでる気体分子がわれわれの鼻の奥、鼻腔の天井にある臭粘膜に達するとそこにある細胞が刺激され、興奮が神経におくりこまれ香りとして感じられるのである。だから、個人差があるのも当然である。
花の香りに対して昆虫たちはどう感ずるだろう。ここでもミツバチを例にひくと、ミツバチはわれわれが区別できるほどの香りは感ずるらしい。さらに蜜の味も区別できるらしい。一匹のミツバチがある場所で花蜜を集めて巣に帰ってくると、一種の身振り(ダンス)でなかまたちに巣と花の距離を、他の身振りでその方向を教える、そしてもってきた蜜の香りと味を覚えさせる。なかまたちは教えられた方向と距離を飛んでいく。目的地近くなると、花の色と形でおよその見当をつけ、覚えた香りで目的の花に達する。このようにして無数のミツバチが同じ種類の花を求めて蜜を集めるから、アブラナの花盛りにはアブラナの蜜が、ソバの花盛りにはソバの蜜が集中的に集められることになる。
○花のかたち
数多い植物の葉のなかには、色もかたちも花弁に見まごうものがある。また逆に、葉と区別のつけにくいような花弁もある。これは花屋をのぞいたことがある人なら気のつくことであろう。想像力のゆたかな人なら、そこで、花も葉ももとは同じものかと考えたかも知れない。
たしかに、花は葉の変態したものである。一般に、花弁のかたちは葉とよく似ているし雄蕊や雌蕊も、どこかしら葉と共通したかたちをしている。葉が茎につくのに一枚ずつたがいちがいについたり、二枚が向いあって対になっていたり、三~六枚が輪になってついたりしているが、萼片、花弁、雄蕊、雌蕊も全く同じつき方をしている。植物を観賞するのに、花をめでるものもあれば、葉をめでるものもあるが、どちらもそれほど異質のことではないといえよう。
さて、花のかたちといえば、花を構成している、萼、花冠、雄蕊、雌蕊を総合したかたちでなくてはならない。それは植物の種類にしたがって、何千、何万というかたちにわかれ、自然の複雑多様さがうかがえるが、大きく見ればいくつかわけることができるのである。
まず、平面的な花、あるひろがりをもっているがあまり立体的でないもので、ヤマブキソウ、フシグロセンノウ、キジムシロ、ハナビシソウ、オトギリソウなどがある。次は空間的というか立体的な花、あるひろがりと高さのあるもので、ホタルブクロ、オドリコソウ、ツリフネソウ、シュンランなどがある。ここで考えてみると、平面的な花は離弁花で立体的な花は合弁花に属するものが多いようである。いうまでもないが、離弁花とはウメやサクラの花のように花弁が一枚一枚はなれているもの、合弁花は花弁が側縁でくっつき合っているもので、アサガオの花などを思いうかべるとよい。また、ヨメナ、コスモスの花を見ると平面的な離弁花のように思えるが、実はこれらキク科の花はたくさんの小さな合弁花の集まりである。たくさんの管状花が密集している中心をいくつかの舌状花がとりかこんでいる同じキク科の花でも、管状花ばかり集まっているもの(アザミの類)もあり、また舌状花ばかり集まっているもの(タンポポ、ニガナのなかま)もある。
植物を分類するのにもっとも重視されるのは花である。茎や葉の性質はそれほど本質的なものではないとされている。したがって、花のかたちののみこみ方を知っておくと便利である。
花のかたちといえば、萼、花弁、雄蕊、雌蕊の総合形であるが、ふつうは花冠が主になる。花冠は離弁花冠と合弁花冠にわけられる。そのかたちですぐ何科の植物であるかわかるものがある。例えば、離弁花冠では、蝶形花冠(マメ科)、十字形花冠(アブラナ科)など。合弁花冠では車形花冠(ムラサキ科)、唇形花冠(シソ科)、仮面状花冠(タヌキモ科)、鐘形花冠(リンドウ科)などがそれである。
○花のいのち
花は、たいていわれわれが知らぬ間に開き、知らぬ間に終っている。いったいいつ開き、いつ終るのだろう。
花が一日のうちいつ開くかという開花時刻は、種類によってきまっている。科とか属とかによってきまっているものもあるが、同じ属でありながら、種類がちがうと開花時刻がちがうものがあるのは興味がある。同じ属であるがユウスゲは夕方に開き、翌朝午前中にしぼみ、ノカンゾウは午前中に開いて夕方にしぼんでしまう。
花は鳥ほど早起きはしないが、朝から昼すぎまで開くものが多い。朝露をふんでいく山路や散歩の道すがら、すでにたいていの花が開いているのに気づく人も多いだろう。朝といっても、開くときに音がするとかしないとかで一時話題になったハスのように夜のあけないうちから開くものもあれば、リンドウのように太陽がてりだしてからはじめて開く花もある。ナデシコなどはゆうゆう正午すぎに花を開く。
このように花によって開花時刻のちがうことを利用して、花の開き工合からおよその時刻がわかるように設計されたものを花時計という。昔、スウェーデンの植物学者リンネがウプサラの植物園でつくったのが有名で、ここに紹介しておく。ウプサラは北緯五〇度、日の長いときの開花時刻であるから、東京や京都で同じ植物でやってもだいぶちがうものになると思う。
▼リンネの花時計 バラモンギク 三~五時 ホンキンセンカ 九時 シナカンゾウ 五時 マッバギクの一種 一〇~十一時 セイヨウタンポポ 五~六時 オシロイバナ 十七時 タイワンハチジョウナ 六~七時 テンジクアオイの一種 十八時 ルリハコベ 八時 マンテマの一種 二十一~二十二時 花がひらくということは、花びらが成長して極限に達することである。そして花びらが外側にそりかえるのは内側、とくに基部のあたりが成長するか緊張するためであり、反対に閉じるのは外側の同じ部分で同じ現象がおこるからである。しかし、その動きがスタートするためには何かのきっかけが必要である。それは温度と光の変化であるという。リンドウが太陽の光にあたってはじめて開花したり、マツヨイグサが日没とともに開花したりするのはそのためである。
では、一度開いた花はどのくらい開いているか。これも種類によってまちまちである。ふつうの花は朝開いて夜しぼみ、これを二、三日くりかえす。ノカンゾウのなかまは朝開いて夕方にしぼみ、それで花が終るので一日花といい、「はかない命」にたとえられる。もっとも短いのはイネの花である。朝十時頃に開いて花粉を受けると、もう用はないとばかり、一、二時間で閉じてしまう。また一夜かぎりの花というものもある。ユウスゲ、カラスウリ、ユウガオ、マツヨイグサ、オシロイバナなどがそれで、夕方に開花して翌日の朝から午前中にしぼんでしまう。サボテンのなかまで、「月下の美人」という花は真夜中に開き、数時間で終ってしまう。「佳人薄命」がそのままあてはまるような花である。しかし、美しい花で長命のものもないではない。ランの類がそれである。数日から一週間ぐらいは開きっぱなしである。山路につきもののように思われているスミレも、花は数日間開いたままである。高原の花リンドウは、朝一度開いても曇って光がさえぎられると閉じてしまい、光がさすとまた開くという工合に、数日間、開閉をくりかえしている。
花がしぼんで終ると、花冠はどうなるか。これもいろいろで、エゴノキのようにすぽっと抜けて落ちるものもあれば、リンドウの類のように未練がましくしわになって残るものもある。なかには花びらがとけてなくなるツユクサの花のようなものもある。
○花の本性
花はなぜ咲くのか、人間からみれば、花は美しければよいと思えるかも知れない。事実そういうことで人々は花を好んでいる。しかし花には大切な役割がある。種子をつくり、それによって子孫をふやしていかなければならない。花は美しく飾られた生殖器官なのである。
花をつける植物は、植物のなかでもっとも進化した植物群である。これを顕花植物という。種子をつくるので種子植物ともいう。これに対して花のない植物を隠花植物とよぶ、隠花という語から、花がかくされて外にあらわれないようにとられるが、そうではない。花という生殖器官に進化する以前の、原始的な生殖器官があるということにほかならない。原始的な生殖器官といっても、これまたきわめて多種多様である。
花の生殖に直接たずさわるのは、雄蕊と雌蕊である。雄蕊からでた花粉が雌蕊の柱頭につくことで生殖のいとなみがはじまる。これは雄蕊の側からいえば送粉であり、雌蕊側からいえば受粉である。雌蕊の柱頭についた花粉から花粉管という管がのびだし、花柱の中を通って子房の中にある胚珠に達し、花粉管の中にある雄核が胚珠の中にある卵細胞と一緒になって受精が起り、胚珠は種子に発達するわけだが、ここではくわしいことは省略する。
花をつける植物のうち、八〇パーセントの種類は、ひとつの花に雌蕊と雄蕊をそなえている。このような花を両性花という。ひとつの花に雄蕊だけがあるか、雌蕊はあっても機能を失っているものを雄花といい、逆に雌蕊だけがあるか、雄蕊があっても機能を失っているものを雌花といい、これらを総称して単性花という。ひとつの株に雄花も雌花もあるものを雌雄同株(ガマ、オモダカ、スゲのなかま)といい、これに対し、雄花ばかりの株、雌花ばかりの株というようにわかれているものを雌雄異株(スイバ、カラスウリなど)という。イチョウの木でギンナンのなるのとならないのがあるのは誰でも知っている。前者が雌の木、後者が雄の木である。しかし自然はなかなか複雑で、ひとつの株に雄花と両性花、他の株に雌花と両性花がつくものがあり、またひとつの株に、両性花、雄花、雌花がつく植物もある。
さて、花粉が雄蕊から雌蕊に運ばれるのに、風によるもの、水によるもの、動物によるものとある。風によるものではスイバ、イネ、ヤナギ、針葉樹などがあり、水によるものではキンギョモなどの水草がある。動物によるものは大部分は昆虫によるが、なかには鳥によるもの、まれにはカタツムリによるものなどがある。夜咲く花、たとえばマツヨイグサなどは蛾の一種によって花粉がはこばれる。
ミツバチ、チョウ、アブ、甲虫などの昆虫は花のために花粉をはこぶためにやってくるわけではない。花粉や蜜を集めるとか卵をうみつけるために花をおとずれるわけで、その結果として花粉を媒介することになるのである。昆虫が花から花へとびまわり花粉や蜜を集めているうちに花粉がめしべの柱頭につくことになる。雌花と雄花の区別がある単性花では、必ず、雌花は他の雄花の花粉をうけなければならない。両性花ではどうかというと、同じ花粉をうけることもあるが、他の花の花粉をうける機会が多い。同じ花の花粉をうけると種子のできる率がわるいという事実がある。同じ花の雌蕊と雄蕊の高さがちがっていたり、雄蕊が先に成熟してすがれた後に、雌蕊が成熟するなどの仕組がみられる。秋の七草のひとつキキョウの花を観察すると、雌蕊がすっかり成熟して柱頭が五つに裂けるころは雄蕊はすでにしおれている。したがってこの雌蕊は他の花の雄蕊の花粉をうけなければ果実にならない。サクラソウの花をしらべてみると、雌蕊の花柱の長い花(長花柱)と短い花(短花柱)の二形の花がある。長花柱の花は短花柱の花の花粉をうけると種子ができるし、短花柱の花は長花粉の花の花柱をうけると種子ができる。しかし、長花柱の花は長花柱の花粉をうけても種子はできず、短花柱の花は短花柱の花粉をうけても種子ができない、といわれている。
一般に、花が開くと、萼片、花弁が開いて、雄蕊、雌蕊が空気に開放される。ところが、花ができることはできるが、決して開放しない花がある。萼、花弁はとじたままで、つまりつぼみのままで、その内部で雄蕊の花粉が雌蕊の柱頭につき受精がおこなわれる。このような花を閉鎖花、または単に閉花という。閉花をつける植物はかなり知られており、スミレ科、カタバミ科、イネ科、マメ科、ツユクサ科、トウシンソウ科、シソ科のあるものに見られる。
スミレの類は、春にふつうの花が開くが、それが終るころから閉花がではじめる。閉花を解剖してみると、花弁は発達せず、雄蕊は大部分退化し、一、二本だけが花粉をつくっている。花粉は葯の中で花粉管をのばし、葯の壁を破ってめしべの柱頭に直接とどくようになっている。閉花のできる原因はよくわからないが、ひとつは低温や乾燥に適応したものと考えられる。
地球上に花のさく植物が出現したのは古生代の石炭紀(約三億年前)といわれる。花といってもこの時代のものは雌蕊は裸の胚珠だけの原始的なものであった。そして、萼や花弁をもち、胚珠が子房の中につつまれた花(われわれがふつう花という)をもつ植物が現れたのは中生代の白亜紀(約一億二〇〇〇万年前)である。それから現在まで長い時間をかけて、現在見るような花さく植物が進化してきたわけである。
(花の手帖――野の花・一九六八年四月)
『花のある風景』コンテンツ一覧▼ 目次(青字)をクリックすると、各文をご覧いただけます
〔花の美術館〕カテゴリリンク
- 第19回 小山鐡夫追悼記念号『黒船が持ち帰った植物たち』より
- 第18回 小山鐡夫追悼記念号『植物園の話』より
- 第17回 『MAKINO 80』東京植物同好会・牧野植物同好会八十周年記念誌
- 第16回 ハマナスの語源を探る
- 第15回 金井弘夫追悼記念号『金井弘夫著作集 植物・探検・書評』より
- 第14回 『花のある風景』
- 第13回 坂嵜信之追悼記念号『日本で育つ・熱帯花木植栽事典』より
- 第12回 楽しい花観察108選『不思議な花々のなりたち』
- 第11回 川島榮生の《ヤマアジサイの世界》
- 第10回 渡辺健二『日本産ギボウシの世界』
- 第9回 『ユリノキという木』─ 魅せられた樹の博物誌
- 第8回 『北米インディアン悲詩』/ エドワード・カーティス写真集
- 第7回 江戸時代の花たち 書物に見る江戸時代の園芸文化
- 第6回 わが国初のボタニカルアーティスト 五百城文哉(いおきぶんさい)の世界
- 第5回 『ビル・ニガントゥ』 19世紀末ネパール秘蔵の本草図譜
- 第4回 植物画家 石川美枝子の作品
- 第3回 サイエンティフィック・イラストレーター 木村政司の作品
- 第2回 植物画家 中島睦子の作品
- 第1回 『PLANTAE ASIATICAE RARIORES』