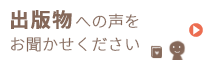- ホーム
- ネイチャーコンテンツ
- Aboc Museum
- 花の美術館
- 第14回『花のある風景』
- わたしの研究歴
わたしの研究歴
昭和十四年(一九三九)十一月以来勤務した国立科学博物館を本年三月末日付で定年退職した。その間の研究その他に関して何か書くように編集委員から依頼され筆をとることになった。
国立科学博物館(前身東京科学博物館)には二十七年四ヶ月御世話になったが、研究に関するものといえばいきおい大学の副手時代、さらに植物分類学を修めるに至ったいきさつにも多少ふれざるを得ないので、冗長の点はお許しを願うことにする。
さて、私は中学時代はエンジニアにあこがれ、母方の叔父が教授をしていた東京高等工業学校にはいる希望をもっていた。機械いじりが好きだったことと、次男坊ではやく職業につくことが原因であった。ところが、兄の若死によって事情が一変し、それまで早川姓を名乗っていたのが佐竹姓にもどり、高等学校から大学へ進むことになった。仙台の第二高等学校を受験し失敗したが、学習院高等科に入ることができた。二年のとき物理学の試験に白紙をだし、一年おくれて卒業し、エンジニアをあきらめ、大正十四年(一九二五)四月、東京帝国大学理学部植物学科に入学した。植物学科を選んだことは、服部広太郎先生の講義と実験をうけ、植物組織のプレパラートをつくり、顕微鏡をのぞくことに興味をもったことが大きな理由である。
当時の植物学教室は小石川植物園内にあって、古ぼけた木造の平屋建物であった。前期一ヶ年で分類学や形態学、遺伝学を、中期一ヶ年で生理学、生態学、生化学などを修め、後期一ヶ年で専攻科目を選んで卒業論文を書くことになっていた。入学したときの教授には細胞学・遺伝学の藤井健次郎先生、生理・生化学の柴田桂太先生、分類学の早田文蔵先生、助教授には分類学の中井猛之進先生、生態学の中野治房先生、講師には分類学の牧野富太郎先生、細菌学の服部広太郎先生、形態学の小倉謙先生、細胞学の山羽儀兵先生がおられた。前期、中期はまたたくまに過ぎ、後期で専攻科目をきめるとき、分類学をやることにした。当時の分類学はまだ現在のように分化せず、クラシックなものでやれるように思ったからである。助教授の中井先生は二年前留学から帰ったばかりで講義をきいたことがなかったので、早田先生につくことにした。ある日、先生の部屋にいき、恐る恐るその旨申しでた。「分類学をやるのに二通りある。一は野外にでて分布やフロラをやることで、これには相当の体力と金力がいる。二は室内でじっくり植物にとりくんで基礎的な仕事をすることで、この方はあまり金力はいらない。どちらをとるか」といわれた。体力も金力も自信がないので後者をとることにした。与えられたテーマは「いらくさ群植物ノ葉ノスポドグラムノ分類学的価値ニツキテ」であった。
スポドグラムSpodogramというのはモッリッシュ博士H.Molischによりはじめられたもので、後に小原亀太郎博士により「灰像」という訳語があてられた。植物の葉にふくまれる無機物の結晶などの形態や分布などを、葉を焼いた灰片によって研究するものである。腊葉室の標本を使い、葉の一部(約三mm平方くらい)を切りとり、磁気のルツボにいれ、ガスバーナーでむし焼きにし、白くなった灰片をスライドガラスの上にのせ、キシロールをかけ、バルサムで封じてプレパラートにする。葉の一部を切りとった標本には、先生がつくってくれた「Specimen from which a fragment is taken for the preparation by Y.Satake」という小さいラベルをはりつけておく。昭和二年四月から分類学研究室の大部屋にいれられ、仕事をはじめた。この大部屋には、助手の本田先生(イネ科の分類)、先輩の山本由松氏(台湾のフロラ)、山田幸男氏(海藻の分類学)、木村有香氏(ヤナギ属の分類)などの錚々たる研究者がいた。また大先輩の大木騏一という、中学の先生をしながら早田先生の指導でササ類の葉の灰像を研究している篤学の士がいた。同期の御江久夫君も同じ部屋で、やはり早田先生について卒論「サルノコシカケ類の分類」をやっていた。
一年はすぐたって、まがりなりにも卒業論文を英語でまとめ、昭和三年三月卒業することができた。同期生には、相弟子の御江久夫、中野先生についた関野武夫、柴田先生についた田沢康夫、田中伊助、村上進、薬師寺英次郎の諸君がいた。田中君は戦前に、関野君は戦後に病死したが、他は今も元気で活躍している。四月には副手を命ぜられ、月手当十五円を支給され、先生の講義や研究のプレパラート作りなどの手伝いをさせられた。
当時、早田先生は台湾植物図譜十巻をすでに完成し、その補遺を山本由松氏にまかせ、もっぱらシダ植物の中心柱の分類学的研究や裸子植物の解剖学的分類に力を注いでおられた。その年(昭和三年)の七月、日光植物園で学生の実習指導のあと一週間ばかり先生と二人植物園にかんづめになり、球果植物の葉のプレパラートを作り、八〇〇倍の解剖図を描いた。翌四年に先生は「日本植物ニ関スル解剖分類学的貢献」と題した論文を植物学雑誌に発表したが、思いがけずも、私を共著者にして下さった。ただ私の描いた解剖図が挿図になったというだけであったが、これが私の名が学会誌上に載った最初である。ついで私の卒業論文が和文で三回にわたり植物学雑誌に、英文で東大理学部紀要に掲載された(一九三一)。これが私の最初の単独発表である。私の研究方法が古典的な分類研究からはずれたものであったが、顕微鏡による仕事が性にあったとみえ、トウシンソウ科の果皮の構造や、モミ属の葉の構造、スギ科やマツ科の球果鱗の構造を研究したり、イワヒバ科の葉の表皮の形態的研究をやったりして数年がすぎた。
昭和九年一月、停年間際に指導教授の早田先生が病死、私は途方にくれた。今までの研究方向では教室に残って研究をつづけることは困難である。というのは早田先生のあとをついで教授になった中井先生の方向はまるでちがうからである。私は悩んだが、方向をまげても教室に残ることにし、中井教授の指導をうけることにした。与えられたテーマは「日本産ヤブマオ属の分類学的研究」で、一年ぐらいでやり、英文で東大理学部紀要に発表した(一九三六)。これが学位論文となり、翌年二月、理学博士の学位をうけた。そのうち、むかし中井先生が手をつけたホシクサ属の再検討を命ぜられ、こつこつとしらべはじめた。花が二~三mmの小さいもので、顕微鏡をつかうことから興味がわき、二、三の新種を発表してからモノグラフをはじめた。その頃、三省堂から、中井、本田両先生の監修で、大日本植物誌発刊の企画があり、その第一号として私のトウシンソウ科が出版された(一九三八)。これは、十号まで発行されたが戦争のため中断され、戦後一冊がでただけでついに廃刊になってしまった。
昭和九年四月、東京農業大学講師を嘱託され、五年間分類学の講義と実験を受持った。また東京高等師範学校、東京文理科大学の講師として分類学の講義を二年ばかりやった。
昭和十四年十一月、東京科学博物館学芸官に任命された。館長は東大教授の坪井誠太郎先生で、科学博物館における研究の重要性が認められ、多少定員が増したために植物関係では私が迎えられたわけである。当時の植物部には、学芸官として今関六也氏、学芸官補には奥山春季氏がいた。
昭和十五年六月から一ヶ月満州国に出張し、ハルビン、チャムスから興凱湖、鏡泊蕗付近、さらに小興安嶺方面を採集し、九月から一ヶ月、今関氏とともに台湾に出張し、太平山から阿里山、新高山に登り、高雄の京都大学演習林などで採集した。この年、ホシクサ属の解説を大日本植物誌第六号に、ホシクサ属校訂(欧文)を東京科学博物館研究報告第四号に、東初雄氏採集の内蒙古植物の目録を植物研究雑誌に発表した。また、まとまった科や属のほかに、気がついた植物について断片的な報告をしたものに、日本植物断報一~六(一九三六~一九三九)、日本植物時報一~四(一九四〇~一九四二)がある。
昭和十六年十二月太平洋戦争がおこった。はじめは連勝したがミッドウェイ海戦以来しだいに旗色が悪くなった。占領地の物資補給は占領地でまかなえということから、蘭領ニューギニアに民政府をたてていた海軍が資源調査隊を組織した。農林産資源、鉱産資源、石油石炭資源、電力資源などを調査する六個班が編成された。田山利三郎氏から東京科学博物館に参加の依嘱があり、科学博物館が主力となって一班をつくるという条件で参加にきまった。結局、科学博物館からは私が林業資源を担当し、新村太郎氏(蝶の専門)が助手格、杉山隆二氏、井尻正二氏が鉱産資源を担当し、小川賢之輔氏が助手として参加。農業資源の担当は東京農業専門学校の長戸一雄氏とその助手千葉弘見氏。早稲田大学理工学部学生の今井直哉君と、東大理学部学生の高沢松逸君が補助員として加わり、第三班をつくり、私が班長をつとめることになった。
昭和十八年一月十三日、調査隊は白山丸に乗って横浜を出発した。第二班に津山尚氏、第四班に三木茂氏がいた。二十四日パラオ、コロール入港。一週間滞在し、二月三日コロールを出港して西ニューギニアの主都マノクワリに上陸したのは二月五日であった。
資源調査隊は膨大な組織で、幹部の人間関係も複雑、その運営は大変なものだったらしく、われわれ三班が現地調査に出発したのは三月十二日になった。三班の担当した地域はワンダメン湾沿岸からヤムール湖で、ワオブに基地をおいた。医療班、測量班数名ずつ、警備兵数名、パプアクーリー数十名を加えた大部隊になった。全班のマネージャーを泉靖一氏がつとめ、人類学、民族学的仕事をしてくれた。調査をまがりなりにもすませ帰還したのは六月初めであった。この時集めた資料、標本は国立科学博物館に保管してある。この調査の実態を記録したのは戦後私の還暦記念に出版した「西イリアン記」である。昭和十八年末から十九年になると戦局いよいよ悪く、博物館の仕事も研究も思うようにいかなくなった。発表したものはイヌタムラソウの所属に関するもの(一九四三)と、日本産センブリ属についての一報(一九四四)があるにすぎない。
昭和二十年になると、東京は米機の爆撃にさらされるようになり、さらに本館建物の大部分を軍用に提供せざるを得なくなった。そのため館を一時閉鎖し、動物、植物、地学、理化学の重要資料、標本を職員とともに疎開し、そこで調査研究をつづけることになった(四月)。私は自宅が浦和にあり比較的安全と考えたことと、たまたま坪井館長が心労のため館務をみることがむずかしくなったことから館長の事務を代行しなければならなくなったので疎開せず、数名の職員と本館にとどまり一部の資料標本をまもり、疎開先との連絡にあたることになった。本館の事務館には将校、陳列館には兵隊が居住することになり、焼い弾を落されたとき、本館をまもるためには木造の別館建物を破壊する必要があるとの軍の要請があり、坪井館長もこれをいれざるを得なくなり、とりこわされた。別館にはまだ多くの資料が残されていたが、これを慎重に片付ける時間がなく、兵隊の手でむやみにこわされたので、紛失したり行方不明のものがたくさんあったことは遺憾であった。
希望のない月日が過ぎていった。坪井館長の病気がはかばかしくないので、七月に私が正式に館長代理を命ぜられた。その私も過労と栄養不良から病気になり、八月はじめ肋骨カリエスの診断をうけ、入院手術し、十五日敗戦の日を迎えた。
戦争は終ったが疎開した標本資料と職員が復帰することは、輸送難、食糧難、住宅難のため容易なことではなかった。そのうち、陳列館だけでも年内に再開すべしとの要求が文部省からだされた。おそらくGHQの至上命令であろう。承諾せざるを得ない。職員はぽつぽつ復帰してきたが、別館はこわされ、住む家もない。物置や温室、鳥小屋を改造して住む職員もあった。残った資料標本で開館の準備に忙殺されているうちに、十一月、文部省科学教育局長山崎匡輔氏が館長事務取扱になり、十二月にまがりなりにも開館することができた。予算もなく、資料も不足の混乱時にそこまでこぎつけた苦労は並大抵のものでなかったことは当時の職員でなければわかってもらえないと思う。
昭和二十一年一月、文部省科学教育局長が交代し、清水勤二氏が館長事務取扱になった。しかし、この繁忙な混乱期に、本腰を入れて館務をとる専任館長の必要を希望する声が大きくなり、ジャワから引揚げ文部省嘱託であった東大名誉教授の中井猛之進博士が館長に補せられたのは昭和二十二年九月である。これについて私は植物学界の先輩諸氏とともに努力したが法制局長官の佐藤達夫氏の御尽力も忘れてはならない。中井館長は東京田端の自宅が戦災で焼け、赤羽の陸軍病院におられたが、そのうち館内の一室に居住して、鋭意博物館の復興に専念するようになった。
昭和二十四年五月、文部省設置法が変り、東京科学博物館が廃止、代って国立科学博物館が設置、それまでの職員はそのまま引きつがれた。八月に、館の内部組織が庶務部学芸部の二部制に改正され、学芸部に動物学課、植物学課、地学課、理工学課、普及課、技術課、図書課が属し、私が部長に補せられた。部長としての事務的仕事、各課の調整、館長の補佐、GHQへの書類の提出、会議などに時間をとられ、研究する時間は少なくなった。
そのうち、戦中、戦後とだえていた学会誌も発行されるようになり、昭和十九年一七号をだしたまま中止されていた科学博物館研究報告も昭和二十二年四月に一八号が発行され、二十五年四月に二八号がでるまでになったが紙が粗悪であった。やや見られるような印刷紙になったのは二九号(二十五年十二月)からである。植物研究雑誌が再刊されはじめたのは昭和二十二年で、私はセンブリ属の研究第二報(一九四七)、オウレン属についての研究(一九四九)などを同誌に発表した。
昭和二十六年七~八月、屋久島、種子島の総合研究が実施され、中井館長は自ら現地に出張して指揮をとった。しかしこれが先生の身体に無理をあたえたらしく、翌二十七年夏発病、十二月に惜しくもなくなられた。文部省社会教育局長寺中作雄氏が館長事務取扱になり年はあけたが専任館長はなかなかきまらなかった。
昭和二十八年一月、文部省令がかわり、内部組織が改められ、それまで学芸部に所属していた普及課、技術課、図書課が分離して事業部になり、庶務部、学芸部とともに三部制になった。専任館長の人選については、文部省側と評議員会側との意見が対立し、難航をつづけたが、われわれの希望がかない、動物学者の東大名誉教授岡田要博士が四月、館長に就任した。
昭和二十七年から理工学館設立準備委員会が設けられ、二十八年から建設にかかり、二十九年一月に第一期工事が、三十二年八月に第二期工事が、三十五年三月に第三期工事が竣功した。
昭和二十五年から新潟大学理学部生物学科の臨時講師をたのまれ、七月上旬の一週間、分類学の講義と実験の集中講義を受持ち、野外実習には苗場山に登ることを七年間つづけた。その後、富山大学と広島大学で同じような集中講義を一回ずつ委嘱された。
かねてから学術会議が日本に本格的な自然史博物館を建設することを政府に勧告していたが、政府は、新設は困難だが国立科学博物館を強化拡充することを認めた。昭和三十七年四月、文部省設置法の一部改正と文部省令第九号により、国立科学博物館は自然史に関する研究部門を強化拡充するとともに、自然史関係の資料標本の整備と研究会議の開催などをサービスする研究センターとしての性格をおびる機関になった。
内部組織は四部一四課――すなわち、庶務部(庶務課、会計課、施設課)、事業部(普及課、技術課、図書課)、第一研究部(動物学課、植物学第一課、第二課)、第二研究部(地学課、古生物学課、理化学課、工学課、極地学課)に改められた。また国立自然教育園が付属機関に統合された。このため定員が一〇名増員になり、自然教育園を統合したために、総定員が前年度より三五名増し、予算も前年度の約二倍になった。その後三十八年度に八名、三十九年度に八名、四十年度に六名の研究職が増員になり、科学博物館としてしだいに充実してきた。昭和四十年度に極地課が極地部になり、昭和四十一年度には従来の第一研究部が動物研究部と植物研究部に、第二研究部が地学研究部と理工学研究部になり、研究部門だけで五部一三課になった。博物館全体としては、庶務部(三課)と事業部(三課)を合せて七部一九課に発展したことになる。
▼年次別論文の篇数と頁数 年次 篇数 頁数 1929 3 55 1930 1 8 1931 3 52 1932 2 15 1933 5 128 1934 7 130 1935 1 3 1936 6 123 1937 1 7 1938 4 129 1939 2 12 1940 4 176 1941 2 10 1942 1 10 1943 2 8 1944 1 11 1947 1 9 1949 1 6 1951 1 6 1952 2 10 1955 2 6 1957 2 12 1959 2 41 1960 1 12 1962 2 12 1964 1 15 1965 1 19 1966 4 25 1968 1 4 1970 1 5 1971 3 16 1973 1 4 1974 1 21 1978 1 5 合計 76 1105 昭和四十年五月、理工学館の最終工事が竣功した。もとのプランでは理工学関係の陳列に使う予定であったが、自然史研究センターの機能を果たすために研究職が増員になったため研究室が狭くなったので、新館の三~五階に研究部がはいることになり、地学関係は三階、動物関係は四階、植物関係は五階に移転した(六~七月)。
このように科学博物館は発展し、いよいよこれから内容を充実し仕事にとりくむことになったとき、岡田館長は四十一年六月末に突然退官することになった。後任には、われわれは学者を期待し、一般からもそれが当然と思われたのに、文部省側が強く反対し、評議員会側と意見が合わず、二度も評議員会が開かれたが、ついに、文部省側の無理押しが通ってしまったのは残念であった。
私は、学芸部長から第一研究部長、植物研究部長に転じ植物第一課長を併任してきたが、四十一年秋、研究職の定年制の内規がきまり、満六十四歳になった年度末に退職する(四十一年度から実施し、経過規定は認めない)ことになった。それに従って、四十二年三月末日に退職することになった。
さて、ここで私の研究業績をふりかえってみると、戦前は毎年少なくとも一篇の報告は発表していたが、戦後一〇ケ年は皆無といってよい。これは私の年齢によるおとろえもあるのだが、戦後の混乱期、管理職としての多くの雑務があったことも原因の一つであると思う。
末尾につけた発表論文報告のリストは学術的のものに限り、一頁未満の短いもの、採集記や新産地に関するもの、啓蒙的のものは除いてある。印刷頁の大小、和文、欧文の別なく、同じ題目のものでも三回にわたるものは三篇として、論文の篇数と頁数をあげると別表のようになる。
この表から次のようなことがわかる。一九二九~一九七八年まで五十年間に発表した論文は七六篇、一一〇五頁(和文七六七頁、欧文三三八頁)である。戦前(一九二九~一九四四)一六ケ年に発表したものは四五篇八七七頁(全体の約七九%)であるのに、戦後(一九四五~一九七八)三四ヶ年のものはわずかに二八篇二二八頁(全体の約二一%)である。そして、戦前一六ケ年の四五篇八七七頁のうち一九三三~一九四〇年の八ケ年にその八〇%にあたる三〇篇七〇八頁を発表したことになる。これは私の年齢三一~三十八歳のとき、東京大学理学部植物学科の副手時代にあたることになる。この時代は、責任もなく、雑務もなく、自分の仕事に打ち込めたときであることを思えば、仕事は若いときにしておかなければと痛感する。
(自然科学と博物館 34巻9~10号・一九六七年)
『花のある風景』コンテンツ一覧▼ 目次(青字)をクリックすると、各文をご覧いただけます
〔花の美術館〕カテゴリリンク
- 第19回 小山鐡夫追悼記念号『黒船が持ち帰った植物たち』より
- 第18回 小山鐡夫追悼記念号『植物園の話』より
- 第17回 『MAKINO 80』東京植物同好会・牧野植物同好会八十周年記念誌
- 第16回 ハマナスの語源を探る
- 第15回 金井弘夫追悼記念号『金井弘夫著作集 植物・探検・書評』より
- 第14回 『花のある風景』
- 第13回 坂嵜信之追悼記念号『日本で育つ・熱帯花木植栽事典』より
- 第12回 楽しい花観察108選『不思議な花々のなりたち』
- 第11回 川島榮生の《ヤマアジサイの世界》
- 第10回 渡辺健二『日本産ギボウシの世界』
- 第9回 『ユリノキという木』─ 魅せられた樹の博物誌
- 第8回 『北米インディアン悲詩』/ エドワード・カーティス写真集
- 第7回 江戸時代の花たち 書物に見る江戸時代の園芸文化
- 第6回 わが国初のボタニカルアーティスト 五百城文哉(いおきぶんさい)の世界
- 第5回 『ビル・ニガントゥ』 19世紀末ネパール秘蔵の本草図譜
- 第4回 植物画家 石川美枝子の作品
- 第3回 サイエンティフィック・イラストレーター 木村政司の作品
- 第2回 植物画家 中島睦子の作品
- 第1回 『PLANTAE ASIATICAE RARIORES』