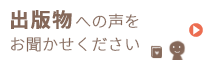- ホーム
- ネイチャーコンテンツ
- Aboc Museum
- 花の美術館
- 第14回『花のある風景』
- 酒と七夕と大名行列
酒と七夕と大名行列
私の郷里は秋田県湯沢市である。古文書によれば、初代義里は佐竹右京太夫源義舜の三子で常陸国太田城を領したが、三代義種の時、慶長七年常陸から秋田に遷封になった佐竹義宣に従って秋田湯沢の地にうつり、以来南家と称して明治維新に至った。私は十九代に当る。
一口に殿様といってもピンからキリまである。私の家などは外様大名の分家であり小禄であるからキリの方である。それが維新の際、勤皇方について朝敵と戦った功により、明治三十三年、私の父義雄の時、華族に列せられ男爵を授けられた。まことに破格の光栄であったと今も郷里の語り草になっている。しかし栄典には浴したものの、財政は豊かでなかったので生活は極めて質素であった。もともとの斜陽族で、大学を出ると自活の道をつけていたから戦後の所謂斜陽族の深刻な気持は味わわなくてすんだ。
さて、郷里を語るとなれば、おくに自慢にならざるを得ないが、酒と七夕祭りと大名行列ぐらいのものであろう。
酒は、「両関」と「爛漫」が割合よく知られている。両関は辛口、爛漫は甘口といわれるが、あまり飲めない私にはどちらに軍配をあげてよいかわからない。
大名行列は、愛宕神社の祭礼当日に行われる。南家は小禄ながら、行列の格式だけは十万石に相当するというのが自慢である。どういう理由で格式が実禄の十倍以上になるのかわからない。行列の人数、服装、持ち物その他、昔をそのまま実現して町中を練り歩く。そして行列の後に、いろいろ趣向をこらした山車が賑やかなおはやし付で色彩を添える。近郷近在から多くの見物人が集まり、一年一度の祝祭日のような気分に浸るのである。
七夕祭り。戸毎に大きな孟宗竹をたて、これに五色の短冊、折紙や紙細工、くす玉などのつくり物を下げ、夜は提灯や大小さまざまの額燈籠をつるして夏の夜を飾る。とくに商店が軒をつらねたメーンストリートはこれらの飾り物でトンネルができる。この七夕祭りは、家中のものが京都奥さんと愛称する奥方が京都からもってきたものであると伝えている。
この京都奥さんというのは、古文書によると、京都五摂家の一つである鷹司家の姫君が南家七代の義安に輿入れした奥方であった。義安は宗家名代として上洛し、正徳元年辛卯二月十五日に参内し、左大臣鷹司兼熈公に謁見し自筆の詠歌を賜った。そして、どういういきさつがあったかわからないがその姫君を娶ることになった。堂上公卿の姫君が僻地の一支族に輿入れするなどは例のないことであった。そこで、姫君はひとまず鷹司家の諸太夫、牧宮内権太夫の養女となり、そこから正徳三年八月に義安に嫁したという。今から二百四十年あまり昔のことである。当時の田舎の人々にとって、清宮さんが島津さんと結婚されること以上に破天荒のニュースだったに違いない。
義安が参内したのは二十歳、結婚したのが二十二歳である。参内したとき見染められて結婚話がもちあがったが、月とスッポンほどちがう当時の身分や家柄のため、話がなかなかまとまらず、二年かかって姫君の思いが達せられた、と想像するのはほほえましい。この京都奥さんは美しく優雅であった上に、七夕祭りその他の行事や、この地方に珍らしい植物を二、三移植したりなどして、庶民から尊敬と人望をあつめたと伝えられている。その植物の一つに檀(まゆみ)があり、今も老木が一本残っているそうだが、私はまだ見ていない。
江戸相撲が湯沢に巡業したとき、奥方が鷹司家の出であるために格式ある御簾をかかげ七本槍を立てて見物したところ、力士は南家の家柄に驚き、直ちに高家御覧の式によって締込みを直して相撲をとったので、家臣も一般見物人も家柄の威力に今更のようにびっくりしたという話も伝わっている。京都奥さんの法号を保寿院殿祝鳳瑞光大姉といい、日善寺という日蓮宗の寺に寺領十石を与えてまつられ、今もその位碑が安置されている。
七夕祭りや愛宕神社の祭礼についで賑うのは浄土寺にある弁天様の祭礼であった。毎年六月十二日がその日に当るが、万延元年の祭りに一事件が持ち上った。門前にかかげた額燈籠にかかれた諷刺画が当局の忌諱にふれたのである。絵は玄人の筆になるので、嫌疑は当時絵師として南家にかかえられていた遠藤昌益にかかった。
昌益を尋問した目付役の記録「遠藤昌益御尋御答書」によってその要領を紹介する。
- 其の方、浄土寺弁天祭礼のとき、燈籠に絵をかいたとのことだが、誰かに頼まれたか或いは自分でかいたのか。
- 講中に頼まれてかきました。
- 趣向も講中からでたのか、其の方が考えたのか。
- 私によい思案がなかったので、浄土寺の長老に何かよい趣向はないかと話しますと、女を尊ぶようなことはどうかと申します。そこへ浄土寺に滞在中の旅僧がきて
という謡がある。この三句の趣意をとりまぜ、趣向よくかいてはどうかと申しますのでかいたのでございます。趣向は旅僧からでました。
- 仏さまより神さまよりもさせる女は有難い/北条家四天王玉門祭/礎は女ですわる娑婆の二字
- その趣向というのは。
- 荒巻内儀を四人の男が拝んでいる図です。
そこで目付は浄土寺の長老を呼びだし、旅僧のことを尋ねると、昌益に絵を頼んだが趣向に困っているので来合せた旅僧に相談したら、この節は女を大切にするようだからこれを趣向にしたらどうかというので、その趣向でかくように昌益に頼んだと答えた。しかし旅僧など講中のもの誰も見たものがない。
食事その他の取扱いはどうしたと更に尋ねると、二階にかくまっていたから人目につかなかったし、食事は人目のあるときは奥座敷でさせ、人目のないときは下人と旅僧と三人でとった。手水は外便所を使わせた、と答えた。
そこで浄土寺の下人末松を呼びだして取調べると、大体は長老の陳述と一致し、風態はと尋ねられると、年齢三十四、五歳、衣服は白と浅黄色、衣は紺黒色、荷物は風呂敷ばかりで、月代は十日ぐらいもそらなかったと答えた。
その後だんだん吟味してみると、旅僧は架空の人物であることが推定されるので、右三名を呼びだして再三尋問すると遂に白状に及んだ。昌益と長老が旅僧をでっちあげ、末松は口止めされたということになった。
趣向の出所は昌益と長老がなすり合ったが結局昌益の仕業と断定され、直ちに自宅に監禁されたが、その夜見張りの隙をねらって逐電して、行方不明、この事件は落着した。
さて問題になった燈寵の絵はといえば、三つの謡文句から何となくエロ的なものを匂わせるが、「女の立姿をかいた掛物を床の間にかけ、男四人が拝んでいる所を他の男達が指さして笑っている」まことに変哲もない趣向である。しかしその女が荒巻の内儀糸子を暗示したことに問題があったのである。
糸子は、南家十五代義孟の子、静姫と義誠の養育係りをつとめ、時の家老荒巻十蔵の後妻になった女である。当時二年間もつづいた家老間の勢力争いを押えてしまったなかなかの女丈夫で、南家の政岡といわれ大いに幅をきかしたので、家中の人々は家老のだらしなさをあざわらい、女ならでは夜もあけぬと噂した。昌益はこれを世に知らせようと、祭りの夜の燈籠を利用したというわけだ。
男女同権の今の御時世でも、女性の権力と教養には揶揄と嘲笑がつきものだが、まして封建時代のこと、家中のお歴々を平伏させた女傑に対する男どもの反感を昌益が代表したものであろう。
事件の主謀者が絵師と坊主であったが故に記録されない何かを想像してもみるのである。
(サンケイ随筆 新年号・一九六〇年)
『花のある風景』コンテンツ一覧▼ 目次(青字)をクリックすると、各文をご覧いただけます
〔花の美術館〕カテゴリリンク
- 第19回 小山鐡夫追悼記念号『黒船が持ち帰った植物たち』より
- 第18回 小山鐡夫追悼記念号『植物園の話』より
- 第17回 『MAKINO 80』東京植物同好会・牧野植物同好会八十周年記念誌
- 第16回 ハマナスの語源を探る
- 第15回 金井弘夫追悼記念号『金井弘夫著作集 植物・探検・書評』より
- 第14回 『花のある風景』
- 第13回 坂嵜信之追悼記念号『日本で育つ・熱帯花木植栽事典』より
- 第12回 楽しい花観察108選『不思議な花々のなりたち』
- 第11回 川島榮生の《ヤマアジサイの世界》
- 第10回 渡辺健二『日本産ギボウシの世界』
- 第9回 『ユリノキという木』─ 魅せられた樹の博物誌
- 第8回 『北米インディアン悲詩』/ エドワード・カーティス写真集
- 第7回 江戸時代の花たち 書物に見る江戸時代の園芸文化
- 第6回 わが国初のボタニカルアーティスト 五百城文哉(いおきぶんさい)の世界
- 第5回 『ビル・ニガントゥ』 19世紀末ネパール秘蔵の本草図譜
- 第4回 植物画家 石川美枝子の作品
- 第3回 サイエンティフィック・イラストレーター 木村政司の作品
- 第2回 植物画家 中島睦子の作品
- 第1回 『PLANTAE ASIATICAE RARIORES』