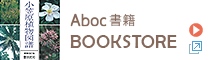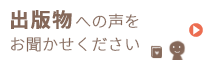- ホーム
- ネイチャーコンテンツ
- Aboc Museum
- 花の美術館
- 第19回 『黒船が持ち帰った植物たち』
- 1. 黒船による日本及びその付近での植物採集
- 2. 東アジアと北アメリカの間の植物の隔離分布について
2. 東アジアと北アメリカの間の植物の隔離分布について
日本を中心とするアジアの極東地方の植物が,12,000km以上も離れた北アメリカの東北部の植物に極めて似ているという驚くべき事実を最初に発見したのが,ハーバード大学の教授であったエイサ・グレイ(Prof. Asa Gray)で,同教授は1846年の報文で初めてこの特異な種子植物の隔離分布について言及し,その後,黒船が採集した多数の日本の植物の詳細な研究をして,第2報を1859年に発表したが,同氏が挙げたこの一群の植物は40属,580種余りにのぼる.グレイ教授の時代には植物の類縁をより正確に示す染色体のデータもなく,また,分布域の地史的変遷を示す植物化石のデータにも乏しかったので,主として外部形態によって,研究がなされた.その後,Fernald,Hultén,Li,Haraを含む数多くの学者がこの興味深い課題を研究し,現在は東亜と北米との間に隔離分布をする一群の植物は「古第三紀要素の植物」と呼ばれ,その分布型,類縁関係,さらにその奇妙な不連続分布域の生因等が,およそ以下のように徐々に解明されてきている.
『黒船が持ち帰った植物たち』コンテンツ一覧▼ 目次(青字)をクリックすると、各文をご覧いただけます
発刊に寄せて
刊行にあたって
はしがき
1.黒船による日本及びその付近での植物採集
何時,何処で,誰が?
エイサ・グレイ教授の研究
昭和天皇による黒船採集植物の御研究
Plant collecting in Japan and its adjoining territories by the Black Ships (Abstract)
2.東アジアと北アメリカの間の植物の隔離分布について
東亜と北米の間の植物の不連続分布の4型
東亜・北米間の隔離分布の由来
東亜と北米の間で隔離分布する植物の生態
隔離分布している植物の分化
Disjunct distribution of flowering plants between eastern Asia and North America (A summary account)
3.米国北太平洋探検隊採集の日本植物の図録
An annotated catalogue of plant specimens collected in Japan by the U. S. North Pacific Exploring Expeditions(1853-1855), based mainly on the set housed in The New York Botanical Garden, U.S.A.
Ⅰタイプ標本 (Type materials)
Ⅱ琉球列島 (The Ryukyus)
Ⅲ九州 (Kyushu)
Ⅳ小笠原 (The Bonin Isls.)
V下田・横浜 (Shimoda and Yokohama)
VI北海道とその周辺 (Hokkaido and its surrounding regions)
書籍詳細
-
小山鐵夫 著 B5判 / 上製 / 98頁(オールカラー) /
定価1,572円(本体1,429+税)/ ISBN4-900358-41-X
〔花の美術館〕カテゴリリンク
- 第19回 小山鐡夫追悼記念号『黒船が持ち帰った植物たち』より
- 第18回 小山鐡夫追悼記念号『植物園の話』より
- 第17回 『MAKINO 80』東京植物同好会・牧野植物同好会八十周年記念誌
- 第16回 ハマナスの語源を探る
- 第15回 金井弘夫追悼記念号『金井弘夫著作集 植物・探検・書評』より
- 第14回 『花のある風景』
- 第13回 坂嵜信之追悼記念号『日本で育つ・熱帯花木植栽事典』より
- 第12回 楽しい花観察108選『不思議な花々のなりたち』
- 第11回 川島榮生の《ヤマアジサイの世界》
- 第10回 渡辺健二『日本産ギボウシの世界』
- 第9回 『ユリノキという木』─ 魅せられた樹の博物誌
- 第8回 『北米インディアン悲詩』/ エドワード・カーティス写真集
- 第7回 江戸時代の花たち 書物に見る江戸時代の園芸文化
- 第6回 わが国初のボタニカルアーティスト 五百城文哉(いおきぶんさい)の世界
- 第5回 『ビル・ニガントゥ』 19世紀末ネパール秘蔵の本草図譜
- 第4回 植物画家 石川美枝子の作品
- 第3回 サイエンティフィック・イラストレーター 木村政司の作品
- 第2回 植物画家 中島睦子の作品
- 第1回 『PLANTAE ASIATICAE RARIORES』