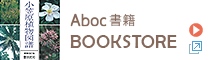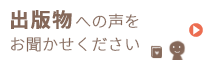- ホーム
- ネイチャーコンテンツ
- Aboc Museum
- 花の美術館
- 第19回 『黒船が持ち帰った植物たち』
- 1. 黒船による日本及びその付近での植物採集
- 2. 東アジアと北アメリカの間の植物の隔離分布について
- 東亜と北米の間で隔離分布する植物の生態
東亜と北米の間で隔離分布する植物の生態
前節に挙げた植物名から推察できるように,古第三紀要素の植物の大部分は温帯の落葉広葉樹林を構成している樹種と,その林の林床に生えている草本である.それらの一部は,しかしながら,温帯落葉樹林の上部から亜寒帯針葉樹林の部分にまたがって生える,例えばオウレン属の植物とかイネ科のフォーリーガヤがこの例である.その更に上部に見られる植物も少数あり,好例がホスゲやミタケスゲである.他の一部は,温帯林の下部から暖帯林にもあり,アジアではいわゆる照葉樹林の構成植物となっている例もある.例えばクロモジ属,モクレン属の常緑性の樹種,シキミ属,ナベワリ属等が暖帯林の構成植物である.森林植生でない湿地等にも古第三紀要素と思われる分布型の植物が見られる.前節で第4群とした沼地生植物のウキヤガラとかイネ科のカズノコグサ,マコモ属植物等がその例である.
古第三紀植物群の主体が生育している温帯広葉落葉樹林は生態的に大変興味深い植生である.なぜというと,この植生には四季の変化が明瞭に見られるという点である.温帯落葉樹林の早春は木の葉がまだ開出していない時期で,カエデ属,ブナ属,ハンノキ属等では葉の無い枝に特有の形の花が咲いているが,この頃は春の日差しが大量に林床まで届くのである.その春の日差しを受けて,ザゼンソウ,カタクリ,スミレ,アマドコロ,エンレイソウ属等の植物が開花する.これら,春に落葉樹林中で開花する春植物―いわゆるspring flora―は,その後急速に物質生産を行い,樹林の葉が成長し切って,林内に届く日差しが少なくなる初夏にはすでに茎葉等地上部が枯れて,種子を落とし,翌春までの休眠状態に入ってしまうものがほとんどである.夏期には落葉樹林の高木の葉が繁って,その樹冠が日差しを遮るため,林床は暗くなる.その暗い林床にはミツバ,ハエドクソウ,ミズヒキ,ミズタマソウ,ノブキ等の陰生植物が生育し,夏に花を咲かせて,秋に種子を落とす.これらと共に,春植物の中で常緑性の葉を持つスハマソウ,ショウジョウバカマ,フッキソウ等も夏の暗い林下で物質生産を続けている.秋になると落葉樹の葉は黄色,紅色,褐色等に変わるので―紅葉―秋の落葉広葉樹林は多彩な秋色となるのであるが,日本の温帯林の中には常緑性の針葉樹のほかに,アセビ,アオキ等の常緑植物も混じるため,紅,黄,緑等が混じった色となるが,北米のこの種の林には,所によってツガ属等の少数の常緑針葉樹が点在するのみなので,緑色がほとんどない,いわゆる,燃えるような秋色となる.ヨーロッパの林の秋色はブナやシナノキ等の黄色が勝っている.

- ブナ、カエデ、ハンノキ類中心の落葉樹林の秋。多少の針葉樹も見える。ヴァーモンド州で。
- An example of forest in northern New York State. Here we can see a few needle-leaved trees mixed with birches, beeches and maples.
『黒船が持ち帰った植物たち』コンテンツ一覧▼ 目次(青字)をクリックすると、各文をご覧いただけます
発刊に寄せて
刊行にあたって
はしがき
1.黒船による日本及びその付近での植物採集
何時,何処で,誰が?
エイサ・グレイ教授の研究
昭和天皇による黒船採集植物の御研究
Plant collecting in Japan and its adjoining territories by the Black Ships (Abstract)
2.東アジアと北アメリカの間の植物の隔離分布について
東亜と北米の間の植物の不連続分布の4型
東亜・北米間の隔離分布の由来
東亜と北米の間で隔離分布する植物の生態
隔離分布している植物の分化
Disjunct distribution of flowering plants between eastern Asia and North America (A summary account)
3.米国北太平洋探検隊採集の日本植物の図録
An annotated catalogue of plant specimens collected in Japan by the U. S. North Pacific Exploring Expeditions(1853-1855), based mainly on the set housed in The New York Botanical Garden, U.S.A.
Ⅰタイプ標本 (Type materials)
Ⅱ琉球列島 (The Ryukyus)
Ⅲ九州 (Kyushu)
Ⅳ小笠原 (The Bonin Isls.)
V下田・横浜 (Shimoda and Yokohama)
VI北海道とその周辺 (Hokkaido and its surrounding regions)
書籍詳細
-
小山鐵夫 著 B5判 / 上製 / 98頁(オールカラー) /
定価1,572円(本体1,429+税)/ ISBN4-900358-41-X
〔花の美術館〕カテゴリリンク
- 第19回 小山鐡夫追悼記念号『黒船が持ち帰った植物たち』より
- 第18回 小山鐡夫追悼記念号『植物園の話』より
- 第17回 『MAKINO 80』東京植物同好会・牧野植物同好会八十周年記念誌
- 第16回 ハマナスの語源を探る
- 第15回 金井弘夫追悼記念号『金井弘夫著作集 植物・探検・書評』より
- 第14回 『花のある風景』
- 第13回 坂嵜信之追悼記念号『日本で育つ・熱帯花木植栽事典』より
- 第12回 楽しい花観察108選『不思議な花々のなりたち』
- 第11回 川島榮生の《ヤマアジサイの世界》
- 第10回 渡辺健二『日本産ギボウシの世界』
- 第9回 『ユリノキという木』─ 魅せられた樹の博物誌
- 第8回 『北米インディアン悲詩』/ エドワード・カーティス写真集
- 第7回 江戸時代の花たち 書物に見る江戸時代の園芸文化
- 第6回 わが国初のボタニカルアーティスト 五百城文哉(いおきぶんさい)の世界
- 第5回 『ビル・ニガントゥ』 19世紀末ネパール秘蔵の本草図譜
- 第4回 植物画家 石川美枝子の作品
- 第3回 サイエンティフィック・イラストレーター 木村政司の作品
- 第2回 植物画家 中島睦子の作品
- 第1回 『PLANTAE ASIATICAE RARIORES』