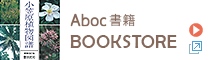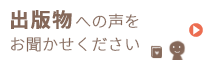隔離分布している植物の分化
植物は生育する環境の変化に適応して形質を変えて行くが,これらの古第三紀要素の植物群も,特に氷河期に何回にもわたる南下と北上の時に,形質の変化をして,それぞれの地域の形に分化したと推定されている.植物の形質の変化の速度,大きさ等は植物の種類によって異なる.全く様々である.形質の変化は,外部形態の変化―形が変わる―として現れる場合が多いが,時には生理的な変化,例えば耐冷性,耐暑性等,また,染色体の変化のみにとどまり,外部形態がそれ程顕著に変わらない場合等,また逆に外部形態に変化が起きても染色体には見える変化がない事もある.
東亜と北米の間の不連続分布に見られる植物の形態的な分化では,最も多い例が,東亜と北米の間で種のレベルでの違いが認められる分化である.つまり,東亜と北米に同じ属が隔離して分布し,両方の分布域にある種が異なる場合である.前に述べた例の中で,オウレン属,チョウセンニンジン属,ハリブキ属,ツバメオモト属,ブナ属等,皆このカテゴリーの大陸間での種の分化をしている.
多少専門的な話になるが,ここで,例えばオウレン属のオウレン(東亜)に対するCoptis asplenifolia(北米西北部)や,オタネニンジン(東亜)に対するPanax quinquefolius(北米東部)を,それぞれオウレンやオタネニンジンの北米代替種(対応種)(vicariads)というが,この場合,これ等2つの代替種はそれぞれ第三紀の同一祖先に由来して,それから分化した一元的なものであるという推測に基づいている.東亜と北米の間での代替種と目されている非常に似通った2種といえども,第三紀にやはり似通った別の2つの祖先があって,そういう似た2種に由来しているという可能性も無論ある.この後者の場合,対応する2つの種は,植物地理学では偽代替種(pseudo-vicariads)と呼んでいる.対応する一組の植物が本当の代替植物か偽代替植物かを検定する研究は,染色体やDNA,化学分類等の解析により行う事ができるが,興味深く応用性のある研究である.
それより両大陸間で形態分化が少ない例では,東亜と北米の植物が同一種と見なされる例で,例えばザゼンソウ,ミツバ,ハエドクソウ,ムツオレグサ,ウキヤガラ等,多くの植物が挙げられる.これら,東亜と北米の間で種のレベルで同一の植物でも,種内での分化は見られるのが普通である.例えば,ザゼンソウの場合,北米のザゼンソウには強い悪臭があるので現地ではスカンク・キャベツ(skunk cabbage)とも呼ばれる程であるが,日本のザゼンソウにはそういう強い悪臭はない.仏焰苞も,北米のものでは,内側へより強く巻き込んで,中の肉穂が見えにくいが,日本のものでは仏焰苞は大きく開き,中の肉穂は外から良く見える.しかし,葉で両者を区別する事は不可能である.ハエドクソウでは北米の植物が花が僅かに大形で,萼に多少毛が多い位の差である.ミツバではアメリカの母種では茎の下部の葉の小葉に短い柄があるが,他は東亜のものと北米のものでは形態的に大同小異であり,北米のミツバには日本人の好むあの芳香がない.

- 日本のザゼンソウ(左)は北米のスカンク・キャベツ(skunk cabbage)の変種になっている。極めて良く似ていて、北米のスカンク・キャベツでは開花期に仏炎苞がザゼンソウのそれのように広く開かない位の違いしかない。
- Japanese Zazenso (Symplocarpus foetidus var. latissimus) is a variety of American Skunk Cabbage (S. foetidus var. foetidus). They are essentially the same except for the spathe of Japanese var. latissimus, which are more widely open during the anthesis than in those of the latter.
染色体についていうと,チョウセンニンジン属では,トチバニンジン,オタネニンジン,アメリカニンジンの3種全部が2n=48本と,同数の染色体を持ち,ハエドクソウも日本・アメリカ両方の植物で2n=28本,ミツバも日本,北米の植物共々2n=20本または22本で染色体は同数である.ザゼンソウでは日本のザゼンソウで2n=30本,アメリカのスカンク・キャベツでは2n=60本と染色体数の倍加が見られる.私共が研究したイネ科植物の中では,ムツオレグサの例で,日本のムツオレグサは2倍体で2n=20本の染色体を,北米のssp. acutifloraは4倍体で2n=40本の染色体を持つ.両者の間の外部形態は極めて似ており,日本のムツオレグサの葯が長い他は,両者間の僅かな差はイネ科の専門家の間でないとわからない程である.逆にコウヤザサの例では,日本のコウヤザサは北米の母種より小花がかなり小さいので比較的明らかに区別できるが,染色体は日本・北米の植物ともに2n=22本で数の変化はない.このように植物の分化は種によってそれぞれ異なり,外部形態と染色体の違いとは必ずしも呼応しておらず,一定していない.
東亜と北米の対応植物の中で,種の段階より更に大きな分化をして,似通った2つの属が対応している例も多く見られる.日本のホツツジには花弁が3枚あり,それに対応する北米東部のElliottia属では花弁は4枚とはっきり異なる.また,日本のショウジョウバカマ属とその北米の対応属のHeloniasでは,花の小苞が顕著か不顕著かという程度の差にすぎない.
東亜と北米の間の植物の分化についてはこれから研究すべき事も多々残っている.例えば東亜と北米の間で種が同じと見なされている植物の間で,人工的な交雑実験をして,数千万年の間隔離された現在でも,両者の間に和合性があるか否かを調査した例もまだ極めて寡いようである.応用上は,例えば,東亜と北米にある薬用植物の対応種での化学分析の比較をすると,将来の薬品改良開発に興味あるデータがでるかも知れない(Koyama1988).
『黒船が持ち帰った植物たち』コンテンツ一覧▼ 目次(青字)をクリックすると、各文をご覧いただけます
発刊に寄せて
刊行にあたって
はしがき
1.黒船による日本及びその付近での植物採集
何時,何処で,誰が?
エイサ・グレイ教授の研究
昭和天皇による黒船採集植物の御研究
Plant collecting in Japan and its adjoining territories by the Black Ships (Abstract)
2.東アジアと北アメリカの間の植物の隔離分布について
東亜と北米の間の植物の不連続分布の4型
東亜・北米間の隔離分布の由来
東亜と北米の間で隔離分布する植物の生態
隔離分布している植物の分化
Disjunct distribution of flowering plants between eastern Asia and North America (A summary account)
3.米国北太平洋探検隊採集の日本植物の図録
An annotated catalogue of plant specimens collected in Japan by the U. S. North Pacific Exploring Expeditions(1853-1855), based mainly on the set housed in The New York Botanical Garden, U.S.A.
Ⅰタイプ標本 (Type materials)
Ⅱ琉球列島 (The Ryukyus)
Ⅲ九州 (Kyushu)
Ⅳ小笠原 (The Bonin Isls.)
V下田・横浜 (Shimoda and Yokohama)
VI北海道とその周辺 (Hokkaido and its surrounding regions)
書籍詳細
-
小山鐵夫 著 B5判 / 上製 / 98頁(オールカラー) /
定価1,572円(本体1,429+税)/ ISBN4-900358-41-X
〔花の美術館〕カテゴリリンク
- 第19回 小山鐡夫追悼記念号『黒船が持ち帰った植物たち』より
- 第18回 小山鐡夫追悼記念号『植物園の話』より
- 第17回 『MAKINO 80』東京植物同好会・牧野植物同好会八十周年記念誌
- 第16回 ハマナスの語源を探る
- 第15回 金井弘夫追悼記念号『金井弘夫著作集 植物・探検・書評』より
- 第14回 『花のある風景』
- 第13回 坂嵜信之追悼記念号『日本で育つ・熱帯花木植栽事典』より
- 第12回 楽しい花観察108選『不思議な花々のなりたち』
- 第11回 川島榮生の《ヤマアジサイの世界》
- 第10回 渡辺健二『日本産ギボウシの世界』
- 第9回 『ユリノキという木』─ 魅せられた樹の博物誌
- 第8回 『北米インディアン悲詩』/ エドワード・カーティス写真集
- 第7回 江戸時代の花たち 書物に見る江戸時代の園芸文化
- 第6回 わが国初のボタニカルアーティスト 五百城文哉(いおきぶんさい)の世界
- 第5回 『ビル・ニガントゥ』 19世紀末ネパール秘蔵の本草図譜
- 第4回 植物画家 石川美枝子の作品
- 第3回 サイエンティフィック・イラストレーター 木村政司の作品
- 第2回 植物画家 中島睦子の作品
- 第1回 『PLANTAE ASIATICAE RARIORES』