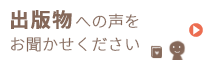- ホーム
- ネイチャーコンテンツ
- Aboc Museum
- 植物名入門
- 福屋 正修
- 植物名学入門
植物名学入門
1.名は根

ナズナ
春の七草のひとつとして若葉を食べる。
ペンペングサともいう。
ぺんぺんとは三味線の音を表す。
果実の形が三味線の撥に似ているから。
やまとことば(日本語の祖語)では、「菜っ葉」の「な」は、「根」の転化したものである[日本国語大辞典]。「名前」の「な」も、「菜」と同じく、「根」から来ている(語源の辞典には、そうは書かれていないが)。「名」は、根をもつもの、根ざしているものの意であったろう。英語に訳せば、enrootedといえようか。
「名」が「根」とは、どういうことか。それは、世界(あるいは場・身の周り)に根を下ろしている、あるいは、世界(場)から生えているということである。例えば、ヒト。ヒトの一人一人は、世界(あるいは場)に根を下ろしている、あるいは、世界(場)に生えているということだ。世界に埋まっているといってもよい。遥かな昔、ヒトは、自らを含め、あらゆるものは、世界に根ざしているというように、世界を理解していた。
「菜っ葉」の「な」は、すべて可食であるという。今日、食用にしていなくとも。例えば、ナズナとか。なぜなら、さもありなん、上代の人々が、生命を、生きているということを、流れに生じたうずのように理解していたからに他ならない。世界は、流れ・うず、すなわち、流体として理解されていたのであった。
2.名前とは何だろう

マンドレーク(Mandragora officinarum)
ナス科。根に薬用・有毒成分。
引き抜くときに鋭い叫び声をあげ、耳が聞こえなくなると伝えられた。
画:フックスの『新植物誌』(1543年)より。-本文と特に関連はありません-
名をつける、名を呼ぶ、発声ということは、それが根ざしている世界から引っこ抜くということであるから、あな、おそろしや。名を呼ぶ、名を声に出すには、慎重が上にも慎重でなければならぬ、上代の人々は、お喋りではなかったろう。口から出る言葉は、まこと(真事・真言。新撰組の誠ではない!)でなければならなかった。
女は、まことの名のほかに、通称を持つのが常であった。男に名を知られようものならどうしようもなくもなく、その男のものになってしまうから。時代下って武士の時代、合戦に際して「やぁやぁ我こそは」と名乗りをあげるのは、たんに氏素姓を明らかにするだけではない、名は生命そのものであった。呪いをかけられてしまうかもしれない。名を明らかにして戦うのは裸で命をさらすようなものであったろう。勇気のいることであった。
世界から言語に引っこ抜かれた根、それが名であった。そのワケは、ヒトが言葉を話す動物だから。言語による世界の理解は、まず名(文法上では名詞)から始まる。
「これは何と言う植物?」と、気安く植物の名前を訊くことが多い。が、その前に、慎み深くありたい。ともかく、プロに対しては、まず敬意を表するべきと思う。
3.忘れてしまった世界観

セイヨウトネリコ
J. E. スミス著/J. サワビー原画
『英国植物誌』(第1692図;1807年)より
北欧神話のイグドラシルのモデル。
ヨーロッパ世界で巨木に成長する落葉樹のひとつとして有名。
高さ40mにもなる堂々たる樹木で、材にはさまざまな用途がある。
世界から名(根)を引っこ抜く際に、ヒトの民族の世界観が顕になる。スワヒリ語の名詞分類には、樹木類がある。フランス語を習うと、名詞には、男性、女性、中性があると教わる。が、歴史的に考えれば、文法が先にあったのではない。世界の理解の仕方、世界観があって、しかる後に、文法が生じた。それが、男であるか、女であるか、はたまた、男でも女でもないものか、そのようなうず世界があった、そしてヒトうず集団が共有していたということだ。
それは、原初のホモサピエンスの頃、十五万年前、あるいは、はるかそれ以前のこと、言語の始まりとともにあった。が、今日では、このような世界観、ものの考え方は、ほとんど忘れてしまったかのようだ。
存在を世界に根ざしているものと理解していたのは、古来、ヒトに共通している。言語による伝承ばかりでない。遺物、絵画に。北欧神話のイグドラシルの木(図;Googleイメージ検索でイグドラシル参照)を見よ。フランス語デラシネ(déraciné。racinéは根の意;英語ではuprooted)は、現代文学では、国・故郷を喪失した人・根無し草の意でよく用いられるが、元来は、根こぎにされた植物ということであり、人間は国・故郷に根ざしているものなのだ。
4.名前なしの世界


左:ナツミカンの園芸品種‘川野ナツダイダイ’(いわゆる甘夏)
右:森林のグランドマスター
(インドに棲息する猿の一種のようです)
名前は「知識の広範な伝達」に必要となるらしい。「森林のグランドマスター」では、ヒトが この猿についての知識を伝達することはむずかしい。 だが、この猿が生きていくにあたって、地球の裏側に棲む別の猿に、自分のことを伝える必要はまずないだろう。
ヒト以外の生物は、名前なしに、ヒトのような言語なしでいきている。
名前なし、言語なしでいきるとは、いったいどういう世界か?
まだことばをしゃべれない赤ちゃんみたいなものか? 思い出そうとしても思い出せない。ともかく親の全面的保護なしには生きられない。
あるいは、男女が同衾している時みたいなものか? 世界中、いろんな人がいるが、この時、ヒトは、あまりしゃべらないようだ。阿久悠詞の歌謡曲に「…… ふたりで名前消して その時心は何かを話すだろう」とあった。が、凡河内躬恒の歌には「むつ事もまだつきなくに明けぬめり……」とある。昔はおしゃべりだったのか?
生命体がいきるには、世界(場・身の周り)の理解が不可欠である。言語を用いるヒトの方が例外なのだ。植物には、脳も神経系もない。植物の個体間にも、電磁波とか媒体によるコミュニケーションがある、情報交換しているとも考えられるが、観測されていないようだ。
おそらく植物は世界(自分の身の周りのこと)を、流れのうずそのままにいきているのだ。科学では理解を、反射とか反応とか称しているが。近代のヒトのような「主体・客体、そして個性とか、自立した個人」などない、それが普通の生命の世界だ。
5.松の語源


左:ゴヨウマツ
右:クロマツ
「まつ」の語源には、諸説*があるが、私は、「まつ」は、「目立つ」の意ではないかと思う。「ま」は、「まなこ」の「ま」。少なくとも「ま」は、目であるような気がしてならない。
アカマツ、クロマツなど松の自然樹形は、 いずれも堂々たる姿だ。清少納言は「マツは五」という。これはゴヨウマツのことだが、いったい彼女はどんなゴヨウマツを見ていたのだろうか。
松の生き残り戦略や生態を考えると、松は純林や一斉林は形成しない。原初の日本列島では、鬱蒼たる照葉樹林にぽつぽつと突き出ていたはずだ。この原初の樹林のようすを、海から、あるいは見通しの利くところから遠望して、ヒトの発したやまとことばが「目立つ」木、すなわち「まつ」だったのではないだろうか。
今日ある語源の諸説は、文献によるものや文化系の発想によるものが多い。やまとことばの語源が考証されるようになったのは、江戸時代、加茂真淵などのいわゆる国学が興ってからだ。江戸時代にはすでに30メートル級の松の大木が照葉樹林から突き出している景観はみられなかった。彼らからはこのように原初のマツの姿を想像して語源を考えるという発想は、生まれなかったのだろう。
*四季にわたって色褪せないマツは常盤木(ときわぎ)として神聖視されていたことから、神が降臨するのを「マツ(待つ)」とする説、長寿の木であるところから「モツ(保つ)」の変化形とする説、行く末を待つ意味の「待つ」とする説、葉が葉元から二ないし五筋に分かれているので「マタ(股)」を語源とする説など。他にも多くの説がある。
〔植物名入門〕各著者(50音順)プロフィールとこれまでのエッセイ
芦田 潔(社団法人日本おもと協会理事)
プロフィール伝統園芸植物「オモト」の銘を考える
岩佐 吉純(岩佐園芸研究室主宰)
プロフィール園芸植物の命名考
荻巣 樹徳(ナチュラリスト):準備中
乙益 正隆(ナチュラリスト・植物方言研究家)
プロフィール植物方言採集秘話
金井 弘夫(国立科学博物館名誉館員)
プロフィール植物の名前を考える
管野 邦夫(仙台市野草園名誉園長)
プロフィール花の名前にご用心
北山 武征(財団法人公園緑地管理財団副理事長)
プロフィール緑・花試験うらばなし
許田 倉園(元:玉川大学教授)
プロフィール植物名に現れた台湾の固有名詞
佐竹 元吉(お茶の水女子大学 生活環境研究センター)
プロフィール生薬名の混乱
下園 文雄(元:小石川植物園)
プロフィール小石川植物園に渡来した植物たち
辻井 達一(北海道環境財団理事長)
プロフィールアイヌ語起源の植物名
豊田 武司(小笠原野生生物研究会)
プロフィール小笠原の植物
中村 恒雄(造園植物研究家)
プロフィール園芸樹木の変わりものたち
藤本 時男(編集者・翻訳家)
プロフィール「聖書の植物」名称翻訳考
三上 常夫(編集者・翻訳家)
プロフィール造園植物の名前の混乱
水野 瑞夫(岐阜薬科大学名誉教授):準備中
山本 紀久(ランドスケープアーキテクト)
プロフィール実と名が違う造園植物