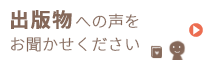- ホーム
- ネイチャーコンテンツ
- Aboc Museum
- 花の美術館
- 第12回 楽しい花観察108選『不思議な花々のなりたち』
- 第二章 種子の不思議
第二章 種子の不思議
第二七話 実生のはなし
小さな種子のエネルギー
〝じっせい〟ではなく〝みしょう〟と読む
実生を「じっせい」と読んでは間違い。「みしょう」が正しく、実(種子)が芽生えることを意味する。最も基本的な園芸用語の一つ。
ぽかぽか陽気の春。地温が上昇し、適度の湿気があり、酸素の供給があれば、たいていの種子は上をもたげてむくむくと芽生えてくれる。上の表面にかすかに亀裂が入り、芽の先がちらっと顔をのぞかせるのを発見したときの感動はなんともいいようがないほどだ。反対に、待てど暮らせど芽が出てこないこともある。種子の中には種皮の硬いもの、不捻(ふねん)のものなどのほか、眠りっ放しのものがあるからだ。
一般に、種子は、成熟すると水分を必要最小限にして休眠にはいる。そして、春になり、温度、湿度、酸素などの諸条件がそろうと発芽する。条件が欠けると眠ったままだ。地中深く千年も眠っていたというハスの種子が、人為的ではあるが、ある日突然目を覚まして芽生えたという話は、世界中の人々を驚かせた。
芽生えの姿にもいろいろある。発芽して最初に出る子葉が2枚あるものを双子葉類。1枚のものを単子葉類という。前者は桜、パンジーなど身近な木や草花に多い。後者は稲、麦、ユリ、ヤシなど、どれも生活にかかわりが深い。マツ類やクルミ類のように、多子葉の特別なグループもある。
種子の内部での動き始めは、無気呼吸。そして皮を破る。芽生えてからは酸素呼吸で生長する。しかも子葉の次に出てくる本葉は、葉緑素、水、光を要素に、空気中の炭酸ガスを加え、同化作用を営み、栄養を作る。その際放出する酸素が、人間を含めた動物が生きるために不可欠なものであることは言うまでもない。その意味でも、植物の芽生えの大切さを再認識してほしい。小さな種子の中に大きなエネルギーが内蔵されているという生命のロマンにも敬意を払って欲しい。また無限の可能性が秘められ、将来的には、生長、開花、結実が約束されていることも。
書籍詳細
-
川上幸男 著 B6変型判 / 並製 / 301頁 / 定価1362円(本体1,238+税)/
ISBN4-900358-40-1
〔花の美術館〕カテゴリリンク
- 第20回 『熱帯植物巡礼』
- 第19回 小山鐡夫追悼記念号『黒船が持ち帰った植物たち』より
- 第18回 小山鐡夫追悼記念号『植物園の話』より
- 第17回 『MAKINO 80』東京植物同好会・牧野植物同好会八十周年記念誌
- 第16回 ハマナスの語源を探る
- 第15回 金井弘夫追悼記念号『金井弘夫著作集 植物・探検・書評』より
- 第14回 『花のある風景』
- 第13回 坂嵜信之追悼記念号『日本で育つ・熱帯花木植栽事典』より
- 第12回 楽しい花観察108選『不思議な花々のなりたち』
- 第11回 川島榮生の《ヤマアジサイの世界》
- 第10回 渡辺健二『日本産ギボウシの世界』
- 第9回 『ユリノキという木』─ 魅せられた樹の博物誌
- 第8回 『北米インディアン悲詩』/ エドワード・カーティス写真集
- 第7回 江戸時代の花たち 書物に見る江戸時代の園芸文化
- 第6回 わが国初のボタニカルアーティスト 五百城文哉(いおきぶんさい)の世界
- 第5回 『ビル・ニガントゥ』 19世紀末ネパール秘蔵の本草図譜
- 第4回 植物画家 石川美枝子の作品
- 第3回 サイエンティフィック・イラストレーター 木村政司の作品
- 第2回 植物画家 中島睦子の作品
- 第1回 『PLANTAE ASIATICAE RARIORES』