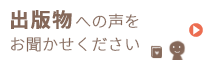- ホーム
- ネイチャーコンテンツ
- 自然史系書籍
- 北米インディアン悲詩 /1898~1928 エドワード・カーティス写真集
北米インディアン悲詩 /1898~1928 エドワード・カーティス写真集
-
2012年1月2日 BSフジ『Earth Walker』放映
当社追跡本のひとつ。滅びゆくネイティブ・アメリカンを活写した前世紀最期の写真集。Curtis『The North American Indian』全24巻よりジェ ロニモはじめ名高い戦士の肖像など105枚、本邦初公開・インディアン年譜・口承文学から20編の詩と説話を収載。当社が原書入手・企画・構成から評伝と解説まですべてを手がけた。作家・中上健次による解説は圧巻。
完売富田虎雄 監修 / 金関寿男・横須賀孝弘 訳 / 中上健次 解説
B4変型判 / 豪華箱入製本 / 176頁 / 定価14,666円(本体13,333+税)/ ISBN4-900358-18-5
[1984/02/01]
新聞・雑誌紹介記事、書評など
美術手帖 紹介記事
西部開拓期、滅ぼされつつあったインディアン諸族の生の表情と慟哭を、好奇心や同情ではなく、真の共感をもって記録。その枠を日本ではじめて総覧する。
朝日新聞 紹介記事
エドワード・カーティス(一八六八―一九五二年)。肖像・風景写真の分野で知られた写真家だったが、モチーフをインディアンにしぼってから、一躍世界的に名声を博するにいたった。
ブルータス 紹介記事
「眼光にこもる無言のメッセージ」
先月、まだ雪におおわれているユタ州のソルト・レイク・シティへ行ったとき、路上で初老のインディアンと会った。浮浪者だった。米軍放出品らしいカーキ色のよれよれのコートを着ていた。
朝日新聞 紹介記事
カーティスがインディアンに関心をもったきっかけは、一九〇〇年、モンタナ州のアブサロケ(別名クロウ)族 の指定居住地に入り、その生活をつぶさに見たことだった。以来、インディアンを訪ねて回り、『北米インディアン』全二十巻にまとめた。三十年を費やしての労作である。
日本読書新聞 紹介記事
「良いインディアンは撮られたインディアンだ」
この本はカーティスの写真集『北米インディアン』全二〇巻(一九〇七~三〇)から編集された日本語版である。独自に詩と説話が付加されその部分の翻訳は金関寿夫(『アメリカ・インディアンの詩』の著者として今さら紹介の必要もあるまい)による。
撮られた者と見る者との恐るべき深淵
毎日新聞 紹介記事
「“滅びゆく民”とその文化を記録」
一八七〇年ごろから、北アメリカ西部に住むインディアンたちは白人たちの武力によって追い払われ、伝統文化は急速に失われていった。滅びゆくインディアンとその文化を記録した貴重な仕事が、エドワード・カーティスがライフ・ワークとした全二十巻の大作『北米インディ アン』である。
中央公論 紹介記事
アメリカ・インディアンの生活と民俗を記述したエスノグラフィーや、彼らを撮った写真家はこれまでも少なくなかった。しかし、六〇年代にいわるゆレッド・パワーは澎湃として起こった時、写真家として顧みられたのはエドワード・カーティスただ一人であった。
カメラ毎日 紹介記事
「写真というテクノロジーの皮肉」
19世紀末から20世紀にかけてのアメリカ合衆国の辺境地帯が舞台となっている二冊の写真集『森へ』と『北米インディアン悲詩』を続けてながめる機会を得、わたしはあらためて歴史の皮肉、というよりもテクノロジーの皮肉というものを考えざるをえなかった。
北海道新聞 紹介記事
シアトルで肖像写真家として活躍していたE・カーティス(一八六八~一九五二)は、三十歳を過ぎてから北米インディアン文化の記録を志し、生涯に八十以上の部族を訪れ、四万枚以上の写真を撮った。
図書新聞 紹介記事
「着飾り堂々たる勇者の肖像写真 批判にも繋がる“美しさ”」
アメリカのインディアン博物館を訪れるたびに、私は複雑な想いにかられる。棚の中に陳列された生活用具、衣装を目にしていると、これらを実際に使っていた民族の存在をつきつけられるからだ。
鎌倉朝日新聞 紹介記事
「巨大な暗箱と硝子乾板が捉えたフロンティアの姿」
前世紀末から今世紀初頭にかけて、主にアメリカの西部を舞台に活躍した二人の写真家の豪華な写真集が、鎌倉、岩瀬のアボック社から、左の二冊が同時に出版された。
アサヒカメラ 紹介記事
ほぼ同時期に活躍したアメリカの写真家二人の作品集である。昨年、本誌でもとりあげたキンゼイは風景、人物を緊迫感あふれる構図で表現しており、原生林を伐採するきこりの写真で知られている。
神奈川新聞 紹介記事
「実録写真の迫力も十分」
鎌倉の「アボック社」(毛藤圀彦社長)から、このほど相次いでアメリカの異色写真集二冊が翻訳出版された。同社は、もともとが公園の樹木などの植物名ラベルを専門に受託製作する会社だが、造園・修景から出版・編集などへも事業を拡大している。
岩手日報 紹介記事
「2人の米人写真家の邦訳豪華本を出版した毛藤圀彦さん」
1976年、百合樹(ユリノキ)を見つけに北米・ノースカロライナを回ってニューヨークに行ったとき、衝撃的な写真と出会った。それがエドワード・カーチスの「北米インディアン悲詩」と、ダリウス・キンゼイの「森へ」である。
神奈川新聞 紹介記事
「滅びゆく民の声が・・・」
写真を撮られるとカメラの目に魂が盗まれてしまうという、インディアンの間の迷信も、世紀の変わり目ごろにはかなりなくなっていたという。
岩手日報 紹介記事
盛岡市出身、神奈川県鎌倉市で「アボック社」を主宰する毛藤圀彦氏が、ニューヨーク・マンハッタンで、二人の写真集に出会い、六年がかりで発刊にこぎつけた。その思い入れの深さを示す豪華本である。エドワード・カーティスとダリウス・キンゼイは、近年アメリカで高い評価を得ている。
夕刊フジ 紹介記事
「“滅びゆく民”を30年がかりで撮影」
前世紀末から今世紀初めにかけ、米国西部を舞台に活躍した写真家、E・カーティスが、“滅びゆく民”インディアンを30年がかりで撮った写真集。原本の民族誌「北米インディアン」は20巻に及ぶぼう大なものだが、本書は原本の別冊ポートフォリオから代表作105点を選び文化圏ごとに配列。
週刊時事 紹介記事
「今聴く西部開拓史のどよめき」
同じ出版社から表題の写真集二冊(いずれもB4変型判)が同時に刊行された。しかしその内容は、単なる名写真といったものではない。両書の背景になっているのは“アメリカ西部開拓史のどよめき”であり、数多くの記録によってアメリカ大陸民族の残像が、共に今日に問題を投げかけている。作家中上健次が、情熱をこめて両書に解説を寄せているのも、そうした文学的関心が、そこに潜められているからだろう。
沖縄タイムス 紹介記事
写真を撮られるとカメラの目に魂が盗まれてしまうという、インディアンの間の迷信も、世紀の変わり目ごろにはかなりなくなっていたという。しかし、自分たちの世界に入り込み私生活を侵そうとする人間への疑いは根深く、著者カーティスにも、四回にわたる狙撃などの危険はあった。
写真家プロフィール

EDWARD CURTIS エドワード・カーティス(1868~1952)
アメリカ合衆国ウィスコンシン州に生まれる。独学で写真技術を身につけ、ワシントン州シアトルで写真スタジオを開く。この頃の写真は、町の人々のポートレイトや附近の風景が中心であり、そのロマンティックな作風が大いに人気を博す。
1900年、平原インディアンのサン・ダンス集会を訪れ、その壮大な光景に深く感動する。これが機になり、“インディアン文化の写真と文章による全記録”をライフ・ワークとして自らに課し、西部の全インディアン部族におよぶフィールド調査を重ねてゆく。それは後に『The North American Indian』全20巻としてまとめられる。
カーティスは、やがて1952年に死去、彼の業績は忘れられてゆくが、1960年代後半になると当時の思想潮流の中で再び脚光を浴び、その写真集は以後本国でロング・セラーを続けている。インディアンの歴史的資料としては最高の位置を占め、その芸術性も高い。