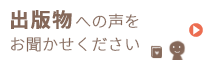図書新聞 紹介記事
北米インディアン悲詩 /1898~1928 エドワード・カーティス写真集

1984年3月10日 図書新聞
着飾り堂々たる勇者の肖像写真 批判にも繋がる“美しさ” (荒 このみ氏)
アメリカのインディアン博物館を訪れるたびに、私は複雑な想いにかられる。
棚の中に陳列された生活用具、衣装を目にしていると、これらを実際に使っていた民族の存在をつきつけられるからだ。かれらこそ最初のアメリカ人として認識しているはずのアメリカ人像とは一体何なのか。またインディアン博物館に来る「アメリカ人」はどのような気持を抱いて先住民族の遺品を見ているのだろうか。
この二月に、私はシアトルのパーク博物館にあるギアキー・コレクションを観た。日曜日のせいもあって家族連れも多く、かれらの反応に注目していると、珍しいもの、ときにはグロテスクなものを見る眼であるような気がした。インディアンとは、自分だちの世界とはかかわりのない地域に住む民族、歴史的過去に属す人間。だが一方で、町の名前にもなった酋長シアルスの墓が小高い丘の上にある。この現実の矛盾を、心の中でどう整理しているのだろうか。
シアトルの写真家エドワード・カーティス(1868 - 1952)が、生涯をかけて取り組んだ『北米インディアン』の写真集が、このたび日本で出版された。といっても原本は全二十巻および別冊ポートフォリオという大部のものであるから、ここに収録されたものは、そのうちのごく一部である。
巻頭を飾る「キャニオン・デ・シェイ=ナヴァホ族」の写真は、巨大なメサ(台地)のもとを馬で移動する人間の姿が半シルエットのように撮られている。光と影が微妙な効果をかもし出している。カーティスの写真の中でも傑作の一つに教えられよう。 日本版の写真集が独自性を主張するのは、写真に添えてあるインディアンの詩や説話の断片で、約20篇が収録されている。たとえば最初の写真には「夜明けでつくられた家」という詩が添えてあり、ナヴァホの少年を主人公にした、N・スコット・ママデイの同名の小説が想い浮かんでくる。
カヌーに乗った「クーテネイ族の鴨猟師」の写真もすばらしい。その他「アリーカラ族の呪い講」や「呪術師」など、民族独特の習俗を伝えるものがある。だが圧倒的に多いのが勇者の肖像写真で、美しく着飾り堂々とした顔だちのかれらを見ていると、強く心惹かれてゆき、「滅びゆく民」の弱さなど少しも感じられないのだ。
カーティスの撮った写真は美しい。ロマンティシズムを掻き立てるものがある。それはカーティス批判にもつながり、白人の眼から、滅び去るインディアンをひたすら芸術作品の対象として美しく描きあげたものとも非難される。
だが、この写真集には載っていないが、「生首を掴んだインディアン」もカーティスは撮っている。嫌なものに目をそむけるような現実認識では美は生まれ出ないのではないか。
「ジャック・レッド・クラウド=オガララ族」の写真を観ていてはっとした。胸に誇らしげにぶらさげているのは、白人の使う銀貨(おそらくシルヴァー・ダラー)ではないか。
(2・1刊、B4一七五頁・アボック社出版局)(津田塾大学助教授・アメリカ文学)
【写真は「嵐」アパッチ族】