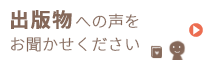- ホーム
- ネイチャーコンテンツ
- 自然史系書籍
- 植物分類表
- 朝日新聞 紹介記事
朝日新聞 紹介記事
植物分類表

2010年3月2日 朝日新聞
避けられる「他人の空似」
(米山正寛氏)DNA情報をもとにした植物の新しい分類体系が広まってきた。花は葉などの形をもとに分類する従来の考え方を大きく改めるもので、類縁関係は遠いのに外形が似ている「他人の空似」を避けられる利点がある。一方で、鮮やかな紅葉で親しまれる「カエデ科」のような科名が消えてしまう変更に、とまどいの声も聞かれる。植物の新しい分類の世界とは。
生きものの分類は、カール・フォン・リンネ(1707~1778)にさかのぼる。リンネが記した「自然の体系」(1735)で学問的な形が整えられ、生物を、属、科といった階層構造の中に位置づけるしくみが生まれた。
チャールズ・ダーウィン(1809~1882)が進化論を発表してからは、分類に生物進化の歴史を反映させ、類縁関係をもとにした系統分類をめざす考えが定着。近年まで踏襲されてきたが、「他人の空似」問題もあって、進化の道筋が分類に正しく反映されているかどうか、課題を抱えていた。
DNAの変異の差から類縁関係がかなりつかめるようになったことを背景に、被子植物では1993年に初めてDNAをもとにした分子系統樹が発表された。その後、欧米で組織された被子植物系統研究ググループが98年に情報を集約して分類体系にまとめ、2003年の改訂で完成度が高まった。シダ植物や裸子植物についてもDNAにも基づいた分類体系がつくられてきた。
今後「国際標準」に
欧米では数年前から新体系をまとめた本が刊行されていた。日本でも昨秋、海外の成果をもとに日本の植物に即した解説書が、一般向けに「高等植物分類表」(北隆館)や「植物分類表」(アボック社)として相次いで出版された。
まだ研究者によって解釈や用語の差は一部残るが、高等植物分類表を著した東北大植物園の米倉浩司助教は「これが国際標準になっていくのは間違いない」、植物分類表の編著者の大場秀章東京大名誉教授は「欧米では図鑑や植物園の表示などが新体系に変わってきている」と話す。新しい分類体系を、これまでの考え方と比較して系統樹のように表すと、図のようなイメージになる。
最大のポイントは、被子植物を、小学校で双葉を観察したアサガオでおなじみの双子葉類と、子葉が1枚の単子葉類とに大別しなくなったこと。新体系では、単子葉類のまとまりは残ったが、双子葉類にはスイレンやモクレンなど進化の歴史で単子葉類より前にできたグループ、後にできたキクやバラなどのグループがあるとわかった。前者の原始的双子葉類に対し、後者は真正双子葉類と呼ばれる。
また新体系では、双子葉植物を、花びらがくっついたアサガオのような合弁花類、サクラのようにバラバラの離弁花類に分ける考え方もなくなった。邑田仁東大教授は「モチノキは以前は離弁花類とされていたが、DNAでは、合弁花類だったキクなどと近いとわかった」と、合弁と離弁の区別をなくす必要が生じた例を挙げる。
消える「スギ科」
また「小規模な科は、できるだけ近縁な科にまとめるような変更がなされた」と米倉さんは説明。大場さんは「近縁でないのに他人の空似で寄せ集められていた科は解体され、分類し直された」と解説する。
親しんだ科名がなくなるのは、例えばカエデ科やトチノキ科。どちらも日本人にはなじみ深いが、ライチなどのムクロジ科に近いとされ、まとめられた。同じようにスギ科も消えてヒノキ科へ、アカザ科だったホウレンソウはヒユ科に変わる。
解体されたのはゴマノハグサ科やユリ科が代表格だ。元の科名は残されたものの、含まれていた多くの植物が別の科に移った。ゴマノハグサ科だった春に小さな青い花を咲かすオオイヌノフグリはオオバコ科へ、スズランもユリ科から離れる。
アジサイは花の構造などからユキノシタ科となっていたが、系統的には異なるとしてアジサイ科が生まれた。紫色の実のムラサキシキブはクマツヅラ科からシソ科に。庭にも植えられるアオキはミズキ科から、ガリア科またはアオキ科とされた。これほどの変更だけに、新しい分類体系に対して、植物愛好家からは「もう浦島太郎でよくわからない」「覚えるのに悪戦苦闘」と嘆く声が聞かれ、普及には時間がかかりそうだ。高等植物分類表を出した北隆館は「牧野日本植物図鑑」などを刊行してきた出版社だが、「将来的には図鑑でも採用すべきだが、すぐに対応するのは難しい」という。
日本植物分類学会の戸部博会長(京都大教授)は「新体系をもとに改めて植物の形態や発生などの研究が深まるのは間違いない。学会からも一般の人たちへの情報発信を工夫していきたい」と話している。