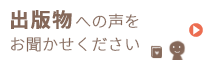- ホーム
- ネイチャーコンテンツ
- 自然史系書籍
- 森へ ダリウス・キンゼイ写真集
- 週刊時事 紹介記事
週刊時事 紹介記事
森へ ダリウス・キンゼイ写真集

(掲載年不明)2月25日 週刊時事
ダリウス・キンゼイ 「森へ」
エドワード・カーティス 「北米インディアン悲詩」
今聴く西部開拓史のどよめき
同じ出版社から表題の写真集二冊(いずれもB4変型判)が同時に刊行された。
しかしその内容は、単なる名写真といったものではない。両書の背景になっているのは“アメリカ西部開拓史のどよめき”であり、数多くの記録によってアメリカ大陸民族の残像が、共に今日に問題を投げかけている。作家中上健次が、情熱をこめて両書に解説を寄せているのも、そうした文学的関心が、そこに潜められているからだろう。
キンゼイは一八六八年、カーティスは一八六九年生まれ。まさに同年代に活躍した写真家で、全二十巻に及ぶそれぞれの写真集は、欧米ではつとに著名だが、わが国への上陸は、本書が初めてだ。
約百年前のアメリカ大陸。6.5×8.5インチ型写真機(いわゆる暗箱)と重さ数十キロもある乾板や身辺具を馬にのせ、直径六メートル、高さ百メートルの巨木が目を閉ざす道なき森へ、あるいはまた白人に追われていくインディアンの社会とその苦悩の中へ、約半世紀にわたって冒険の旅を続けた二人の写真家。彼らはどのようなロマンに身を焦がし、どのような美と怨念の世界に触れたのだろうか。
それを写真と文章で訴えているのがこの両書で、いずれも約五千枚の乾板から、前者が百八十五枚、後者が百五枚選びぬかれ、掲載されている。
例えば「森へ」のある一枚には、「千年以上もの冬の嵐が、森林のこの古代からの地標(直径六メートルの杉の巨木)に痕跡を残してきた」と記され、三人の山男が豆粒のように、その根元に立ちすくんでいる。
ある一枚は、一九〇二年に撮られた直径六.六メートルの杉の切り株住居で、入植自作農民四人が切り株の窓から顔を出していたりして、ほほえましい。
訳者(田口孝吉)はあとがきで、森が哲学者であることを実感させたキンゼイの天才的な写真表現のついて、こう書いている。キンゼイの生涯は「偉大なるオデッセイ(叙事詩)と呼ばれている。写真技術の発展とともに生き、森の中の美を求めて、未知の表現へと彷徨したキンゼイにふさわしいと思う」
「森へ」が深遠な森林の静謐を語り、また鉄道施設のため巨木が伐採されていく崩壊の姿を追っているのと同じように、「北米インディアン悲詩」におけるインディアンもまた、その運命を同じくしている。
カーティスは八十以上の部族を訪れ、彼らの姿を四万枚を超える当時の大きなガラス乾板に刻み撮っている。カーティスのもつロマン主義―騎士道精神、冒険、驚異等々が、インディアンの“落日の影”と合致したからだろう。 この「北米インディアン悲詩」もまた、写真集というよりも、民俗学上の論考として、インディアン文化の再発見に連なる貴重な記録といえるものだ。
スー族に次の言葉がある。
「私たちを結束させる中心は、もはやなくなった。聖なる樹は死んだのだ」
物悲しげに遠ざかっていく部族群―まさに滅びゆく民族や自然の姿を、この両書は物語って余りある。
営業日カレンダー
2025年4月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 2828日 … GW休業 | 2929日 … 昭和の日 | 3030日 … GW休業 | 1 | 2 | 3 |
- 28日 … GW休業
- 29日 … 昭和の日
- 30日 … GW休業
=休業日
土曜・日曜・祝日・GW休暇・夏季休暇・冬季休暇(年末年始)