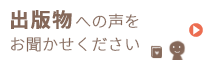- ホーム
- ネイチャーコンテンツ
- 自然史系書籍
- 森へ ダリウス・キンゼイ写真集
- 日本カメラ 紹介記事
日本カメラ 紹介記事
森へ ダリウス・キンゼイ写真集

1984年4月号 日本カメラ
森と写真に憑かれた男 (飯沢耕太郎氏)
ここに森と写真に憑かれた男がいる。男の名前はダリウス・レイノルズ・キンゼイ(一八六九~一九四五)。カナダとの国境に近いワシントン州で、一八九〇年代から一九四〇年代にかけて写真業を営んでいた。彼の主要な仕事は、この一帯に広がる巨大なシーダーの森の中でおこなわれた。全体で40キロ以上にもなるガラス乾板写真器材を荷馬車、あるいは鉄道に積みこみ、この写真家は材木伐採地の奥深く踏みこんでいく。そこで働く男たちを伐り倒されていく巨樹を背景として撮影し、彼らにその写真を売りさばくことが彼の仕事だったのである。
撮影された乾板は、鉄道便で街の写真館に送られ、彼の妻のタビサによる細心の注意を払った素晴しい現象、引伸しの処理を受けることになる。その後これらの写真は注文者ごとに封筒い入れられ、ふたたび伐採地に送り返されて、一枚50セントで男たちの手にわたるのである。
この写真集は、そのようなダリウスとタビサの半世紀にわたる共同作業から生み出された四五〇〇枚に及ぶネガから、風景写真家のD・ボーンとR・ペチェックによってセレクトされて一九七五年にアメリカで出版された『Kinsey PHOTOGRAPHER』の日本語版である。全体は二部に分かれ、第一部には主に家族のポートレートと初期作品が、第二部には驚くべき緊密な構成力を示す、森と樵夫たちの写真の大部分がおさめられている。
これらの写真の中にわれわれが見ることができるのは、これまで写真に撮影されて中でも、最も力に満ちた、最も繊細で美しい、しかし最も残酷で悲痛な光景の一つ一つである。直径5メートル以上もの巨木が、悲鳴をあげながら次々に伐り倒され、森林鉄道によって運ばれていく。斧や鋸によって入れられた刻み目は、生々しい傷口のようにも見える。そしてその周囲には、石で打ち倒された巨人の死体のように、巨木の丸太が横たわっている。
しかし写真そのものから受ける印象は、けして荒々しいものではなく、むしろ静謐な安らぎといたものさえ感じることができる。おそらく写真家によって注意深く運ばれている柔らかな光――ほとんど影を落とすことなく、風景の内側から滲み出し、その全体を静かに包みこんでいるように見える透明な光のベールが、その印象を強めているい違いない。
樵夫たちもまた、けして勝利者の驕りやたかぶりの表情を見せることはない。激しい労働のためでもあるのだろうが、彼らは一様に肩を落とし、むしろ悲しげな雰囲気すらただよわせている。戦いはもう既に終っているのである。勝ったのは人間たちであろう。だが彼らもまた、樹々と同じように見えない深い傷を負っているのである。やがてその傷口は次第に広がり、失われた樹霊の叫び声に応えてうずくことになるであろう。
ダリウス・キンゼイもまた、そのような樹霊の呼び声を聞く者の一人であったに違いない。彼は樹を伐り倒すかわりに、写真の中に風景を切り取り、閉じこめていく。敬虔なメソジスト派協会の信者であった彼にとって、写真を撮影することは、死にゆく者への祈りにも似た宗教的な行為であったことが想像できる。しかしその聖なる儀式に彼を駆り立てていったものは、単純な使命感や商売上の利益だけではなく、危険な力を保ち続けている森の樹霊だちの魂を鎮めようとする欲求ではなかったのだろうか。彼は写真を撮影することによって、森と樹木を征服しようとする人間たちの行為に最後の仕上げをほどこす。そのことがぬぐいきれない負いめとなって、ダリウスとタビサに苦業とも言えるような超人的な努力を強いているように思われるのである。
この写真集の最後におさめられたダリウス自身のポートレートは、この「夢中で写真に身を入れていたので、心がいっぱいで他のことは何ひとつ入る余地がなかった」男の風貌をよく写し出している。山高帽をかぶり、きちんと正装して、彼の背の二倍以上もある三脚の下で愛用のカメラに囲まれた小柄な写真家は、一点に目を据えて口を結んでいる。彼の耳には永遠に、倒された樹木のあいだを吹き渡る風の声が聞こえているに違いない。