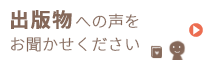- ホーム
- ネイチャーコンテンツ
- 自然史系書籍
- 森へ ダリウス・キンゼイ写真集
- 現代詩手帖 紹介記事
現代詩手帖 紹介記事
森へ ダリウス・キンゼイ写真集

1984年4月号 現代詩手帖
樹は泣いている (諏訪優氏)
ダリウス・キンゼイ写真集『森へ』(アボック社出版局)の、一枚一枚の写真が語りかける感動は何なのか、わたしにはまだ、よくわからない。
こんな写真を残した人物は、たいした人にちがいないが、それよりも、古い乾板に写されて今わたしの目に触れる、たかだか百年前の、アメリカの自然、そして大樹、さらには、その森林と係わった人間像に心が揺すられる。
アメリカと“森”とくれば、わたしのごとき文弱の徒は、すぐソーロウと『ウォールデン』(Walden, or, Life in the Woods. 1856)を結びつけてしまうのだが、キンゼイの『森へ』を見て、アメリカ合衆国の東部と西部が、いかにちがうかを更めて知った次第であった。
写真にもあるワシントン州ヌークサックの荒地や森林(ゲイリー・スナイダーの詩にこのあたりを書いたものが何篇かある)とくらべたら、ウォールデン池畔など、東部の恵まれた牧師の息子が理想を優雅にためしているお子様向け自然公園のようなものである。
東部と西部では、人情や意識がちがってくるのは当然であろう。
キンゼイの写真の中心は、何といっても“大樹”であり“巨木”であって、キンゼイならずとも、これらの“大樹”に接したら、人間誰しも只では離れられまい、と思う。
テレビの画面でジャイアント馬場を観るのと、数メートル先に現実の、生身の馬場を見ることのちがいを、現代人たちは真剣に考えたりはしない。
情報とか映像が、いろいろ示してはくれるが、そこには匂いもなければ、匂いに到達するための苦しみも痛さもないのである。 写真が、絵が、そして詩も、今や急速に変るのもいたしかたあるまい。(言語は、ひいては詩は、唯一そうではないものだと老詩人は信じているのだが…)
伐られる木は“泣いている”と、かつてインディアンは詩に書き残している。
杉一本とはいえ、千年も生きた大樹に霊魂がないと、誰れに言えるだろうか。